戦の終末、そして、それぞれの思惑、悲しみ、絆、愛などが盛りだくさんだった。しかも、それらが単なる羅列ではなく深いものだったので、見ごたえがあった。
頼長の最期
今回一番印象に残った。
頼長(山本耕史)が矢で首を射られたシーンでギクッとさせられ、父・忠実(國村隼)に会うのを拒まれ、失意の涙を流し舌を噛み切り絶命。
忠実は、摂関家のため断腸の思いで息子を拒んだが、頼長が飼っていたオウムが、痩せこけた姿で「チチウエ、チチウエ」と言いながら事切れる姿を見て、息子を見捨て、失った後悔・悲しみが堰を切ったようにあふれ出す。
動物を使うのは反則だと思いつつ、このオウムと頼長を巧妙にダブらせていた。言葉を話す才(=学問に秀でていた)はあったが、飼い主・頼長の擁護(父・忠実の擁護)がなくなり、自然界では生きられなかった(四面楚歌状態になった)。
頼長の父への思いも「チチウエ、チチウエ」というオウムの声で、醸し出されていた。
更に、ダメを押すように、信西が頼長邸の廃墟で、日記を見つけ、頼長の政治への清廉な思いを感じ取る。本当に真っ直ぐな風紀委員長……
武士の世は近い?―清盛と義朝―
戦の悲惨さを感じるが、安堵感と達成感を持つ清盛(松山ケンイチ)と義朝(玉木宏)。「武士の世が近い」という期待もあり、友情モード復活。
「面白きこと(面白く生きる)」「強く生きる」……西行(佐藤義清)「美しく生きる」を交えての青春談義がここに復活。
「もののけの血」とか「面白きこと」をずっと引っ張るというのは一貫性はあるが、過去がそれこそ「面白くなかった」ので、今後の展開に期待する私としては、嫌なイメージーがぶり返してしまう。この先「海賊王になる」というフレーズが復活しないか不安。
名を変えようと思う。「友を切る」という名は縁起が悪いと、義朝。
「友」という言葉に反応する清盛を見て、(「友」とは)お前のことでないと、あわててムキになって訂正する。
清盛も照れがあり、義朝の無精ひげを揶揄し「髭切」にせよと照れ隠し。馬鹿な名を!と思いつつ、「髭切」……まんざらでもなさそう。
あまりに緩い展開はどうかと思うが、この先の二人の決裂の対比としての伏線か?しかし、ここまで、①宮廷のドロドロ愛憎劇、②もののけの血が中心で、③平氏(清盛)の台頭、そしてついでに④源氏(義朝)の内紛(奮闘)が描かれてきたので、遠い過去の青春話を持ち出すしかないのは苦しい。これまでに、もう少し清盛、義朝の衝突を描いて欲しかった。
清盛、義朝の身内への思いと行動
清盛、義朝ともに、敗軍の将の平忠正(豊原功補)、源為義(小日向文世)が気にかかる。残党狩りで捉えられるよりはと、清盛は自らが命を出し、源氏は由良(田中麗奈)が、身柄を確保する。
清盛は、罪の軽減に望みを懸け、忠正にも生きて欲しいと説得する。義朝は既に親子の縁を切ったと会わない。義朝とのやり取りでも、義朝の武勲を素直に認め、忠正の処遇でも人間の大きさを感じさせたが、一族の長としての選択は微妙。忠正自身をはじめ皆が敵将をかくまう罪を問われるという危惧していたはずだが、忠正と清盛の情にストーリーも恩赦が受けられるかどうかに流れ気味で、これが一族の災いをもたらすという危機感がなくなってしまっていた。
ま、それはともかく、忠正も為義も、清盛と義朝が朝廷に武勲を認められたことを素直に喜ぶ。今週は頼長が退場し、清盛と義朝に反目していた二人が次回、いよいよ退場するかと思うと、寂しい。
黒い信西、その胸の内は?
第二部の始まりあたりから、黒く豹変した信西(阿部サダヲ)。(その心境の変化が描ききれていなかったのには、大いに不満)
今回、かつては共に学問の道を歩んだ頼長の焼けた落ちた館を訪れ、彼の政治への清廉さを思いやったようだ。
しかし、後半は崇徳院(井浦新)側へ厳しい処分を下す。
反対意見に「何のための戦か?!」と強く問う。
これは、まったくの素人考えだが、信西は天皇、上皇、そして貴族による政治には失望しており、それで出家したはず。
しかし、近衛天皇(北村匠海)の病死により、雅仁親王(後白河帝・松田翔太)の乳父の立場を利用して、政権を牛耳る機会を得た。(傀儡にするなら崇徳院の方が適しているが、そう贅沢も言っていられなかった)
という経緯はあるが、先に述べたよう、心境の変化がどこで起こったのかがあやふやなのは残念。
横道にそれたが、信西は自らの政治理想の実現を目指すため、心を鬼にして非情に徹した。今回の保元の乱も、政敵の排除が目的で、戦後も反乱因子の排除を徹底したかった。頼長もその一人で、彼の政治理念を認めながらも、信西の理念実現には邪魔な存在だった。
私は歴史に疎いので、平治の乱の原因や結果を知らない。(ネットで容易にある程度のことは知ることが出来るが、この際、何も知らない方が、面白くドラマを見ることができると考えている)
信西としては、二度と争乱を起こしてはならないと考えていたはずで、そのために政敵排除を徹底したはずであったが、そう簡単に事が運ばなかったようだ。
では、武士はどうであろう?政治理念を実現するために武士は必要と考えていちゃはずだが、政権を手中に収めつつある今となっては、手駒として利用するだけの存在で、あまり力を持っては困ると考え、一族分裂の因を作っておこうと考えたのだろうか。
しかし、平氏や源氏を敵に回す可能性もある。どのように考えて、処分を決めたのだろうか?それが次回に明かされるのだろうか?
とにかく、もう少し、胸のうちを語らせて欲しい。
後白河帝 対 得子
双六をしながら後白河帝に釘を刺す美福門院得子(松雪泰子)は迫力があった。また、この行為に不敵に笑う後白河帝も面白く、ドラマとしては見ごたえがあった。
しかし、この得子も、信西同様、胸のうちが良く分からない。璋子(檀れい)の本質を見抜き、また、璋子が変容していくにつれ、得子も変容していった。ただ、行動に一貫性がないので、本心がつかめない。
鳥羽院が、崇徳院に政権を譲ろうとした際、戦乱が起こると止めたのは、心底からだったのか、政治的野心があったからなのか?
崇徳院に、病床の鳥羽院を見舞うよう諭したのは、彼女自身が改心していたからなのだろうか?
今回の大河は、登場人物が時々「いい人」「優しい人」になる。確かに、人の心は微妙で変わりやすいが、ドラマでこれを言い訳にして、その場限りの良い話にするのは、観る方は困る。なので、良いシーンだったとは思うが、このシーンは必要だったかという疑問を感じてしまう。
本人が胸の内を語るのは、ドラマが浅くなるというのなら、璋子に堀川局、清盛
に盛国(上川隆也)のような側近を置いて欲しい。信西には西行あたりが適任か。
いい人だった忠正
清盛が頭領になるころから、おとなしくなっていった忠正。それ以前は、清盛の息子の重盛・基盛のために竹馬を作ってやったエピソードぐらい。
この竹馬のエピソードだけ、やたらいい人だったので、違和感を感じたが、今回そのエピソードを生かすとは!
でも、こういう過去に種をまいておいて、穂がついてから回収というパターンが多い。巧妙と思えるが、その途中があまりの出来なので、あざとさを感じてしまうのは私だけ?
それと、あの竹馬(現代のとは違う)、面白いのかなと、疑問に感じるのも私だけ?
出家しようにも、剃刀がございません
あまりにも、崇徳院のままならない人生を象徴する台詞。
付き従ってきた従者を自由にしてあげるという優しい人だったのに。
【ストーリー】(番組サイトより)
保元の乱で負けた崇徳上皇(井浦新)方はちりぢりになる。左大臣・藤原頼長(山本耕史)は、逃げる途中で追っ手の矢により重傷を負う。崇徳上皇はあてもなく山をさまよい、やがて近臣・藤原教長(矢島健一)と二人きりになると、何一つ思いどおりにならない自分の人生を振り返り、泣き崩れた。
一方、勝軍の平清盛(松山ケンイチ)や源義朝(玉木宏)たちは、戦いで落命した者たちを悼んでいると、後白河天皇(松田翔大)があらわれ、武士たちをじきじきにねぎらった。やがて二人きりになると清盛は義朝の武勇をほめ、武士の世がやって来ると喜んだ。満足げな義朝は源氏の宝刀・友切の名を変えたいと告げると、清盛は義朝の不精ひげを見て「髭切(ひげきり)」と言う名を思いつく。
妻・時子(深田恭子)の元に帰り喜びをかみしめる清盛だが、敗軍の将となって姿を消した叔父・忠正(豊原功補)の行方が気がかりだった。義朝もまた、敵方についた 父・為義(小日向文世)に対して同じ思いをかかえていた。
ひん死の頼長は最後に父・忠実(ただざね・國村隼)を訪ね、救いを求めるが、罪に問われることを恐れた忠実は門を開かない。自分の運命を悟った頼長は、舌をかみきり絶命する。翌朝、忠実の前に頼長が飼っていたオウムが舞い降り、「チチウエ」と繰り返し鳴いて息絶えた。忠実はオウムを抱きしめ泣き叫んだ。
敵ながら頼長の才を認めていた信西(阿部サダヲ)は焼け崩れた頼長邸を訪ね、日記を見つけた。そこには頼長の政治に対する熱い思いがつづられていた。
やがて、行方しれずだった忠正と息子たちが、忠清(藤本隆宏)に連れられて清盛のもとへ戻る。残党狩を心配した清盛がひそかに捜索を命じていたのだ。抵抗する忠正を清盛は力ずくで押さえ、軽い罪で済むように頼むので、今後も平氏のために力添えをしてほしいと説得する。
一方、義朝にも為義が尾張で見つかったことが知らされた。妻の由良(田中麗奈)が探すよう命じていたのだ。もはや父子の縁はないと言って為義と会わない義朝。そして義朝に救ってもらう気はないという為義だが、義朝が殿上人となったことを由良から聞かされ、宿願がかなった喜びをかみしめた。
後白河天皇は崇徳上皇が仁和寺で出家し、忠正、為義がそれぞれ平氏と源氏の館にいることを知らされた。ただちに罪を定めよと命じる後白河天皇の前に美福門院得子(松雪泰子)が訪ねてくる。双六(すごろく)をしながら得子は後白河天皇の慢心を戒めて去る。悔しさをかみしめながら後白河天皇は笑みを浮かべた。
清盛は忠正の罪を軽減するよう信西に訴える。信西は世にとって最もよい判断をくだすから任せろと答える。
後白河天皇の前で崇徳上皇側についた敗者たちの処分が議論される。貴族たちの前で信西が次々と厳しい処分を提案する。藤原摂関家の長に復帰した忠通は、忠実の荘園も召し上げられることに抗議するものの認められず、出家した崇徳上皇は流罪となった。そして武士たちの処分は―――。
翌朝、信西に呼び出された清盛は、叔父・忠正を斬首せよ、という命令を聞き、にわかに信じられなかった。
頼長の最期
今回一番印象に残った。
頼長(山本耕史)が矢で首を射られたシーンでギクッとさせられ、父・忠実(國村隼)に会うのを拒まれ、失意の涙を流し舌を噛み切り絶命。
忠実は、摂関家のため断腸の思いで息子を拒んだが、頼長が飼っていたオウムが、痩せこけた姿で「チチウエ、チチウエ」と言いながら事切れる姿を見て、息子を見捨て、失った後悔・悲しみが堰を切ったようにあふれ出す。
動物を使うのは反則だと思いつつ、このオウムと頼長を巧妙にダブらせていた。言葉を話す才(=学問に秀でていた)はあったが、飼い主・頼長の擁護(父・忠実の擁護)がなくなり、自然界では生きられなかった(四面楚歌状態になった)。
頼長の父への思いも「チチウエ、チチウエ」というオウムの声で、醸し出されていた。
更に、ダメを押すように、信西が頼長邸の廃墟で、日記を見つけ、頼長の政治への清廉な思いを感じ取る。本当に真っ直ぐな風紀委員長……
武士の世は近い?―清盛と義朝―
戦の悲惨さを感じるが、安堵感と達成感を持つ清盛(松山ケンイチ)と義朝(玉木宏)。「武士の世が近い」という期待もあり、友情モード復活。
「面白きこと(面白く生きる)」「強く生きる」……西行(佐藤義清)「美しく生きる」を交えての青春談義がここに復活。
「もののけの血」とか「面白きこと」をずっと引っ張るというのは一貫性はあるが、過去がそれこそ「面白くなかった」ので、今後の展開に期待する私としては、嫌なイメージーがぶり返してしまう。この先「海賊王になる」というフレーズが復活しないか不安。
名を変えようと思う。「友を切る」という名は縁起が悪いと、義朝。
「友」という言葉に反応する清盛を見て、(「友」とは)お前のことでないと、あわててムキになって訂正する。
清盛も照れがあり、義朝の無精ひげを揶揄し「髭切」にせよと照れ隠し。馬鹿な名を!と思いつつ、「髭切」……まんざらでもなさそう。
あまりに緩い展開はどうかと思うが、この先の二人の決裂の対比としての伏線か?しかし、ここまで、①宮廷のドロドロ愛憎劇、②もののけの血が中心で、③平氏(清盛)の台頭、そしてついでに④源氏(義朝)の内紛(奮闘)が描かれてきたので、遠い過去の青春話を持ち出すしかないのは苦しい。これまでに、もう少し清盛、義朝の衝突を描いて欲しかった。
清盛、義朝の身内への思いと行動
清盛、義朝ともに、敗軍の将の平忠正(豊原功補)、源為義(小日向文世)が気にかかる。残党狩りで捉えられるよりはと、清盛は自らが命を出し、源氏は由良(田中麗奈)が、身柄を確保する。
清盛は、罪の軽減に望みを懸け、忠正にも生きて欲しいと説得する。義朝は既に親子の縁を切ったと会わない。義朝とのやり取りでも、義朝の武勲を素直に認め、忠正の処遇でも人間の大きさを感じさせたが、一族の長としての選択は微妙。忠正自身をはじめ皆が敵将をかくまう罪を問われるという危惧していたはずだが、忠正と清盛の情にストーリーも恩赦が受けられるかどうかに流れ気味で、これが一族の災いをもたらすという危機感がなくなってしまっていた。
ま、それはともかく、忠正も為義も、清盛と義朝が朝廷に武勲を認められたことを素直に喜ぶ。今週は頼長が退場し、清盛と義朝に反目していた二人が次回、いよいよ退場するかと思うと、寂しい。
黒い信西、その胸の内は?
第二部の始まりあたりから、黒く豹変した信西(阿部サダヲ)。(その心境の変化が描ききれていなかったのには、大いに不満)
今回、かつては共に学問の道を歩んだ頼長の焼けた落ちた館を訪れ、彼の政治への清廉さを思いやったようだ。
しかし、後半は崇徳院(井浦新)側へ厳しい処分を下す。
反対意見に「何のための戦か?!」と強く問う。
これは、まったくの素人考えだが、信西は天皇、上皇、そして貴族による政治には失望しており、それで出家したはず。
しかし、近衛天皇(北村匠海)の病死により、雅仁親王(後白河帝・松田翔太)の乳父の立場を利用して、政権を牛耳る機会を得た。(傀儡にするなら崇徳院の方が適しているが、そう贅沢も言っていられなかった)
という経緯はあるが、先に述べたよう、心境の変化がどこで起こったのかがあやふやなのは残念。
横道にそれたが、信西は自らの政治理想の実現を目指すため、心を鬼にして非情に徹した。今回の保元の乱も、政敵の排除が目的で、戦後も反乱因子の排除を徹底したかった。頼長もその一人で、彼の政治理念を認めながらも、信西の理念実現には邪魔な存在だった。
私は歴史に疎いので、平治の乱の原因や結果を知らない。(ネットで容易にある程度のことは知ることが出来るが、この際、何も知らない方が、面白くドラマを見ることができると考えている)
信西としては、二度と争乱を起こしてはならないと考えていたはずで、そのために政敵排除を徹底したはずであったが、そう簡単に事が運ばなかったようだ。
では、武士はどうであろう?政治理念を実現するために武士は必要と考えていちゃはずだが、政権を手中に収めつつある今となっては、手駒として利用するだけの存在で、あまり力を持っては困ると考え、一族分裂の因を作っておこうと考えたのだろうか。
しかし、平氏や源氏を敵に回す可能性もある。どのように考えて、処分を決めたのだろうか?それが次回に明かされるのだろうか?
とにかく、もう少し、胸のうちを語らせて欲しい。
後白河帝 対 得子
双六をしながら後白河帝に釘を刺す美福門院得子(松雪泰子)は迫力があった。また、この行為に不敵に笑う後白河帝も面白く、ドラマとしては見ごたえがあった。
しかし、この得子も、信西同様、胸のうちが良く分からない。璋子(檀れい)の本質を見抜き、また、璋子が変容していくにつれ、得子も変容していった。ただ、行動に一貫性がないので、本心がつかめない。
鳥羽院が、崇徳院に政権を譲ろうとした際、戦乱が起こると止めたのは、心底からだったのか、政治的野心があったからなのか?
崇徳院に、病床の鳥羽院を見舞うよう諭したのは、彼女自身が改心していたからなのだろうか?
今回の大河は、登場人物が時々「いい人」「優しい人」になる。確かに、人の心は微妙で変わりやすいが、ドラマでこれを言い訳にして、その場限りの良い話にするのは、観る方は困る。なので、良いシーンだったとは思うが、このシーンは必要だったかという疑問を感じてしまう。
本人が胸の内を語るのは、ドラマが浅くなるというのなら、璋子に堀川局、清盛
に盛国(上川隆也)のような側近を置いて欲しい。信西には西行あたりが適任か。
いい人だった忠正
清盛が頭領になるころから、おとなしくなっていった忠正。それ以前は、清盛の息子の重盛・基盛のために竹馬を作ってやったエピソードぐらい。
この竹馬のエピソードだけ、やたらいい人だったので、違和感を感じたが、今回そのエピソードを生かすとは!
でも、こういう過去に種をまいておいて、穂がついてから回収というパターンが多い。巧妙と思えるが、その途中があまりの出来なので、あざとさを感じてしまうのは私だけ?
それと、あの竹馬(現代のとは違う)、面白いのかなと、疑問に感じるのも私だけ?
出家しようにも、剃刀がございません
あまりにも、崇徳院のままならない人生を象徴する台詞。
付き従ってきた従者を自由にしてあげるという優しい人だったのに。
【ストーリー】(番組サイトより)
保元の乱で負けた崇徳上皇(井浦新)方はちりぢりになる。左大臣・藤原頼長(山本耕史)は、逃げる途中で追っ手の矢により重傷を負う。崇徳上皇はあてもなく山をさまよい、やがて近臣・藤原教長(矢島健一)と二人きりになると、何一つ思いどおりにならない自分の人生を振り返り、泣き崩れた。
一方、勝軍の平清盛(松山ケンイチ)や源義朝(玉木宏)たちは、戦いで落命した者たちを悼んでいると、後白河天皇(松田翔大)があらわれ、武士たちをじきじきにねぎらった。やがて二人きりになると清盛は義朝の武勇をほめ、武士の世がやって来ると喜んだ。満足げな義朝は源氏の宝刀・友切の名を変えたいと告げると、清盛は義朝の不精ひげを見て「髭切(ひげきり)」と言う名を思いつく。
妻・時子(深田恭子)の元に帰り喜びをかみしめる清盛だが、敗軍の将となって姿を消した叔父・忠正(豊原功補)の行方が気がかりだった。義朝もまた、敵方についた 父・為義(小日向文世)に対して同じ思いをかかえていた。
ひん死の頼長は最後に父・忠実(ただざね・國村隼)を訪ね、救いを求めるが、罪に問われることを恐れた忠実は門を開かない。自分の運命を悟った頼長は、舌をかみきり絶命する。翌朝、忠実の前に頼長が飼っていたオウムが舞い降り、「チチウエ」と繰り返し鳴いて息絶えた。忠実はオウムを抱きしめ泣き叫んだ。
敵ながら頼長の才を認めていた信西(阿部サダヲ)は焼け崩れた頼長邸を訪ね、日記を見つけた。そこには頼長の政治に対する熱い思いがつづられていた。
やがて、行方しれずだった忠正と息子たちが、忠清(藤本隆宏)に連れられて清盛のもとへ戻る。残党狩を心配した清盛がひそかに捜索を命じていたのだ。抵抗する忠正を清盛は力ずくで押さえ、軽い罪で済むように頼むので、今後も平氏のために力添えをしてほしいと説得する。
一方、義朝にも為義が尾張で見つかったことが知らされた。妻の由良(田中麗奈)が探すよう命じていたのだ。もはや父子の縁はないと言って為義と会わない義朝。そして義朝に救ってもらう気はないという為義だが、義朝が殿上人となったことを由良から聞かされ、宿願がかなった喜びをかみしめた。
後白河天皇は崇徳上皇が仁和寺で出家し、忠正、為義がそれぞれ平氏と源氏の館にいることを知らされた。ただちに罪を定めよと命じる後白河天皇の前に美福門院得子(松雪泰子)が訪ねてくる。双六(すごろく)をしながら得子は後白河天皇の慢心を戒めて去る。悔しさをかみしめながら後白河天皇は笑みを浮かべた。
清盛は忠正の罪を軽減するよう信西に訴える。信西は世にとって最もよい判断をくだすから任せろと答える。
後白河天皇の前で崇徳上皇側についた敗者たちの処分が議論される。貴族たちの前で信西が次々と厳しい処分を提案する。藤原摂関家の長に復帰した忠通は、忠実の荘園も召し上げられることに抗議するものの認められず、出家した崇徳上皇は流罪となった。そして武士たちの処分は―――。
翌朝、信西に呼び出された清盛は、叔父・忠正を斬首せよ、という命令を聞き、にわかに信じられなかった。











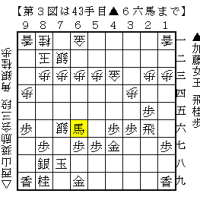

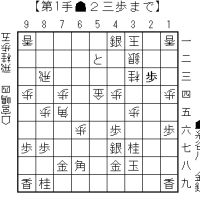




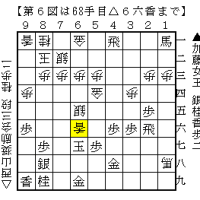






今回も 概ね面白く見ることが出来ました
特に 悪左府父子が見せてくれましたね
家盛をたらし込み 忠盛に悲憤を与えた人とは思えぬ最期でした
その他諸々よく出来ているとは思いますが
なんだか物足りない
その理由は(バカの1つ覚えで恐縮です)
清盛が出てくると面白くない!!!
に尽きます
何故なのかなぁ?
彼が 「面白き世」とか「面白う生きる」と言うと反射的に萎えるクセがつきました
松山ケンイチさの演技が悪いわけではないですしねぇ
40才を目前にするまで
乱暴な子供のような描かれ方をして
演ずる苦労もあったでしょう
ドラマとしてはマシになって来ているので
今後に期待して もう少し頑張ります
平安末期なんて滅多に見られないですからね
>主役が光らない
>清盛が出てくると面白くない
最近は清盛が人間として大きくなり、主人公も光り始めてきたように思います。
ただ、全くの憶測になってしまいますが、脚本家さんが、「清盛が好きではない」あるいは、清盛を描くことよりも、宮中のドロドロ情念劇を描く方が好きだからじゃないかなと。このドロドロ劇に比重を掛け過ぎて、他の事がおろそかになってしまった。
それと、このドラマの主題である「もののけの血」を絶ち切ろうとする清盛であるが、これをテーマにすることでドラマの深みが増すということはありますが、私はこれが嫌いで、このフレーズが出ると気持ちが冷めてしまいます。
最近は、これらのフレーズ(「もののけの血」「面白く生きる」)が出てきても、心を揺らさないようにしていますが、本文で書いたように、登場人物の心情をもう少し分かるようして欲しいです。
今回の得子が後白河帝に釘を刺したが、これは「いい気になるなよ」と嫌みを言ったのか、「いい気にならず、しっかり乱の事後処理をしなさい」というアドバイスだったのかが、よくわかりません。