
東海道本線の丹那トンネルは、
熱海と三島間にある鉄道トンネルで、完成当時は清水トンネルに次ぐ、
日本第二の長さ(7,8キロ)のトンネルです。
完成したのは1934年(昭和9年)でした。
それまでの東海道本線は、
国府津駅から御殿場を経由して、三島の先の沼津駅まで60,2キロを走っていました。
御殿場線の開通は1889年(明治22年)でしたが、
その当時の鉄道は勿論、蒸気機関車でした。
電気に比べて非力な蒸気機関車で勾配の急な御殿場線を走るには、
急勾配の区間になると、先頭にもう一台の機関車を連結したり、
後から押す機関車を繋いだりととても面倒で時間がかかったのです。
しかし、丹那トンネルが開通すると、距離は12キロ短くなり、
その時間も大幅に短縮されました。
丹那トンネルの工事が開始されたのは1918年(大正7年)でした。
日本最長の清水トンネルは9年間で完成したのですが、
7年の工期で完成する筈だった丹那トンネルは、
難工事に完成は遅れに遅れ、16年もかかり、
1934年(昭和9年)になってようやく完成したのでした。
何故それほどの難工事だったのでしょう?
それは、丹那トンネルの通る場所の地質によるものでした。
丹那トンネルの真上には水の豊富な、丹那盆地があります。

かつての丹那盆地は至る所から水が湧き、
周囲が羨むほど潤っていました。
ところが、トンネル工事が始まって6年後の、
1924年頃から盆地の水が枯れ、田畑は干上がり、
飲料水にも事欠くようになってしまったのです。
地元住民は渇水の原因はトンネル工事にあると、
鉄道省に再三にわたり対策を求めたのですが、
国には逆らえない時代だった為に認めてもらえませんでした。
しかし、拡大する渇水被害を無視できなくなり、
トンネル工事との因果関係を認めたのです。
国からの補償金を元に、農家は酪農に転換して行きましたが、
豊富な湧水が戻ることはありませんでした。
トンネル内には現在でも大量の水が湧き、
熱海の水道や函南町の農業用水として使われています。

しかし、丹那トンネルは何故、それほどの難工事だったのでしょう。
それは、丹那盆地の湧水でした。
とに角、掘れば掘る程、大量の水が流れ落ちて工事を阻むのです。
最終的に流れ出た水の量は、芦ノ湖3杯分だったといいます。
函南町の豊かな水は完全に元を断たれてしまったのでした。
その大量の水は何度もトンネルを崩壊させ、
最終的に67人もの犠牲者を出してしまいました。
犠牲者の遺体を引き出すと、全員の鼻がもぎれていました。
上がってくる水位から逃げようと、
上に張られていた板の隙間に鼻をねじ込ませ、
何とかして息をしようと作業員たちがもがき苦しんで死んで行った姿だったのです。

この難工事の様子は、吉村昭氏が、
「闇を裂く道」というドキュメンタリー小説で描いています。


そんな歴史が無かったかの如く、
現在の函南駅には平和な風景が広がっているのでした。

















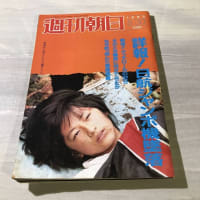










私、知の冒険というブログを運営する丹治と申します。
たまたまこちらのブログにたどり着いたのですが、こちらの地図に御殿場線、東海道線を描いた画像が、以下の私のブログと同じものだと思われるのですが、いかがでしょうか?
https://chinobouken.com/gotenbasen/
コピーして許可なく使われているのであれば削除していただきたいです。
宜しくお願いします。