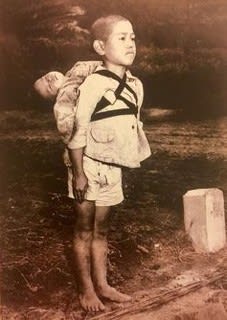逆転の発想、とかよく成功の秘訣として述べられる。逆境を力に変えるとかいうものだ。
果たしてそんなことが本当にできるのだろうか?
経営論でもはやりの考え方だ。しかし、「失敗なんかせずに成功だけするのが良い」のは言を俟たない。常勝軍団はあり得ないので人はみんな敗北からしか学べないとかいうわけだ。成功例からも沢山学ぶことはできる。
人間は数々のミスから、自分が復活するために色んな処方箋を作り上げてきた。その例は大いに参考にする必要がある。
私は「起きてもいないことを予測して、今からあれこれと心配して不安を強める傾向にある」ようだ。非常に考え物である。これも「自分」の一端だが実は非常に鬱陶しい。すぐに将来への資金、親の介護、に不安を感じてしまう。率直に言ってこの2点だけである。
・親の介護費用と自分の老後資金
若い頃、お金のことなど気にもしなかったのはどうしてだろうか?今になると不思議である。
逆境を力に変える。嫌なことに出会うが、それを淡々とこなす能力。周囲を見渡して現実吟味力を発揮して、自分の快楽原則との調整を上手くとる。気分の障害とも上手に付き合って無理をせず、感情を表出して、自分がやりたかったことを見つめ直して人生を進めてゆく。しかし、なにがしかの希望を胸に抱いて生きていないとますますやりきれなくはなってしまう。
実梅落ち漬けることなく安息日 自作