雍正帝は皇位簒奪者ではないか、と言われているが、
それを可能にしたのも、息子の弘暦(後の乾隆帝)との共同作業であった嫌いがある。
祖父帝(康熙帝)の晩年、あまたいる皇子らの皇位継承争いは、熾烈だった。
優秀な皇孫を持つことは大きな点数稼ぎになるため、
雍正帝はこの息子の聡明さを全面的に押し出したのである。
元来、弘暦(乾隆帝)は嫡男でも長男でもない。
弘暦は雍正帝の五男、上三人の兄が相次いで夭折したので、実質的には次男、上には七歳年上の異母兄、弘時がいた。
弘時の生母は側福晋(夫人)李氏、雍正帝の即位後は斉妃に封じられている。
側福晋は正福晋(正妻)の下に二人しかいないので、弘時の生母は極めて地位が高かったことになる。
その兄を差し置いて生母の地位が低い、召使いに毛が生えた程度の地位しかない生母を持つ弘暦が父親に見出され、
最終的には祖父の康熙帝にも特別扱いされたのは、ひとえに弘暦が優秀だったからである。
雍正帝は、この五男の聡明さを見込み、父帝に全面的に強調した。
康熙帝も百人を超える孫の中でも、弘暦をとりわけ気に入り、
宮中に引き取り育てるたった二人の孫の中の一人という特別な地位を与えた。
いわば今上陛下の皇帝としての地位は、父子で力を合わせて勝ち取ったものだ。
それもつらい幼年時代の苦労がばねとなっているに違いない。
そこが英廉が今上を敬愛する部分でもあった。
自分だって長男ではないし、生母も父親の寵姫でもなかった。
それでもそうやってここまでがんばってきたのだ。
当時の社会のいいところは、そういった庶出と嫡出をまったく差別しなかったことである。
皆が同じ屋敷に住み、すべての子供たちが正妻の子供という建前になるのだ。
例えば、最後の皇帝溥儀やその弟溥傑などの自伝を見ると、
「私の父は」と紹介し、その次には「私の嫡母は」と紹介が来る。
そしてその後に「私の生母は」となるのである。
その一族の出身であれば、社会での扱いはまったく同じ。
後の世のように「妾腹」「父なし子」と陰口をたたかれることはない。
その後は才覚がものをいう。
悪くない家柄の子供でありながら、
周りの少年たちにいじめられるようなみすぼらしい出で立ちで出されてくる善保(シャンボー)という少年の家庭の事情は
大方想像がつくというものである。
英廉の想像が自らのみじめな少年時代や今上の生い立ちにまで及んでいるとは、露知らぬネズミ男に英廉がふと聞いた。
「善保は庶出かね」
ネズミ男は、ほい来た、とばかりに目の色を変えた。
「そこなんですよ。あの兄弟の気の毒さは。ひひ。」
ぜんぜん気の毒と思っていないことを隠そうともせず、ネズミ男は卑猥に笑った。

紫禁城、雨花閣。
紫禁城の中にあるチベット寺院。
一般公開はされていないが、工事中のところを通らせてもらう貴重な機会。
ぽちっと、押していただけると、
励みになります!

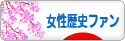
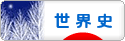
それを可能にしたのも、息子の弘暦(後の乾隆帝)との共同作業であった嫌いがある。
祖父帝(康熙帝)の晩年、あまたいる皇子らの皇位継承争いは、熾烈だった。
優秀な皇孫を持つことは大きな点数稼ぎになるため、
雍正帝はこの息子の聡明さを全面的に押し出したのである。
元来、弘暦(乾隆帝)は嫡男でも長男でもない。
弘暦は雍正帝の五男、上三人の兄が相次いで夭折したので、実質的には次男、上には七歳年上の異母兄、弘時がいた。
弘時の生母は側福晋(夫人)李氏、雍正帝の即位後は斉妃に封じられている。
側福晋は正福晋(正妻)の下に二人しかいないので、弘時の生母は極めて地位が高かったことになる。
その兄を差し置いて生母の地位が低い、召使いに毛が生えた程度の地位しかない生母を持つ弘暦が父親に見出され、
最終的には祖父の康熙帝にも特別扱いされたのは、ひとえに弘暦が優秀だったからである。
雍正帝は、この五男の聡明さを見込み、父帝に全面的に強調した。
康熙帝も百人を超える孫の中でも、弘暦をとりわけ気に入り、
宮中に引き取り育てるたった二人の孫の中の一人という特別な地位を与えた。
いわば今上陛下の皇帝としての地位は、父子で力を合わせて勝ち取ったものだ。
それもつらい幼年時代の苦労がばねとなっているに違いない。
そこが英廉が今上を敬愛する部分でもあった。
自分だって長男ではないし、生母も父親の寵姫でもなかった。
それでもそうやってここまでがんばってきたのだ。
当時の社会のいいところは、そういった庶出と嫡出をまったく差別しなかったことである。
皆が同じ屋敷に住み、すべての子供たちが正妻の子供という建前になるのだ。
例えば、最後の皇帝溥儀やその弟溥傑などの自伝を見ると、
「私の父は」と紹介し、その次には「私の嫡母は」と紹介が来る。
そしてその後に「私の生母は」となるのである。
その一族の出身であれば、社会での扱いはまったく同じ。
後の世のように「妾腹」「父なし子」と陰口をたたかれることはない。
その後は才覚がものをいう。
悪くない家柄の子供でありながら、
周りの少年たちにいじめられるようなみすぼらしい出で立ちで出されてくる善保(シャンボー)という少年の家庭の事情は
大方想像がつくというものである。
英廉の想像が自らのみじめな少年時代や今上の生い立ちにまで及んでいるとは、露知らぬネズミ男に英廉がふと聞いた。
「善保は庶出かね」
ネズミ男は、ほい来た、とばかりに目の色を変えた。
「そこなんですよ。あの兄弟の気の毒さは。ひひ。」
ぜんぜん気の毒と思っていないことを隠そうともせず、ネズミ男は卑猥に笑った。

紫禁城、雨花閣。
紫禁城の中にあるチベット寺院。
一般公開はされていないが、工事中のところを通らせてもらう貴重な機会。
ぽちっと、押していただけると、
励みになります!



















E. Toddという学者さんは中国の家族構造を外婚制共同体と分類していますが、これはユーラシアの北部(ロシア、モンゴル)にも広く分布しているようです。
blue.ap.teacup.com/applet/salsa2001/3477/trackback
そしてその傾向は、今でも中国の家族に生きています。 もしかするとこうした伝統は度々中国を支配した北方騎馬民族から受け継がれたものかもしれませんね。
>もしかするとこうした伝統は度々中国を支配した北方騎馬民族から受け継がれたものかもしれませんね。
なるほどー。
それはユニークな見方ですね。
考えてみたこともなかったですが、
なかなか興味深いです。