アルタン・ハーンは、ダヤン・ハーンの孫に当たる。
父親はダヤン・ハーンの三男バルス・ボラト・ジノン、その次男として生まれる。
前述のとおり、チンギス・ハーンの直系の子孫がすべて皆殺しにされた後、ダヤン・ハーンだけが正当な血筋を持つ人物となった。
ダヤン・ハーンは11人の息子たちをモンゴル各地の有力な部族の族長の元に婿入りさせた。
アルタン・ハーンの父親は、ダヤン・ハーンの三男、婿入りした先はトメト部、
領地の草原は、今でいう山西省の大同の北辺りからフフホトにかけての地域である。
モンゴルの中でも明朝の首都・北京に最も近い地域といえる。
アルタンは確かにダヤン・ハーンの孫ではあるが、ダヤンに11人もの息子がいたことを考えると、孫の数は100人近くいたに違いない。
その中でアルタンの優先順位はかなり低い。
アルタンは三男の子供であり、長男でさえなかった。
トメト部の部族長ファミリーの一員という程度の位置づけでしかない。
トメト部の部族長だった父親の位は「ジノン」、貴族的な地位をあらわす言葉の一つだ。
父親亡き後は兄グンビリク・モンゲンがジノンの位を継ぎ、アルタンは次男としてそれをサポートした。
しかししばらくして兄がなくなる。
それ以後、アルタンがトメト部を率いることになる。
かれは青台吉(チン・タイジ)、ハラハンなどの他のモンゴル勢力、
さらには塞外に割拠する漢人の高懐智、李天章などの勢力と連合し、数十万人の兵力を傘下に収めるようになる。
長城の外には、かなりの漢人「アウトロー」が法の届かない新天地を求めて入ってきていたらしい。
のちにアルタン・ハーンが建設するフフホトの町は、
そういった長城の中から入植してきた漢人の開墾した地区「板昇」の中心にある。
飢饉で食い詰めた農民のほかにも、国内で犯罪を犯し、逃亡してきた者、白蓮教一揆の指導者で
指名手配になっている者など雑多な漢人らが草原には多く存在したのである。
アルタンはそういったならず者の漢人集団も勢力に抱き込みつつ、実力を拡大し、
これを背景にダヤン・ハーンの嫡出後継者である「小王子」に圧力をかけた。
小王子は、最も継承順位の高いダヤン・ハーンの長男の長男の系統であり、
つまりはアルタンには、いとこに当たる。
小王子の勢力は、アルタンらに押され、ついには東のかなたに追いやられ、アルタンがハーンの位につくに至る。
アルタンがハーンになった時、明との貿易関係はとっくの昔に途切れていた。
明は国境に沿い、万里の長城を延々と建設している。
東は渤海湾に顔を突っ込むところまで長城を延長させた山海関から始まり、
西は甘粛の砂漠のかなたまで、行軍しやすい場所は、ほぼ長城で封鎖する。
このため長城の中と外にいる漢人と遊牧民の交易は、ごく小規模となる。
密貿易をこそこそとすることはできても、規模を大きくすることはできない。
どっさり荷を積んだ荷車を堂々と引いていけるような公道や谷間を通る関所を通ることができないからだ。
これでは、経済活動の質も量もごく限られた規模の中に制限されてしまう。
そもそも遊牧という形態は、自給自足ができないことはないが、やはりやや無理がある。
衣服からして麻、綿、絹を着ずに獣の皮だけでもいいではないか、ということも可能だが、
通気性、吸収性に悪い獣の皮より植物繊維の方が心地いいに決まっている。
一度着用してしまえば、それなしの生活に戻ることは、できるなら避けたいと思うようになるのが人情だろう。
穀物やお茶がなくても、乳製品と獣の肉だけで生きていけないこともないが、
炭水化物でエネルギー分を効率的に補い、お茶でビタミンを補給できれば、大きく健康状態を改善し、寿命も長くすることができる。
湯を沸かす鉄鍋を草原で自給できるわけもないし、漢人の持つ各種鉄器の武器に対抗するためには、
同レベルの鉄器は、最低限必要ともなる。
長期的に長城の外に閉め出されることは、今でいう経済封鎖であり、この状態が続けば、
命がけで南下してくるのは、生産構造からしてどうしても避けられない。
これをなんとか慰撫するため、朝貢という名の元に金品を与えることは、明初から行われてきた。
つまりは遊牧民側が属国であることを認め、臣下としての礼を尽くし、献上物を差し出す。
これに対して明が、数倍の返礼を下賜するという形で、経済的に懐柔しつつも、王朝としての面子を損なわないという構造である。
そのほかにも「互市」が開かれた。
しかし「互市」という名前にも関わらず、まったく「相互」関係ではなく、どちらかといえば、明の一方的な決まりに基づいていた。
開催期間、場所、入場人数、品目、売り値、取り引数のすべてが明側の一存で決められており、やはり「施し」のニュアンスが強く、対等ではない。
モンゴル側がもっとたくさん売りたい、高く売りたい、と思ってもできない。
馬だけと決められており、牛、羊を売りたいと思っても売れない、という形式である。
最も早い朝貢と「互市」は、永楽3年(1405)からウリャンハ三衛を相手に開かれた。
彼らだけが明に臣下の礼を取ることに甘んじ、服従の意を示したからである。
この当時モンゴルの他の部族は、ウリャンハを通してしか、中原との経済関係を得ることができなかった。
その後、徐々に他の部族も朝貢貿易に参加するようになるが、これにより利益を得たからといって
彼らが長城を超えて侵入・略奪をしないかといえば、そうでもなかった。
草原で優れたリーダーが出現し、統率力が高まれば武力に訴えて略奪を行い、
弱まれば、再びしばらくの間は朝貢だけに甘んじる、といったいたちごっこが繰り返された。
オイラトのエセン・ハーンの時代(正統年間=1440年代前後)には、遊牧民側の傍若無人ぶりが暴走して止まらない状態までいく。
朝貢貿易は行えば行うほど明側の出費が増えるので、明としては最低限の頻度と規模に抑えたい。
ところが、エセンはその規定を守らず、1年に一度と決められていたものを
「前の使節がまだ都を離れないうちに、次の使節が到着する」始末である。
そのほかにも使節の人数も大量に規定をオーバー、持ち込んだ産物は粗悪品であるなど
あまりにも目に余る行動をとる。
ついに我慢できなくなった明側が英宗の親征でモンゴル討伐に向かい、
逆に大敗して皇帝がモンゴル側の捕虜となってしまうのが、「土木の変」である。
数十万人の戦死者を出したといわれる大惨事が起きたにも関わらず、
その後も中原の物資がほしいエセンの譲歩により朝貢貿易は再開される。
ダヤン・ハーンの時代になっても一時は朝貢貿易が続けられたが、
再び朝貢の頻度、使節の人数など取り決めで明側ともめたため、完全に決裂、
それ以来、国交断絶のままアルタン・ハーンの時代に入った。
弘治年間(1488-1505)以来というから、アルタンが政権を把握した嘉靖初年(1521-)には
すでに30年以上の経済封鎖状態だったことになる。
その間の両者の交流といえば、密貿易と不定期にモンゴル側が組織する長城を超えた略奪活動のみである。
アルタン・ハーンも当初は略奪を行った。
嘉靖8年(1529)オルドスから楡林、寧夏に侵入し、周辺を荒らした。
佳県は楡林のすぐ南にあるので、まさにこの辺りである。
しかしダヤン・ハーン時代、政権が安定し、平和が長く続いた後、
モンゴル側も略奪というリスクの大きい方法ではなく、市場での取引という平和な形での
経済活動を望むようになってきていた。
モンゴル側も南下して漢人の村を襲い、略奪するが、自分たちも無傷ではいられない。
戦いで命を落とすかもしれないし、明側の報復もある。
ダヤン・ハーンのかの姉さん女房マンドフィ・ハトンもどうやらある時の明側の夜襲により命を落としたといわれる。
そこで嘉靖20年(1541)、アルタンは使者を出し、明側に正式な「互市」の開催を申し出た。
朝貢ではないことが重要だ。
朝貢はわざわざ都に出て行かなければならないだけでなく、使者団の人数、献上する物品の量、頻度まですべて制限されている。
市場原理を無視した、「施し」を目的をしているのだから、
取引が多いほど、明の朝廷にとっては迷惑な話なわけで、なるべく小さな規模に抑えたいと意図する。
もっと中原の物品を手に入れたいモンゴル側と押し問答になる、という昔からの伝統的な構図が続いていた。
「もっと取引させろ」、「いやだ」の押し問答である。
そうではなくて市場原理に則った、「施し」ではない、対等な取引がしたい、というのが、アルタンの主張だった。
朝廷はそんなに多くの毛皮も馬もいらないかもしれない。
モンゴル側から献上される物品は、市場に出回ることなく、
皇帝一家や朝廷の官僚たちの間で消費されるだけなので、その需要はたかがしれている。
しかし民間には、もっと多くの需要があるはずだ。
毛皮があれば、暖房がなくても暖かく過ごせるではないか。
北方だけではなく、広東以北は冬も寒い。
馬は交通手段だから、民間だってほしいではないか。
牛は耕作に必要だから、需要があるではないか。
明代、牛を食用に殺してはならない、という法律まである。
畑を耕してくれるありがたい牛さまを殺して食べるとは、もってのほか、というわけだ。
ちょうどこの時代、嘉靖年間の明代を背景としたテレビドラマ『大明王朝』でも
こんなせりふが出てくる。
「ちょうど某家の牛が、事故で崖から落ちて死んだそうだ」
牛肉が市場に出回るのは、事故死か自然死による以外は許されないというわけだ。
モンゴルの物産は、市場があるのに、自由に取引させてもらえない。
「貿易の自由化」を!
それがアルタン・ハーンの申し出であった。
経済封鎖している間、では明側の軍馬の調達はどうしていたのだろうか、という疑問がある。
当時の戦争に騎兵は欠かせない。
良質な軍馬を大量に確保することができなければ、モンゴルに勝つことはできない。
永楽7年(1409)、永楽帝は寧夏を鎮守する寧陽伯に
「官庫の絹・織物・現金を韃靼(=モンゴル)の馬と替えてよし」
と勅令を出している。
永楽帝はモンゴルへの大規模な戦争を幾度もしかけ、明の軍事的な立場を有利にした皇帝である。
戦争のために必要な大量の軍馬を確保するため、経済封鎖を一部解くこともやむを得ない、としたのだろう。
が、それも永楽年間に不定期(恐らくは戦争で急に多く必要となった時のみ)に開かれただけで
両国の経済に決定的な影響を及ぼすまでにはいかない規模で終わる。
やはり敵を倒すための軍馬を敵に依存するのは、あまりにも危険である。
明代前期の軍馬の供給は、主にチベットに頼っていた。
チベットは明の朝貢国となっており、敵対関係になかった。
そこでTao州(さんずいに兆。甘粛省臨夏。蘭州の西南。チベットとの境)、河州(同左)、西寧(青海省。チベットの北の入り口)で馬市を行い、
チベット族の馬を買い入れた。
明代、馬の調達と管理のために「馬政」なる行政系統が設けられ、その下に
行太僕寺、太僕寺、苑馬寺などの機関が設けられていた。
建国まもない洪武年間から、中央官庁の出先機関として、すでに陝西、甘涼(甘粛一帯)に行太僕寺を、
平涼(蘭州と西安の間)に苑馬寺を設け、軍馬の調達と管理を行っていた。
チベットから買い入れられた馬は、この傘下にある24の官営牧場で飼育され、
必要に応じて随時、甘粛、延sui(延安・楡林つまりは陝北の前線)、寧夏に送り込んだのである。
明初、このシステムで軍馬は充分に供給できていたらしい。
が、永楽年間以後、軍馬が足りない、と訴える奏文が次第に増えてくるようになる。
*****************************************************************************
メインストリートにある骨董屋さん。
陝西には、まだまださまざまな掘り出し物があり、北京の骨董商もこういうところへ来ては、
定期的に品物を仕入れているという。

横に並ぶ典型的な北方の四合院も風情がある。

万佛楼の門洞。

高さがあり、まさに「騎乗」のままですり抜けていける。

楼の中からも横に胡同が伸びていく。


骨董屋が公共スペースを占領しておりますぞ。
売り物の仏像を勝手に陳列。
どこかの古寺から買い取ってきたものでしょうか。
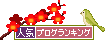

父親はダヤン・ハーンの三男バルス・ボラト・ジノン、その次男として生まれる。
前述のとおり、チンギス・ハーンの直系の子孫がすべて皆殺しにされた後、ダヤン・ハーンだけが正当な血筋を持つ人物となった。
ダヤン・ハーンは11人の息子たちをモンゴル各地の有力な部族の族長の元に婿入りさせた。
アルタン・ハーンの父親は、ダヤン・ハーンの三男、婿入りした先はトメト部、
領地の草原は、今でいう山西省の大同の北辺りからフフホトにかけての地域である。
モンゴルの中でも明朝の首都・北京に最も近い地域といえる。
アルタンは確かにダヤン・ハーンの孫ではあるが、ダヤンに11人もの息子がいたことを考えると、孫の数は100人近くいたに違いない。
その中でアルタンの優先順位はかなり低い。
アルタンは三男の子供であり、長男でさえなかった。
トメト部の部族長ファミリーの一員という程度の位置づけでしかない。
トメト部の部族長だった父親の位は「ジノン」、貴族的な地位をあらわす言葉の一つだ。
父親亡き後は兄グンビリク・モンゲンがジノンの位を継ぎ、アルタンは次男としてそれをサポートした。
しかししばらくして兄がなくなる。
それ以後、アルタンがトメト部を率いることになる。
かれは青台吉(チン・タイジ)、ハラハンなどの他のモンゴル勢力、
さらには塞外に割拠する漢人の高懐智、李天章などの勢力と連合し、数十万人の兵力を傘下に収めるようになる。
長城の外には、かなりの漢人「アウトロー」が法の届かない新天地を求めて入ってきていたらしい。
のちにアルタン・ハーンが建設するフフホトの町は、
そういった長城の中から入植してきた漢人の開墾した地区「板昇」の中心にある。
飢饉で食い詰めた農民のほかにも、国内で犯罪を犯し、逃亡してきた者、白蓮教一揆の指導者で
指名手配になっている者など雑多な漢人らが草原には多く存在したのである。
アルタンはそういったならず者の漢人集団も勢力に抱き込みつつ、実力を拡大し、
これを背景にダヤン・ハーンの嫡出後継者である「小王子」に圧力をかけた。
小王子は、最も継承順位の高いダヤン・ハーンの長男の長男の系統であり、
つまりはアルタンには、いとこに当たる。
小王子の勢力は、アルタンらに押され、ついには東のかなたに追いやられ、アルタンがハーンの位につくに至る。
アルタンがハーンになった時、明との貿易関係はとっくの昔に途切れていた。
明は国境に沿い、万里の長城を延々と建設している。
東は渤海湾に顔を突っ込むところまで長城を延長させた山海関から始まり、
西は甘粛の砂漠のかなたまで、行軍しやすい場所は、ほぼ長城で封鎖する。
このため長城の中と外にいる漢人と遊牧民の交易は、ごく小規模となる。
密貿易をこそこそとすることはできても、規模を大きくすることはできない。
どっさり荷を積んだ荷車を堂々と引いていけるような公道や谷間を通る関所を通ることができないからだ。
これでは、経済活動の質も量もごく限られた規模の中に制限されてしまう。
そもそも遊牧という形態は、自給自足ができないことはないが、やはりやや無理がある。
衣服からして麻、綿、絹を着ずに獣の皮だけでもいいではないか、ということも可能だが、
通気性、吸収性に悪い獣の皮より植物繊維の方が心地いいに決まっている。
一度着用してしまえば、それなしの生活に戻ることは、できるなら避けたいと思うようになるのが人情だろう。
穀物やお茶がなくても、乳製品と獣の肉だけで生きていけないこともないが、
炭水化物でエネルギー分を効率的に補い、お茶でビタミンを補給できれば、大きく健康状態を改善し、寿命も長くすることができる。
湯を沸かす鉄鍋を草原で自給できるわけもないし、漢人の持つ各種鉄器の武器に対抗するためには、
同レベルの鉄器は、最低限必要ともなる。
長期的に長城の外に閉め出されることは、今でいう経済封鎖であり、この状態が続けば、
命がけで南下してくるのは、生産構造からしてどうしても避けられない。
これをなんとか慰撫するため、朝貢という名の元に金品を与えることは、明初から行われてきた。
つまりは遊牧民側が属国であることを認め、臣下としての礼を尽くし、献上物を差し出す。
これに対して明が、数倍の返礼を下賜するという形で、経済的に懐柔しつつも、王朝としての面子を損なわないという構造である。
そのほかにも「互市」が開かれた。
しかし「互市」という名前にも関わらず、まったく「相互」関係ではなく、どちらかといえば、明の一方的な決まりに基づいていた。
開催期間、場所、入場人数、品目、売り値、取り引数のすべてが明側の一存で決められており、やはり「施し」のニュアンスが強く、対等ではない。
モンゴル側がもっとたくさん売りたい、高く売りたい、と思ってもできない。
馬だけと決められており、牛、羊を売りたいと思っても売れない、という形式である。
最も早い朝貢と「互市」は、永楽3年(1405)からウリャンハ三衛を相手に開かれた。
彼らだけが明に臣下の礼を取ることに甘んじ、服従の意を示したからである。
この当時モンゴルの他の部族は、ウリャンハを通してしか、中原との経済関係を得ることができなかった。
その後、徐々に他の部族も朝貢貿易に参加するようになるが、これにより利益を得たからといって
彼らが長城を超えて侵入・略奪をしないかといえば、そうでもなかった。
草原で優れたリーダーが出現し、統率力が高まれば武力に訴えて略奪を行い、
弱まれば、再びしばらくの間は朝貢だけに甘んじる、といったいたちごっこが繰り返された。
オイラトのエセン・ハーンの時代(正統年間=1440年代前後)には、遊牧民側の傍若無人ぶりが暴走して止まらない状態までいく。
朝貢貿易は行えば行うほど明側の出費が増えるので、明としては最低限の頻度と規模に抑えたい。
ところが、エセンはその規定を守らず、1年に一度と決められていたものを
「前の使節がまだ都を離れないうちに、次の使節が到着する」始末である。
そのほかにも使節の人数も大量に規定をオーバー、持ち込んだ産物は粗悪品であるなど
あまりにも目に余る行動をとる。
ついに我慢できなくなった明側が英宗の親征でモンゴル討伐に向かい、
逆に大敗して皇帝がモンゴル側の捕虜となってしまうのが、「土木の変」である。
数十万人の戦死者を出したといわれる大惨事が起きたにも関わらず、
その後も中原の物資がほしいエセンの譲歩により朝貢貿易は再開される。
ダヤン・ハーンの時代になっても一時は朝貢貿易が続けられたが、
再び朝貢の頻度、使節の人数など取り決めで明側ともめたため、完全に決裂、
それ以来、国交断絶のままアルタン・ハーンの時代に入った。
弘治年間(1488-1505)以来というから、アルタンが政権を把握した嘉靖初年(1521-)には
すでに30年以上の経済封鎖状態だったことになる。
その間の両者の交流といえば、密貿易と不定期にモンゴル側が組織する長城を超えた略奪活動のみである。
アルタン・ハーンも当初は略奪を行った。
嘉靖8年(1529)オルドスから楡林、寧夏に侵入し、周辺を荒らした。
佳県は楡林のすぐ南にあるので、まさにこの辺りである。
しかしダヤン・ハーン時代、政権が安定し、平和が長く続いた後、
モンゴル側も略奪というリスクの大きい方法ではなく、市場での取引という平和な形での
経済活動を望むようになってきていた。
モンゴル側も南下して漢人の村を襲い、略奪するが、自分たちも無傷ではいられない。
戦いで命を落とすかもしれないし、明側の報復もある。
ダヤン・ハーンのかの姉さん女房マンドフィ・ハトンもどうやらある時の明側の夜襲により命を落としたといわれる。
そこで嘉靖20年(1541)、アルタンは使者を出し、明側に正式な「互市」の開催を申し出た。
朝貢ではないことが重要だ。
朝貢はわざわざ都に出て行かなければならないだけでなく、使者団の人数、献上する物品の量、頻度まですべて制限されている。
市場原理を無視した、「施し」を目的をしているのだから、
取引が多いほど、明の朝廷にとっては迷惑な話なわけで、なるべく小さな規模に抑えたいと意図する。
もっと中原の物品を手に入れたいモンゴル側と押し問答になる、という昔からの伝統的な構図が続いていた。
「もっと取引させろ」、「いやだ」の押し問答である。
そうではなくて市場原理に則った、「施し」ではない、対等な取引がしたい、というのが、アルタンの主張だった。
朝廷はそんなに多くの毛皮も馬もいらないかもしれない。
モンゴル側から献上される物品は、市場に出回ることなく、
皇帝一家や朝廷の官僚たちの間で消費されるだけなので、その需要はたかがしれている。
しかし民間には、もっと多くの需要があるはずだ。
毛皮があれば、暖房がなくても暖かく過ごせるではないか。
北方だけではなく、広東以北は冬も寒い。
馬は交通手段だから、民間だってほしいではないか。
牛は耕作に必要だから、需要があるではないか。
明代、牛を食用に殺してはならない、という法律まである。
畑を耕してくれるありがたい牛さまを殺して食べるとは、もってのほか、というわけだ。
ちょうどこの時代、嘉靖年間の明代を背景としたテレビドラマ『大明王朝』でも
こんなせりふが出てくる。
「ちょうど某家の牛が、事故で崖から落ちて死んだそうだ」
牛肉が市場に出回るのは、事故死か自然死による以外は許されないというわけだ。
モンゴルの物産は、市場があるのに、自由に取引させてもらえない。
「貿易の自由化」を!
それがアルタン・ハーンの申し出であった。
経済封鎖している間、では明側の軍馬の調達はどうしていたのだろうか、という疑問がある。
当時の戦争に騎兵は欠かせない。
良質な軍馬を大量に確保することができなければ、モンゴルに勝つことはできない。
永楽7年(1409)、永楽帝は寧夏を鎮守する寧陽伯に
「官庫の絹・織物・現金を韃靼(=モンゴル)の馬と替えてよし」
と勅令を出している。
永楽帝はモンゴルへの大規模な戦争を幾度もしかけ、明の軍事的な立場を有利にした皇帝である。
戦争のために必要な大量の軍馬を確保するため、経済封鎖を一部解くこともやむを得ない、としたのだろう。
が、それも永楽年間に不定期(恐らくは戦争で急に多く必要となった時のみ)に開かれただけで
両国の経済に決定的な影響を及ぼすまでにはいかない規模で終わる。
やはり敵を倒すための軍馬を敵に依存するのは、あまりにも危険である。
明代前期の軍馬の供給は、主にチベットに頼っていた。
チベットは明の朝貢国となっており、敵対関係になかった。
そこでTao州(さんずいに兆。甘粛省臨夏。蘭州の西南。チベットとの境)、河州(同左)、西寧(青海省。チベットの北の入り口)で馬市を行い、
チベット族の馬を買い入れた。
明代、馬の調達と管理のために「馬政」なる行政系統が設けられ、その下に
行太僕寺、太僕寺、苑馬寺などの機関が設けられていた。
建国まもない洪武年間から、中央官庁の出先機関として、すでに陝西、甘涼(甘粛一帯)に行太僕寺を、
平涼(蘭州と西安の間)に苑馬寺を設け、軍馬の調達と管理を行っていた。
チベットから買い入れられた馬は、この傘下にある24の官営牧場で飼育され、
必要に応じて随時、甘粛、延sui(延安・楡林つまりは陝北の前線)、寧夏に送り込んだのである。
明初、このシステムで軍馬は充分に供給できていたらしい。
が、永楽年間以後、軍馬が足りない、と訴える奏文が次第に増えてくるようになる。
*****************************************************************************
メインストリートにある骨董屋さん。
陝西には、まだまださまざまな掘り出し物があり、北京の骨董商もこういうところへ来ては、
定期的に品物を仕入れているという。

横に並ぶ典型的な北方の四合院も風情がある。

万佛楼の門洞。

高さがあり、まさに「騎乗」のままですり抜けていける。

楼の中からも横に胡同が伸びていく。


骨董屋が公共スペースを占領しておりますぞ。
売り物の仏像を勝手に陳列。
どこかの古寺から買い取ってきたものでしょうか。



















北京の白雲観と佳県のそれとどのような位置づけになるのか気になっていたのですが、南宋の時代にモンゴル領の佳県に全真教の道灌を建て後に白雲観としたのでしょうかね。
ところで、今日から2006年香港で製作されたTVドラマ「天下第一」を見始めました。主演リーヤーポンということで見ることにしたのです。見て驚き。時代考証がまるでめちゃめちゃなんですね。
明の武宗正徳帝(朱厚照 在位1505年 - 1521年)の時代に柳生但馬守(寛永6年(1629年)3月に従五位下に叙位、但馬守に任官する。)が出てくるんですよ。
家紋が違うし、紋の付いている場所も違う。袴の下に中国の昔のズボンをはいているんです。
めちゃめちゃなのはそのほか多数です。
さすが中国! でも気にしないことにします。
何かの手違いで、知らせメールが届いておらず、気がつかずにすぎてしまいました。
佳県の白雲観に関しては、明代以前はただの山だったようです。
テレビドラマの時代考証、相変わらずなんでもありですね。これでも前よりはだいぶよくなってはいるのですが。。