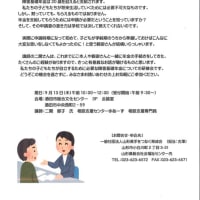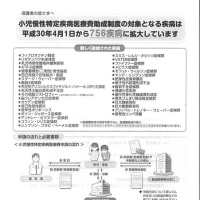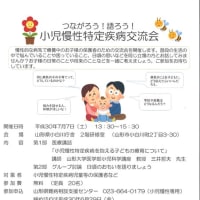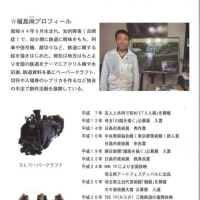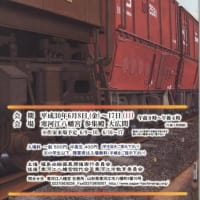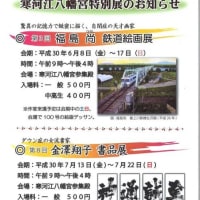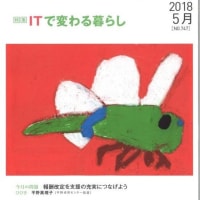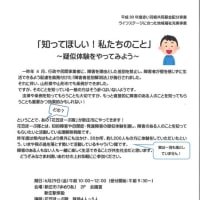日本発達障害福祉連盟から届いた
福祉連盟ニュースを見ていたら
なるほどな~と思うような記事がありました。
対人援助学の観点から障害のある子どもの「生命倫理」を考える
という 難しい題名がついていましたが・・・
難しい題名がついていましたが・・・
小見出しには
人はみな「他立」とありました



 (引用)
(引用)



「自立」という言葉が、しばしば個人の人生の
目標のように使われるが
この言葉は、曲者で、
ことさら「独りでできる」ことに
焦点化しすぎるきらいがある。
しかもこの「独りで」という目標は
障害がある個人について
とくに強調されるきらいがある。
一方「自律」という言葉がある。
これは、個別の当事者の
「自己決定」や「嗜好」であり
「(あなたの)望む選択肢の拡大」という
対人援助学で最も大切な
作業原則に関わる。
「立」と「律」を用いて
「人として望ましいありかたはどれか」と尋ねると
多くの人は「自立的自律」と答えるそうです。
「自律」(好きなことをする)は
「自立」(単独でできる)があってこそという捉え方だそうです。
「他立」ではダメかと問うと
「助けを借りる」場合、どうしても
助ける人の決定が「助けられる人」の決定と
混濁する可能性が生じる。
つまり「他立的他律」になってしまう。
という事のようです。
しかし、最悪なのは、そして往々にして
障害のある個人に押し付けてしまいがちな方針が
「自立的他律」つまり、独りで他人が決めたことをやる
という図式である。
対人援助学とは、簡単にいえば、
どうやって「他立」を前提にしながらも
「自律」を担保できるか、つまりは
「他立的自律」
(他者の援助や協力をもとに自分のやりたいことをする)
を、理念のみでなく具体的方法に至るまでを
様々な対人援助場面で追求しようというものである。


 (引用終わり)
(引用終わり)


読みながら、なるほどなるほど・・・
と、納得してしまいました。
育成会で広めている障害認識ワークショップのなかに
『可能性を見るために』という学習プログラムがあります。
「障害」を見る前に、
1人の人として「その人」を見ることが大切だと
教えてくれているプログラムです。
「できない」ことだけに目を向けるのではなく
「これ」があれば「できる・決定できる・生きられる」とか
本人の情報の理解力に応じた情報の提示をしよう。など
可能性を見るためのポイントに気づく事ができます。
これがまさに「他立的自律」ではないでしょうか。
育成会が作ったものですので、
基本的には親や、きょうだい向けですが
他県では、ワークショップに施設の支援員の方や
学校の先生などが参加されて開催した
という話も聞きました。
ともすると、私たち親は、親が決めた事に
本人を従わせようとするきらいがあります。
「他立的他律」ですよね・・・
もちろん本人にとって良かれと思って決めるのですが
本人の意見は無視・・・か、または
親が決めたことを選ぶように誘導してしまったりします。
人にはそれぞれ「自分流」があります。
そして知的障害がある場合には
「自分流」を追求しにくい状況がたくさんあります。
そのようなときには、支援を使って、本人なりの
「自分流」をサポートしてもらう。
という事がとても重要なのかもしれません。
親だけでは、目の前の事でいっぱいいっぱいになってしまい
本人の可能性に目が向かない事もあるかもしれません。
自分の子どもの状態を良く理解してくれ
適切な援助をしてくれる支援者がいれば
「他立的自律」
(他者の援助や協力をもとに自分のやりたいことをする)
「自分流」をサポートしてもらい自分らしく
生きられるようになるのだな~と感じました(F)
福祉連盟ニュースを見ていたら
なるほどな~と思うような記事がありました。
対人援助学の観点から障害のある子どもの「生命倫理」を考える
という
 難しい題名がついていましたが・・・
難しい題名がついていましたが・・・小見出しには
人はみな「他立」とありました



 (引用)
(引用)



「自立」という言葉が、しばしば個人の人生の
目標のように使われるが
この言葉は、曲者で、
ことさら「独りでできる」ことに
焦点化しすぎるきらいがある。
しかもこの「独りで」という目標は
障害がある個人について
とくに強調されるきらいがある。
一方「自律」という言葉がある。
これは、個別の当事者の
「自己決定」や「嗜好」であり
「(あなたの)望む選択肢の拡大」という
対人援助学で最も大切な
作業原則に関わる。
「立」と「律」を用いて
「人として望ましいありかたはどれか」と尋ねると
多くの人は「自立的自律」と答えるそうです。
「自律」(好きなことをする)は
「自立」(単独でできる)があってこそという捉え方だそうです。
「他立」ではダメかと問うと
「助けを借りる」場合、どうしても
助ける人の決定が「助けられる人」の決定と
混濁する可能性が生じる。
つまり「他立的他律」になってしまう。
という事のようです。
しかし、最悪なのは、そして往々にして
障害のある個人に押し付けてしまいがちな方針が
「自立的他律」つまり、独りで他人が決めたことをやる
という図式である。
対人援助学とは、簡単にいえば、
どうやって「他立」を前提にしながらも
「自律」を担保できるか、つまりは
「他立的自律」
(他者の援助や協力をもとに自分のやりたいことをする)
を、理念のみでなく具体的方法に至るまでを
様々な対人援助場面で追求しようというものである。


 (引用終わり)
(引用終わり)


読みながら、なるほどなるほど・・・
と、納得してしまいました。
育成会で広めている障害認識ワークショップのなかに
『可能性を見るために』という学習プログラムがあります。
「障害」を見る前に、
1人の人として「その人」を見ることが大切だと
教えてくれているプログラムです。
「できない」ことだけに目を向けるのではなく
「これ」があれば「できる・決定できる・生きられる」とか
本人の情報の理解力に応じた情報の提示をしよう。など
可能性を見るためのポイントに気づく事ができます。
これがまさに「他立的自律」ではないでしょうか。
育成会が作ったものですので、
基本的には親や、きょうだい向けですが
他県では、ワークショップに施設の支援員の方や
学校の先生などが参加されて開催した
という話も聞きました。
ともすると、私たち親は、親が決めた事に
本人を従わせようとするきらいがあります。
「他立的他律」ですよね・・・

もちろん本人にとって良かれと思って決めるのですが
本人の意見は無視・・・か、または
親が決めたことを選ぶように誘導してしまったりします。
人にはそれぞれ「自分流」があります。
そして知的障害がある場合には
「自分流」を追求しにくい状況がたくさんあります。
そのようなときには、支援を使って、本人なりの
「自分流」をサポートしてもらう。
という事がとても重要なのかもしれません。
親だけでは、目の前の事でいっぱいいっぱいになってしまい
本人の可能性に目が向かない事もあるかもしれません。
自分の子どもの状態を良く理解してくれ
適切な援助をしてくれる支援者がいれば
「他立的自律」
(他者の援助や協力をもとに自分のやりたいことをする)
「自分流」をサポートしてもらい自分らしく
生きられるようになるのだな~と感じました(F)