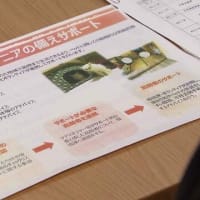病院へのペットの持ち込みを許可する病院が増加しているという記事がありました。
ただでさえ、病棟というのは暗いイメージがあり患者にとっては決して良い環境とはいえないでしょう。
残された命を大切にする環境というのはとても大切なことです。
ペットは癒しの心を持っています。
こういう病院がもっと増加することによって、ペットを大切にする風土が向上する相乗効果を期待したいものです。
ペットも一緒ホスピス増加 癒やし効果、医学的に注目
2010年11月6日(土) 産経新聞
末期がんなどの患者をケアする「ホスピス・緩和ケア病棟」で、ペットの持ち込みを許可する病院が全国的に増えている。
これまで病院では、感染症の恐れがあるとされ、ペットはご法度だったが、精神的な癒やしやストレスを和らげる医学的な効果の大きさに着目。
緩和ケアでは患者やその家族が鬱(うつ)状態に陥ることもあり、患者を力づける“家族”としての役割をペットが担っている。(北村理)
富士山を一望できる山梨県中央市の玉穂ふれあい診療所。
雄大な自然のもとで療養生活を送りたいと大阪や奈良などからも患者が来ている。
60代の夫妻は約4カ月間、愛犬のチワワと一緒に病室で療養生活を送った。
2人暮らしの夫妻がチワワを家族に迎えた直後に妻の病気が判明した。
夫(63)は「病院にペットなんてダメかと思ったら、いいというので驚いた。妻もそれで亡くなる最期まで気持ちが安定したと思います」と語る。
昭和48年、先駆的にホスピスを開業した淀川キリスト教病院(大阪市)では当初から一定の理解を示してきた。ホスピスは独立棟でないため、小さいペットはケージに入れて持ち込み、大きなペットは玄関での面会としている。
ホスピス専門病院「ピースハウス病院」(神奈川県)では、動物の苦手な患者に配慮して公共部分は利用できないが、大型犬なども各部屋が面した庭側のドアから出入りできるよう工夫する。
また先月18日にオープンした大阪府和泉市立病院の緩和ケア病棟でもペットの面会を検討しているという。同病院がんセンター長の福岡正博医師は「厳しい闘病を強いられる患者や家族の気持ちをどう緩和するのかも医療者の重要な仕事」としている。
こうした現象はペットの飼育人口が増加しているのも理由だが、ペットの医学的効用にも注目されている。
がん患者は病気の進行に伴い、意識混濁や幻覚など精神症状を伴う「せん妄」が起こる。
予防には病室を自宅の環境に近い状態にすることも重要であることが研究で明らかになり、緩和ケアでのペットの位置づけがさらに重要になっている。
情緒水準が高度な哺乳(ほにゅう)類との触れ合いは人間に内在するストレスを軽減させる効果が考えられ、医療の補助治療として近年世界で用いられている。
このため9月に緩和ケア病棟を増築オープンした和歌山県田辺市の南和歌山医療センターでは、これまでのペットの面会に加え、近くアニマルセラピーも実施する予定だ。
がん患者や家族の精神的ケアを専門にする埼玉医科大の大西秀樹教授(精神腫瘍(しゅよう)科)は「人間は五感を刺激すると精神的に安定する。がんの闘病は、家族の精神的負担も大きく鬱病などの診断がつくことも少なくない。患者が穏やかに過ごせれば、その家族の精神的ケアにとっても効果は大きく、ペットの持ち込みには大きな意味がある。今後もペットに理解のある病院は増えるだろう」と話している。