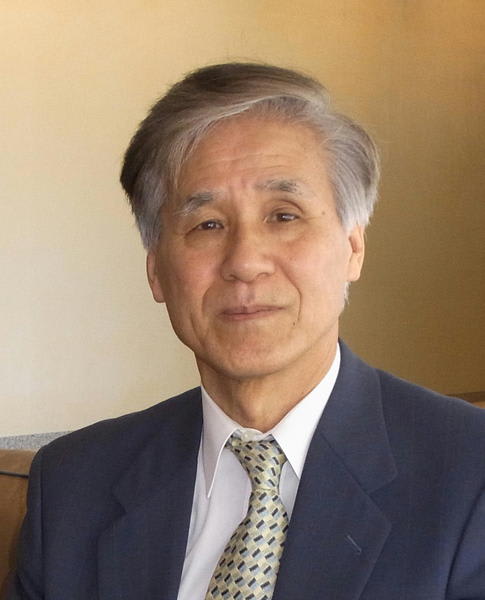『女性自身』が、女系天皇容認の記事を出している。
これを理論的根拠として使う女系天皇容認派も多いと推察されるので、コピー。
勿論、私はこれらのことは既に全て知っている。
知った上で、「天皇は男系男子でなければならない。」と考えているのですが、他の男系男子派を標榜する方々は、私以上に広く、深く、これらのことを知っておられるだろうと思います。
「男系限定は中国の模倣」女系天皇こそが日本の伝統である理由
2021年04月30日 11時00分 女性自身
今年1月、『女系天皇 天皇系譜の源流』(朝日新書)を上梓した大東文化大学名誉教授の工藤隆氏だ。その中で工藤氏は「男系と女系がないまぜとなった継承こそが本来のヤマト文化」だと主張しているのだ。いったい、どういうことなのだろうか? その根拠を工藤氏に解説してもらった(以下、「」内は工藤氏)。
「去年の8月、河野太郎防衛大臣(当時)がインターネット番組で『安定的な皇位継承に向け、父方が天皇の血を引かない女系天皇も検討すべきだ』と、踏み込んだ発言をしました。女系天皇容認論を時の大臣が公言したということで話題になったのですが、その河野氏ですら『我が国の皇室は、過去ずっと男系で継承されてきており』という前提で話しています。この認識がそもそも正確ではないのです。
男系での皇位継承が本格的に採用されたのはあくまでも西暦600年代以降です。当時、隆盛を誇っていた中国大陸の唐を手本に国家体制を整える中で、皇位継承についても唐を模倣して男系に限定されたと考えられます」
西暦600年代というと飛鳥時代にあたる。宮内庁のホームページにも掲載されている天皇系図では、初代の神武天皇が即位したのは紀元前660年の縄文時代とされているが、
「縄文、弥生など非常に古い時代にも天皇氏族が存在したかのように記述された天皇系譜は、『古事記』(712年)や『日本書紀』(720年)にまとめられているのですが、それらは700年代初頭の権力集団である天皇氏族が整理・編纂したものであり、客観性という点ではかなり疑わしいのです。
近年の研究では、そもそも『天皇』という称号が登場したのは600年代末、天武天皇、持統天皇の時代です。『古事記』や『日本書紀』で、初代・神武からすべての『大王(族長)』に『天皇』号を与えてしまったことによって、非常に古い時期から天皇氏族が存在していたかのような錯覚が生じています。
王(皇帝)が男系継承でかつ男性でなければならないというのは、もともと中国・漢民族由来の思想です。日本でも、500年代くらいから族長位継承は男系継承優位に傾いてはいたようですが、600年代末から700年代初頭、唐の国家体制を模倣するうちに、天皇につながる古い時代の大王(族長)の系譜も男系でまとめたほうがいいという観念が優位になり始めたのでしょう(男性でなければならないという部分は受け入れませんでしたが)。
そして、以後の皇位継承を男系に限定するだけでなく、それ以前の大王の系譜にも、おそらくはいくつかの創作や改変を加え、初代・神武から続く男系の天皇の系譜として『古事記』や『日本書紀』にまとめたのではないかと考えられます。綏靖(すいぜい)天皇(2代)、懿徳(いとく)天皇(4代)の系譜に残された女性始祖の痕跡や、継体天皇(26代)の系譜に見られる女系継承の痕跡などは、男系継承への整理作業から漏れ落ちた事例だと考えられます」
■日本には数多くの女性リーダーが存在した
それでは600年代以前、縄文・弥生から古墳時代に至る古い時代の族長位(皇位)継承は、どのようになされていたと考えられるのだろうか?
「当時の日本列島には、弥生時代の卑弥呼をはじめとして、数多くの女性リーダー(族長)が存在したらしいことは、『古事記』『日本書紀』『風土記』からわかります。九州から関東まで、何人もの女性族長の存在が伝承されています。また、同じ九州から関東までの地域で、被葬者が女性と推定される古墳が少なくとも18例はあるという考古学者の報告もあります。
族長位継承の実態については歴史的資料が乏しいものの、文化人類学的資料を参考にすれば、古い段階では男性の族長と女性の族長の両方が存在していたと考えられます。これも推測ですが、女性族長がいれば、女系継承もありえたでしょう。すなわち、600年代以前の族長位の継承は、男系と女系の両方がないまぜになっていたのではないかと推測されます。
『古事記』『日本書紀』の天皇系譜でも、推古天皇(在位592~628年)など、600年代以後にも女性族長(女性天皇)が珍しくありませんでした。やはり、男系と女系がないまぜになって継承されていた古くからの感覚が600年代以後にも生き続けていて、少なくとも女性天皇は可とする考えははっきりと維持されていたのでしょう」
701年には日本初の成文法である「大宝律令」が制定されて、その中の「継嗣令(けいしりょう)」には、皇族の世継ぎや婚姻についても規定されていた。
「《およそ天皇の兄弟と皇子を、皆親王とせよ》としたうえで、《女帝の子もまた同じ》という注がつけてあるのですが、女帝の子の父についての条件は書かれていません。この条文の解釈には諸説がありますが、私は、女帝の夫が男系の皇族ではない人だったとしても、つまり“女系”の子でも、皇位継承権のある親王になれるという共通認識が当時の権力者にあった可能性があると考えています。
その後、『古事記』や『日本書紀』がまとめられた奈良時代(710年~)には、皇位継承は男系重視に強く傾いていったのですが、それが明文化されることはありませんでした。女性天皇はもちろんのこととして、女系天皇も許容される余地がかすかに残されていたのだと思われます」
■ヤマト文化本来の姿に戻る時期が来た
女性天皇に限っていえば、実際、江戸時代(1603年~)にも、明正(めいしょう)天皇(109代、即位1629年)、後桜町(ごさくらまち)天皇(117代、即位1762年)という2人の女性天皇がいた。
「皇位継承の規定を『男系』ばかりか『男子』とまで明文化したのは、明治時代(1868年~)の大日本帝国憲法下で制定された旧皇室典範が初めてなのです」
天皇氏族が紀元前から存在し、その系譜が男系継承だけだったとする考え方が国家の法によって支持されたのは、明治時代以後のことである。それを踏まえたうえで、工藤氏は皇位継承問題についてこう提言する。
「現行の皇室典範にも規定されている“男系かつ男子継承絶対主義”に固執する限り、皇位継承の危機的状況から抜け出すことはできないでしょう。もともと日本列島のヤマト文化では、族長位(皇位)の継承にも男系と女系が併存していて、おそらく臨機応変に両者が使い分けられていたのだと思われます。
男系継承の強化は唐の皇帝制度の、日本古代国家整備の必要性に後押しされた模倣だったのであり、それに男子継承まで加えたのは西欧列強との対抗を意識した明治政府の選択だったのです。21世紀の近代国家日本では、そろそろその模倣の行き過ぎから脱して、ヤマト文化本来の姿に戻る時期が来たのではないでしょうか」
それぞれの項目、反論はあるが一つだけ。
「万世一系男系男子天皇の系譜」を幻想というのなら、
「ヤマト文化本来の姿」もまた幻想でしょう。
私は「万世一系」を事実と認識する人にも用心するが、「ヤマト文化本来の姿」を提唱する人にも用心する。
工藤 隆(くどう たかし、1942年4月7日 - )は、日本文学・演劇研究者、大東文化大学名誉教授。 栃木県宇都宮市生まれ。東京大学経済学部卒業、早稲田大学文学研究科大学院演劇専修修士課程修了、同博士課程単位取得退学。はじめ劇作家・演劇評論家、のち上代口承文芸の研究に移り、大東文化大学文学部教授。2013年退任。『歌垣の世界 歌垣文化圏の中の日本』で2015年度志田延義賞受賞。