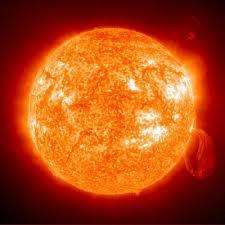こんにちは
小野派一刀流免許皆伝小平次です
小平次の妄想的歴史探訪
今回は
「渡来人とはナニモンだ?」
と題して妄想をお送りいたします
中学校の歴史教科書なんかを見てみますと
「紀元前4世紀頃、主に朝鮮半島から移り住んだ人たちによって稲作が伝えられ…」
などと書かれており、事実、遣唐使の廃止のころまでになるのでしょうか
百済や新羅、高句麗、歴代支那王朝から仏法の指導者であるとか、建築の技術者などなどの来日、帰化の記録が残っております
ではそのような文献的記録のない時代、弥生時代と言われるその時代、大陸から移り住んだ人たち、いわゆる
「渡来人」
ってな人たちはいったい「ナニモン」だったのでしょうか
小平次が子供のころ、歴史の授業でこの事を学んだ時のイメージとしては、何だか「石斧担いでゴゴーンゴーン♪」みたいな原始人が「ウッホ、ウッホ」と唸り声を上げていたような未開の野蛮な島であった日本に、それはそれは優しく手取り足取り、朝鮮半島からやってきたススンだ人達が文化文明、技術などを伝えたというような、そんな感じでしたよ
今でもそんなイメージを持っている人たちも多いんじゃないでしょうか
少なくともお隣の国ではそんな風に思っているようですし、教育もされているようなのであります
「主に朝鮮半島から移り住んだ人たちによって文化や技術が伝えられ…」
教科書なんかには実にさらりと書かれておりますが、小平次としては大変素朴な疑問があるのです
その人たちは一体何の得があって海を渡り、わざわざ日本に文化文明、技術を伝えにやって来たのだろうかということに対しての疑問です
少なくともこの時代、日本と大陸、双方で海を渡り行き来をしていたことは間違いないでしょう
航海技術も後世で考えているよりもずっと優れていた可能性もあります
半島の南端から九州までは、決して遠い距離ではないかもしれません
しかしながら、青森と函館の決して遠くはない距離を結んでいた青函連絡船「洞爺丸」の事故は昭和の出来事です
多数の犠牲者を出したセウォル号の転覆事故や、イタリアの大型客船コスタ・コンコルディアの座礁事故なんてつい最近のできごとです
現代の最新技術を持った船でさえ、自然条件、人的ミス、その他によって、多大な犠牲を払う事故を起こしているのです
漁船やその他の船の事故も含めれば、世界中で今も海難事故はしょっちゅう起きているのです

それが2千年以上前の航海、いかにその技術が優れていた可能性もあり、北九州と半島南端の距離は、今でこそ近いと言えたとしても、当時は命懸けの航海であったことに間違いはないでしょう
「主に朝鮮半島から移り住んだ人たちによって文化や技術が伝えられ…」
命を懸けてまで日本にやってきて文化や技術を伝える理由はなんでしょうか
そもそもが、何の見返りもないのに「文化や技術」、その他「何か」を伝える事だけを目的に命を懸ける人たちなんているんでしょうか
「命懸けで何かを伝える」
小平次には例えば後の「鑑真和上」のような強い信仰心を持った「宗教者」くらいしか思いつきません(鑑真和上も朝廷の招聘ですので見返りがなかったわけではないでしょうが…)

しかし弥生時代初期、そのような宗教者が大挙してやって来たような痕跡はもちろんありませんので
「何の見返りもないのに「文化や技術」、その他「何か」を伝える事だけを目的に命をかける人たち」
は、初期の「渡来人」からは外して良いように思います
ではどんな人たちであったのか
妄想してみましょう
初期の渡来人が
「何の見返りもないのに「文化や技術」、その他「何か」を伝える事だけを目的に命をかける人たち」
ではなかったのであれば
「命を懸けてでも日本に渡るしか生き残る道がなかった人たち」
か
「命を懸けてでも日本に渡れば大きな利益があると考えた人たち」
大別するとこんな感じですかね
どちらにしても「命懸け」の航海をして、ということは忘れてはなりません
まずは「命を懸けてでも日本に渡るしか生き残る道がなかった人たち」について妄想してみます
この時代、朝鮮半島にはまだまだ「国」と呼べるような集団もなく、日本に文化や技術を伝えることができるような状態ではなかったでしょう
そうなれば、当然その人たちは支那地域、大陸内部からやって来た人たちでしょう
弥生時代初期、支那地域はいわゆる「春秋戦国時代」、戦乱によって大変に乱れていた時代でありました

「長平の戦い」などにおける何十万人を生き埋め、なんて数字は大袈裟にしても、大陸や半島での戦乱において、残忍な虐殺や強姦などが常態であったことは否定できません
長い戦乱によって征服された国々の民や支配階級の人たちの一部は、おそらく命からがら朝鮮半島方面に逃げ込んだのかもしれません
特に身分の高い支配階級の人たちは、反逆の芽を摘むという意味で、一族郎党、地の果てまで追い詰められたかもしれません
最終的に逃げ場のなくなった人たちが、ついには海を越えて安全な日本に逃げ込んだ
言わば「難民」ですね
「難民」と言ってもこの時代、日本へ渡ることのできる船を手に入れることは、そう容易なことではなかったでしょう
さらにはそれを操船し、日本までの航海ができる技術者を雇うとなれば一層困難なことであったでしょう
そうなりますと、以前の「ボートピープル」のように、一か八か大海に乗り出し、運よく日本に辿り着いたような人たちもいたかもしれませんが、基本的には一般の戦乱難民には無理な話であったでしょう
「日本に渡ることのできる船と操船者」
それを手に入れることのできる難民、それは捕まれば確実に地獄が待っているであろう被征服地域のそれなりの身分の人たち、財力や人脈を兼ね備えた言わば
「高貴な難民」
が、「命を懸けてでも日本に渡る他、生きる道のなかった人たち」の中心であったのではないでしょうか
この人たちは、日本での生活も考え、自分たちの一族の他、領民のうち技術者なども引き連れ、それなりの船団を組んで脱出したのかもしれません
朝鮮半島南部に、この後日本の影響が色濃く残る痕跡が見つかっておりますが、すでにこの時代(小平次はもっと古くからと思っておりますが)多くの日本人が住んでいたかもしれません
そうなりますと、古代版杉浦千畝のような人が半島南部にいて、追っ手からかくまい、日本に逃がしていたなんて事があったりして…、まっ、妄想しすぎですね!
さて、次へ行きましょう
「命を懸けてでも日本に渡れば大きな利益があると考えた人たち」
とはどんな人たちだったのでしょうか
真っ先に思いつくのは「交易商人」のような人たち
長き戦乱の時代も終わり、秦の始皇帝によって支那地域が大規模に統一されます
その安定とともに、交易も活発化していったことでしょう
日本ブランドの翡翠の加工品や、漆の装飾品などは、ひょっとすれば高値で支那マーケットで取引され、それを求め行き来する人たちがいたのかもしれません
いずれにせよこの「命を懸けてでも日本に渡る他、生きる道のなかった人たち」や「命を懸けてでも日本に渡れば大きな利益があると考えた人たち」は、小平次の妄想のような難民や商人ではなかったかもしれませんが、文化や技術を伝えること自体を目的に海を渡ってきたわけではなく、双方の往来の中で、文化や技術が日本へ自然と伝わっていったのでしょう
さて、もう一つ考えてみたいと思います
「何の見返りもなく」
文化や技術を伝える事自体を目的に命懸けで海を渡って来た人などはいなかった、と先に申し上げましたが
「それなりの見返り」
があるからこそ、文化や技術を伝える事自体を目的に命懸けで海を渡って来た人たちはいたのではないかと思うのです
それは最初にも述べましたが、ずっと時代を下り、大和朝廷の時代になりますと、百済や新羅、高句麗や支那の王朝地域から多くの仏教の指導者やその他の技術者を招聘していることが記録に残っております
それに対しては当然「対価」が支払われたことでしょう
そしてこのことは、明治のころの日本によく似ております
西洋的近代化を急いだ明治政府は、多くの西洋人技術者や教師、学者などを「対価」をもって招聘し、学んだわけです
そしてある程度学び、あとは自分たちでやれるとなれば母国へお帰りいただいたわけですね
小平次は案外このようなことは、実は文献的資料のない時代、つまり弥生時代のある程度早い段階から起きていたのではないかと思うのです
そのためにはある程度の統一された集団(クニ)の存在があったのでは、ということが前提にはなると思いますが
さて
「渡来人とはナニモンだ?」
小平次の妄想的現時点での結論はですね
結局どんな理由にせよ、双方の往来があり、その中で自然と文化や技術が日本に伝わってきたのであろう、ということでして
とりたてて「渡来人」なる特別な一団が存在していたわけではないのかなと思うのです
明らかな「渡来人」というのは、日本側から「対価」をもって招聘した一部の人たち、ということなのではないでしょうか
しかしながら、伝わったのは文化や技術だけではなく、やがて住み着いた渡来系の人たちの大陸的価値観
つまりは、征服して支配する、という弱肉強食の価値観も持ち込まれてきたのでありましょう
それが前回申し上げたこと
戦闘方法が徐々に縄文期の「一人対数人」の形式から「集団対集団」の形式に変わっていったこと、この事実がまさにこの文化や技術の流入と時を同じくしていることはそれを物語っているのではないでしょうか
それまでの縄文期の「平和的に融合」する価値観と、大陸的、いや、日本以外の世界共通の価値観、「弱肉強食」の価値観との戦いがついに始まってしまったのです
「日本の歴史は国防の歴史」
私たちの先人の国防の戦いは、まさにここから始まったのであります
御免!
小野派一刀流免許皆伝小平次です
小平次の妄想的歴史探訪
今回は
「渡来人とはナニモンだ?」
と題して妄想をお送りいたします
中学校の歴史教科書なんかを見てみますと
「紀元前4世紀頃、主に朝鮮半島から移り住んだ人たちによって稲作が伝えられ…」
などと書かれており、事実、遣唐使の廃止のころまでになるのでしょうか
百済や新羅、高句麗、歴代支那王朝から仏法の指導者であるとか、建築の技術者などなどの来日、帰化の記録が残っております
ではそのような文献的記録のない時代、弥生時代と言われるその時代、大陸から移り住んだ人たち、いわゆる
「渡来人」
ってな人たちはいったい「ナニモン」だったのでしょうか
小平次が子供のころ、歴史の授業でこの事を学んだ時のイメージとしては、何だか「石斧担いでゴゴーンゴーン♪」みたいな原始人が「ウッホ、ウッホ」と唸り声を上げていたような未開の野蛮な島であった日本に、それはそれは優しく手取り足取り、朝鮮半島からやってきたススンだ人達が文化文明、技術などを伝えたというような、そんな感じでしたよ
今でもそんなイメージを持っている人たちも多いんじゃないでしょうか
少なくともお隣の国ではそんな風に思っているようですし、教育もされているようなのであります
「主に朝鮮半島から移り住んだ人たちによって文化や技術が伝えられ…」
教科書なんかには実にさらりと書かれておりますが、小平次としては大変素朴な疑問があるのです
その人たちは一体何の得があって海を渡り、わざわざ日本に文化文明、技術を伝えにやって来たのだろうかということに対しての疑問です
少なくともこの時代、日本と大陸、双方で海を渡り行き来をしていたことは間違いないでしょう
航海技術も後世で考えているよりもずっと優れていた可能性もあります
半島の南端から九州までは、決して遠い距離ではないかもしれません
しかしながら、青森と函館の決して遠くはない距離を結んでいた青函連絡船「洞爺丸」の事故は昭和の出来事です
多数の犠牲者を出したセウォル号の転覆事故や、イタリアの大型客船コスタ・コンコルディアの座礁事故なんてつい最近のできごとです
現代の最新技術を持った船でさえ、自然条件、人的ミス、その他によって、多大な犠牲を払う事故を起こしているのです
漁船やその他の船の事故も含めれば、世界中で今も海難事故はしょっちゅう起きているのです

それが2千年以上前の航海、いかにその技術が優れていた可能性もあり、北九州と半島南端の距離は、今でこそ近いと言えたとしても、当時は命懸けの航海であったことに間違いはないでしょう
「主に朝鮮半島から移り住んだ人たちによって文化や技術が伝えられ…」
命を懸けてまで日本にやってきて文化や技術を伝える理由はなんでしょうか
そもそもが、何の見返りもないのに「文化や技術」、その他「何か」を伝える事だけを目的に命を懸ける人たちなんているんでしょうか
「命懸けで何かを伝える」
小平次には例えば後の「鑑真和上」のような強い信仰心を持った「宗教者」くらいしか思いつきません(鑑真和上も朝廷の招聘ですので見返りがなかったわけではないでしょうが…)

しかし弥生時代初期、そのような宗教者が大挙してやって来たような痕跡はもちろんありませんので
「何の見返りもないのに「文化や技術」、その他「何か」を伝える事だけを目的に命をかける人たち」
は、初期の「渡来人」からは外して良いように思います
ではどんな人たちであったのか
妄想してみましょう
初期の渡来人が
「何の見返りもないのに「文化や技術」、その他「何か」を伝える事だけを目的に命をかける人たち」
ではなかったのであれば
「命を懸けてでも日本に渡るしか生き残る道がなかった人たち」
か
「命を懸けてでも日本に渡れば大きな利益があると考えた人たち」
大別するとこんな感じですかね
どちらにしても「命懸け」の航海をして、ということは忘れてはなりません
まずは「命を懸けてでも日本に渡るしか生き残る道がなかった人たち」について妄想してみます
この時代、朝鮮半島にはまだまだ「国」と呼べるような集団もなく、日本に文化や技術を伝えることができるような状態ではなかったでしょう
そうなれば、当然その人たちは支那地域、大陸内部からやって来た人たちでしょう
弥生時代初期、支那地域はいわゆる「春秋戦国時代」、戦乱によって大変に乱れていた時代でありました

「長平の戦い」などにおける何十万人を生き埋め、なんて数字は大袈裟にしても、大陸や半島での戦乱において、残忍な虐殺や強姦などが常態であったことは否定できません
長い戦乱によって征服された国々の民や支配階級の人たちの一部は、おそらく命からがら朝鮮半島方面に逃げ込んだのかもしれません
特に身分の高い支配階級の人たちは、反逆の芽を摘むという意味で、一族郎党、地の果てまで追い詰められたかもしれません
最終的に逃げ場のなくなった人たちが、ついには海を越えて安全な日本に逃げ込んだ
言わば「難民」ですね
「難民」と言ってもこの時代、日本へ渡ることのできる船を手に入れることは、そう容易なことではなかったでしょう
さらにはそれを操船し、日本までの航海ができる技術者を雇うとなれば一層困難なことであったでしょう
そうなりますと、以前の「ボートピープル」のように、一か八か大海に乗り出し、運よく日本に辿り着いたような人たちもいたかもしれませんが、基本的には一般の戦乱難民には無理な話であったでしょう
「日本に渡ることのできる船と操船者」
それを手に入れることのできる難民、それは捕まれば確実に地獄が待っているであろう被征服地域のそれなりの身分の人たち、財力や人脈を兼ね備えた言わば
「高貴な難民」
が、「命を懸けてでも日本に渡る他、生きる道のなかった人たち」の中心であったのではないでしょうか
この人たちは、日本での生活も考え、自分たちの一族の他、領民のうち技術者なども引き連れ、それなりの船団を組んで脱出したのかもしれません
朝鮮半島南部に、この後日本の影響が色濃く残る痕跡が見つかっておりますが、すでにこの時代(小平次はもっと古くからと思っておりますが)多くの日本人が住んでいたかもしれません
そうなりますと、古代版杉浦千畝のような人が半島南部にいて、追っ手からかくまい、日本に逃がしていたなんて事があったりして…、まっ、妄想しすぎですね!
さて、次へ行きましょう
「命を懸けてでも日本に渡れば大きな利益があると考えた人たち」
とはどんな人たちだったのでしょうか
真っ先に思いつくのは「交易商人」のような人たち
長き戦乱の時代も終わり、秦の始皇帝によって支那地域が大規模に統一されます
その安定とともに、交易も活発化していったことでしょう
日本ブランドの翡翠の加工品や、漆の装飾品などは、ひょっとすれば高値で支那マーケットで取引され、それを求め行き来する人たちがいたのかもしれません
いずれにせよこの「命を懸けてでも日本に渡る他、生きる道のなかった人たち」や「命を懸けてでも日本に渡れば大きな利益があると考えた人たち」は、小平次の妄想のような難民や商人ではなかったかもしれませんが、文化や技術を伝えること自体を目的に海を渡ってきたわけではなく、双方の往来の中で、文化や技術が日本へ自然と伝わっていったのでしょう
さて、もう一つ考えてみたいと思います
「何の見返りもなく」
文化や技術を伝える事自体を目的に命懸けで海を渡って来た人などはいなかった、と先に申し上げましたが
「それなりの見返り」
があるからこそ、文化や技術を伝える事自体を目的に命懸けで海を渡って来た人たちはいたのではないかと思うのです
それは最初にも述べましたが、ずっと時代を下り、大和朝廷の時代になりますと、百済や新羅、高句麗や支那の王朝地域から多くの仏教の指導者やその他の技術者を招聘していることが記録に残っております
それに対しては当然「対価」が支払われたことでしょう
そしてこのことは、明治のころの日本によく似ております
西洋的近代化を急いだ明治政府は、多くの西洋人技術者や教師、学者などを「対価」をもって招聘し、学んだわけです
そしてある程度学び、あとは自分たちでやれるとなれば母国へお帰りいただいたわけですね
小平次は案外このようなことは、実は文献的資料のない時代、つまり弥生時代のある程度早い段階から起きていたのではないかと思うのです
そのためにはある程度の統一された集団(クニ)の存在があったのでは、ということが前提にはなると思いますが
さて
「渡来人とはナニモンだ?」
小平次の妄想的現時点での結論はですね
結局どんな理由にせよ、双方の往来があり、その中で自然と文化や技術が日本に伝わってきたのであろう、ということでして
とりたてて「渡来人」なる特別な一団が存在していたわけではないのかなと思うのです
明らかな「渡来人」というのは、日本側から「対価」をもって招聘した一部の人たち、ということなのではないでしょうか
しかしながら、伝わったのは文化や技術だけではなく、やがて住み着いた渡来系の人たちの大陸的価値観
つまりは、征服して支配する、という弱肉強食の価値観も持ち込まれてきたのでありましょう
それが前回申し上げたこと
戦闘方法が徐々に縄文期の「一人対数人」の形式から「集団対集団」の形式に変わっていったこと、この事実がまさにこの文化や技術の流入と時を同じくしていることはそれを物語っているのではないでしょうか
それまでの縄文期の「平和的に融合」する価値観と、大陸的、いや、日本以外の世界共通の価値観、「弱肉強食」の価値観との戦いがついに始まってしまったのです
「日本の歴史は国防の歴史」
私たちの先人の国防の戦いは、まさにここから始まったのであります
御免!