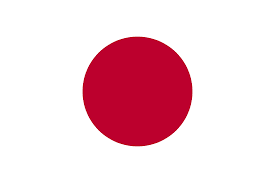
新年明けましておめでとうございます
本年もまた、宜しくお願い申し上げます
当記事は、加筆訂正をしようとしたところ、誤操作をしたため、一括で削除されてしまいました(泣) 復元もかなわず…
そのままにしていてもよかったのですが、コメントを下さった方もいらっしゃるので一先ず、同じことは書けませんので、要約して公開させていただきます
なぜ、自分がブログを書くのか
それは当たり前のことですが、自身の内心、感情を発信したいからにほかなりません
特に時事や歴史について書くときは、今の日本の状況を憂う気持ちからだと思います
小平次よりも、今の日本の現状を憂い、もっと理論的にブログなどで多くの人が発信しているにも関わらず、一向に日本の状況は良くならないどころか悪くなっている
それでも、たとえ主義主張が異なれど、根っこの価値観を共有できるのであれば互いに啓発しあいながら少しでも前に進んで行けるのではないか
しかしながら、やはり微力であることに間違いなく、世の中を変えるには政治的な力が必要、にも関わらず、国政、地方問わず選挙の投票率は若年層を中心に低いままであり、これではどうにもならない
で下記サイト
投票率を上げるために「各人の意識を変える」のはどうやら無理。ではどうするか
若年層の投票率が低いのは、政治に無関心の言うよりも
『よくわからない』
という、より素朴な理由であり、無理に上目線で選挙へ行け!、とやってしまうと、何か宗教のように感じ、押し付けられている、と感じてしまうそうです
「選挙が周りで話題になったこともなく、教えてもらったこともなく、新聞をよむ習慣もなく、テレビニュースを見る習慣もない」という環境にずっと身を置いてきた人たちだから
つまりは環境の問題が大きいようです
上記サイトに、良し悪しは別として、若者を選挙へ行かせ、投票率を上げるためのアイデアが出ています
日本人には効果的な方法かもしれません
日本人は、他人に迷惑をかける、とか、逆に人のためになる、と言ったことの方が、自分自身のため、よりも行動の基準になり得る、ということが実験でわかっているそうです
そういった特性も選挙の投票率を上げるのに役立つかもしれません
小平次は今、毎月1回、地域の大学生数人と、それぞれ持ち回りでテーマを決め、皆の前でプレゼンをしてもらい、その後それについてみなで考える会を主催しています
前々回、小平次が担当、江戸時代の農民の暮らしぶりについて語りました
理系学生君は、歴史の勉強は暗記ばかりでつまらない、と言ってましたが、小平次がある時点での米の収穫量、年貢の量、人口などのデータに基づきその暮らしぶりについて話しますと、大変興味を持ってくれて、これまでの圧政の中、搾取され、重税にあえいでいたイメージとはまるで別の江戸時代の農民の姿が浮き上がったと言い、質問や自分の想像も語ってくれました
今年の小平次の目標は、このような実生活の中で若者たちと語り、決して押し付けにならないよう、自分自身の感性で選挙へ行く重要性を感じてもらえるよう手助けをすることです
以上が、令和2年1月5日に投稿した記事の概要です 加筆訂正しようとしていた部分もあり、最初の記事とは少し違い、あくまで概要を述べただけですので、当初コメント頂いた方や、応援ボタンを押して頂いた方には失礼なことをしてしまい、深くお詫び申し上げます
本年も何卒宜しくお願い申し上げます
御免!

















