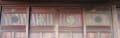紅葉真っ盛りの都内、少し早起きをして神宮外苑の銀杏の黄葉を
確認するため、勤労感謝の日の振替休日の11月24日に伺ってみた。
既に紅葉は始まっていたものの半分ほどは緑色の葉が目立ち、あと
1週間から十日程の時の経過がほしいところだ。
外苑を後に、中野の街を巡ろうと移動した。
最初に訪れたのは、中野区役所のエントランスにある「中野の犬
屋敷跡」。犬屋敷は、5代将軍綱吉が設置した幕府の野犬保護施設
で「お囲い御用屋敷」とも呼ばれていた。よって中野4丁目辺りの
旧町名は“囲町”である。
「生類憐れみの令」によって作られた犬屋敷は、元禄8年(1695)
頃開始され、綱吉が死去する宝永6年(1709)に廃止するまで15
年間存続した。敷地は現在の区役所を中心に約30万坪におよび、最
盛期には8万数千頭の犬が飼育されていた。飼料費だけでも年間9万
8千両(1両20万円と換算すると)という莫大な費用がかかってい
る。犬屋敷のもろもろの維持費は、幕府の国庫からではなく、商家や
天領の農民たちから摂取されたそうだ。
(中野区中野4丁目8番地辺り)
外苑銀杏_11_24 サンプラザの鈴時計
確認するため、勤労感謝の日の振替休日の11月24日に伺ってみた。
既に紅葉は始まっていたものの半分ほどは緑色の葉が目立ち、あと
1週間から十日程の時の経過がほしいところだ。
外苑を後に、中野の街を巡ろうと移動した。
最初に訪れたのは、中野区役所のエントランスにある「中野の犬
屋敷跡」。犬屋敷は、5代将軍綱吉が設置した幕府の野犬保護施設
で「お囲い御用屋敷」とも呼ばれていた。よって中野4丁目辺りの
旧町名は“囲町”である。
「生類憐れみの令」によって作られた犬屋敷は、元禄8年(1695)
頃開始され、綱吉が死去する宝永6年(1709)に廃止するまで15
年間存続した。敷地は現在の区役所を中心に約30万坪におよび、最
盛期には8万数千頭の犬が飼育されていた。飼料費だけでも年間9万
8千両(1両20万円と換算すると)という莫大な費用がかかってい
る。犬屋敷のもろもろの維持費は、幕府の国庫からではなく、商家や
天領の農民たちから摂取されたそうだ。
(中野区中野4丁目8番地辺り)
外苑銀杏_11_24 サンプラザの鈴時計