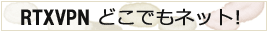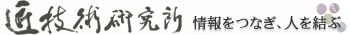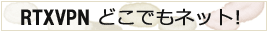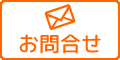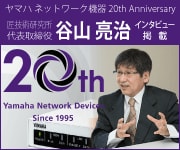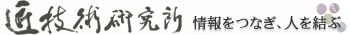
OpenSolaris 2009.06を最新開発版132にアップデート
こんにちは。匠技術研究所の谷山 亮治です。
OpenSolaris 2009.06を2010.02 Preview build 132にコマンドで、アップデートしました。
更新するOpenSolarisにssh接続してpkgコマンドでアップデートを実施します。
以下の方法は「正式リリース前の最新版へのアップデート」です。正式リリース前版には不具合もあります。アップデートには十分注意してください。
!!!!!!!
このアップデートを実施すると、SSHログインできなくなります。アップデートを完了し、再起動後のSSH接続前に、以下の行のコマンドの事前実行が必要です。十分ご注意ください。
手元のLinux等のsshコマンドで、
$ ssh -l takumi 192.168.0.148 "pfexec chmod 666 /dev/ptmx"
!!!!!!!
1.リポジトリを「開発版」にセットする
$ pfexec pkg set-publisher -O http://pkg.opensolaris.org/dev opensolaris.org
2.パッケージマネージャを更新する
$ pfexec pkg install SUNWipkg
このイメージで使用可能な更新は存在しません。
(*)これで正常です。
3.イメージアップデートを実行する
$ pfexec pkg image-update
DOWNLOAD PKGS FILES XFER (MB)
SUNWgtk2 50/742 4348/61963 82.73/854.86
(*)イメージアップデートでは855MBの更新ファイルがあります。コーヒーでも飲んで待ちます。
(*)イメージアップデートが終わると以下のメッセージが出ます。詳細は実行した環境で異なります。
opensolaris-5 のクローンが存在しており、それが更新およびアクティブ化されました。
次回リブート時にはブート環境 opensolaris-6 が「/」にマウントされます。
準備が整ったらリブートしてこの更新済みの BE に切り替えてください。
---------------------------------------------------------------------------
注: 次の場所で公開されているリリースノートを確認してください:
http://opensolaris.org/os/project/indiana/resources/relnotes/200906/x86/
---------------------------------------------------------------------------
4.再起動して新しい環境を起動する
$ pfexec reboot
手元のLinuxからsshで再接続します。
build 132では接続できないので、この記事の冒頭のコマンドを実施します。
$ uname -a
SunOS vlabgreen 5.11 snv_132 i86pc i386 i86pc Solaris
そういえば、zoneはどうなっているでしょうか。
$ pfexec zoneadm list -vc
ID NAME STATUS PATH BRAND IP
0 global running / ipkg shared
4 zfs00c running /rpool/zones/zfs00c ipkg shared
- test-zone installed /rpool/zones/test-zone ipkg shared
- zfs00 installed /rpool/zones/zfs00 ipkg shared
$ pfexec zoneadm -z test-zone boot
$ pfexec zlogin -C test-zone
[Connected to zone 'test-zone' console]
num1 console login: root
Password:
Last login: Tue Feb 9 23:30:38 on pts/4
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.11 snv_111b November 2008
root@num1:~# uname -a
SunOS num1 5.11 snv_132 i86pc i386 i86pc
root@num1:~#
ログイン時のバナーは古いカーネルを示していますが、uname -aの出力は新しいカーネルになっています。
このブログのOracleの関連記事へ
このブログのSUNの関連記事へ
このブログのLinuxの関連記事へ
このブログのSolaris/OpenSolarisの関連記事へ
企業・団体のオープンソース活用のご相談はこちら
匠技術研究所はこちら