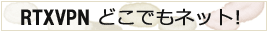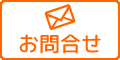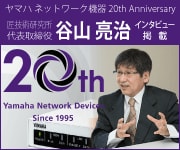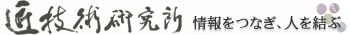
Red Hat Enterprise Linux 7(RHEL7)が正式リリース
こんにちは。匠技術研究所の谷山 亮治です。
今日は、サーバー系OSとして普及しているRed Hat Enterprise Linux 7(RHEL7)が正式リリースとなったことを紹介します。
2014年6月10日にRed Hat Enteroprise Linux 7がリリースされました。2024年6月30日までの長期間のサポートが受けられます。正規購入品であれば、バージョンアップを含めサポートを受けることができます。サポート無の販売はありません。
RHEL 7の大きな変更点は、以下のとおりです。Fedora19と20を基本として、その他の変更を行って開発されました。
1.Kernel 3.10.0-123
2.起動管理フレームワークをinitからsystemdに変更
3.Dockerコンテナ型仮想サーバーフレームワークを標準採用
4.XFSをext4の代わりに標準ファイルシステムに採用
5.MariaDBをMySQLの代わりに標準DBに採用
各バージョンのリリース日、最終アップデートリリース日、最終カーネルの関係は以下のとおりです。
RHEL 7:2014年6月9日GA/3.10.0-123
RHEL 6:2010年11月9日GA/2013年11月21日update 5/2.6.32-431
RHEL 5:2007年3月15日GA/2013年10月1日update 10/2.6.18-371
RHEL 4:2005年2月15日GA/2011年2月16日update 9/2.6.9-100
RHEL 3:2003年10月22日GA/2007年6月20日update 9/2.4.21-50
上記で分かるとおり、RHEL 4から6まではKernel2.6系でした。この系統のカーネルで10年間続けており、エンタープライズ用途であることから、安定性を重視してきたことが良く現れています。
RHEL 7はKernel3.1系統に更新されたことで、これから10年に向けたリリースと言えます。










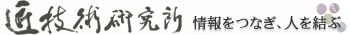


 ヤマハルーター @takuminews
ヤマハルーター @takuminews