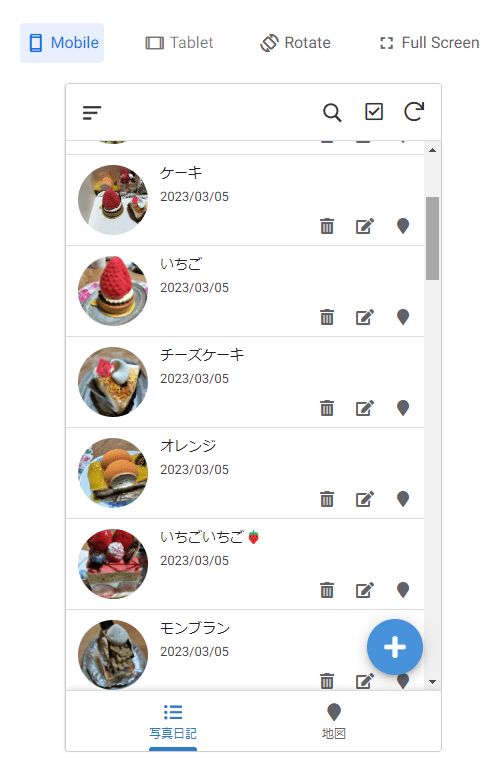

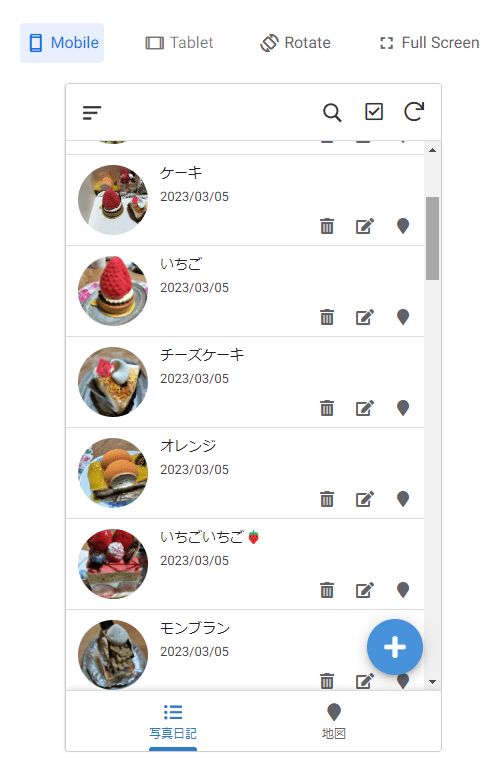


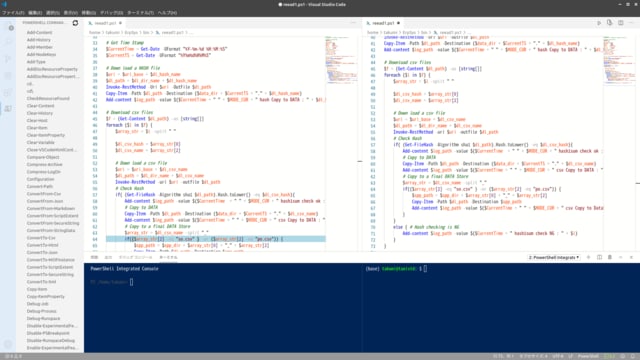
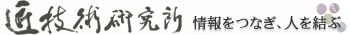
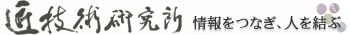
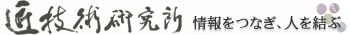

MVNOスマホでテザリングに切り替えて、投稿中。3G接続ですがSNSのネット接続では、全く問題ありません。快適です。
連休も、二日目が終わろうとしています。今日明日は、家内不在につき、若干の家事にも取り組みました。チャキチャキと進まないのですね。これが。
明日は、東京駅から秋葉原駅で子供の用事と、私の用事を済ませます。子供が大きくなって、行動がバラバラです。
「匠のIPネットワークの通信障害対応演習-入門編」を2015年8月15日(土)開催で計画中です。休み明けにヤマハ通信技術スクールのHPで情報を公開します。この講座はLinuxを使ってIP通信網の障害対応を行います。先ずは、環境作りと基礎固めを目指して演習します。...
zabbixで社内のルーター間通信の確認のために運用を開始しました。早速夜になってPing応答時間が長くなった経路を発見。やっぱり、自動監視は便利です。
レイバンからの投稿の件、皆様ごめんなさい。ご迷惑をお掛けしました。先ほどパスワードのリセットを行いましたが、他に対処すべきことがあれば、教えていただければ助かります。引き続き、よろしくお願いします。
レイバンからの投稿の件、ご迷惑をお掛けしました。パスワードのリセット,アプリ連携確認、投稿の削除を行いました。他に対処すべきことがあれば、教えていただければ助かります。引き続き、よろしくお願いします。
「"Ubuntu MATE for the Raspberry Pi 2"が公開されています」 goo.gl/U25SZs
今日は、最後に「痛いこと」をしてしまった。人差し指と中指の根本付近にポットの熱湯を注いでしまったのです。たいへんな熱さで、思わず飛び上がりました。家に戻り、保冷剤で一時間くらい冷やしたところで、痛みが軽減しています。ふ~っ。ふ~っ。です。