第2章 今見るべき価値が最も高いドラマとは
第3章 アメリカのTVドラマの歴史
第4章 日本における海外ドラマの歴史
第5章 面白い海外ドラマの見つけ方・楽しみ方
第6章 架空のドラマ作りを通じて理解するアメリカTV業界用語集
第7章 これからの海外ドラマ




2018.11.8朝日新聞、マイケル・ムーア監督、インタビュー記事
「民主主義というのは、国民が参加してこそ守られるのです。もし国民が民主主義に参加するのをやめたり、人々が何が起きているのか理解できないくらいのレベルに下げられたりすると、揺らぎかねないのです。学校の機能が衰え、図書館は閉鎖される。メディアは大企業に買収され、きちんとした仕事をして居る記者がどんどん少なくなっています」
民主主義というのは、基本、手間がかかって効率が悪い。
手間がかからず効率がいいのは、独裁主義。
そこのところを考える必要がある。
手間と時間を惜しんではいけない、と。

「消費大陸アジア 巨大市場を読みとく」川端基夫
P30
ポカリスエットについて、
スポーツドリンクのイメージがあるが、正しくは発汗で失われた水分とイオンを補給する飲料であり、大塚製薬が医療機関向けに製造販売してきた点滴剤の製造ノウハウをベースにした飲料水である。
大塚製薬がインドネシア市場でポカリスエットを販売し始めたのは1989年のことであった。
ところが全く売れなかった。
インドネシア人は熱帯の気候下でスポーツに汗を流そうと思わないし、湯に浸かる習慣もない。
よって、風呂上がりに飲むこともない。
酒が禁じられたイスラム教徒なので二日酔いになることもない。
値段も他の競飲料より3-5割高額。
故に、さっぱり売れなかった。
2004年大塚製薬ににとって大きな転機が訪れる。
デング熱の大流行であった。
デング熱時の水分補給剤として広く認知されたのである。
地道な医療機関へのマーケティングが、功を奏したのだ。
その後、イスラム教の「ラマダン明けの乾きを癒やす」に、マーケッティングをシフトする。
当初、現地宗教に関わるデリケートな部分にマーケティングをかけることに戸惑いがあったようだが、現地営業スタッフの後押しもあり、2005年からラマダン明け脱水シーンへの働きかけを行った結果、飛ぶように売れ出したのだ!
スポーツ飲料→デング熱の渇き→ラマダン明け
P37
一気に二億人の消費者にとって大きな価値を持つ商品に変貌したのである。
このように、プロジェクトX、アジア・ビジネス戦士篇のような話が詰まっている。
吉野家の牛丼の話(P42)など興味深い。
また、ラーメンは麺と思っている日本人には「ラーメンはスープだ」と意味づけされる話も面白い。(P68)
日本に行ったら買わねばならない12の神薬
【ネット上の紹介】
増加する訪日観光客、喧伝される中間層の増加、進出が続く日本のメーカーや飲食店…アジアの市場・消費が注目されてから久しいが、その重要性はますます高まってきている。中国、台湾、タイ、ベトナム、インドネシアなどアジア各国で長年調査してきた著者が、各地に進出した日本企業の成功と失敗の豊富な事例から、その成否を左右するアジア市場固有の論理を読みとく。日本企業の海外展開や訪日観光客誘致のポイントを知りたい人はもちろん、アジアの地理や文化に関心がある人も必読の一冊!
序章 世界は意味と価値のモザイク
第1章 ポカリスエットはなぜインドネシアで人気なのか?―「意味」と「価値」の地域差
第2章 ドラッグストアに中国人観光客が集まる理由―「意味」と「価値」を生み出す社会の仕組み
第3章 意味づけを決める市場のコンテキスト―日本人が知らない「脈絡」
第4章 アジアの中間層市場―意味づけと市場拡大
終章 アジア市場の論理―市場のコンテキストに迫るために
ブレグジットという言葉がある。Brexit、Britain+exitである。
2016年、国民投票では僅差で英国はEU離脱となった。
この背景と、その後をリポートした作品。
また、トランプ現象とEU離脱は、同じポピュリズムの流れで論じられたが、それってどうなの?
Bregret=ブレグジット+Regret(後悔)というけど、彼らは離脱を後悔してるの?
気になる案件を分かりやすく解説。
P23
英国のブレグジットが、「労働者たちの反乱」といわれるほど、労働者階級の人々に支持されたのに対し、米国のトランプ大統領は、じつは貧しい層には支持されなかったことが明らかになっているのだ。
P28
彼ら(英国労働者階級)はトランプを支持した米国の人々とは異なり、政治の経験も乏しいのに奇抜な政策を唱えるような人物を国のトップにするようなリスク・テイカーではないのだ。
P59
『ワイフ・スアップ』は、2004年から2013年までのあいだ、チャンネル4で放送された人気シリーズで、実在するリアルな2つの家庭の母親を入れ替えて、1週間生活させてみるというリアリティー番組である。(中略)
それが4年ぶりに、単発特別番組として『ブレグジット・スペシャル』を放送したのだ。(これは興味深い。日本でもテーマを変えてやってみてはどう?モニタリングやドッキリなんかより、よっぽど面白いんじゃない?)
P172
第一次大戦が始まると、中流・上流の家庭から、召使いたちがいなくなった。若い女性たちが軍需工場に集められたからだ。
P173
戦時中に軍需工業で働いた女性たちは、戦争が終わっても召使いの仕事に戻りたがらなかった。工場で働く女性たちは、メイドを自分たちよりも劣る存在と見なしていたし、第一次世界大戦は、若い労働者階級の女性たちにとって、階級社会の不平等を切実に考える機会となったのだった。(ちなみに「エマ」は19世紀末が舞台。メイドになるかガヴァネスになるか…選択は少ない→「奇跡的めぐりあわせ」 http://bbkids.cocolog-nifty.com/bbkids/2009/11/post-d027.html#more)
EU離脱の原因は何?
P273
日本の多くの人々は、「欧州の危険な右傾化」と「ポピュリズムの台頭」が原因であるというところで止まってしまい、「緊縮が理由などと書くのは、右傾化した労働者階級を擁護することになり、レイシスト的だ」と苦情のメールが来た。
P186
1928年の第5回選挙法改正で、ついに21歳以上のすべての女性に選挙権が与えられたのである。(1918年の改正では、30歳以上の納税している女性にしか選挙権が与えられなかった)。(選挙権はともかく、被選挙権って私のような者でも立候補できる…通らないけど。これってどうなの?って思う。日本国憲法を理解し、法律、歴史、経済…それなりの知識は、政治家に必要と思う。共通一次じゃないけど、試験をして、その点数を選挙ポスターに記載するくらいの措置をしてもいいんじゃない?)
【蛇足】
英国には愛憎相半ばするものがある。
好きかと聞かれて、素直になれない。
英文学、ブリティッシュロックは、好きなので影響を受けた。
けれど、世界史を見ると、どうだろう?
中東、アフリカ、アジアで彼らがしたことは。
植民地の宗主国として彼らはどうだったのか。
イギリス人がいなかったら、もう少し平和だったのでは?と思ってしまう。
でも、これを極めていくと、地球にとって人類ってどうなの?って話になるのでキリが無い。
人類は悪性腫瘍なので、地球が免疫として戦争を起こして人類を減らしている、と。
…などという、うがった、こざかしい事は考えないようにしている。(今日は独白が多くなってしまった。妄言多謝 )
【ネット上の紹介】
英国在住、「地べたからのリポート」を得意とするライター兼保育士が、労働者階級の歴史と現状を生の声を交えながら伝える
第1部 地べたから見たブレグジットの「その後」(ブレグジットとトランプ現象は本当に似ていたのか
いま人々は、国民投票の結果を後悔しているのか
労働者たちが離脱を選んだ動機と労働党の復活はつながっている ほか)
第2部 労働者階級とはどんな人たちなのか(40年後の『ハマータウンの野郎ども』
「ニュー・マイノリティ」の背景と政治意識)
第3部 英国労働者階級の100年―歴史の中に現在が見える(叛逆のはじまり(1910年‐1939年)
1945年のスピリット(1939年‐1951年)
ワーキングクラス・ヒーローの時代(1951年‐1969年) ほか)



【ネット上の紹介】
地べたのポリティクスとは生きることであり、暮らすことだ―在英20年余の保育士ライターが放つ、渾身の一冊。
1 緊縮託児所時代 2015‐2016(リッチとプアの分離保育
パラレルワールド・ブルース
オリバー・ツイストと市松人形
緊縮に唾をかけろ
貧者分断のエレジー ほか)
2 底辺託児所時代 2008‐2010(あのブランコを押すのはあなた
フューリーより赤く
その先にあるもの。
ゴム手袋のヨハネ
小説家と底辺託児所 ほか)

「ポピュリズムとは何か」水島治郎
硬いテーマの割に、おもしろく読めた。
各国の事情を知ることが出来て興味深かったから。
次のような構成になっている。
1章---導入
2章---ラテンアメリカ
3章---ベルギー
4章---オランダ
5章---スイス
6章---イギリス
7章---アメリカ、グローバルな展開
P5
かつて多様な層の人々の「開放の論理」として現れたポピュリズムが、現代では排外主義と結びつき、「抑圧の論理」として席巻しているのである。
ポピュリズムの語源
P30
ポピュリズムが政治現象として本格的に歴史のなかに姿を現し、幅広く注目を集めたのは、19世紀末のアメリカ合衆国である。1892年に創設され、二大政党の支配に挑んだ人民党(People's Party)は、別名ポピュリスト党(Populist Party)と言われ、人民党の党員はポピュリストと呼ばれた。こうした、人民に依拠してエリート支配を批判する政治運動が、それ以降ポピュリズムと呼ばれるようになる。
P156
そもそも国民投票は諸刃の剣である。
P231
デモクラシーという品のよいパーティに出現したポピュリズムという泥酔客。
【ネット上の紹介】
イギリスのEU離脱、反イスラムなど排外主義の広がり、トランプ米大統領誕生…世界で猛威を振るうポピュリズム。「大衆迎合主義」とも訳され、民主主義の脅威と見られがちだ。だが、ラテンアメリカではエリート支配から人民を解放する原動力となり、ヨーロッパでは既成政党に改革を促す効果も指摘される。一方的に断罪すれば済むものではない。西欧から南北アメリカ、日本まで席巻する現状を分析し、その本質に迫る。
第1章 ポピュリズムとは何か
第2章 解放の論理―南北メリカにおける誕生と発展
第3章 抑圧の論理―ヨーロッパ極右政党の変貌
第4章 リベラルゆえの「反イスラム」―環境・福祉先進国の葛藤
第5章 国民投票のパラドクス―スイスは「理想の国」か
第6章 イギリスのEU離脱―「置き去りにされた」人々の逆転劇
第7章 グローバル化するポピュリズム

「異国のヴィジョン」北川智子
ヨーロッパを旅しながら、そこに回想シーンが入る趣向。
P6
ロンドン市内。ハイドパーク。午後四時。
夏のはじめの肌寒い夕方でも、池のまわりにはたくさんの人が集まる。わたしは池の端に腰かけ、この週末が終わったらしばらく旅に出るよと、となりのカモメに話しかける。(こうして五ヶ国を巡る旅が始まる)
P124
思い返さなければ、今という時の流れは違った方向に向かっていたのではないかと、今という状況がわからなくなる。わたしは、そんな過去の時間が今に与える錯乱的なひずみを感じ、苦しくなっていた。
『野うさぎ』、1502年
P128
ウイーンにあるアルベルティーナという美術館
描かれてからずっと、さみしいような、かなしいような、怒ったような。どうして、そんな表情でいるのだろうか。
アルブレヒト・デューラー - Wikipedia
【ネット上の紹介】
ハーバードからケンブリッジへ!日本から北米へ、北米からヨーロッパへ。日本を離れたところにいると、異国の人が見ているプリズムの中の光の道筋が見えてくる。
1 水の街アムステルダム(はじめての旅
マルチカルチュアリズム
ヴィジョン)
2 時の街ボン(異国で日本を語る
フリーマン・ダイソンとの出会い
生きている歴史)
3 光の街パリ(歴史のプリズム
命とインプレッション
それぞれのプリズム)
4 音の街ウィーン(現在を生き、未来を生きる時間
失われた命を語る
歴史をシェアする)
5 匠の街ミラノ(「現代のWe」
戦後を生きる)

「世界基準で夢をかなえる私の勉強法」北川智子
この勉強法を学生時代に知っていたら、と思った。
今からでも遅くない?
P60-61
とにかく何度も繰り返して思い出してみることで、記憶の保存が上手になる。そして、これも、記憶をたぐり寄せる作業と同様、試せば試すほど、うまくなる。(中略)
記憶の整理の手順の基本は、繰り返しになるが、まず何が一番重要だったのか、何が分かって何が分からないかをはっきりさせることだ。そしてなぜか思い出せないこととか、脈絡がつかめない議論などは、教材に戻って確かめる。つまり記憶の整理というのは、単に覚えようとするだけではどうにもならず、重要な情報が前後の関係する情報とどのようにからまっているかを検討することが大切だ。そうすると、分からない点が、なぜ分からないのか、よりはっきり見えてくる。
P171
また私は、歴史を学ぶことは、最終的に道徳を育てることだと思っている。過去をどのようにとらえるのか。過去に失われた命をどうとらえるのか。どう讃えるのか。
【ネット上の紹介】
グローバル環境で結果を出すのに不可欠なのはマニュアルよりも自分らしさ。ベストセラー『ハーバード白熱日本史教室』著者が贈る、ワクワクする未来を創る生き方・学び方。第1部 大きな壁は回り道をして越える―カナダ・ホームステイ・英語編(人生初の独立宣言
英語力向上のびのび作戦)
第2部 カジュアルに、エンドレスに勉強する―カナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学・留学編(自分に合った勉強法
4:3のタイム・マネジメント
友だちの助言からどう学ぶか
いつも「世界基準」で考える
無理して玉砕しないためのメンタル・ケア)
第3部 24時間を144時間の濃さにする―米国・プリンストン大学・大学院編(途方もない仕事量のこなし方
熱意は必ず伝わる)
第4部 結果を出すには準備がすべて―米国・ハーバード大学・先生編(教えることは最高の学び
アクティブ・ラーニング
忘却力でミスを乗り越える)
第5部 勉強は「約束」を果たすために―英国・ケンブリッジ・飛躍編(軌道修正は楽しみながら忍耐強く
約束は人間の「存在理由」)

「世界の産声に耳を澄ます」石井光太
世界のお産事情をレポート。
読んでいて、初期の作品「神の捨てた裸体」「物乞う仏陀」を思い出した。
旅する作家、石井光太健在である。
タイの代理母出産事情
P70
――もし人助けの仕事じゃなければやらなかった?
「しないですよ。お寺で人に喜んでもらえて借金も返せることだって言ってもらったから、したんだもん」
仏教に敬虔なタイ人らしい考えだと思った。特に地方の人々は、高い教育を受けていないこともあって社会的な倫理観より、仏教の教えに従った生き方を選ぶ。メムもまた寺院の僧侶が示した「人助け」という考え方で、代理母出産を善行だとして受け入れたのだろう。
シリア内戦状態のお産事情
P168
覚えているのは、21歳の妊婦さんが、旦那さんを失ってわずか1週間後に出産したことです。入院当初は、妊婦さんは夫を亡くしたショックから「もう赤ちゃんなんていらない!」と泣き叫んでいました。自暴自棄になっていたんでしょう。
いよいよ始まったお産は大変な難産でした。(中略)それでも3日後の夕方になって無事に産むことができました。
あの時、付き添っていた助産婦さんの喜びようといったらなかったですね。赤ちゃんを抱えて病院中を回って言いました。
「ついに生まれましたよ!みんな祝ってあげてください!」
【参考図書】

「レンタルチャイルド 神に弄ばれる貧しき子供たち」石井光太
「地を這う祈り」石井光太
「感染宣言」石井光太
「飢餓浄土」石井光太
「ルポ餓死現場で生きる」石井光太
「遺体 震災、津波の果てに」石井光太
「ニッポン異国紀行 在日外国人のカネ・性愛・死」石井光太
「アジアにこぼれた涙」石井光太
「戦場の都市伝説」石井光太
「ノンフィクション新世紀」石井光太/責任編集
【ネット上の紹介】
過酷な環境でも、日々生まれてくる新たな生命。先住民族、ストリートチルドレン、代理母出産、HIV感染者、紛争地…。海外ルポルタージュの名手が七年ぶりに世界を旅し、悲しみの現場から“希望”を見つめた、新機軸ノンフィクション!
第1話 ミャンマー―流浪の首長族
第2話 グアテマラ―秘境に消えて
第3話 ホンジュラス―嬰児の川/妊婦の家
第4話 フィリピン―ミルクとココナッツ
第5話 タイ―子宮貸します
第6話 シリア/ヨルダン―戦場で産む/砂に描く絵
第7話 タンザニア―アフリカの白い精霊たち
第8話 スワジランド―HIVの王国
第9話 スリランカ―家庭の味

「ハーバードで喝采された日本の「強み」」山口真由
交渉や面接で重要な事
P36
「決して嘘をついてはいけない。加えて、情報を隠さないこと、誠実であること――この二つが大事だ。(中略)自分という人間に、決して嘘をつくな」
P42-45
「バッド・コップ」「グッド・コップ」…これは実践で役に立つ。
でも、これって日本の警察で実践済み?
アメリカの男女平等について
P49
「アメリカは、先進国のなかで唯一、産休中に給与が保証されない」
TOEFLはリーディング、リスニング、スピーキング、ライティング各30点満点、合計120点満点。有名ロースクールの場合105点。ハーバードでは、足切りで各25点以上必要。
P83
英語が苦手だった私は、20回以上TOEFLを受け続けた。それでも最終的な点数は、リーディング29点、リスニング30点、ライティング27点、スピーキング18点の合計104点。(中略)スピーキングの点数がこれほど低い人は聞いたことがないとのこと。(う~ん、充分優秀、と思うけど)
日本人と韓国人の違い
P95
仲が良くなったときの距離の取り方とのこと。この人が好きだと思うと、韓国人はぐっと距離を縮めるが、そこで何らかの行き違いがあると、「裏切り」と感じて、「好き」が一気に「嫌い」に変わる傾向があるという。きっかけがちょっとした誤解であっても、いったん感情的対立が起こると、元の関係に戻るのは難しい。
香港から来た美少女・シャロンとの会話
P110
「私、自分が自分じゃなくなっちゃった気がする。日本にいたときには、何をしているときも自信があった。人を気遣う余裕もあった。でも、アメリカに来てそういうのが全部なくなっちゃった」
(中略)
「真由、だいじょうぶよ。あなたと話すの楽しいもの」
その瞬間に、目の前が明るくなり、ねじけていた気持ちがすっと解けた。
ストーリーテリングについて
P136
「ストーリーテリング」とは、口伝えに伝承されてきた物語を指すが、そこから転じて、難しいロジックで相手を説得するのではなくて、印象的なストーリーで相手に訴えかける手法も指すようになった。
144
「それを使ううえでどんな素晴らしい生活が送れるのか」といったストーリーを、スティーブ・ジョブズ本人がプレゼンした。アップルが多くの「信者」を生み出してきたのは、まさにこういった魅力的なストーリーゆえといえる。
P219
ハーバード・ロースクールで、私はありのままの自分を肯定することを学んだ。
英語も話せない。日本での経歴も肩書きも通じない。そんな私をクラスメイトたちはそのまま受け入れてくれた。
【感想】
想定以上のおもしろさ。
以前にも、この著者の作品を読んだことがあるが、こちらの方がずっと面白い。(→「天才とは努力を続けられる人のことであり、それには方法論がある。」山口真由)
【ネット上の紹介】
東大首席元財務官僚が学んだ、ハーバード白熱教室の実態!トランプ大統領を生んだアメリカという国の二極対立思考法や、ハーバード流交渉術、LGBT問題、人種問題など、アメリカそしてこれからの日米関係を理解するための必読の書。
第1章 私を白熱させたハーバードの授業
第2章 ハーバードで受けた洗礼
第3章 トランプ大統領を誕生させたアメリカ社会の二極対立
第4章 ハーバードで喝采された日本の「強み」

「イスラーム圏で働く」桜井啓子/編
イスラム体験記・・・様々な分野で活躍する日本人が、イスラム社会を語る。
早稲田大学で、全学の学生を対象に、「働く日本人のイスラーム」という講演会を毎月1回開催して、それを著者がまとめたのが本書。…講演会は、イスラーム圏への赴任経験をもつさまざまな業種の方たちを大学にお招きし、ご自身の仕事体験を学生に語っていただくというものだった。(P203)
P8
「イン・シャー・アッラー」は、「神さまがそう望めば」という意味ですから、本来はネガティブな意味はないはずです。しかし、機内や社内での一般的な使い方は、たとえば、自分の仕事で手一杯な時に、同僚から「あれをやっておいて」と振られたとします。断るときには、「ノー」ですが、自分の仕事が済めば、やってもいいけども、今はできないといった場合には、「イン・シャー・アッラー」と返します。とりあえず流すときに「イン・シャー・アッラー」と言っているわけですね。
P12
日本では、縁の下の力持ち的な働き方は尊敬されますが、こちらではほぼ評価されません。しっかり働いていることを上司に見せることが重要なのです。
P13
また、アラブの特に女性たちは一般に気が強く、自分に非があってもあまり謝りません。一番やっかいなのは、自分のミスを相手に転嫁するパターンです。
P17
現在、国際的に機内への液体物の持ち込みは規制されていますが、エミレーツ航空では、100ミリを超えていても、メッカの聖モスク内にあるザムザムの泉の神聖な水をつめたボトルだけは、持ち込み可となっています。
P42
イランでは、女性は、親族以外の男性と接触してはいけないのです。(だから、握手を求めてはいけない)
P76
中東のムスリムは旅人を歓待すると言われていますが、本当にそうです。
「マレーシ」=要は「僕のせいでもないし、君のせいでもない」
P138-139
日本人が「反省する」といった場合、三つの意味が一つになったものだとある本で読みました。自分の間違いを認めること。その間違いを恥ずかしいと思うこと。その間違いを二度と繰り返すまいと自分に誓うこと。では、自分の間違いを認めることが正しいとされている文化を持っている国はどれぐらいあるか。おそらく少数でしょう。少なくともアラブでは、日本人のように「反省」する人はいないはずです。「あなたのせいでもないし、僕のせいでもない」のです。
【ネット上の紹介】
世界に広がる一六億人のイスラーム市場。これからのビジネスに、イスラームの人びととの付き合いは必須だ。でも、なじみがなく戸惑う人も多いのでは?そんな時の心強い味方―商社・石油・建設・食品・観光など、現地で活躍する日本人が、土地と人と仕事を語る。地域別解説も付した体験的イスラーム案内。
[目次]
第1章 イスラームの懐に飛び込む―湾岸諸国
第2章 アラブとの付き合い方―アラブ諸国
第3章 誇り高きペルシアの人びと―イラン
第4章 西洋に最も近いイスラーム圏―トルコ
第5章 イスラーム?それとも地域の風習?―南アジア
第6章 イスラームとの新しい付き合い方―東南アジア、そして日本

「アジアの歩き方」野村進
先日、「コリアン世界の旅」を読んだ。
本作品は、同著者による。
他の作品を読んでみよう、と。
アジアを深く旅した著者による、蘊蓄が語られる。
ベトナムについて、P151に書かれている。
香港のコンサルタント会社の調査で、「外国人ビジネスマンにとってアジアで最もストレスのかかる国」に選ばれた。(次点は韓国)
ベトナムに進出する中小企業へのアドバイス
P152
「従業員が横になれる部屋を作ったほうがいいですよ。特に女子従業員のためには絶対必要ですね。『疲れた』とか『頭が痛い』と言う人が、けっこう出てきますから。それと、お昼ごはんは給食にして、栄養のあるものをたくさん出してください。(後略)」
【ネット上の紹介】
食、危険回避の方法、常識の違い、日本との関わり、ボーダレス化するいまの姿など、アジアの「真実」が見えてくる。
大宅賞作家が案内するアジアのおもしろさ。20年あまりにわたりアジアとディープに付き合う著者が真の姿を浮かび上がらせる。
[目次]
プロローグ 旅立つ前に
第1章 ディープ・アジアの旅
第2章 されど渡る世間に鬼はなし
第3章 意地でも同じものを食ってやる
第4章 私のアジア事始め
第5章 “アジアはひとつ”なんてわけないだろ
第6章 どれがいったい“日本”なんだ
第7章 それぞれのアジア
第8章 定住する日本人
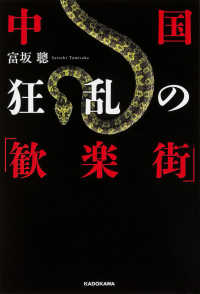
「中国狂乱の「歓楽街」」富坂聰
隣国・中国の動向・状況は気になる。
先月の天津爆発事故など、負の側面だ。(→天津爆発事故 中国社会の深い闇)
この作品も闇の部分を描いている。
“東莞”とういうのは、中国最大(あるいは世界最大)の売春都市と言われる。
それが壊滅した。
何がおきたのか?
現地に行って取材してレポートしている。
P24
中国で売春に対する大規模な取り締まりキャンペーンは“掃黄”(=売春・ポルノ取り締まりキャンペーン。日本ではピンク産業だが、中国ではイエローの「黄」となる)と呼ばれているけど、その実態はたいてい出来レースで手心も加えられてきた。しかし、2014年2月上旬に東莞を狙って行われた掃黄”は、その取り締まりの規模も厳しさも新中国の歴史のなかで間違いなくナンバーワンだった。
【おまけ】
難を言うなら、ここに生活する人たちの「顔」が見えないこと。
もし、これが石井光太作品なら、春を売らざるを得なくなった人たちの
過去・現在を丹念に取材され、表現される、と思う。
この作品は心に残った↑
【ネット上の紹介】
中国最大の売春都市“東莞”が壊滅した。東莞ISOといわれた“性”の都にいったい何が起きたのか!? 愛人村、死体の結婚、母乳健康ビジネス、野生動物市場etc...“欲望”に暴走する中国社会の闇に迫る!
[目次]
第1部 “性都”壊滅―東莞一斉摘発と中国性風俗の闇(激増する風俗業界の迷惑メール
狙われた“性の都”
一斉摘発「東莞の36時間」 ほか)
第2部 中国・愛人事情―社会的弱者から「告発者」へと変貌する女たち(ネット社会に現れたトリックスター
中国赤十字を殺した女
中国全土を駆けめぐった郭美美逮捕の知らせ ほか)
第3部 「金」と「欲」に乱れ狂う中国―母乳健康ビジネスから野生動物市場、死体の結婚まで(学生売春が大学の目と鼻の先で行われていた
母乳健康ビジネス
レッサーパンダの肉も手に入る野生動物市場 ほか)