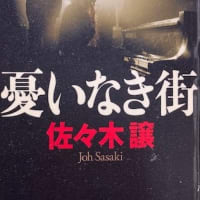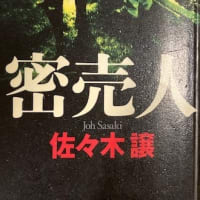ガブリエル・ガルシア=マルケス(新潮社)
2年以上かかってやっと読了した。解説を入れると492ページ。
登場人物の名前が、同じ名前が多く、重なって複雑で理解できないので、混乱する。しかし、何となく、一族の100年と言う流れを感じることができたような気がするのだ。
内容紹介は
『蜃気楼の村マコンド。その草創、隆盛、衰退、ついには廃墟と化すまでのめくるめく百年を通じて、村の開拓者一族ブエンディア家の、一人からまた一人へと受け継がれる運命にあった底なしの孤独は、絶望と野望、苦悶と悦楽、現実と幻想、死と生、すなわち人間であることの葛藤をことごとく呑み尽しながら…。20世紀が生んだ、物語の豊潤な奇蹟。
著者
ガルシア=マルケス,ガブリエル
1927年生まれ。コロンビアの作家 』
あまりにも複雑?なので、ネットの書評を引用する。
『これは、コロンビアの架空の村におこった一族の物語です。
夏の間に一気に読みましたが、熱帯のような蒸し暑い気候によくあう本でした。
一族の歴史のうねりを、若かった作者がどうやって書いたのだろうと不思議に思いましたが
作者は小さなころから噂好きの祖母の話を聞いていたそうなので
年を重ねた人間の視点を、若いうちから自然と身につけていたのかもしれません。
一家の男たち、または新しく生まれる子供たちは、それぞれに個性(癖)があって、
おもいおもいの人生を形作っては、一つ一つの物語としてこの本を彩っていきます。
が、それらは全体からすれば1つのエピソードにすぎず、淡々と時系列で
物語が起こっては消え、語られ続けていくのです。
(これが退屈に思う人は途中挫折しそうになるかもしれません!)
そんな中、一族の家長の妻であるウルスラは、
家族を愛し、家の存続のために熱心に働き、1世紀以上という長い人生のほとんどすべてをかけて、
家族を見つめています。
男たちがどんなに暴れても、戻ってくる場所は、母が守り続けてきた家。
この母、地味なようでいて、実は一族にとってのふるさとであり、軸となり、舞台であると感じました。
ただし、母もまた時間の経過によって、老化していきます。
そしてまた、これだけの厚みをもった一族すらも、
世界の歴史という物語全体からすればただの1エピソードである…?
スケールが大きい話なので、一人一人のエピソードが語られている間は
泥臭い感覚があるのですが、全体を通して見れば、一族の動きを空から
覗いているような感じです。
また、語り口調もどこかユーモラスなので、読了後は妙にさっぱりと、
心静かな状態になりました。
(もうひとつ)
複雑すぎる人間関係(といってもみんな家族だが)、
西欧的、近現代的な世界法則を無視して展開される物語、
陰鬱で陰惨な物語の閉じ方。
読みにくいことこの上ない本作ではあるが、
この閉じた物語と自分の生きている世界とを対照すると
いろいろとハッとする発見があって楽しい。
これがガルシア=マルケスという天才一人の頭の中から繰り出されたと思うと
憎らしくさえ感じてしまうが、
キリスト教徒が聖書を読むのはこんな感じなんだろうなと思ってしまう。
(3つ目の書評が分かりやすい)
今回読んで、この物語の中心主題のひとつは「反復」だと気づきました。このモチーフは、次の数行のなかだけでも何度も現れています。
<ホセ・アルカディオ・セグンドは、相変わらず羊皮紙を読みふけっていた。もつれた紙の下から、緑がかった歯くそが縞になった歯並びと、動きのない目だけがのぞいていた。曾祖母の声に気づいた彼はドアのほうを振り向き、笑顔を作りながら、無意識のうちに昔のウルスラの言葉をくり返した。
「仕方がないさ。時がたったんだもの」
つぶやくようなその声を聞いて、ウルスラは言った。「それもそうだけど。でも、そんなにたっちゃいないよ」
答えながら彼女は、死刑囚の独房にいたアウレリャノ・ブエンディア大佐と同じ返事をしていることに気づいた。たったいま口にしたとおり、時は少しも流れず、ただ堂々めぐりをしているだけであることをあらためて知り、身震いした。>
くり返されるモチーフはほかにもたくさんあります。生まれた子に父祖の名をつけること、近親間の愛(叔母と甥)、ひとりの女が同時に兄弟ふたりの愛人になること、ブエンディア家の人々の多くが超常的な死を遂げること、ひとりの男が17人の女に17人の息子を産ませること、「豚のしっぽ」、百五十年ほども生きる女二人、五年近くも降り止まぬ雨、などなど。
しかし終末部で、この反復の物語は、二度と反復しないと宣言されます。
<また、百年の孤独を運命づけられた家系は二度と地上に出現する機会を持ちえないため、羊皮紙に記されている事柄のいっさいは、過去と未来を問わず、反復の可能性がないことが予想されたからである。>
つまりこれは、「反復」という本質をもつがゆえにけっして反復されない物語なのです。
それと、「過剰」のモチーフも重要ですね。ありえないほど長命、絶倫、巨根、美貌の登場人物が出てきて笑えます。
たとえば途方もないほど美しい小町娘のレメディオスは、その色香のために近づく男たちをことごとく恋に狂わせ、ひとり残らず不幸な死に追いやります。
それでも荒唐無稽な感じはしないんですよね。何か神話を読んでいるような、妙な現実感があります。
人生の折々に読み返したいと思える、まぎれもない傑作です。』
・・・これで少しは輪郭が見えてくるというものだ。
・・・ともかく、大部な小説をよく読んだねと言うのが、感想ですわ。(苦笑い)
2年以上かかってやっと読了した。解説を入れると492ページ。
登場人物の名前が、同じ名前が多く、重なって複雑で理解できないので、混乱する。しかし、何となく、一族の100年と言う流れを感じることができたような気がするのだ。
内容紹介は
『蜃気楼の村マコンド。その草創、隆盛、衰退、ついには廃墟と化すまでのめくるめく百年を通じて、村の開拓者一族ブエンディア家の、一人からまた一人へと受け継がれる運命にあった底なしの孤独は、絶望と野望、苦悶と悦楽、現実と幻想、死と生、すなわち人間であることの葛藤をことごとく呑み尽しながら…。20世紀が生んだ、物語の豊潤な奇蹟。
著者
ガルシア=マルケス,ガブリエル
1927年生まれ。コロンビアの作家 』
あまりにも複雑?なので、ネットの書評を引用する。
『これは、コロンビアの架空の村におこった一族の物語です。
夏の間に一気に読みましたが、熱帯のような蒸し暑い気候によくあう本でした。
一族の歴史のうねりを、若かった作者がどうやって書いたのだろうと不思議に思いましたが
作者は小さなころから噂好きの祖母の話を聞いていたそうなので
年を重ねた人間の視点を、若いうちから自然と身につけていたのかもしれません。
一家の男たち、または新しく生まれる子供たちは、それぞれに個性(癖)があって、
おもいおもいの人生を形作っては、一つ一つの物語としてこの本を彩っていきます。
が、それらは全体からすれば1つのエピソードにすぎず、淡々と時系列で
物語が起こっては消え、語られ続けていくのです。
(これが退屈に思う人は途中挫折しそうになるかもしれません!)
そんな中、一族の家長の妻であるウルスラは、
家族を愛し、家の存続のために熱心に働き、1世紀以上という長い人生のほとんどすべてをかけて、
家族を見つめています。
男たちがどんなに暴れても、戻ってくる場所は、母が守り続けてきた家。
この母、地味なようでいて、実は一族にとってのふるさとであり、軸となり、舞台であると感じました。
ただし、母もまた時間の経過によって、老化していきます。
そしてまた、これだけの厚みをもった一族すらも、
世界の歴史という物語全体からすればただの1エピソードである…?
スケールが大きい話なので、一人一人のエピソードが語られている間は
泥臭い感覚があるのですが、全体を通して見れば、一族の動きを空から
覗いているような感じです。
また、語り口調もどこかユーモラスなので、読了後は妙にさっぱりと、
心静かな状態になりました。
(もうひとつ)
複雑すぎる人間関係(といってもみんな家族だが)、
西欧的、近現代的な世界法則を無視して展開される物語、
陰鬱で陰惨な物語の閉じ方。
読みにくいことこの上ない本作ではあるが、
この閉じた物語と自分の生きている世界とを対照すると
いろいろとハッとする発見があって楽しい。
これがガルシア=マルケスという天才一人の頭の中から繰り出されたと思うと
憎らしくさえ感じてしまうが、
キリスト教徒が聖書を読むのはこんな感じなんだろうなと思ってしまう。
(3つ目の書評が分かりやすい)
今回読んで、この物語の中心主題のひとつは「反復」だと気づきました。このモチーフは、次の数行のなかだけでも何度も現れています。
<ホセ・アルカディオ・セグンドは、相変わらず羊皮紙を読みふけっていた。もつれた紙の下から、緑がかった歯くそが縞になった歯並びと、動きのない目だけがのぞいていた。曾祖母の声に気づいた彼はドアのほうを振り向き、笑顔を作りながら、無意識のうちに昔のウルスラの言葉をくり返した。
「仕方がないさ。時がたったんだもの」
つぶやくようなその声を聞いて、ウルスラは言った。「それもそうだけど。でも、そんなにたっちゃいないよ」
答えながら彼女は、死刑囚の独房にいたアウレリャノ・ブエンディア大佐と同じ返事をしていることに気づいた。たったいま口にしたとおり、時は少しも流れず、ただ堂々めぐりをしているだけであることをあらためて知り、身震いした。>
くり返されるモチーフはほかにもたくさんあります。生まれた子に父祖の名をつけること、近親間の愛(叔母と甥)、ひとりの女が同時に兄弟ふたりの愛人になること、ブエンディア家の人々の多くが超常的な死を遂げること、ひとりの男が17人の女に17人の息子を産ませること、「豚のしっぽ」、百五十年ほども生きる女二人、五年近くも降り止まぬ雨、などなど。
しかし終末部で、この反復の物語は、二度と反復しないと宣言されます。
<また、百年の孤独を運命づけられた家系は二度と地上に出現する機会を持ちえないため、羊皮紙に記されている事柄のいっさいは、過去と未来を問わず、反復の可能性がないことが予想されたからである。>
つまりこれは、「反復」という本質をもつがゆえにけっして反復されない物語なのです。
それと、「過剰」のモチーフも重要ですね。ありえないほど長命、絶倫、巨根、美貌の登場人物が出てきて笑えます。
たとえば途方もないほど美しい小町娘のレメディオスは、その色香のために近づく男たちをことごとく恋に狂わせ、ひとり残らず不幸な死に追いやります。
それでも荒唐無稽な感じはしないんですよね。何か神話を読んでいるような、妙な現実感があります。
人生の折々に読み返したいと思える、まぎれもない傑作です。』
・・・これで少しは輪郭が見えてくるというものだ。
・・・ともかく、大部な小説をよく読んだねと言うのが、感想ですわ。(苦笑い)