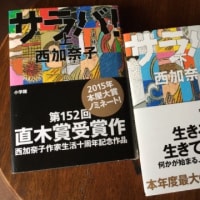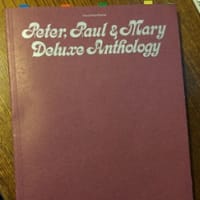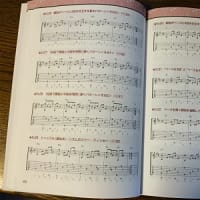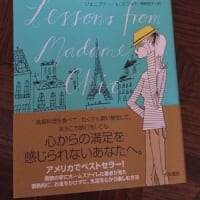はっきりいつからとは言えませんが、多分、5、6年前頃からBS日テレで始まった『イタリアの小さな村の物語』を見るようになってイタリアの小さな村・町に憧れるようになり、インターネット上でそれらしき町や村の情報を求めてネットサーフィンし、小さな町を取り上げた書籍を読みあさり、年甲斐もなく(?) “恋しい想い”を密かに持ち続けてきました。あのTV番組のプロデューサーは、それは哲学の問題だとの指摘をしているのですが、イタリアの小さな村・町は本当に不思議なほどの魅力を持っているのです。それが“哲学”と言われると困るので、何か別の見方をしたいなと考えている時に、格好の本に出会いました。
島村奈津著『スローシティ:世界の均質化と闘うイタリアの小さな町』(2013年3月初版)

イタリアは20年位前に始まったスローフード運動発祥の地、同じ著者の『スローフードな人生~イタリアの食卓から始まる』を興味深く読んでいたので、この本を見つけた途端、直ぐに購入してしまいました。ページをめくる前から、私のイタリア好きのテーマの一つである小さな町の分析に関するものに違いないと確信していましたが、その通りのものです。どうやって小さな町が元気でいられるのか、なぜ小さな町が魅力的なのか、その鍵はサブタイトルにある“均質化と闘う”ことにあるようです。元々“均質”が文化とも言える日本に対して、個性尊重と見られているイタリアで“均質化と闘う”というのは不思議な気もするのですが。でも読んでみて、程度こそ違え、イタリアでも同様の問題があることが理解できました。
イタリアで1999年にスローシティを謳う連合が出来た時の初代会長は、スローシティ宣言の中で「人間サイズの、人間らしいリズムが残る小さな町を心がけよう」と挨拶したそうです。スローシティに認定されている町の元町長は「人が生きていく上で根源的なもの、それは環境であり、人間サイズのほど良い大きさの町で、そこに文化的なものが息づいていること。(中略)スローシティとは、決して町の構造や建築だけの問題ではない。むしろ大切なのは、目に見えないものの価値だ。人と人との交流、会話、農家の知恵、職人の技、食文化、・・・」因に、「人間サイズのほど良い大きさ」として、人口2万人以下を認定条件の一つにしているそうです。

こういった考えの実現のためには、拡大を求めず、むしろ人口増加や企業の進出を制限すらすることで、人間サイズの価値を維持しようとしているとか。日本だと小さな村・町の活性化というと、即、経済規模の拡大、人口の増加、そのための企業誘致という流れが当たり前になっているようですが、それは正に個性を犠牲にして均質化に向かう道なのですね。ある町長は、拡大しすぎてしまった現状を少し縮小したいとまで言っています。また、ある町では、大規模スーパーの進出を必死に抵抗して防いだとか。そして、過疎の村の良さに気付いて活性化のきっかけとなったのは、外国からの旅行者や移住者だった例もあるとか。興味深い事例が多数ありました。
著者曰く;
現代の文明国と呼ばれる国々にみられる閉塞感の理由の一つに「生活空間の均質化」あるのではないか。巨大なショッピング船体―、世界中で同じような映画ばかりのシネコン、駅前に連なるチェーン店、画一的な住宅街・・・
ううんと唸らされてしまいます。確かに私の地元でも、スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどの大規模チェーンに置き換えられてしまい、昔ながらの個人商店は殆どが姿を消してしまっています。買物する上での不便はないし、むしろ便利なのですが、その一方で、確かに会話がなくなっています。買物に行って会話をするのは、個人経営の酒屋さんとパン屋さんくらいかな。この傾向・現象をどうとらえるかがスロー路線との分かれ目になるのでしょうね。私自身、矛盾をかかえながらですが、それでもスローライフを意識していたいものです。
それにしても、スローフードといい、このスローシティといい、いわゆる近代的経済発展に逆行するような動きを世界に先駆けて始めるイタリアという国に、あらためて敬意を表し、また一段とイタリア好きになりました!
島村奈津著『スローシティ:世界の均質化と闘うイタリアの小さな町』(2013年3月初版)

イタリアは20年位前に始まったスローフード運動発祥の地、同じ著者の『スローフードな人生~イタリアの食卓から始まる』を興味深く読んでいたので、この本を見つけた途端、直ぐに購入してしまいました。ページをめくる前から、私のイタリア好きのテーマの一つである小さな町の分析に関するものに違いないと確信していましたが、その通りのものです。どうやって小さな町が元気でいられるのか、なぜ小さな町が魅力的なのか、その鍵はサブタイトルにある“均質化と闘う”ことにあるようです。元々“均質”が文化とも言える日本に対して、個性尊重と見られているイタリアで“均質化と闘う”というのは不思議な気もするのですが。でも読んでみて、程度こそ違え、イタリアでも同様の問題があることが理解できました。
イタリアで1999年にスローシティを謳う連合が出来た時の初代会長は、スローシティ宣言の中で「人間サイズの、人間らしいリズムが残る小さな町を心がけよう」と挨拶したそうです。スローシティに認定されている町の元町長は「人が生きていく上で根源的なもの、それは環境であり、人間サイズのほど良い大きさの町で、そこに文化的なものが息づいていること。(中略)スローシティとは、決して町の構造や建築だけの問題ではない。むしろ大切なのは、目に見えないものの価値だ。人と人との交流、会話、農家の知恵、職人の技、食文化、・・・」因に、「人間サイズのほど良い大きさ」として、人口2万人以下を認定条件の一つにしているそうです。

こういった考えの実現のためには、拡大を求めず、むしろ人口増加や企業の進出を制限すらすることで、人間サイズの価値を維持しようとしているとか。日本だと小さな村・町の活性化というと、即、経済規模の拡大、人口の増加、そのための企業誘致という流れが当たり前になっているようですが、それは正に個性を犠牲にして均質化に向かう道なのですね。ある町長は、拡大しすぎてしまった現状を少し縮小したいとまで言っています。また、ある町では、大規模スーパーの進出を必死に抵抗して防いだとか。そして、過疎の村の良さに気付いて活性化のきっかけとなったのは、外国からの旅行者や移住者だった例もあるとか。興味深い事例が多数ありました。
著者曰く;
現代の文明国と呼ばれる国々にみられる閉塞感の理由の一つに「生活空間の均質化」あるのではないか。巨大なショッピング船体―、世界中で同じような映画ばかりのシネコン、駅前に連なるチェーン店、画一的な住宅街・・・
ううんと唸らされてしまいます。確かに私の地元でも、スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどの大規模チェーンに置き換えられてしまい、昔ながらの個人商店は殆どが姿を消してしまっています。買物する上での不便はないし、むしろ便利なのですが、その一方で、確かに会話がなくなっています。買物に行って会話をするのは、個人経営の酒屋さんとパン屋さんくらいかな。この傾向・現象をどうとらえるかがスロー路線との分かれ目になるのでしょうね。私自身、矛盾をかかえながらですが、それでもスローライフを意識していたいものです。
それにしても、スローフードといい、このスローシティといい、いわゆる近代的経済発展に逆行するような動きを世界に先駆けて始めるイタリアという国に、あらためて敬意を表し、また一段とイタリア好きになりました!