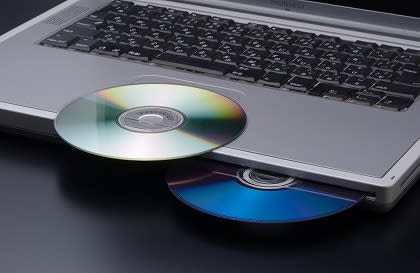弁理士法人サトーから法改正や事務所の最新情報を提供します。
このブログでもたびたび取り上げてきました東京オリンピックのロゴ。
今回、デザイン案が取り下げられたことで、とりあえず一段落しました。
名古屋ではなかなか目につきませんが、先日東京へ行った際、駅や繁華街ではこのロゴを頻繁に目にしました。
東京でこれだけロゴが利用されていると思うと、今回の騒動の影響(特に、金銭的)は非常に大きなものになると予想されます。
ところで、この騒動で気になったのは、メディアによる専門家の使い方。特にテレビにおける専門家の使い方。
何か事件があると、その筋の専門家がテレビに呼ばれて色々と説明をするわけですが、今回の騒動でも例外ではありませんでした。
毎日、いつもの専門家の方々が説明していました。
しかし、ここに違和感がありました。
専門家として呼ばれたのは、「著作権に詳しい弁護士」や「商標に詳しい弁理士」という方々。
このブログで何度もお伝えしたように、商標法や著作権法の視点からは、今回のロゴに法律的な問題はほぼありません。
商標としての類似の範囲、著作物としての複製に相当するかなど、法律的な視点で見る限り、問題はない(無い可能性が高い)のです。
また、ベルギーで訴訟を提起されようが、IOCのあるスイスで提訴されようが、属地主義※が基本の知的財産権に影響は与えません。
このような状況で「著作権に詳しい弁護士」さんや、「商標に詳しい弁理士」さんにお話を伺ったところで、「法律的には問題ありませんね。」という回答しか得られません。そう回答するしかないもの。
そうなると、テレビの前の人々は、「何だよ、こんなに似てるのに問題ないなんて、専門家って適当だよな。」という印象を受けてしまいます。
何度も繰り返しますが、今回の騒動は、商標権侵害や著作権侵害といった法律の問題ではなく、クリエイターとしての誇り・モラルの問題だと思うのです。
ですから、今回の騒動に関する問題は、弁護士や弁理士などの専門家に尋ねるのではなく、クリエイターであるデザイナーさん達に「デザインとしてどうよ?」と尋ねるのが本筋だと思います。
テレビをはじめとするメディアでは、自らの報道の正当性を担保するために専門家の意見を聞きたがりますが、今回のケースは選択すべき専門家を間違っているように思います。
変なとばっちりがこないといいのですが。
※属地主義:知的財産権は、その国の法律に従って成立するものであり、他国の判断や法律の影響を受けません、という趣旨の考え方です。
お盆休みも終わり、通常営業に戻りました。
このお盆休み、名古屋では毎日暑い日が続いていましたが、13日の雨を境にちょっとだけ秋の雰囲気が感じられるようになってきました。
このお盆休み、暑かったのは気候だけでなく、休み前から話題だった東京オリンピックのエンブレムのロゴについても熱い・・・。
デザイナーさんの実績として挙げられているデザインに、次々と疑惑が持ち上がり、夏の暑さを忘れるような「炎上」状態となっています。
この疑惑の暑さのせいでしょうか、お盆休み中にもかかわらず、当ブログにもたくさんのアクセスを頂きました。やはり関心が高いのでしょうね。
以前も触れましたが、正直なところ、知的財産の専門家を自負する弁理士としては、今回のオリンピックのロゴについて、知的財産という視点での法律的な問題はあまり大きくないように思います。
要するに、今回の騒動は、法律的な問題よりも、モラルの問題にあるようです。
繰り返しになりますが、商標の視点からは、ベルギーの劇場のロゴと今回のオリンピックのロゴとは、誤認混同を生じるおそれが低いです。仮にベルギーの劇場のロゴが商標登録されていたとしても、誤認を招くほどの類似性はないでしょう。
また、著作物の視点からも、まるっとコピーしているわけでもないですし、相違点も多々あることから、仮にデザイナーさんがベルギーのロゴにインスパイアされていたとしても、権利侵害を問うのは難しいでしょう。
そうなると、最終的には、クリエイターのプロフェッショナルの仕事として妥当であったかどうか、つまりモラルの問題に帰着するように思えます。
ここからは、個人的な感想。
僕自身、デザイン業界はよくわかりませんが、今回のデザイナーさんの実績として挙げられている各種のデザインには今一つ一貫性が無いように思います。
例として正しいかどうかわかりませんが、例えばJR九州の車両デザインを行なわれている「水戸岡」さんなんかは、JR九州に限らずどのデザインを見ても「ミトーカ」だなと言えるデザインのコンセプトが感じられます。
さらに例として正しいかわかりませんが、「村上春樹」の小説は、誰が読んでも「村上春樹」だとわかる文体です。「小室哲哉」の曲は、誰が聴いても「小室哲哉」です。「天野喜孝」のキャラは、一見して「天野喜孝」です。
このように、クリエイターというのは、個性が一貫していて、自分自身の才能も統一した一つのブランドとしてうまくブランディングを行なっていると感じます。
これに対して、今回のデザイナーさんは、マルチな才能なのか、柔軟な方なのか、デザインコンセプトに幅広さを感じてしまいます。今回のオリンピックのロゴと、日光江戸村の「ニャンまげ」が同一のデザイナーさんだとは思いませんでした。
オンデマンドで「何にでも対応しますよ。」というマルチな才能も大切でしょうが、プロフェッショナルな世界、特にクリエイターの世界では独自の個性を貫くのも大切な気がします。
我々のような明細書を作成する弁理士でも、明細書を読めば誰が作成したかだいたい見当がつきますからね。だから、「この人、この事務所に依頼したい。」という次のビジネスにつながって行くように思いますし、これこそがプロフェッショナルの価値だと思っています。
個性が無いのが個性でしょうか。

今朝の日経新聞に、アメリカの特許出願件数が6年ぶりに減少したという記事がありました。
何でも、パテントトロールの対策のために行なった法律の改正が影響したとのことです。
記事では、パテントトロール対策として特許法を改正して特許を消滅させるための「異議申立」の要件を緩和したところ質の高い特許も取消になりやすくなったり、パテントトロール対策として訴訟制度を改正して敗訴者の費用負担を大きくしたところ敗訴時のリスクを考慮して特許を取得するのを躊躇したりした結果、特許出願件数の減少につながったのではないかとの指摘でした。
結局、ユーザにとって特許制度が使いにくくなると、出願件数が減る、米国の出願件数が減ると特許制度への信頼性に疑問が生じ、他国でも出願件数が減る、日本も影響を受けるかも知れない、といった論調でした。
確かに、そういう傾向はあるでしょう。しかし、アメリカは、特許を重視するプロパテントと、特許を競争を妨げる制度とみるアンチパテントとが、コロコロと入れ替わる国です。そうすると、ここまでプロパテント政策を維持していたのですが、パテントトロールなどの問題で過剰な保護が問題となり、アンチパテントに舵を切ったとみることができます。
アンチパテントになると、特許を取得するウマミが減るので、当然出願件数も減少することになるでしょう。
ところで、国ごとの特許の出願件数は、その国の研究開発活動の活発さに結び付けられ、国の産業競争力の指標ともなっています。
一般的には景気がよく、企業活動が活発な時期は、特許の出願件数が増え、産業競争力も向上すると考えられています。
企業活動が活発な時期は、先行投資として研究開発へ投入する資金も増えるので、成果としての特許出願が増えるというのもうなずけます。
ところが、特許の出願件数は、このような景気や研究活動よりも、政策によって増減することの方が多いように思います。
僕が特許業界へ入った15年ほど前、アメリカのプロパテント政策、IT革命といった産業革新によって、特許業界は空前の好況でした。ビジネスモデル特許などもこの時代です。日本では、年間で40万件近い特許出願があり、2005年頃には40万件を突破していました。
日本は、世界一の特許出願大国でした。
しかし、この世界一の出願件数に手を焼いた人々がいます。特許庁です。
年間40万件を超える特許出願を捌くための人員やインフラが不足し、パンク状態となっていきました。そこで、特許庁が執った政策は・・・。
審査請求料を倍額に増額し、出願件数の多い出願人(大企業)に出願を選別するように要求したのです。
この政策が功を奏したのか、それとも2008年のリーマンショックが効いたのかわかりませんが、2009年頃を境に、日本における特許出願は急激な減少を見せ始めます。年間40万件近かった特許出願は、年々激減傾向を示し、2012年には全盛期の3/4である30万件を切る勢いとなり、現在も減少傾向が続いています。もちろん、上記の政策だけでなく、日本でも訴訟制度の変更(特104条の3の導入)などによる、権利者側の不利感も影響しているでしょう。
とはいえ、2013年頃から日本の景気は回復傾向にあるようですが、特許出願件数は減少が続いています。
このように、アメリカに限らず日本でも、特許出願件数は、景気や産業競争力ではなく、そのときの政策であることが明らかですね。
よく引き合いに出される中国は、特許出願件数が日本とは逆に激増しています。これも、中国の発展もあるでしょうが、中国政府による特許出願推進の政策による影響が大きいことは周知の事実です。
日本の出願件数の減少は、世界の知財制度における日本の発言力の低下に結びつきます。
これに気づいた特許庁は出願件数を増加させるための政策を打っているのですが、効果は見えず減少傾向が続いています。
ちょっとした政策が業界全体に大きな影響を与えるのは、アメリカだけでなく日本も同じですね。

これまで新幹線の話に絡めたTBT協定や洗濯機の話で、「標準化は重要です!」という解説ばかりをしてきました。しかし、「標準化」を進めたばかりにビジネスで失敗した事例もあるので紹介しておきます。
「標準化」というのは、身近には、メートルやキログラムといった度量衡の単位にはじまり、コンセントの形状など、みなさんが安心して生活をするための共通のルールだといえます。
「技術標準」も、工業的な製品をできる範囲で共通化して、コスト削減や部品の共通化を目指すルールと考えても差支え有りません。
そしてこの「技術標準」に含まれるルールにも、様々な技術が含まれており、ときには特許で保護することも必要となってきますし、現実には「技術標準」に採択される技術に対して知的財産をいかに絡めるかが重要な戦略にもなっています。
反面、標準化をするためには、みなさんが安心して使えるように技術の「オープン」が求められるわけですから、知的財産の保護と標準化との間にはギリギリの戦略を構築することが求められます。
ところが、技術標準を目指すあまりに、「オープン」とすべきところと、「クローズ」とすべきところを誤ってしまったケースも当然存在します。例として、DVDやデジタルテレビが挙げられます。
DVDもデジタルテレビも、日本の家電機器・音響メーカなどが主体となって国際標準を策定していきました。そして、それら日本メーカによる技術を中心に国際標準が構築されました。しかし、この技術に対する知的財産の側面からの保護が不十分だったのです。
技術標準は、繰り返すように「標準化」によって部品や制御に関するルールを統一し、コスト削減を目指すものです。そして「標準化」によって、市場には「標準化製品」が迅速かつ幅広く出回ることとなります。これを上手に利用すれば、「標準化」された製品の市場競争力が高められ、「標準化」された自社製品の売り上げ増大に結び付く、というのが標準化によって利益を上げる青写真です。
DVDやデジタルテレビでは、確かに「標準化」によって日本のメーカの技術が世界をリードし、技術的には優位に立つことができました。しかし、これらの分野で「標準化」によって大きな利益を上げたメーカはありません。なぜなら、「標準化」によって部品や制御に関するルールが統一された結果、より安価に部品を製造できるメーカに注文が集中したのです。つまり、台湾や韓国といった国々のメーカの安価な部品が市場に溢れたために、日本のメーカの部品は駆逐されてしまいました。もちろん、性能や耐久性などは日本のメーカの部品が優れていたのですが、より安価な製品が好まれ大規模な売上が見込まれる途上国の市場で敗れてしまいました。
これは、日本のメーカが国内のメーカ間の差別化を視野において高度な技術を中心に知財の保護を進め、「標準化」の根幹となる部分の知財保護が疎かになっていたのが原因です。
結果的には、「標準化」を進めるあまりに技術の手の内を公開してしまったために、これを利用する海外のメーカがあっという間に世界の市場に「標準品」を供給することとなりました。
例えば、南米では、デジタル放送の仕組みとして日本と同一のシステムが採用されているのですが、使用されている受像器つまりテレビのシェアは、韓国のメーカが大部分を占めているのです。つまり、「標準化」では日本が目的を達成したのですが、製品を売って利益を上げる部分では日本は目的を達成することができませんでした。
やみくもに標準化を進めたわけではないのですが、国内に複数のメーカが乱立して互いに競争している日本の場合、自社製品にとって有利な標準化を目指すことで他社を意識するあまり、大切なところを見落としてしまったのかもしれません。
繰り返すようですが「標準化」は、製品の汎用化にもつながります。戦略を誤ると、「標準化」が「敵に塩を送る」ことにもなりかねません。適切に知財を保護することで、この「標準化」を利益につなげることができます。
「標準化」の戦略は、どこを「標準化」するか、どこを自社の強みとして固有の技術として保護するか、「標準化」した技術と自社の強みとなる技術とのつながりをどこで確保するか、など複雑です。
「標準化」と「知財戦略」とは、切っても切れない関係にあるのです。
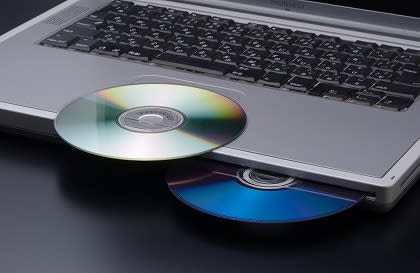
先日の活用例の続編です。
名古屋に住んでいると、弁理士会の活動や顧客への訪問で月に数回は新幹線を利用します。東の東京、西の大阪、名古屋から新幹線は大変便利です。しかも、他の交通機関と比較して「安全」だと思っています。
確かに、この新幹線。みなさんご存知の通り、開業以来「乗車中」の旅客の死亡事故は「0」ということで、日本の安全神話の第1条のようになっています。安全性や時間の正確さは、世界一と誇ることができるでしょう。
さて、その安全で有名な新幹線ですが、どうして安全、何をもって安全と、誰が証明しているのでしょう?
昭和39年の開業以来、「乗車中」の旅客の死亡事故がないのだから、別に異存なく「安全」ということでしょうか?
そうなんです、これも国際規格によって「安全」が証明されているわけではなく、実績の積み上げによって「安全」が保証されているのです。
例えばISOなんかに「時速200km以上で走行する鉄道車両は、開業から30年間旅客の死亡事故が発生しなければ『安全』と定義する。」なんて条項があれば、日本の新幹線は「安全」といえるのですが、実際にはそんな条項はありません。
これが問題となったのが、海外への新幹線の売り込みです。
地震の多い日本でも、地震の影響で走行中の新幹線で旅客に影響が出たことはありません。だから「地震国でなければなおさら大丈夫です。」と言っても、新幹線の導入を検討する国では「安全の基準」が不明確としてなかなか導入してくれません。
欧州などのように各国の鉄道が相互に乗り入れている地域では、当然ながら車両や安全の規格が統一(標準化)されています。閉鎖された島国を走行する新幹線の場合、日本の国内規格(法令)があるだけで、外国でも通用するような安全の規格がありませんでした。
台湾へ行くと、日本のJR新幹線とそっくりの新幹線に乗ることができるのですが、こちらは車両だけが純日本製であり、構造物の規格や信号システムなどは欧州の規格との折衷です。つまり、日本は、システム全体として新幹線システムを売り込むことができなかったのです。
安全性や機能性を証明するためには、客観的な指標としての国際規格が不可欠です。