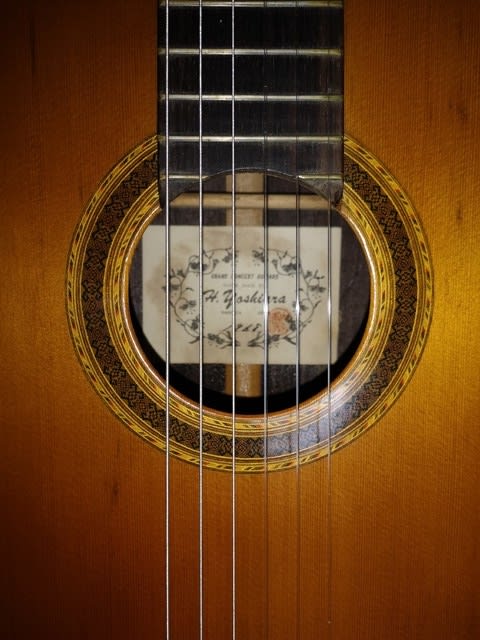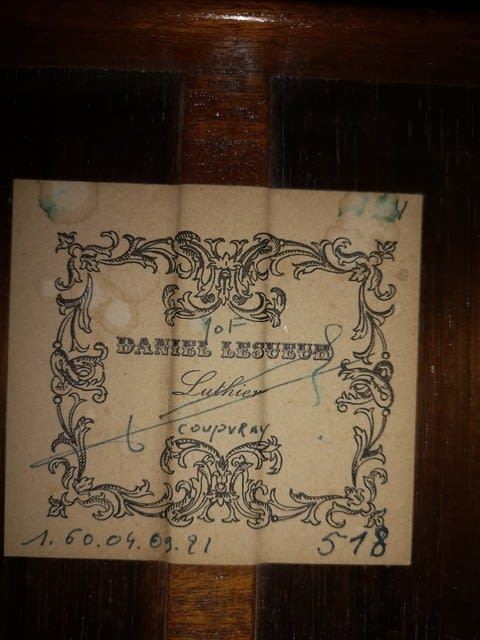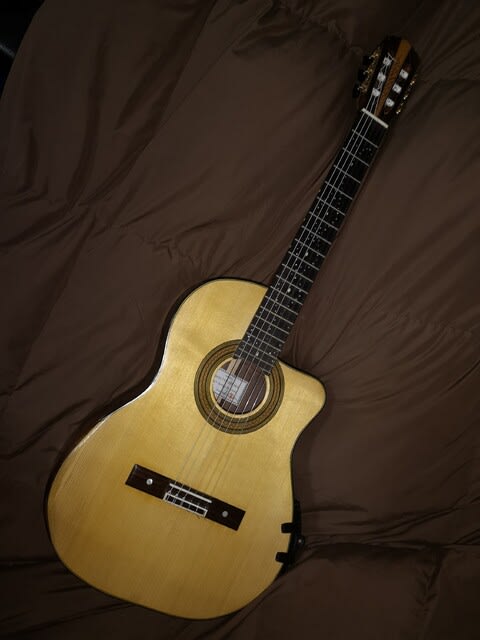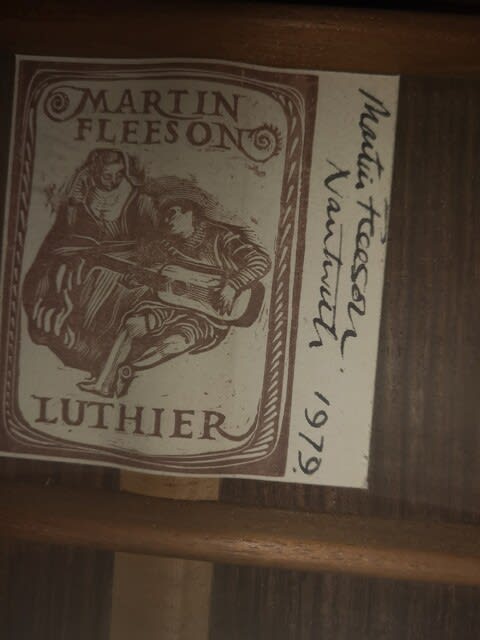このパターンは久しぶりですが、、、、
何か届いた。

あれ????
ギターケースかなあ????(←白々しい!!!)
梱包を剥がすと

やっぱりケースですねえ。
ケースにしては、ちょっと重たいかなあ?
もしかして中身が入っているのかあああああ!!!(←さらに白々しいです。)
箱の中身は?

表面板の黒っぽいヤツですな。
良い面構えです。

少しアップ
裏は

何の材だろう?
俗に言う中南米ローズ???
ラベルです。

川田一高さんの2020年製SKW-55
ワッフルバー構造のギターです。
川田さんのギターは、買っては手放してを繰り返して、これで6台目だったかなあ?
最後は結局、黒田・川田の両巨頭のギターをメインで弾いていく事になるんでしょうねえ。
今回はヤフオクで比較的お手頃価格で落札しました。
とは言え、それなりのお値段です。
それにギターの台数を減らしている最中だった気がする。
また1年間動き続けてくれた私の心臓への感謝のプレゼントって事で、まあまあ良いでしょう。
新たにギターが欲しくなるってのも、精神的に元気なってきている証拠だろうしね。
前向きに考えましょう!!!
今回のギターは、リサイクルショップの出品でギターケースがスーパーライトの赤。
2020年と新しいギターで定価55万円(税抜価格)のギター。
何となくですが、前オーナーは現在施設にいるのか?あるいは旅立たれているのか?
なんて想像してしまいます。
前オーナーが自分の意思で手放すのならば、リサイクルショップ→ヤフオクとはならない気がしてしまいます。
明日は我が身だなあ、、、
写真では判りづらいですが、年式が新しい割には使用感があります。
色々と傷だらけです。
それなりに弾き込まれている感じもします。
普段使いに丁度良い感じです。
さっそく自分仕様に色々とギターに貼り付けました。

中国製アームレスト(脱着式に加工してあります。)

ドイツ製滑り止め(これも剥がせます)

ヒールにマグネットチューナー(当然ですが脱着式)
あとはポジションマーク付けて、弦を張り替えてと、、、
さて弾いて見ます。
おお!!!
低音がパワフルだああ。
音も太く柔らかい音で、中々気持ち良いです。
ダイナミックレンジも大きいです。
音色の変化はつけ辛いかなあ??
黒田ex.が繊細過ぎるのかな。
中々良いギターがお手頃な価格で手に入りました。
もうギターは増やさんぞ!!!
などと思いながら、Jギターを眺めたりしてしまっています。
もう1台くらいは良いかなあ、、、、
何か届いた。

あれ????
ギターケースかなあ????(←白々しい!!!)
梱包を剥がすと

やっぱりケースですねえ。
ケースにしては、ちょっと重たいかなあ?
もしかして中身が入っているのかあああああ!!!(←さらに白々しいです。)
箱の中身は?

表面板の黒っぽいヤツですな。
良い面構えです。

少しアップ
裏は

何の材だろう?
俗に言う中南米ローズ???
ラベルです。

川田一高さんの2020年製SKW-55
ワッフルバー構造のギターです。
川田さんのギターは、買っては手放してを繰り返して、これで6台目だったかなあ?
最後は結局、黒田・川田の両巨頭のギターをメインで弾いていく事になるんでしょうねえ。
今回はヤフオクで比較的お手頃価格で落札しました。
とは言え、それなりのお値段です。
それにギターの台数を減らしている最中だった気がする。
また1年間動き続けてくれた私の心臓への感謝のプレゼントって事で、まあまあ良いでしょう。
新たにギターが欲しくなるってのも、精神的に元気なってきている証拠だろうしね。
前向きに考えましょう!!!
今回のギターは、リサイクルショップの出品でギターケースがスーパーライトの赤。
2020年と新しいギターで定価55万円(税抜価格)のギター。
何となくですが、前オーナーは現在施設にいるのか?あるいは旅立たれているのか?
なんて想像してしまいます。
前オーナーが自分の意思で手放すのならば、リサイクルショップ→ヤフオクとはならない気がしてしまいます。
明日は我が身だなあ、、、
写真では判りづらいですが、年式が新しい割には使用感があります。
色々と傷だらけです。
それなりに弾き込まれている感じもします。
普段使いに丁度良い感じです。
さっそく自分仕様に色々とギターに貼り付けました。

中国製アームレスト(脱着式に加工してあります。)

ドイツ製滑り止め(これも剥がせます)

ヒールにマグネットチューナー(当然ですが脱着式)
あとはポジションマーク付けて、弦を張り替えてと、、、
さて弾いて見ます。
おお!!!
低音がパワフルだああ。
音も太く柔らかい音で、中々気持ち良いです。
ダイナミックレンジも大きいです。
音色の変化はつけ辛いかなあ??
黒田ex.が繊細過ぎるのかな。
中々良いギターがお手頃な価格で手に入りました。
もうギターは増やさんぞ!!!
などと思いながら、Jギターを眺めたりしてしまっています。
もう1台くらいは良いかなあ、、、、