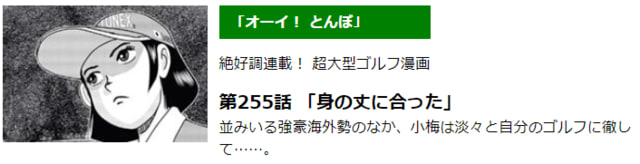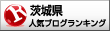以下,『デイリー新潮』よりそのまま転載する。ただし,特別重要な箇所はゴシック色付きで修飾します。
%====転載開始
欠陥を指摘されても準備の遅れが露呈しても、文部科学省がかたくなに見切り発車しようとした、大学入試共通テストの英語民間試験活用。萩生田文科相のおかげで欠陥がわかりやすく伝わり、見送られたが、そもそも問題は、入試改革が某企業ファーストであることにあった。
教育現場の大混乱を受けて、全国高等学校長協会が見送りを強く主張していたが、良くも悪くも、事態を動かす力はむしろ失言のほうが強いらしい。だが、和歌山大学教育学部の江利川春雄教授は、
「強行するよりはよかったにせよ、遅きに失した」
と、こう苦言を呈する。
「大学入試には2年前予告のルールがあります。入試制度を変更する場合は、2年前までに告知するのが前提とされ、2020年度の入試であれば、18年度のうちに告知をしておかなければならないのです」
導入を見送るなら、本来は今年3月までに決める必要があったというのだ。一方、個々の大学は一刻も早い告知を意識していたとみえ、たとえば、東京大学は昨年3月10日、英語民間試験は「合否判定に用いない」と発表した。ところが、ひと月余りのちの4月27日、一転して「使う方向で検討を始めた」と公表したのである。
その間になにがあったのかについて、さる政府関係者は耳打ちする。
「下村博文さんが東大の五神(ごのかみ)真総長と幹部を自民党本部に呼びつけ、“センター試験廃止は教育再生実行会議で決まっている”“これ以上、遠藤(利明)さんを困らせるな”と、叱責したと聞いています。大学への金銭的プレッシャーも仄めかされ、幹部は蒼ざめて帰っていったそうです」
この件を「100%ない」と否定する文教族の下村代議士は、13年1月、第2次安倍内閣の諮問機関として教育再生実行会議が設置された当時、文科相兼教育再生担当相としてこの会議を先導していた。また遠藤代議士も、自民党の教育再生実行本部長として、英語民間試験導入を盛り込んだ教育改革案を、安倍総理に提出していた。
ちなみに、大学入試センターが認定した民間試験は、日本英語検定協会の「実用英語技能検定」やベネッセコーポレーションの「GTEC」をはじめ、6団体の7種類。当初は7団体だったが、7月にTOEICが離脱していた。さらに細分化すると22種類になる。
「それぞれ目的も内容も異なる試験の結果を、セファール(CEFR、ヨーロッパ言語共通参照枠)という一つの規格に落とし込んで測るなんて、土台無理な話です。たとえれば、50メートル走とフルマラソン、走り幅跳びの結果が共通の規格では測れないのと同じことです」
江利川教授はそう言い、今回の決定について、
「萩生田大臣が会見で“自信をもって薦められない”と口にしたのは、率直な気持ちだったのでは。この入試改革は延期ではなく、中止しかありません」
と、きっぱり語る。それにしても、全国の高校の現場からも、個々の高校生からも悲鳴ばかりが聞こえてくるこんな「改革」が、なぜギリギリまで推し進められてきたのだろうか。
京都工芸繊維大の羽藤由美教授は、
「今回の入試改革をさかのぼれば、安倍内閣のもとで13年、教育再生実行会議が第4次提言を公表したことに端を発します。このときの文科相は下村さんで、それ以来、すべては“民間ありき”でズルズルと話が進んでいきました」
と指摘。文科省担当記者が補って説明してくれるが、そもそも、英語民間試験は教育界からでなく、産業界から湧いた話だった。
「13年6月、“大学の英語入試への民間検定試験の活用をめざす”という内容が盛り込まれた、第2期教育振興基本計画が閣議決定されました。ただ、そこに至るまでの前段があります。13年2月、楽天の三木谷浩史会長兼社長が、自民党の教育再生実行本部で“英語ができないため日本企業が内向きになって、世界の流れに逆行している”と指摘、大学入試にTOEFLを導入することを提言しました」
すると、それを受けるかたちで翌3月に、
「遠藤本部長の下、実行本部がまとめた教育改革案に“TOEFLを大学入試に活用する”という内容が組み込まれました。続いて5月には、教育再生実行会議が、“TOEFLなどの民間試験の活用”などを含む提言を安倍総理に提出し、翌月の閣議決定につながっていきます」
また、実行会議では、
「“TOEFLは問題が難しすぎるから、ほかの試験を活用するべきだ”という意見が出されました」
こうしてGTECなども認定の対象になったのだが、ともかく、民間への“払い下げ”を主導したのが、塾や予備校業界から受ける献金により、たびたび問題視されてきた下村氏であった。
ただし、下村氏とタッグを組んだ感のあった楽天について、江利川教授は、
「楽天社員の葛城崇さんが、14年から2年間、文科省初等中等教育局国際教育課に出向して、読む、書くのほか、聞く、話すを加えた英語4技能化のキーパーソンとして、英語教育改革に従事していました」
と話すが、週刊誌にそのことが報じられると楽天は失速。その後、急速に食い込んだのがベネッセコーポレーションで、
「入試用に認定された民間試験のうち、ベネッセが主催するGTECが、大勢の受験生を集める試験になるのではないかと、最有力視されていました」(同)
だが、ベネッセについて深く覗く前に、子供たちの一生を左右する入試改革が、いかに民間主導で進められていたか見ておきたい。文科省関係者が言う。
「各民間試験とセファールの対応関係を決めるための文科省の作業部会は、メンバー8人のうち5人までもが、GTECのベネッセや、英検の日本英語検定協会など、民間試験を実施する団体の幹部職員でした。民間試験をどう測るかも、民間企業にお伺いを立てて決めているんです。また、作業部会の主査は、日本英語検定協会主催の試験TEAPの開発者の一人、上智大学の吉田研作教授で、主査代理である東京外大の根岸雅史教授や、部会員でやはり東京外大の投野由紀夫教授は、共にベネッセのHPにGTECの推薦者として名を連ねています」
ベネッセ関係者が目立ってきたが、この程度にはとどまらないという。
「14年12月、中央教育審議会会長として“民間資格・検定試験の活用”という方針を打ち出した安西祐一郎氏は、GTECをベネッセと共催している進学基準研究機構(CEES)の評議員でした。教育再生実行会議委員だった武田美保氏もCEESの理事。元民主党参議院議員で、14年に当時の下村大臣に招聘されて文科省参与に就任、15年から18年まで文科相補佐官を務めた鈴木寛氏は、ベネッセグループの福武財団の理事です。文科省とベネッセグループは一心同体で、“第二の加計疑惑ではないか”という声も聞こえます」
そう語る文科省関係者によれば、個別の大学にもベネッセ関係者の天下りが増加中だという。
「たとえば、大阪大学高等教育・入試研究開発センターの山下仁司教授は、ベネッセでGTECの開発統括を務めた人。旧帝大で阪大だけが英語民間試験を必須としていたことと、関係があるといわれています」
もはや受験生ファーストでなく、ベネッセ・ファーストの入試改革が進んでいたようにさえ見えるが、そうなった背景を教育ジャーナリストが説明する。
「14年に発覚した個人情報漏洩事件で、ベネッセは250億円を超える特別損失を計上。また事件を機に主力の“こどもちゃれんじ”や“進研ゼミ”など通信教育の会員が減少したため、一刻も早い業績回復が急務とされていました。その点、入試に英語民間試験が導入され、毎年、仮に20万人の受験生がGTECを選ぶことになれば、1回7千円として1人2回受けるとして、黙っていても28億円の売り上げが加算されます。そのうえ、GTECを受ける子は当然、GTECを作っているベネッセの問題集を買い、通信添削も受けておこう、ということになるでしょう」
だが、それだけではない。
「ベネッセの営業マンは全国の高校を巡回し、模試や教材を売っていますが、高校にすれば買わざるを得ない状況にあるのです。ベネッセは8月には、大学入試共通テストに新たに導入される記述式問題の採点業務を、61億円で落札しています。加えて英語民間試験でも、GTECの受検者が多ければ、入試に関する情報をもっているベネッセの教材を、高校が無視できるはずがないのです」
さらには、大学にもプレッシャーをかけていた、と打ち明けるのは、某大学関係者である。
「ベネッセは大学に、合格者のGTECのスコアが何点だったとか、他大学との併願状況がどうだとか、受験生情報を売りさばいています。実際、私学の担当者は、そういうデータを見て受験日を設定したりしますが、特に併願情報については、ベネッセは1学部につき350万円で販売しています。教育に関わる企業の倫理として認められるものでしょうか。リクナビが企業に学生の情報を売って問題視された件と、どう違うというのでしょうか」
ベネッセに聞くと、
「スコアデータは個人が特定できないもの」
「志望動向を350万円で販売している事実はない」
と答えるのだが。
また、別の大学関係者が語るには、
「世界大学ランキングを発表する『タイムズ・ハイヤー・エデュケーション』誌を有するTES Globalの国内総合パートナーで、各大学にランキングの上げ方を指南しています」
入試が牛耳られ、大学は弱みを握られ、ベネッセに逆らうのは、高校にとっても大学にとっても困難だったという。それがいまは頼みの綱が失われ、株価も急落した。しかし、
「下村氏は見送りが決まってからも、まだ入試改革をあきらめていません。自民党内の部会では、国が英語民間試験の導入を私学助成金で支援することまで仄めかしています。導入しなければ助成金をもらえないのか、と大学側は受けとりかねません」(羽藤教授)
絆は強いようだが、「甘い汁」は、未来を担う受験生を犠牲にして吸い上げられるものだと、業者も政治家も、どこまで認識しているのか。教育さえ利権の対象にする姿勢は、醜聞が噴出する安倍内閣のタガの緩みと、無関係ではあるまい。
%=====転載終了
自分は,萩生田大臣には御礼をいうほかない,とあらためて思う。
- 「身の丈」発言のおかげで問題喚起された。
- 教育問題に興味の薄い層にまで訴求した。
- 結局,共通テストでの民間試験採用は延期にはなった。
- 英語4技能以上に問題の多い,記述式採点についても,ようやく語られた。
これら「実績」は萩生田「身の丈」発言がすべてのきっかけ。持論は展開していたが,ようやく僕の主張も「ありていな」主張になってきた。
週刊誌が政治を変えるという事実がここ何年も続いている。
権力と闘う「決意」は,誰にでもある。
各大学・受験生・高校は,上記の一連「パワハラ」に屈することなく,「生きた学習」を,いままさに起きている事象から真実を掴み取ってほしい。

 。
。