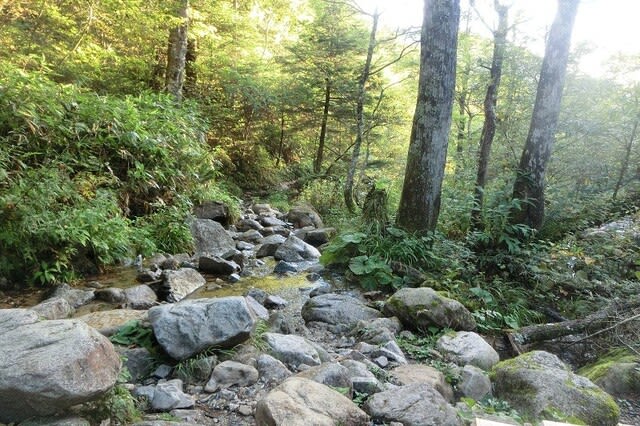新年の扉は激しくきしむ音を立てて開いた。
元日の参拝は、毎年決めていることであるが、深夜に一人家を出て、近所の神社まで往復一時間ほど歩き、仕事の成就を祈願する。もう十何年もこんなことを続けている。この時ばかりは一人でないと意味がないと思うし、それも深夜じゃないと効き目が薄い気がする。もちろん、そんな意味や効き目など、最初から独りよがりに過ぎないことも重々承知している。
今年の元日は例年ほど寒くなかった。それでもスキーウェアを上下に着こみ、毛糸の帽子をかぶってマスクをして、防塵服のような完全防寒体制で出かけた。神社にいた、和気あいあいとした若者や家族連れにはさぞ異様な光景に映ったろう。
こちらは毎年これを続けているのだ。万が一にも風邪菌をもらわないよう配慮してのことだ。どう思われようと知ったこっちゃない。
お参りして破魔矢を買って、帰宅して寝て起きたら正月である。雑煮を食べ、年賀状を読みながら、自分はなぜこんな風に同じことを繰り返したがるのだろう、などと考えていたら、地震が来た。ゆっさゆっさと音のするような揺れだった。慌ててテレビをつけると、臨時ニュースで、石川県などの様子が映し出されていた。慎ましく穏やかだったはずの日常があっという間に奪われていく。それは、心を持たない悪魔に鷲摑みにされたような悲劇だった。
呆然とテレビを眺めるしかなかった。阿呆のように目を見開き、繰り返し流れるニュースにくぎ付けになった。東北の地震と津波のときもそうだったように。もっとさかのぼれば、アメリカのツインタワーが煙を上げて崩れゆくときもそうだったように。いつでも自分はただ眺め、無力だった。熊本の地震の時も。台風で長野市が水浸しになった時も。
平凡な日常というものがいかに貴重であるかを、どうしてこういう大惨事を目の当たりにしたときでしか、自分は自覚できないのか。
自分は本当に、できることをしてきたのか。
まずは目を閉じ、黙祷せよ。