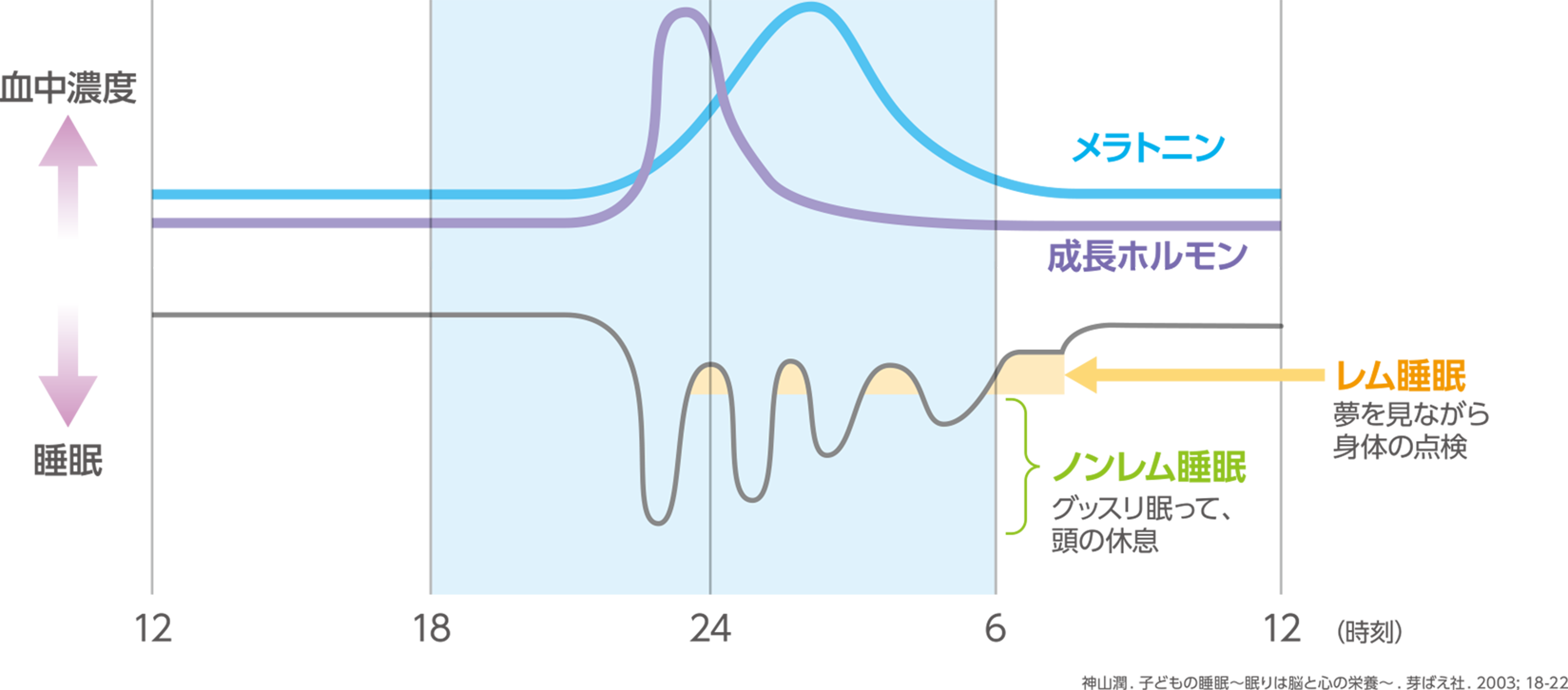防災の日・救急の日
あらゆる災害に対する防災知識の普及や備えを強化することを目的として、防災の日を含む1週間(8月30日~9月5日)を防災週間とされています。
防災の日
台風や地震、津波などといった災害についての認識を深め、災害に対する心構えを準備する日として1960年に制定されました。1923年に起こった関東大震災の日が9月1日であったため、9月1日が防災の日と定められています。
保育園では、火災・地震・水害などを想定して毎月避難訓練を行っています。こども達と「おかしもち」のルールを約束し、避難訓練を行っています。
お「押さない」、か「駆けない(走らない)」、し「しゃべらない」、も「戻らない」、ち「近づかない」
地震時の避難行動について以下のサイトを参考にしてみてください。
東京消防庁<安全・安心情報><地震に備えて:地震 その時10のポイント>
家族で話し合っておきましょう!
①避難所・集合場所
避難所はどこなのか、地図を見て確認しておきましょう。また、家族と一緒にいる時に被災するとは限りません。どこで集合するか決めておきましょう。
②連絡方法
スマートフォンが使えなくなる場合もあります。どこにどのように連絡を取るのか、また災害用伝言ダイヤル(171)の使い方も一緒に確認しておきましょう。
③非常用持ち出し袋・備蓄
非常用持ち出し袋の中身や食料品の備蓄は十分か確認しましょう。賞味期限が近い物は食べ、新しく買い足しましょう。
非常用持ち出し袋や備蓄に関して首相官邸より提示されている、災害の「備え」チェックリストを参考にしてみてください。
災害が起きる前にできること | 首相官邸ホームページ
救急の日
9(きゅう)と9(きゅう)のごろ合わせで9月9日を救急の日と言います。
救急の日を機会に、よくあるケガの応急処置についてお話しします。
応急手当
【切り傷・擦り傷】
①傷口を流水でよく洗い流し、清潔なガーゼなどで押さえて止血します。
②傷口を市販の傷パットなどで覆い、保護します。傷口を乾燥させないようにしましょう。
※ 受診が必要とされる場合
砂利などが多くついて取れない時 鋭利なもので切った時 出血が続く時 傷口が深く大きい時 化膿した時 など
【爪が剥がれた】
①傷口を流水でよく洗い流し、清潔なガーゼなどで覆います。
②爪が剥た時はそのまま爪を元に戻します。汚れた手で傷口を押えないようにしましょう。
※ 受診が必要とされる場合
爪が剥がれて痛むとき 爪が大きく欠けて出血したとき 化膿した時 など
【捻挫・打撲】
すぐに冷やしましょう。放っておいているうちに、腫れがひどくなってきて治りが悪くなります。とにかくすぐに安静にして冷やします。
腫れや変形がひどい場合は、すぐに病院に行きましょう。
捻挫・打撲をした時の応急処置はRICEが基本です!
RICE処置は、損傷部位の障害を最小限にとどめるためにおこなう応急処置です。
R(Rest)安静:ケガしたところを動かさないようにします。無理に動かしたり、体重をかけるとケガが悪化することがあります。
I(Icing)冷却:冷却することで、痛みをやわらげ、内出血や炎症をおさえます。15 分~20 分を目安にして感覚がなくなったらはずして、痛みが出たらまた冷やすことを繰り返します。
C(Compression)圧迫:圧迫します。出血や腫れを防ぐために、弾性包帯やテーピングで軽く圧迫するように巻き
ます。強く巻きすぎていないか、しびれがないか、指先が変色していないかを確認します。
E(Elevation)挙上:挙上します。心臓より高い位置に上げることで、内出血を防ぎ、痛みをやわらげることが出来ます。
【鼻血】
小鼻の上を指で圧迫し、下を向きましょう。
なかなか止まらない時は鼻の上部を冷やします。
【蜂に刺された】
①刺された場所から離れましょう。
②蜂の針が残っているときはそっと抜きましょう。
③蜂に刺された部分を流水で洗い流し、毒液を絞り出すようにしましょう。
④患部を冷やしましょう。
⑤応急処置をしながら様子を見て、必要な場合は病院を受診してください。
【目にゴミが入った時】
洗面器の水に顔をつけてまばたきをします。
【火傷】
①すぐに15~25℃程度のきれいな水で流し続けて冷やしましょう。痛みがなくなる程度まで冷やしましょう。
②衣類は無理に脱がさず、服の上から冷やしましょう。
③痛みが和らぐまで15~20分程度冷やしましょう。
④氷やアイスパック、氷水は避けましょう。
※水ぶくれは雑菌が入るため、潰さないようにしましょう。
火傷が広範囲の場合は、迷わず救急車を呼びましょう!
【♯8000】
休日・夜間のこどもの症状に困った時に小児科の医師や看護師に判断を相談できるダイヤル番号です。受診するか判断に困ったときは、相談してみるといいでしょう。
救急用品を点検しましょう!
▢体温計 ▢絆創膏 ▢包帯 ▢ガーゼ ▢サージカルテープ
▢脱脂綿 ▢清浄綿 ▢綿棒 ▢三角巾 ▢ピンセット ▢毛抜き
▢爪切り ▢ハサミ ▢氷嚢 ▢熱さまシート ▢ポリ袋
▢ポケットティッシュ ▢ウェットティッシュ ▢湿布薬 ▢消毒液
▢化膿止め ▢虫刺され用軟膏
▢総合感冒薬 ▢解熱鎮痛薬 ▢下痢止め ▢胃腸薬 ▢目薬
ご家庭に救急箱はありますか?いざという時の為に必要な物をそろえておくと安心です。ときどき中身をチェックして、期限の切れた薬品の入れ替えやよく使うものの補充をしておきましょう。
最近、地震やゲリラ豪雨、雷雨、洪水などの災害が続いております。万が一の為に備えておきましょう。