| 覚書2020.7.13 ―言葉の舟 1. 当たり前と思われるかもしれないが、同じ言葉でも発する、あるいは受けとめる人によって言葉は固有の色彩やイメージを持っているように見える。もちろん、言葉は誰にでも通じるという概念や意味やイメージの一般性(共通性)も持っている。例えて言えば、「言葉の舟」という点では共通でも、それぞれ大きさや形や飾りや速さの違う言葉の舟によって言葉は運ばれ、そのような言葉の舟によって受けとめられる。遙か太古からの長い時間のくり返しの中で、そのことは割りと自然なものとなっている。 八月六日の昼前磯介が久しぶりに泳ぎに誘いに来た。僕は彼と連れ立って海へ向って歩き出した。 「米屋の兄さまが死んだとよ」と磯介はしばらくしてから不意にいった。 「えっ?」 「米屋の兄さまって、松の姉さんの」 「これよ」といって、磯介は拇指を立てて見せた。 「本当に死んだのかい」 「アメリカの飛行機に撃たれてな。舞鶴で何やら作業をしとった時にやられたとよ」 「機銃掃射に会ったんだね」 「それよ」と磯介はいった。「キジュウソウシャに会ったんやと」 「気の毒だね」 「ああ」と磯介はいった。 (『長い道』P423 柏原兵三) 中公文庫 主人公の少年杉村潔と知り合いの磯介とが話している。磯介は、説明しながらたぶん「機銃掃射」という言葉が出て来なかったのだろう。「キジュウソウシャ」というカタカナ書きの言葉は、その言葉が自然に出て来る杉村潔と違って磯介にとっては知ってはいても十分に使いこなせる自分の言葉になっていなかったということが表現されている。これらのやりとりは、「機銃掃射」という言葉自体とは別の、先に述べた言葉の「固有の色彩やイメージ」の二人における違いを示している。 ここでは、「機銃掃射」以外の二人の会話は自然に運んでいるように見える。しかし、磯介の語った言葉を「〈アメリカ〉〈の〉〈飛行機〉〈に〉〈撃たれ〉〈て〉〈な〉。〈舞鶴〉〈で〉〈何やら〉〈作業〉〈を〉〈しとっ〉〈た〉〈時〉〈に〉〈やられ〉〈た〉〈と〉〈よ〉」と分解してみるとわかるように、ここにはたくさんの言葉(単語)が連結されている。しかも、この言葉の内容は、磯介が誰かから聞いた伝聞の言葉である。こうした言葉のやりとりが、自然になされているということはなんらふしぎには見えないが、それは人類の歴史や個の歴史の中でくり返しくり返して培われてきたからと言うほかない。人の生涯においても、まだ言葉の経験が少ない小さい子どもにはこういう言葉の表現や理解は不可能である。 2. 柏原兵三の『長い道』という作品は、村瀬学『いじめの解決 教室に広場を』(言視舎2018年)の「第3章 いじめを描く文学作品の読み解き ―「文学の力」へ」で取り上げられている。それがきっかけで読んでみた。 この物語は、主人公の少年杉村潔が、昭和十九年九月に戦時下の「縁故疎開」(学童疎開)で東京から父の故郷の北陸の舟原村にやって来るという話である。そこで、学校を中心とする場でいじめを含む少年たちの徒党を組む物語が展開する。そういう徒党を組む、媚びへつらう独特の少年期の権力構造が切開される。いじめられたりもする主人公の、中立を選びたいとかはねのけたいと思いつつ付き従ってしまう、揺れ動く内面の劇がこの作品のモチーフだと思われる。その内面は、わたしたち読者にはたぶんよくわかると思われるが、学校の教師や家族の父や母からは見えないもの、見えにくいものとして描かれている。この作品は、依然として現在的でもあり、長い時間に耐える作品である。つまり、人間が容易には解決できないいじめと徒党を含む人類的な課題、個と集団の問題に触れているからである。 このことを、言葉の問題に引き寄せて言えば、ひとりひとりの個の固有性と自由を制圧したり抑制したりすることのない、あるいはそのようなものを欲求する言葉や物語は、どのように描かれるかという問題になる。 『長い道』という作品は、序章・全十二章・終章の構成になっている。九章で物語の流れが大きく転回し、学校を主な場として続いてきた進の徒党権力がつぶされ、松の徒党権力にとって変わられる。学校へ通う「長い道」は、主人公の潔に課せられた未来の見えない底なし沼のような試練である。こうした閉塞的な精神の状況が死を呼び寄せるのは自然であろう。最後は、主人公の潔本人による解決ではなく、敗戦が縁故疎開を終わらせて東京に引き揚げることになる。いじめの状況がこうした現実の小さく見える偶然によって解除されることも少しはあるのだろうと思う。 そうした偶然によって潔は救われることになるが、作者は主人公の潔の揺れ動く内面に誠実に付き合おうとしてきているように思われる。当然ながら、「ひとりひとりの個の固有性と自由を制圧したり抑制したりすることのない言葉や物語」は、ここで描かれているようないじめの現実や構造を白日の下に描き出すことの中からしか小さな明かりのようなものとして未来に光を放つことはあり得ない。言ってみれば、「ひとりひとりの個の固有性と自由を制圧したり抑制したりすることのない言葉や物語」は、言葉の舟がネガティブでしかあり得ない現実のなかを進みゆく様を、言葉は隠し立てすることなく描写する欲求を持っていると言うことができる。それが作者の表現の倫理であろうと思われる。 |
最新の画像[もっと見る]
-
 水詩(みずし) #5
5日前
水詩(みずし) #5
5日前
-
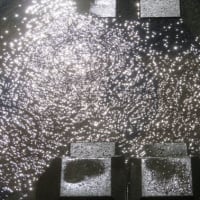 画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
1週間前
画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
1週間前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2週間前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2週間前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2週間前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2週間前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2週間前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2週間前
-
 最近のツイートや覚書など2024年6月
1ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年6月
1ヶ月前
-
 最近のツイートや覚書など2024年6月
1ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年6月
1ヶ月前
-
 水詩(みずし) #4
1ヶ月前
水詩(みずし) #4
1ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
1ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
1ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
1ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
1ヶ月前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます