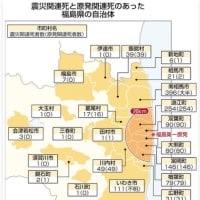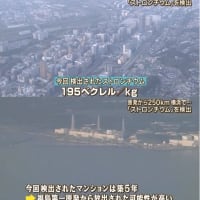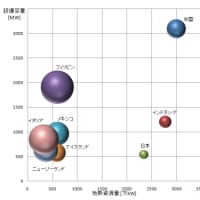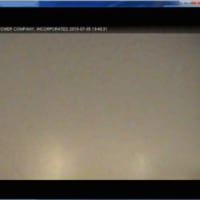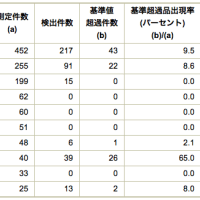先日、京都国立博物館で開催されている『没後200年記念上田秋成 展』を拝見する機会を得ました。
浅学非才な僕は上田秋成というと怪異小説『雨月物語』を溝口健二監督の映画で二度ほど見たことしかなくて、ほとんど無知ですので、京都国立博物館の歴史的な文人にスポットライトを当てて大規模な展覧会を催すという意気込みにとても興味を持ち、展覧会場を割と丁寧に見て回りました。不遇な幼少期の逆境を跳ね返して小説や俳諧、和歌、国学の分野で多くの書物を残して、18世紀後半の関西のインテリゲンチャとして見事に面目躍如し、国学者の本居宣長と激論を交わしたり、円山応挙や呉春をはじめ池大雅、与謝蕪村や、交友のあった田能村竹田、伊藤若冲らの文人や画家たちとの幅広い交友関係を物語る展示品が数多く出品されていて、18世紀後半の文学と芸術の世界を垣間みる事ができ、とても学ぶことが沢山あります。美術館の解説目録をみていて、特に驚いたのは円山応挙の『四季富士図』という安永8年に描かれた四幅対についての解説です。「とてもいい絵だな、うまいな」と即座に自分は思ったのですが、解説では、応挙は「旅嫌いで知られ、恐らく実際の富士は見ていない」と書かれていました。また、応挙の『龍門図』という作品は名品である、と思うのですが「中腹の鯉のみ、鱗に金泥の縁取りが入っており、今まさに龍になろうとする瞬間が表されている」という解説にとても感動しました。偏見かもしれませんが歴史上の人物として上田秋成という名前を知っている人はかなり少なくなっているように思うのですが『没後200年記念』と題して歴史的な偉人を再評価する主催者の誠実な姿勢に敬意を表したいと思います。簡単な展覧会図録(500円)が作られていてとても楽しめます。展覧会は☆☆☆でした。