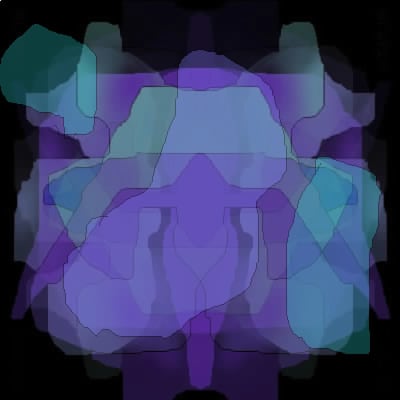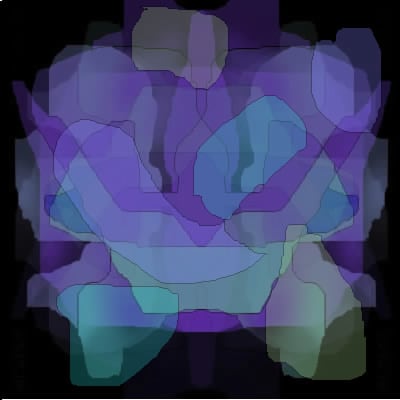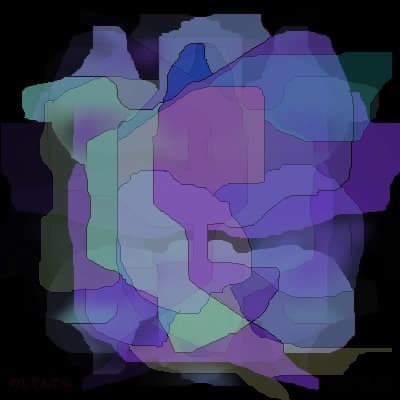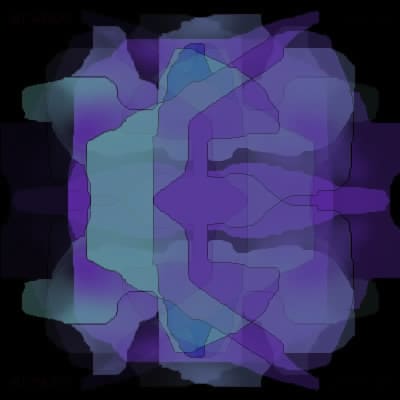ペンキのはげ落ちた板壁の向こうは、死んだように空気が淀んでいた。歩くと古びた板張りの廊下が大きな音をたてて四方に響き渡った。
その廊下は狭く、直線に通っていた。廊下に添って教室が並び、その教室の入り口は釘や南京錠で止められて、中に入ることができなかった。
それでも、戸の開くところがあって、覗けばそこは意外にも小さな、小学生が使うような教室だと思われた。埃にまみれて机や椅子が雑然と転がり、長 . . . 本文を読む
学生たちが三々五々、グループで下りてくる。彼らは私を見て決してよそ者とは思わないだろう。私はきっと商大の学生のように見えているに違いない。彼らとすれ違うたびに私はそう思った。
私は何気ない顔をしてキャンバスに入って行った。学舎は春休みのためであろう、学生の姿はなく閑散としてほとんどその入口は施錠されているようだった。
それは先ほどのすれ違った学生たちの活気からは想像できなかった静けさだ . . . 本文を読む
私は爽やかな気分で自分のペースを取り戻して歩き始めた。
するといくらも行かないうちにパン屋があった。ちょうど昼時であったし、小林多喜二をまた思い起こさせたので、私は一度通り過ぎた店の前を折り返してそのパン屋に入って行った。
中は薄暗く、外光に焼けた目にはすぐにその店の様子が分からなかったが、奥に人かげが動き、ようやくそれが店の女主人だとわかった。
私はパンを買い、その場でほおばりながら、 . . . 本文を読む
交差点で進路を迷っていると、一人の老人が坂を上ってきた。私が老人に道を聞くと、この道をまっすぐじゃと、しわだらけの顔をほころばせて教えてくれた。
私はその老人を一目見て気に入った。足もとが不自由らしく、訥々と杖をつきながら老人にはきついこの坂を上っていく。
私はその老人の歩調に合わせて、わざとのんびりした足取りで歩き、ゆっくりと喋った。
老人は小樽商科大学を知っていたが、伊藤整のことは知 . . . 本文を読む
小樽の駅から右に行くと、すぐガードの下をくぐる坂道に出、それが小樽商科大学に続く上り坂のゆったりとした坂道であった。
この坂道を、伊藤整たちは女学生とあと先にになりながら、それぞれに青春の思惑を抱いて学校に通ったのだ。遠くに向かう思いが懐かしさに似た感情を伴って浮かんできて、その思いと歩調を合わせるように私はゆっくりと坂を上りはじめた。
雪解けの水が絶えず流れ下って来るその坂道を、清楚な面 . . . 本文を読む
千歳から札幌までの電車の中で、里依子に伊藤整の本を開いてみせたのであったが、その時私は「蘭島村」とあるのを「ラントウムラ」と読んで彼女に示した。すると里依子は笑いながら「ランシマ」と読むんですと教えた。あるいはまた、「塩谷村」を「シオタニムラ」と言えば、本当に楽しそうに微笑みかけて「シオヤ」だと教えるのだった。それが可笑しくて私たちはもう一度笑った。その時の里依子の表情が実に爽やかで愛おし . . . 本文を読む
列車を待つ間も、電車の中にあっても、終始心は晴れなかった。
里依子はなるべく私といたくないと思っているのだろうか。そんな考えがいくら否定しても湧き上がってきて私を悩ませた。
列車がいよいよ小樽に着くころになって、私はもう一度伊藤整の本を取り出し、これからの道順を考え始めた。
私の前に札幌からずっと一緒に座っている若い男女がいた。二人は私のことなどまるで意識もしていないようだったが、私の方は . . . 本文を読む
「今夜札幌から夜行列車で流氷を見に行きませんか。」
以前里依子の手紙に、流氷を見に行きたいというこを書いていたことを覚えていた私が、咄嗟に思いついたことだったが、あるいは彼女も賛成するかもしれないと思ったのだ。
ところが彼女はだめだと言った。次の日に会社の祝賀会があって、その受付をしなければならないというのだった。
何度か勧めてみたが、彼女は首を横に振るばかりで、残念だと言えば一人で行 . . . 本文を読む
里依子は札幌までの切符を買った。
私は不審に思って、そのことを里依子に訊いた。札幌は小樽の手前の駅なのだ。
「昨夜電話をしたら札幌まで迎えが来ることになったんです。だから先に小樽まで行ってください。」
それは彼女の親戚の家からの出迎えのことらしかった。小樽まで一緒にという昨日の約束が、その日のうちに反故になっていたのだ。
「そうですか・・・」私はそう応えたものの淋しい気持ちの湧き . . . 本文を読む
次の朝8時に里依子から電話があって、40分にタクシーを拾って行くと伝えてきた。
今日は千歳から小樽までの間が、里依子と一緒にいられる唯一の時間となるだろう。それはここにやってくる時からわかっていたことで、里依子は小樽の親戚の家に、私は小樽の街を一人伊藤整の本を片手に歩き回る予定だった。
それは「若い詩人の肖像」という本で、詩人伊藤整の青春期をその詩情と共に描いた私小説だった。いい本だからと . . . 本文を読む