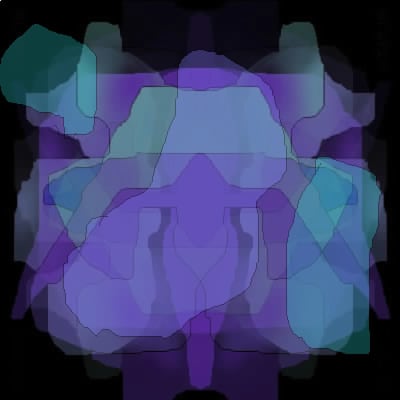
千歳から札幌までの電車の中で、里依子に伊藤整の本を開いてみせたのであったが、その時私は「蘭島村」とあるのを「ラントウムラ」と読んで彼女に示した。すると里依子は笑いながら「ランシマ」と読むんですと教えた。あるいはまた、「塩谷村」を「シオタニムラ」と言えば、本当に楽しそうに微笑みかけて「シオヤ」だと教えるのだった。それが可笑しくて私たちはもう一度笑った。その時の里依子の表情が実に爽やかで愛おしく思えたために、私はそれらの言葉をひそかに胸の奥にしまいこんだ。
そのおかげで、いま目の前にいる若い男女に笑われずに済んだのだ。
やがて電車は小樽についた。私は二人に礼を言い、スケッチブックを片手に席を立った。
駅前の電話ボックスに入り、私は早々ワシントンホテルを呼び出した。しかしそこに出たフロントの係員はそっけなく満室だということを伝えてきた。
特に宿の心配はしなかったが、今夜の連絡は里依子からそのホテルに電話するということであったから、私はそのことが気になった。
里依子が今日予定通りに寮へ帰るのなら連絡の方法はあるが、万一小樽の親戚の家で泊まることになったらこれはもうどうしようもなくなる。
昨日小樽まで一緒のはずの約束が小樽の親戚の一言で変わったのだから、今度もそれは十分考えられるだろう。いろいろとよからぬ考えは巡ってきても、いい方法は思い浮かばなかった。
里依子がホテルに電話しなくていいのですかと聞いた時、素直に電話をかけていればよかったと後悔し、しかしなんとかなるだろうと思い直して私はまず、伊藤整の通ったという高等商学校に行ってみることにした。
今は小樽商科大学という名に代わっているはずで、これも里依子の教えてくれたことだった。そしてその校舎は今もその場所にあって、小樽の港町を見下ろしているはずであった。
 HPのしてんてん
HPのしてんてん 



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます