きのう開催されたがまかつの小国川大会の様子です。
2時30分前に、目覚まし時計がなる前に起床。 用意して自宅出発は3時15分頃。外は雨、細かい霧状の雨が音もなく降っています、舞っている感じ。 今回のR48は仙台から山形方面に行く車が数台あり。 25日のダイワの時とはかなり異なる。
今回の大会参加が最後となるかもしれないので、車の中ではラジオではなく ピンクフロイド を聴く。 もう40余年のピンクフロイドのファンであり、CDもたくさん持っています。 #原子心母#、久しぶりに聴きます。 心が落ち着きます。 次に#THE WALL#、帰りは #DELICATE SOUND OF THUNDER# を聴きました。
県境の関山トンネルと超えるとそこに広がっていたのは、何となんとナント”乾いた道路”でした。そして明るさ(といってもまだ暗いのですが)の違う空が待っていました。嬉しかったですね、晴れている!これなら気温も上がるかもしれないと勝手に思ってしまいます。
途中道の駅でトイレ休憩(25日の時は節水にご協力くださいという張り紙があり、一体何のことかと不思議でした。こんなに雨が降っているのに水が足りない?これはどういうことか? そしたら水が多すぎて処理能力を超えていたのでした。 浄水能力が間に合わなかったための節水であり、断水でした。TV報道で知りました。こういうこともあるのかと意外な盲点に驚きました。)、コンビニで食料の確保をして、舟形町へ向かいます。
丹生川は以前よりも減水しており、この分なら小国川も減水傾向にあるだろうと内心少し嬉しくなりました。私にとっては水量は少ないほどいい!!
5時前後に集合場所到着。小国川は幾分神秘的な流れとなっていました。
(一関大橋の上流側)

(下流側)

遠くに月山が見えます。 考えてみると月山を見るのは7月に入って初めてかも。

雪を抱いています。

月山が見えたし、川は澄んでいて水量もやや少なくなっているし、東の方面が明るいのが嬉しかったですね。 これは時間の経過とともに陽も射し、夏らしい夏となってくれるかもしれない。 気持ちがいいものです。

駐車場で懐かしい地元の釣り友、かって一緒にがまかつの全国大会に出たことのある人に会え、いろいろ雑談しました。 (もう一人の全国大会参加者はシマノとダイワには出たのですが、がまかつは出ていなかったようです。) なぜか話が家族のことになり、何となんとナント彼の3人の孫の一番年下の子は仙台育英で野球部に入っているとのこと。きょう仙台で試合(夏の甲子園大会)があるかどうか心配していました。 意外でした。 一番若い孫が18歳高校生で、その上に二人の孫がいて、一番上はもう結婚して一緒に生活している、とはいっても二世代別々とか言っていました。 そんなに大きい孫がいる歳だなんて、全く想像もしていませんでした。 そうであれば70歳は超えているのではないかと思います。年齢は聞きませんでしたが。 そしてそろそろ大会は引退しようかと思っているとも言っていました。 そこまで大会で頑張っていたんだ!と思うと、こっちも負けてはいられないななんて思ったりして、まことに人間はいい加減なものです。勝手ですね。少々考えてしまいました。 (彼もBグループです。)
5時30分から受付開始。 がまかつはABCと3つのグループに分かれます。 私はB-12でした。 Aは上流域で長沢堰堤下流、Bは大会本部から歩いていける経壇原、Cは国道までの下流域となります。 今回初めて上流域に入る(入らざるを得ない)ことになります。 もともと経壇原は好きな場所ですので、あとはどこに入るか、入れるかということになります。
丁度下の写真の上流域、写真でいえば中央右側になります。

Bグループは24人。 オトリは24番から自分で選び、入川は1番からとなります。10秒おきで、追い越し禁止。 B-12はちょうど真ん中、オトリを選ぶとき樽の中には4匹しかオトリが入ってなく、選ぶのは容易かったですが、いいオトリがいなければ惨めになってしまいます。 やや大き目と中型のオトリを選び、下流に向かいました。 大半の人は上流を目指します。 敢えて下流の急瀬・荒瀬を選びました。
というのも741CHフィッシングTVでみた「2013 鮎」で、ダイワマスターズで2回優勝している瀬田匡志の6月下旬の中国地方での鮎釣りを参考にさせて貰いました。 彼の語り口や説明には好感を持ちました。なるほどなと思わせます。 その中で多いに参考となったのは、キャスティング「鮎の空中輸送」とおもり釣りの解説です。
個人的にはおもりは根掛かりしやすく、はっきり言って苦手にしていました。嫌っていました。おもりがタモの中でこんがらがったりするためです。 またオトリの交換が面倒でもあります。 始められるところは各グループの責任者の判断で早く始めてもいいことになっています。 Bは結局は6時45分頃からスタートとなりました。
竿とハリはがまかつ製品を使用することとなっています。いつもでしたら竿は「ファインスペシャル引抜早瀬95」を使うのですが、今回はおもり釣りにも挑戦すること、荒瀬に挑むことを考えて、昔の名前入りの竿「ヴィンテージ鮎引抜急瀬90」にしました。 水中糸は敢えて太目を使い、メタビートの0.1号、ハリはがまかつのものですが、いろんなものが一杯あって名称は分かりません。7号クラスの4本イカリとしました。 おもりは3号です。
上流側からやや左に流れ込むかなり流れの荒い、根掛かりしたら絶対に外しに行けない荒瀬と急瀬です。


竿を出せたのは下の2枚の写真の流れです。


最初オトリはなかなか流れに入ってくれませんでしたが、手前からゆっくり入れて、あとは竿の操作でベタ竿にして川底に沈めました(そのつもり)。 川は上の方が流れが速く、川底は意外と速くはないという瀬田さんの言葉を思い出しオトリを沈めました。
そしたら意外とオトリは元気で急瀬の中でも泳いでくれました。 そしてオトリを泳がせてすぐに軽い当たりが感じられました。掛かったかもしれないという程度の当たりです。でも掛かっていました。 慎重に竿を溜めて、左岸の浅瀬に誘導し抜きました。 13センチクラスの小さい鮎です。目にかかっていました。掛かりどころがよくありませんし、小さいので養殖オトリには引き続き頑張ってもらうことにしました。
そしたら2,3分過ぎに今度は明快なドンという大きな当たりです。やったあ!と喜びながら抜きに掛かりますが、なかなか浮いて来ません。これは大きい、もしかして大きすぎるかも?、二ゴイかサクラマスかもと思いながら、少し下って浅瀬から引き抜きました。水面スレスレを飛んできます。無事キャッチ、途中で分かりました、ハヤだと。 大きい丸々と肥えたハヤでした。これが大きい鮎ならその後の展開は変わっていたかどうか?何とも言えませんが。
(途中ですが、ここでいったんアップしておきます。続きは午後に)
(脱原発みやぎデモに参加して、ずぶぬれで帰ってきました。)
今回の予選はここの急瀬と荒瀬に賭けました。この20から30メートルくらいの距離で時間一杯粘ってやろうと思い、自分としてはよくやったものと思っています。 正直なところはどこに移っても同じだろう、あまり掛からないだろうと思った次第です。 粘り続けること1時間以上、8時20分頃ですかようやく3回目の当たりが伝わってきました。
急瀬の中心よりもやや右岸側にオトリを入れて泳がせていました。 そしたらいい当たりが伝わってきたのです。 左岸に寄せて引き抜くと、嬉しいことに大きな、オトリよりも大きい鮎でした。 8時20分頃でしょうか。 今年釣った鮎の中で一番大きかったと言っていいでしょう。 さすが荒瀬に縄張りを持っている鮎だけのことはあります。 しかも立派な背掛かりです、文句のつけようのない立派な鮎でした。
よし、これなら荒瀬でも十分泳いでくれるだろうし、仲間も数匹呼び寄せてくれるのではなかろうか?なんてかってに自分に都合のいいように考えるのです。 でも現実は厳しく、すぐには続いてくれません。 入れ掛かりを期待するのは、今年の現在の鮎では無理でしょう。 次にようやく掛かったのは8時35分頃か、チビ鮎でした。 オトリ鮎が小さいと掛かるのは大きい鮎、オトリが大きいと小さい鮎が掛かるというのは確かですね。
これでハヤを除いて掛けたのは3匹、オトリ込で5匹ですか。 これで予選を通過するのは厳しいかもしれないとは思いました。 2,3人私の下流域に入ってくる人がいましたが、掛かってはいなかったし、すぐ上流粋で竿を出している人は早々に竿を畳んでいるような感じでしたし、もしかしてぎりぎりセーフかもしれないとも正直思いました。
結局その後は掛からず。9時45分には上がりました。検量の結果、Bのトップは10匹です。上流の方で釣ったようです。 どこにでもいるのですね、厳しくても釣る人が。 でも何が幸いするか分かりません。 5匹は3人いましたが、Bグループでは5匹までの人が予選通過となりました。 引っかかりました。 今年3回の大会に出て、最後の最後でようやく引っかかりました。予選を通過しました。
これをどう考えたらいいのでしょうか? これで最後だからこそ神がほくそ笑んでくれたと思うのか、これからも出続ければいいことがあるかもしれないという神のお告げなのか?何とも言えません。
予選の時の天気は思ったほど暖かくはなりませんでした。 時折陽が差し、その時は背中に暖かさを感じて嬉しくなるのですが、それは長くは続きません。股下まで入っていると冷たさを感じてしまいます。朝方が一番いい天気だったようなものです。
まあ、何にしろ予選は通過しました。 ABC3グループからの勝ち抜き者での決勝戦は11時15分からとなりました。天気がいつ急変するか分からないので少しでも前倒しで早く実施しようという主催者側の意向が読み取れます。 全体で24人ですか、決勝に残った形になるのは。 くじ引きをして入川順位を決定します。 オトリ配布は入川が一番遅い人からとなります。 私は11番。またしてもほとんど真ん中の番号。 面白くないですね。 中庸は。 中途半端です。
決勝戦はどこに入るか? 決勝戦のエリアは一関大橋を挟んで、BブロックとCブロックの中間となります。 このエリアは決勝戦用に確保しておいたということになります。 シマノもダイワもそういうことはありませんでした。 下流の方の荒瀬に入ろうかと最初は思っていました。ここはシマノもダイワも誰も竿を出してはいません。竿抜けとなっています。おもりをつけて、オトリさえ入ってくれれば、入れ掛かりは無理でもそこそこ掛かってくれそうに思いました。
でも選んだのは一番の近場の一関大橋のすぐ上流左岸側です。ここは結構な流れと水量があり、ダイワのときの決勝戦で青森の村田寅少年がたくさんのギャラリーを前にして、少しも臆することなく竿を出し、ギャラリーの期待に応えて結果として見事3位となったところです。
そこに入ろうとオトリを受け取って上流に向かいましたが、流れに抗して進むのは大変でした。ダイワの時よりも水量は減っています。でもすごい体力がいるのです。 見た目よりも水圧が強かったです。 一歩一歩歩を進めるのですが、なかなか思うようには進みません。 早く進もうと気ばかり焦ります、そのためでしょうか、こともあろうにギャラリーのまえでこけてしまいました。 前のめりに倒れてしまいました。 流れに垂直に向かっていたためですが、足もとを掬われるような形で前に倒れてしまい、深さは膝上くらいでしたので上半身はずぶぬれとなりました。 右手に竿を、左手では曳舟を持っていましたが、そのままの形で前のめりに突っ伏してしまい左手の薬指と右足の弁慶の泣き所を打ってしまいました。 そのときは大して痛いとは思わず、それ以上に恥ずかしい思いが強かったです。
これも悲しいことに体力の低下、加齢に伴う体力の低下ということなのでしょうか?またしても悲しい厳しい現実を突き付けられてしまいました。 25日は若手も若手の村田少年が余裕をもって竿を出し、ポツポツながら確実に鮎を掛けていたところです。 しかも25日の方が水量が確実にありました。流れも急でした。 比較しても始まらないことは重々承知の上ですが、年齢を感じさせられてしまいました。
決勝戦は本来は11時15分から13時15分の2時間ということでしたが、結論から言うと11時45分までの30分で終了となりました。 それは昼近くになってから、天気は暗雲が立ち込め、その度合はますます強くなり、ついに雨が降り出し、それだけならいいのですが何となんとナント雷様までが最初は低く、ついにはすぐ近くで聞こえるようになってきました。 こうなると自分としては釣りどころではありません。 拙いのではないか、試合を中止にするか、いったん休止にするかどちらかにすべきではないかと思いながら、つまりは気もそぞろのまま竿を出していました。
掛かったのですよ、私も。 左岸へチの急流はとてもオトリが入りそうにもなかったので、逆に川の中央付近に竿を出すようにしました。 つまりはギャラリーに背を向ける形です。おもりは2号にしました。 5分もかからないところで、軽い当たりがあって15センチくらいの鮎が掛かりました。周囲の中では早い方の掛かりです。 でもその後が続きません。 気持ちが集中できませんでした。
正直なところ予選さえ通過すればいいやという気持ちがありましたし、強い雨や雷が鳴る中での釣りは集中力を欠いてしまいます。 よく周りの選手たちが平気で竿を出しているなと思いながら、自分も竿を出している有様です。
でも強烈な雨脚に加えて、雷鳴も強く響くようになったため、本部としても30分経過後に終了としました。 13時15分を待つことなく、11時45分で決勝戦は終了となりました。
その後は大変な集中豪雨となり、車に入り着替えましたがまるで台風の暴風雨みたい。この天気の急変は一体なんだ?!気まぐれな天気、まあこれは全国どこでも経験しているところです。 ずーと車から出なかったためでしょうか、その間橋下の本部では集計作業をし、表彰を行い、抽選会までしていたのです。 こちらは何らかの連絡があるだろうと車の中で指示を待っていたのですが、楽をした罰ということなのか、抽選会に加わることができませんでした。
大変長くなりました。ということでG杯の小国川の大会も終了したということです。最後が拙かったというか自己責任でよくなかったことになってしまいました。
 タオル
タオル
 6.5号のハリ7本(4本イカリ)
6.5号のハリ7本(4本イカリ)
 エチケットケース これはいい!
エチケットケース これはいい!
この3点が参加賞でした。 帽子は、今年はありません。帽子は溜り過ぎていますので、なくても構いません。




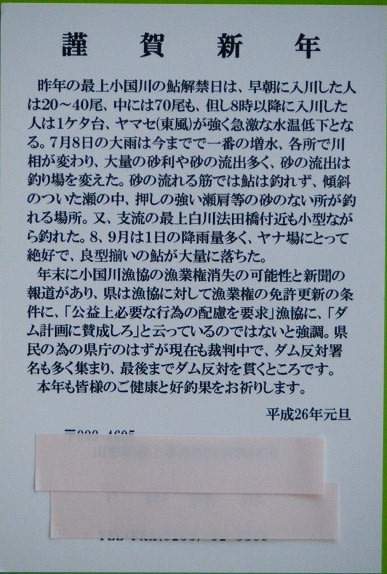 (漁協の組合員です。)
(漁協の組合員です。)
 (これも南へ向かっていました。)
(これも南へ向かっていました。)
























 大きくはならないカマキリです。
大きくはならないカマキリです。




























 タオル
タオル 6.5号のハリ7本(4本イカリ)
6.5号のハリ7本(4本イカリ) エチケットケース これはいい!
エチケットケース これはいい!




































































