写真を撮る人はわかると思いますが、
マクロレンズを覗くと、被写体がまったく違った表情を見せますね。
マクロ、いわゆるドアップで被写体に近づくと、
ファインダー越しに見える相手は
その触感、色かたち、性格まで違う表情を見せるから不思議です。
近づくとディーテイルがはっきりして、
1つの物体が形の違うパーツの集合体に見え、
その1つ1つに意志が感じられます。
物事を理解するとき、そのパーツに気がつかないと
全体が見えないことがよくあります。
反対に、細かいところばかりに気をとられ、
本来の目的や全体像を見失ってしまうこともありますね。
距離だけじゃなく、目線も同じように
自分の目の高さから見上げたり、見下ろしたりするだけでは
自分を軸にした世界しか見えてこないな、と常々思います。
大事なのは、相手の目線に合わせてみること。
よく子供と話すときには子供の視点におりてみるといい、なんて言いますが、
彼らの視点の先に照準を合わせてみると、
きっと長いこと忘れていたような光景も見えるかもしれません。
意外と日常生活の中では、自分の視点からしか物事を見ようとしない
ことって多いんじゃないかと思います。
ネットラーニングはお客様のニーズに合わせてeラーニングコースを
カスタマイズすることを一つのサービスの柱にしていますが、
お客様目線、基本姿勢としていたいですね。
上のようなことを考えていたら、
昔見たイームズの『Powers of Ten』という映像を思い出しました。
インダストリアル・デザイナーの巨匠、チャールズ&レイ・イームズ夫妻が
70年代に撮影した約10分間の科学映像で、
最初ピクニックで芝生に寝ころんだ男性を写していたカメラは
画面の中心にその男性を据えたまま10秒ごとに10倍ずつ高度を上げていく。
10の25乗の太陽系をも超えたところで、今度は同じスピードで高度を下げ、
男性の細胞の奥、DNAまで映像は到達する。
そのマクロからミクロへの静かな空間の移動に、結構感動したのを覚えています。
DVDにもなっているのでご興味があったらぜひ。
 CCつれづれ日記
CCつれづれ日記イベリコ豚。なぜ最近君たちばかりがモテモテなのだ。
どうでもいいと言えばどうでもいいが。
豚界の名古屋コーチンみたいな存在?












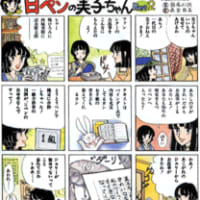








自分の好きな日本語表現に、
「人の気持ちを察する」というのがあります。
心のゆとりが必要な素敵な行為だと思っています。
諸々のサービスを受ける時、こちらに目線を合わせてくれている感じがあると快いです。
話は変わりますが、幼年期、とある所で豚さんと触れ合う機会があった後、しばらくお肉がコワかった。。よくある話。
人の気持ちを察する、というのは時には言葉ではなく、
そっとしておくということも必要ですね。
仕事の面で言えば、ネット社会では顔が見えないコミュニケーションが多く、
ホスピタリティが伝わりにくいケースがよくありますね。
講演会の話を思い出しました。
日本の講演会は質問の時間が少なく、講師からの一方通行、聞き手からの質問も自分が言いたい内容の発言で一方通行。
good question とは、参加者のみんなが聞きたかったこと、講師が話したかったことをひきだす質問で、双方向を実現し、講演会を充実させるのだということです。
一方通行ではコミュニケーションになりませんね。
昔、「会話はキャッチボールだよ」と助言されたことがありましたが、
会話に限らずあらゆるコミュニケーションシーンにおいて共通だと思います。
日本人はまだまだシャイなんでしょうか?