【幕間】

地球の総力を結集した一大決戦――火星沖海戦は無残なまでの敗北に終わった。地球には未だ建造中や改装中、慣熟訓練中の艦艇も存在したが、火星沖で一どきに失われた戦力を思えば、焼け石に水としか思えなかった。
つまりそれは、宇宙レベルでいえば至近の地である火星にガミラス軍主力が展開し、地球本土へ直接侵攻を開始した場合、国連宇宙海軍にそれを食い止める実効的な手段は最早皆無であることを意味していた。
しかし、ここでまたしても地球人が目を疑うような事態が発生する――火星沖海戦後、火星圏を制圧したと思われていたガミラス軍が撤退したのである。
火星沖海戦序盤、空間障害物を利用した国連宇宙海軍の戦術は有効に機能し、ガミラス艦隊にかなりの損害を与えたものの、海戦後半に大規模なガ軍増援が戦闘加入したことで、海戦終了後もガミラス艦隊は未だ百隻以上の戦闘可能艦艇を保持していた。そしてそれだけの戦力があれば、制圧後の火星圏維持も容易であり、地球側の根拠地を接収するなどすれば、拠点構築にも困難はない筈であった。
しかし――ガミラス軍は撤退した。
当初、地球人たちはガ軍の撤退を何らかの欺瞞か次作戦に向けての予備行動ではないかと疑い、訝しんだ。しかし、いつまでも経ってもガ軍蠢動の兆候は確認できず、数週間が経過した後で、ようやく偵察用艦艇を火星圏に送り込むことを決定する。
警戒に警戒を重ねて派遣された偵察艦は、監視用衛星などの ガミラスの“置き土産”こそ発見したものの、宙域にガ軍潜伏を疑わせるような兆候を全く見出すことができなかった。また偵察艦は、自軍の通信周波数帯において極めて微弱な通信波やレーザー信号を複数傍受していた。確認の結果、それらは海戦中、大きな損傷を受けて航行不能や通信不能に陥った国連宇宙海軍所属艦艇たちであり、その数は意外なほど多かった。更に、完全に破壊されたと信じられていたグラディウス・ステーションも一部の機能は未だ生きており、健在な部隊が存在していることも同時に確認されている。
その報告に、国連統合軍司令部は久方ぶりに明るい空気に包まれ、宇宙海軍司令部に対して直ちに救援艦の派遣が命ぜられた。
しかし、それでも疑問は残った――何故ヤツらは引き上げたんだ?
その疑問に答えられる唯一の男――大ガミラス帝星国防軍第七五七空間機甲旅団長バルケ・シュルツ大佐にとって、その答はシンプル極まりないものだった。火星沖海戦における大佐の目的は、あくまで地球の機動戦力(主力艦隊)の殲滅であって、火星圏の制圧ではなかったからだ。
第二四重空間機甲旅団という増援を得て大勝利を飾ったものの、重機甲旅団は当初の予定通り引き上げられ(一部は既に次の任地である小マゼランへの移動を開始していた)、以降の地球攻略は元から存在する第七五七空間機甲旅団のみで行わなければならなかった。そして、火星沖海戦で被った損害も決して小さくない七五七旅団にとって、火星圏の掌握はもちろん、事後の地球・月の攻略を目的とした大規模攻勢など、戦力的に全く不可能な状況だった。
だが、そうした状況は海戦前から決定若しくは予想されていたものばかりであり、少なくとも大佐にとっては驚くような事態ではなかった。それどころか、現在の状況はシュルツ大佐と彼の幕僚団がデザインした大戦略そのものだった。
開戦以来の地球の抵抗の激しさを思えば、どれほど強力な増援(重機甲旅団)であれ、それが短期間の限定的な派遣に留まる限り、大規模戦闘(決戦)には勝利できても、粘り強い攻略戦が必要な敵首都星の制圧は難しい。それならばむしろ、決戦における完全勝利を徹底的に追及、増援部隊を積極的に用いて敵機動戦力を根こそぎにすることで敵の継戦意欲を破砕し、降伏勧告を受諾させる――それが大佐らの描いた戦略構想であった。
もちろん、制圧した火星圏に居座り、地球に対し軍事的プレッシャーをかけ続けた方が上記戦略にとって遥かに効果的であるのも間違いなかった。しかし方面軍からの増援が撤退した今、すり減らされた七五七旅団の戦力(稼働艦三十隻余)を火星と冥王星に二分するのは、あまりに危険であるとシュルツ大佐は判断した。
そんな危険を冒さずとも、火星沖海戦の大勝利をバックに、地球に対して揺さぶりをかけつつ降伏勧告を行えば、艦隊戦力という最も効果的な抗戦手段を失った地球は容易に陥ちる――その筈であった。
シュルツ大佐とその幕僚団によって築き上げられた戦略構想は極めて現実的且つ健全な判断から導きだされたもので、火星沖海戦の大勝利という戦術的成果も相まって、その実現性は非常に高かった。また、その実現性と確実性を更に高める為の“支作戦”が作戦参謀ヴォル・ヤレトラー少佐の主導で実行に移され、かなりの効果を挙げたことも地球に潜入中の工作員を通じて確認されていた。
地球に本戦略を打ち破ることが可能な現実的方策は殆どなく、ガミラス――いや、シュルツ大佐は本戦争(戦闘ではない)にチェックメイトをかけたも同然と思われた。
だが、完璧且つ完成直前と思われた大佐の戦略構想に思わぬところから待ったがかかる。敵からではない、他ならぬ彼らの上官――銀河方面軍作戦司令長官グレムト・ゲール少将からであった。
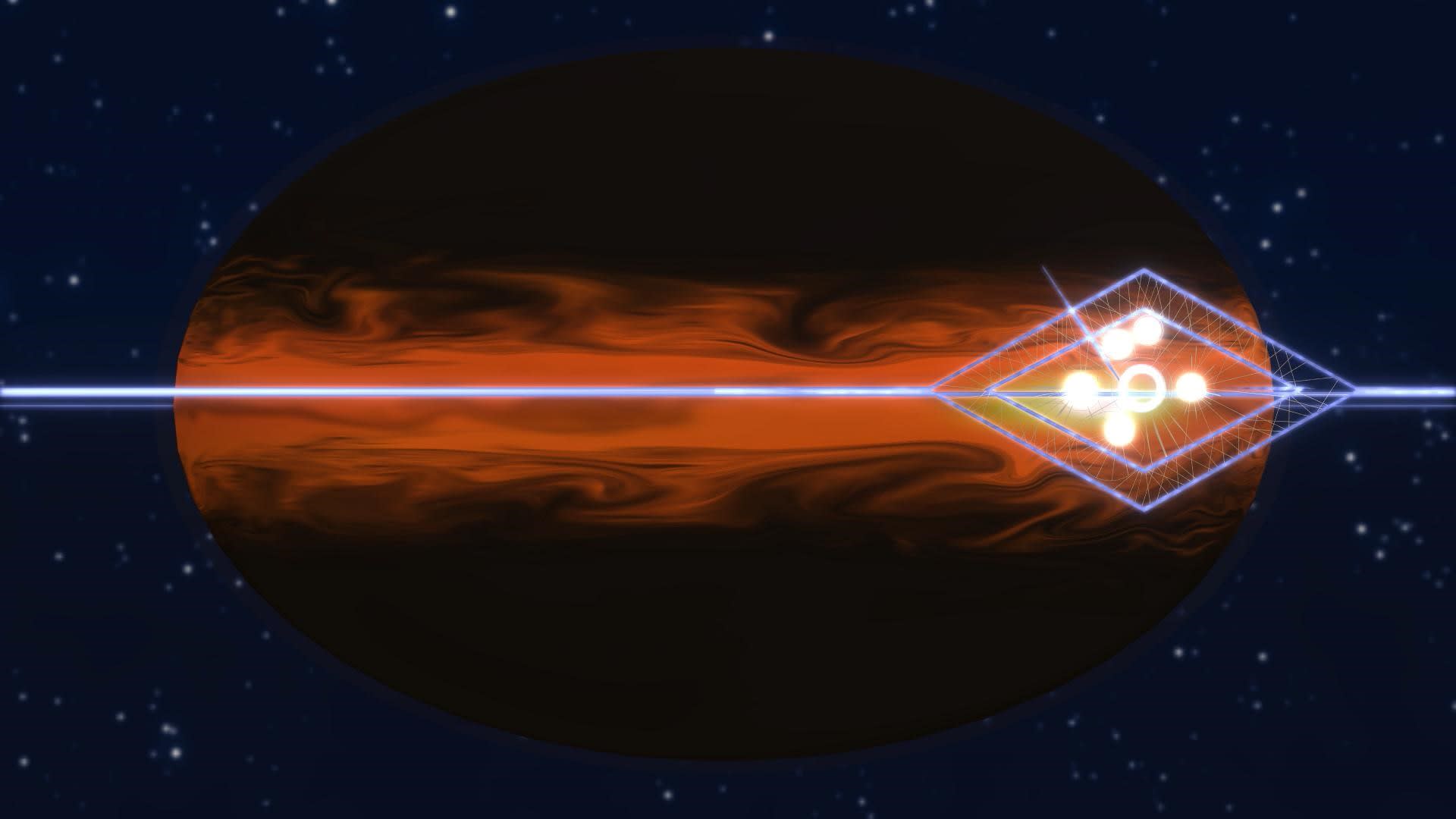
ゲール少将は歓喜していた。
長らく持て余し気味(殆ど存在を忘れるほど)だった重機甲旅団が、“自らの”完璧な作戦指導によって赫々たる戦果を挙げ、小マゼランへの転出に華を添えた。更に、自身が属する派閥の長であるゼーリック国家元帥からも直々にお褒めの言葉まで(『で、あるか』程度だが)賜った。これで、更に大きな戦果を挙げれば、本国への転属、いや栄転も夢ではない――少将の期待、いや野心は膨らむ一方だった。
そんな折に七五七旅団より上げられた、帝星国務省を通じた地球に対する降伏勧告という意見具申は、少将を激怒させるに十分だった。少将が望んでいたのは、降伏という確かではあっても地味な実績よりも、自らの栄転に値する見た目に派手な戦果――つまり、激戦の結果としての敵首都星の直接占領だったからだ。
具申に対する少将の返答は、それを目にしたシュルツ大佐が思わず『馬鹿な――』と絶句したとされるほど苛烈なものだった。
曰く――既に敵軍は先の大敗北によって意気消沈、残存戦力も僅かである。即刻、敵首都星攻略作戦を発起せよ。降伏勧告など、栄光あるガミラス軍人が発案すべき戦策に非ず。ガーレ・デスラー。
驚愕に打ちのめされたシュルツ大佐であったが、容易に引き下がることもできなかった。自身と幕僚団が築き上げた大戦略に絶対の自信があったことは勿論だが、純軍事的に地球の降伏が最早確実である以上、自らに忠誠を誓う部下たちの生命を危険に晒す必要性を全く認められなかったのである。
さすがにそれは公には口にできないにしても、現実問題として彼の手元には攻勢に出られるだけの戦力がなかった。七五七旅団は地球の降伏勧告受諾という戦略目標達成のために手持ちのリソースを完全に使い切っており、ゲール少将の求める“即時の攻勢発起”には少なくとも方面軍からの何らかの支援は不可欠だった。
シュルツ大佐は、まずは言を左右にして時間を稼ぎ、その間にゲール少将を翻意させるべく画策を図った。だが、本国への栄転への想いの強さ故か、少将を翻意させるのは容易ではなく、それどころか大佐が予想もしていなかった行動に出る。
突如、シュルツ大佐に命令不服従の疑いがあるとして、方面軍司令部への召喚命令を発したのである。しかも、命令は大佐のみならず旅団の主要幕僚全員に及んでおり、最早その狙いは明白だった。
シュルツ大佐が査問を受ける間、大佐の指揮権は停止され、旅団には旅団長代行が置かれることになる。ゲール少将はその代行者を意のままに操ることで、強引に攻勢を再開しようというのだ。
シュルツ大佐は自らの読みの甘さに臍を噛んだが、既に正式な召喚命令が発令されている以上、抵抗の余地はなかった。彼に可能であったのは、一分一秒でも早く旅団の指揮権を取り戻すべく、旗艦シュバリエルで方面軍司令部に出頭し、命令違反の事実などない事を証明することだけであった。
しかし太陽系――ガミラス人たちの言うところの『ゾル星系』――は、バラン星に設置された方面軍司令部までどれほど急いでも片道二ヶ月以上を要する辺境の地であり、その間に事態は大きく動くことになる。

「――陽電子衝撃砲?」
「はい、我々はショックカノンと呼んでいます」
後に地球と全人類を救った英雄と称えられることになる沖田十三提督が、最初に“新兵器”の概要説明を受けた際、そんなやり取りが交わされたとされている。この場面は、後にガミラス戦争や火星沖海戦が映画化・ドラマ化される際には必ずインサートされており、一般にも広く知られたシーンと言えるだろう。ただ、多くの作品において、沖田提督はこのやり取りだけで新兵器の全てを理解したかのように描かれているが、実際の状況はかなり異なるらしい。
開発技術者から一通りの概要説明を受けた後、宇宙物理学博士号すら有するこの歴戦の提督は、“新兵器”の構造、特性、制限、それらから導き出される現実的な運用方法に至るまでを長時間に渡り徹底的に技術者から聴取した。その様は、後に開発技術者の一人が『まるで試問か尋問のようだった』と述懐したほど容赦のないものであったが、同時に沖田提督の問いや指摘は極めて合理的且つ的確なもので、本ディスカッションを通じて、この新兵器に今後必要な改良点が浮き彫りになったと証言する技術者もいる程だ。
陽電子衝撃砲――通称:ショックカノン
後に地球防衛軍の主戦兵器の地位を獲得することになるこの新型艦載砲は、その名称からも明らかである通り、ガミラス軍の主戦兵器“陽電子ビーム砲”と基本的には同原理の兵器である。しかし、当時の地球の科学技術力では陽電子の生成はともかく、ガ軍の陽電子ビーム砲と同一の手法では十分な収束状態を実現することができなかった。結果、ガ軍よりも砲を大口径化してエネルギー量を稼ぎつつ、長大な砲身内で形成した電磁フィールドによってエネルギーを螺旋状に誘導、陽電子ビームが延伸する過程で更に収束率を向上させるという逆転の発想で、強引に射程と威力を引き上げていた。
その点、新型砲は機構やサイズ、エネルギー効率等、純技術的な洗練度ではガミラスよりも数段“遅れた兵器”であったが、大口径化と長砲身化の効能はそれを補って余り有り、開発技術者も一発あたりの威力と射程においてはガミラス軍の陽電子ビームを凌駕すると太鼓判を押していた。
だが、そうした強引な大威力化は他のスペックを犠牲にすることで達成されているのも事実であり、それ故の代償が存在した――それも、艦の死命を決しかねないほどの代償が。
『陽電子衝撃砲』を成立させ得るエネルギー量はあまりに膨大で、機関を全力稼働させても発射に足るエネルギーの充填には分単位の時間が必要であった。テンポの速い空間戦闘における分単位とは最早永遠にも近く、他艦の支援なしでは自艦の安全を確保しつつ連続発射を実現するのは事実上不可能と考えられた。また、陽電子ビームの螺旋誘導に必要な砲身も極めて長大であり、艦艇への搭載は主艦体そのものを砲身化する単装の軸線砲でしか不可能であった。
後に、開発技術者たちはこれらの問題点を様々な技術革新と画期的艦艇用機関――次元波動エンジン――の実用化によって解決することになるが、2193年時点においてそれらの問題点は、戦場で用兵家たちが運用の妙によって解決しなければならなかったのである。
そして、この未だ実用段階とは言い難いウェポンシステムの運用を任されたのが、開戦時の天王星沖海戦で戦傷を負い、この度ようやく復帰したばかりの沖田十三提督であった。
陽電子衝撃砲の試作砲は、まず金剛型宇宙戦艦最後の生き残りであるキリシマに搭載され、当初計画では数ヶ月間の実用テストの後、その結果をフィードバックした初期生産型が量産される予定であった。しかし、風雲急を告げる戦局はそれを許さず、キリシマでのテストを待たずして試作型をスケールダウンした増加試作品が急遽製作され、それらを装備した六隻の村雨型宇宙巡洋艦も沖田提督の指揮下に入ることが既に決定していた。
火星沖での大敗北後、地球各国政府の足並みは大きく乱れた。
地球にとって最後にして唯一の希望であった国連宇宙海軍は全滅し、遂に地球本土までもが侵略者の直接攻撃圏内に捉えられたことで恐怖に駆られた市民たちは、自国政府を激しく突き上げた。それに耐え切れず、非常任理事国を含む幾つかの国家が、国連で早期講和を唱え始めたのである。
未だ抗戦を諦めていない国家や人々――徹底抗戦派――からすれば、それは平和の美名を騙った紛れもない裏切り行為であったが、民主主義下においては許容された政治行為であり、民意の表明ではあった。
そして徹底抗戦派が最も憂慮したのが、早期講和派が公然化したことで、未だ徹底抗戦を明言している国家においても、国内に講和派が台頭してくることであった。もしそんな状況になってしまえば、国連及び常任理事国の強い指導で辛うじて維持されている地球規模の挙国一致体制は瓦解し、現状の劣勢が更に悪化するのは確実だったからだ。
事実、各国での世論調査の結果は講和派が急速に台頭しつつあることを示しており、徹底抗戦派の懸念は決して根拠のないものではなかった。
その点、こうした地球国家内での足並みの乱れは、ほぼはシュルツ大佐の狙い通りに進展していたと言えるだろう。しかも、地球攻略に向けて明快な大戦略を掲げたこの老獪なザルツ人大佐は、惹起した地球の混乱を更に拡大すべく次なる一手まで打っていた。
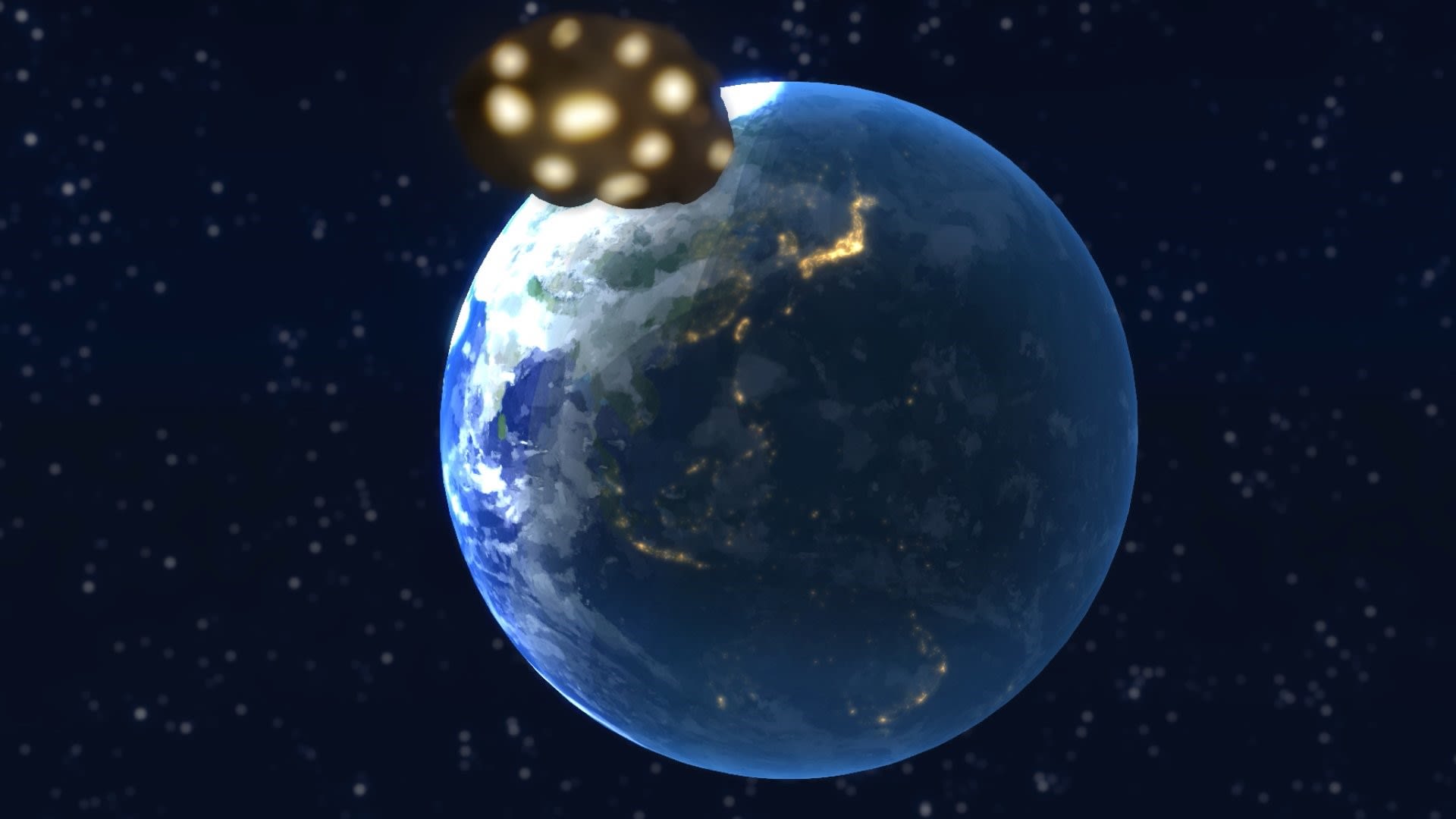
2193年4月12日、灼熱の火球と化した直径百メートル大の微惑星が地球に落下――後に『遊星爆弾』として怖れられることになる星間戦略爆撃の初弾である。
“爆弾”とはいえ、その実態はエッジワース・カイパーベルト天体に属する微惑星に、重金属充填による質量調整と耐熱用の簡易な表面処理を施しただけのもので、後の同種兵器のような生物兵器化――環境改造用植物の“種”が埋め込まれ、地球衝突後に飛散・発芽・胞子拡散する――は行われていなかった。また、爆撃が本格化する2194年以降のそれと比べれば比較的規模も小型であったが、それでもその威力は戦略級の熱核兵器にも匹敵した。
作戦参謀ヴォル・ヤレトラー少佐から、自然物を利用したこのロー・コスト兵器の上申を受けたシュルツ大佐は火星沖決戦後の“とどめ”として本兵器の採用と投入を決定、地球側の監視・警戒網が火星に向けて出撃するガミラス艦隊(七五七旅団)に引きつけられている間隙を突いて放出を果たしていたのである。
2193年当時、冥王星前線基地には未だ超大型陽電子ビーム砲『反射衛星砲』は設置されておらず、遊星爆弾第一号の初期加速は簡易なブースターによって行われた。更に、地球とのコリジョンコース設定も極めて慎重に行われた結果、地球圏への到達まで二ヶ月以上を要した
しかし、その間に行われた火星沖海戦と、その大敗による混乱から脱しきれていなかった国連宇宙海軍による察知は遅れに遅れ、気がついた時には遊星爆弾は既に木星軌道を通過していた。更に火星沖海戦で有力な機動戦力の大半を失っていた地球に有効な邀撃手段は残されておらず、国連軍による地球―月軌道での懸命の迎撃も空しく、遊星爆弾は地球への落着を果たす。
当初、遊星爆弾の落下地点はアメリカ合衆国ヴァージニア州と予測されていたが、国連軍の迎撃によって軌道が大きく変化し、結果的に爆弾が落下したのは遥か極東――日本国高知県南部――であった。
四国山地に属する山々とそれに源を発する多数の清流、それらが育んだ豊かな自然に彩られた古の土佐国は、この一弾によって無残に、そして完全に破壊された。破壊の一部は地殻を貫いてマントルにまで達しており、その後も長きに渡って深刻な地殻異常を引き起こすことになる。
遊星爆弾落着の事実とその光景は、発生した事象があまりに巨大であった為に報道管制など全く無意味であり、肉眼で本事象――真っ赤に灼けた巨大隕石が落下し、地上が眩い閃光に包まれる――を目撃した者の数は実に数百万人にも達した。更にネットワーク・インフラが発達した日本国内に落下したことも災いし、各種ネットワークを介した中継によって、世界中で数十億もの人々がほぼリアルタイムでこの凄惨な光景を目撃することになった。
当初、国連及び各国政府はこの事件を不運な隕石落下――つまりは自然現象と発表したが、それを信じるものは極僅かであり、多くの者が抗戦中の異星人の仕業であると確信していた。そしてその確信は、ガ軍に対する凄まじいばかりの恐怖へと容易に直結した。なぜなら彼らが敵に回した異星人は、軍人も民間人も関係なく数十万人を虐殺してしまうような無差別大量破壊兵器を――それも、現在の地球の科学軍事力では阻止困難な兵器を――平然と使用するような連中なのだ。
結果、強大且つ非道な敵に対する恐怖と、それに対してあまりに無力な国連や各国政府、軍への不信から、多くの市民が当時台頭しつつあった講和派へと流れることになる。彼らの多くが、開戦前には異星人の撃退を強く主張していたことを思えば、“変節”と評しても良い世論の変化だった。
徹底抗戦派の分析では、火星沖海戦の敗北発表後も民意は未だ七対三で抗戦派が優勢だったが、遊星爆弾の落下によってその比率は遂に六対四を切り、三ヶ月以内に民意は完全に逆転すると予想された。更に、この予想は現状で戦況が固定された場合のもので、更なるガミラス軍の攻勢や微惑星爆撃が実施された場合には、抗戦派と講和派の形勢は完全に逆転するとも考えられていた。
三ヶ月以内の反攻作戦――『カ2号作戦』――は、こうした戦略環境を受けて未だ徹底抗戦派が多数を占める国連宇宙防衛委員会で急遽決定された。
だが、決定こそ下されたものの、状況は最悪の一言に尽きた。
火星沖で機動戦力の大半を失ったことに加え、遊星爆弾の落下により各国政府の足並みの乱れは各国軍にまで及んでおり、国連統合軍に派遣した部隊の引き上げや、指揮系統からの離脱が相次いだからだ。
その為、反攻作戦は“政治的に信頼がおける国”の軍を主体にせざるを得ず、元より乏しい残存戦力を更に低下させることになった。しかも、これまで国連宇宙海軍の主力の地位を占めていた米・中軍は既に壊滅状態であった為、結果的に反攻作戦は比較的まとまった戦力を残していた日本国航宙自衛隊が主力とされた。
だがこの時、陸・海・空・宙の各自衛隊は遊星爆弾直撃による大被害への対応に忙殺されており、それは反攻作戦主力に任じられた航宙自衛隊すら例外ではなかった。現在も継続中の救難・救援活動からどうしても引き抜くことができない艦艇や隊員も少なくなかったのである。
結果、宙自単独では不足する戦力を補填する為に、国連宇宙軍を介した調整によって数ヶ国からの増援が加えられることになった。しかし当初は、編成が多国籍化することで指揮命令系統に不安が生じると宙自上層部が難色を示し、事実、日本隣国からの艦隊参加表明が“歴史”に係る厄介な政治問題を引き起こすという一幕もあった。
幸い、本作戦の編成主体である国連統合軍が馬鹿げた面倒を嫌った為、200年以上前の歴史を盾に非常識極まりない要求――艦隊指揮官は日本人以外とする、自国艦艇の指揮権の独立、連絡将校の受け入れ拒否――を送りつけてきた隣国に対しては、統合軍が簡潔且つ辛辣に艦隊参加を拒絶している。
曰く――貴国艦艇の能力・練度・士気、いずれにおいても本作戦への参加に能わず――と。
本顛末の唯一の救いは、半ば面罵するような国連統合軍の回答(意図的に一般にもリークされた)が各国にも広く知れ渡ったことで、生半可な覚悟と練度と装備では本作戦参加を表明することができなくなり、各国精鋭のみを集成した艦隊編成が可能になったことだけだった。
こうして、多少の軋轢こそ発生したものの、なんとか編成を完結した地球艦隊の指揮官には、戦傷から回復したばかりの沖田十三提督に白羽の矢が立てられた。
しかし軍務局は、開戦時の攻撃命令を拒絶して解任された沖田提督の指揮官就任に強く反対し、冥王星からの撤退戦で活躍した土方宙将(当時は航宙軍士官候補生学校長に就いていた)を推した。だが、他ならぬ土方宙将本人から頑として固辞された結果、渋々ながら沖田提督の就任を了承している。
反攻作戦決定後、慌ただしく招集された『カ2号作戦』準備会議には、作戦参加予定部隊の艦長以上の指揮官、新型砲搭載艦の砲雷長、航空隊幹部、そして沖田提督の強い要請で多数のオブザーバーが招かれており、その中には火星沖海戦で奮戦した突撃宇宙駆逐艦ヒビキ艦長の姿もあった。

ヒビキは海戦序盤においてガミラス艦二隻に大きな損傷を与えたものの、ガ軍重機甲旅団の戦闘加入後はデブリゾーンに立てこもっての耐久を強いられた。そして海戦最終盤、ヒビキは盾にしていたデブリごとガミラス軍の陽電子ビームに射抜かれてしまう――だが、彼女は沈まなかった。
こと防御においては脆弱極まりない突撃駆逐艦の被弾は即轟沈に繋がるケースが多いにもかかわらず、彼女が生き残ることができたのには、幾つかの幸運と必然が作用していた。
一つ目の幸運は、あまりに激しいガミラス艦隊の砲撃に、最早被弾は避けられないと判断した艦長の命令で残存魚雷と実体弾の全投棄、機関も完全停止の上、総員でのダメコン準備が発令されていたことだった。ヒビキの被弾は、それら全ての命令履行が確認された直後のことで、結果、誘爆などの二次被害を免れた彼女は一撃で爆沈するという最悪の事態を避けられたのである。
とはいえ、ガミラス艦の陽電子ビームは極めて強力であり、ヒビキは機関を完全に破壊された上に全電源も喪失、デブリゾーンの中を殆ど残骸のような姿で漂流することになった。
そして彼女の二つ目の幸運は、漂流の過程で他艦が仮泊地としていた大型デブリに接触できたことであった。元々そのデブリを仮泊地にしていた駆逐艦の消息は不明であったが(後に撃沈が確認された)、残されていた資材や消耗品を活用することで、ヒビキとその乗員たちは電源と通信機能を回復すると共に、救難艦の到着まで何とか生き延びることができたのである。
艦長以下乗員たちは大破したヒビキを何とか地球まで曳航し、修復しようと四苦八苦していたところを、艦長のみが急遽作戦準備会議に招聘され、不承不承この会議に加わっていた。
会議では、火星沖海戦時のヒビキのガン・カメラ映像が映し出され、艦長はその際の戦術状況を手始めに、自らが採った戦術意図と実施における過程と結果の説明を細部に渡って求められた。更に、彼女の説明に対しても沖田、土方両提督を筆頭に多数の質問が次々に浴びせられ、そのあまりの執拗さに、ヒビキ艦長が内心で辟易した程だった。
ようやくヒビキ艦長に対する質疑応答が終わると、今度は海戦後の火星沖で回収されたガミラス艦の装甲板が会議室に持ち込まれ、南部重工から出向中の素材技術者がその特性と破損状況の報告を行った。

火星沖海戦以前の戦いでは、いずれも戦闘後の戦場の支配権はガミラス軍が掌握しており、国連統合軍はガ軍艦艇の残骸や遺棄物資を回収することができなかった。しかし、火星沖海戦後にガミラス軍が火星圏から撤退したことで、初めてガ軍艦艇から脱落した部品や装甲板を回収することができた。回収物の解析は未だ緒に就いたばかりであったが、それでもこれまで完全な謎に包まれていたガ軍艦艇の防御上の特性が幾つも明らかにされていたのである。
最後に、艦隊砲術参謀がヒビキ艦長と素材技術者の報告を総括し、以下のように結論を取りまとめた。
・高圧増幅光線砲単独では、至近且つ同一箇所に集中して命中させない限り、ガミラス艦艇の装甲は射貫不可能
・ガミラス艦艇は、装甲表面に特殊なコーティングを施し、装甲強度と耐弾性を著しく高めている
・件のコーティングは、光線砲でも連続して命中させることで剥離が可能
・コーティング剥離後の装甲に対しては、光線砲よりも空間魚雷や高初速実体弾の直撃が有効
その報告に、会議室内は大きくどよめいた。これまで、よほどの僥倖に恵まれない限り、ダメージを与えられないと考えられていたガ軍艦艇の具体的且つ実戦的な撃破方法が初めて示されたからである。
それを端的に述べれば――攻撃艦は攻撃目標のガ軍艦艇に肉薄しつつ、高圧増幅光線砲の集中射撃にてガ軍艦艇の耐弾コーディングを除去、そこへ至近距離からピンポイントで対艦砲か空間魚雷を撃ち込む――というものであった。
開戦後、光線砲のあまりの威力不足から、ガ軍艦艇への攻撃は空間魚雷が主となっており、更に肉薄時にできるだけ自艦の存在と位置を秘匿する為、光線砲の砲撃は一層控えられる傾向にあったことを思えば、大きな戦術の転換と言えた。
攻撃の成功にはこれまで通り敵艦への肉薄が不可欠であり、砲撃による自位置と存在の暴露で攻撃難度は上がるが、敵艦にダメージを与えられる確度も飛躍的に向上するのは間違いなく、戦術の変更を指示された巡洋艦や駆逐艦の艦長たちの顔はいずれも明るかった。
そして更に、事前に沖田提督とショックカノン搭載艦の幹部にのみ開示されていた新型砲――ショックカノン――の存在が会議参加者に明らかにされたことで、作戦準備会議の雰囲気は目に見えて変化し始めていた。
――これならば、勝てるかもしれない。
そこにあったのは、長らく忘れていた勝利の予感であり、感触だった。ほぼ無敵と思われたガミラス艦艇を撃破可能な戦術と新兵器の存在はそれ程のインパクトを持っていた。
彼らの大半は、これまでの戦いで多くの仲間――上官や部下、同期――を喪っており、中には四国南部への遊星爆弾落下によって肉親や友人まで亡くした者もいる。いずれの会議参加者も表面上はヴェテラン軍人そのものという冷静さを維持していたものの、そのぎらつくような瞳の輝きは、復仇の機会を渇望し、それを目前にした者に特有のそれであった。
だが、そうした会議室の空気を一人の男が変えた。
その男――土方竜宙将は沖田提督から発言の許可を得ると立ち上がった。その眼光は指揮下の艦隊乗員や候補生たちから奉られた“鬼竜”という異名そのままに、どこまでも鋭い。
彼もまたオブサーバーとして会議に参加していたが、本作戦の立案にあたり、旧友である沖田提督に強く請われ、実質的には作戦参謀としての役割を担っているという専らの噂であった。
彼は、その噂を自ら肯定するように会議出席者を睥睨しつつこう言い放った。
「諸君らには今一度思い出してもらいたい。
火星沖でも、我々は勝利を確信した。
しかしその確信は、敵の増援投入によって粉微塵に打ち砕かれた。
――今回も同じだ。
我々の勝機は、数が限られ、未だ不完全な新兵器と、危険極まりない肉薄戦術にしかない。
それらの優位はあまりに脆弱であり、圧倒的に優勢な敵軍はそれを容易に覆し得る――それを絶対に忘れてはならない」
醸成されつつあった興奮と熱気が消え、再び水を打ったように静まり返った会議室に土方宙将の声だけが神託のように響く。
だが、彼の“役割”は会議出席者の楽観を引き締めることだけではなかった。むしろ、ここからが本題だった。

「我々は火星沖で敗れた。だが、我々にはまだ戦う力が――新たな力がある。
そして、敵はまだ“それ”を知らない。
今次作戦『カ2号』はその奇襲効果を最大限に利用する」
宿将の瞳に込められた決意の強さに、会議参加者全員が威儀を正して彼の次なる言葉を待った。だが、続いて彼の口から語られた作戦構想は、あまりに破天荒なものであった――。
「本当によかったのか、これで」
「ああ。この役は今の俺にしかできん。こんな綱渡りのような作戦を完遂するには、艦隊全員がお前の命令に従って一糸乱れずに行動する必要がある。
その為には、非情な作戦を立案し、押し付ける汚れ役が必要だ。そんな役は、安全な後方で教師の真似事をしているような男にしか務まらん。
――気に病む必要などない。もしお前と俺の立場が逆なら、お前はどうした?」
「すまんな。しかし・・・・・・安田君は全て気づいていたようだが」
「あぁ、奴とは付き合いが長い。目端も利く。だから一番危険な任務を任せた」
「彼は分っているよ。それがお前の信頼の証だということを」
「そうだな・・・・・・」
既に会議が散会して十五分が経過していた。会議参加者の大半は退室し、残っているのは何らかの打合せをしている者たちだけだ。
沖田の視線が出口に向かう一人の士官を捉えた。土方もつられるようにそちらを見る。
艦長用制服に身を包んだ若手士官――腕章には『TERUZUKI』とある――は二人の視線に気がつくと立ち止まり、ピシリと敬礼をささげた。その瞳には、上官に向けた敬意というだけでは説明できない真摯さと親しみがある。
沖田と土方が揃って答礼を返すと、士官は待たせていた副長を連れて足早に立ち去った。その後ろ姿をじっと凝視している親友の姿に、土方は微かな羨望と共に、消しようのない胸の痛みを覚えた。
だが、今の彼にその痛みを吐露することは許されない。だからこそ、彼は言った。
「――沖田、生きて帰ってこい。どんなことがあっても、必ずだ」
そんな同期二人を遠くから眺めている別の二人がいる。世代こそ違うが、彼らもまた同期だった。
「親父ドノたちの苦労は絶えん、ってところか」
どこか諧謔を感じさせる口調のテンリュウ艦長 安田俊太郎二佐に、キリシマ艦長 山南修二佐が噛みついた。
「バカ野郎。どう考えても、この作戦で一番苦労するのは貴様だろうが。
自分から貧乏クジを引きやがって。」
普段のシニカルな物言いを好む山南を知る者からすると、その口調は随分と荒々しく感じられたが、そこは勝手知ったる同期の仲、安田の返答も慣れたものだった。
「任せておけよ。こういう役は得意だ。知っているだろ?
貴様に乗せられた俺が、何度女の子に声をかけて、何度貴様の前まで引っ張ってきたことか」
「ふん、率は精々四分六だったがな――」
「それを言うな。それに、俺の引いたクジなんてまだまだ序の口さ。
増援で送り込まれる航空隊には、訓練中の学生までいるって話だ」
「本当か?それは」
山南は目を剥くと同時に慄然とした。
――俺たちは、本来は守るべき半人前の子供たちまで動員してこの戦争を継続してようとしているのか?
「なんでも一人は、教官すら叩き落すような凄腕らしいが・・・・・・」
そう続ける安田も釈然としないのは同様らしい。しかし、一艦を預かる指揮官として、既に動き始めた作戦に対する批判は厳に慎まなければならない。
山南は内心の屈託を断ち切るように、両手で制帽を被り直した。
「しかし尾崎のこともある。貴様も気をつけろ。
で・・・・・・あいつの容態は?」
「こっちに来る前に軍病院に寄ったが、まだ意識が戻らん。ここ二、三日がヤマらしい」
「・・・・・・そうか」
先の火星沖海戦では、彼らのもう一人の宇宙防衛大学同期である尾崎徹太郎二佐が重傷を負っている。
尾崎は、キリシマと同じ金剛型のネームシップ『コンゴウ』の艦長を務めていたが、海戦終盤のガミラス軍の攻勢――メルトリア級を主力とした突破戦闘――に浮足立つ友軍を後目に孤軍奮闘、複数艦での近距離集中砲撃によってガミラス艦数隻に無視できない損害を与えていた。

しかし、海戦の帰趨を覆すことは叶わず、最後まで奮戦したコンゴウもまた激しく損傷し、遂には総員退艦命令が発せられるに至る。艦長の尾崎は艦内に取り残された乗員がいないかを確認していた際、発生した爆発に巻き込まれ重傷を負ったという。幸い、他の乗員たちによって救助された彼は急ぎ地球に後送されたものの、未だその意識は戻っていない。
せめて俺が、俺のキリシマが参戦していれば――山南の心中にはそんな忸怩たる想いがある。もちろん、内惑星戦争以来の豊富な実戦経験を有する彼は、いくら期待の新型砲を装備したキリシマといえど、たった一隻であの戦いをひっくり返せたとは毛ほども思っていない。しかしそれでも、キリシマの参戦によって一人でも多くの戦友を、一隻でも多くの友軍を救えたのではないかという想いを抱かずにはいられないのだ。
その点、彼はこの過酷極まりない戦況の中にあっても、未だ指揮官としての責任と人間としての優しさ、良識を維持している漢だった。
とはいえ、そんな彼の内心にも消しようのない怒りがある。だが、その怒りは敵軍に対してよりも、寧ろ自らと友軍――その上層部――に向けられたものだった。
確かに地球艦隊の戦力は、個艦レベルで敵に対して圧倒的に劣勢だ。だが、全く無力という訳ではない。
火星沖海戦では、その格差を少しでも縮めるべく、大規模な空間障害を設置するなど、局所的な戦術上の優位を獲得すべく様々な努力が払われた。更に、文字通り『根こそぎ』というレベルで全地球圏から艦隊戦力が抽出され、敵に数倍する戦力が揃えられていた。
だが――本当にそれだけで十分だったのか?艦隊や司令部のお偉方は、本当に最善を尽くしたと言えるのか?
世界中からかき集められた戦力にしても、もっと有効な運用が可能だったのではないのか?かき集めた物量に満足し、それを過信した結果、戦術面での工夫が徹底しなかったのではないのか?
尾崎たちの奮戦と彼らが達成した戦果は、失敗に終わった冥王星救援作戦時に土方宙将が効果を証明した戦術によって成し遂げられたもので、他の地球艦隊でも十分に実践可能だった。だが、実際にはそうはならず、ガ軍の増援艦隊がデブリ・バリアーを突破した時点で地球艦隊は完全に動揺、その後は個艦単位の場当たり的な防御戦闘しか行うことができなかったという。
せめて、戦隊単位の集中砲撃戦術が徹底できていれば、自らの損害はともかく、敵軍に更なる出血を強いることができていたかもしれない。そこに俺のキリシマが加わっていれば、あるいは――。
「――山南、お前の悪いクセだ。何でもかんでも一人で抱え込むな」
不意に肩を小突かれ我に返ると、先程までとは対照的な表情を浮かべた安田が山南を見据えていた。
「確かに俺たちは艦を預かる指揮官だ。だが、俺たちだけで艦を背負っている訳じゃない。
幹部も乗員も、若手もヴェテランも、皆それぞれ艦を背負っているという気概を持っている。
責任とは違う。心構え、気構えみたいなものさ。
俺たちの上には、沖田さんや土方さんだっている。
艦も艦隊も、この戦争だって同じことさ。どれもこれも個人が背負いきれるほど軽くはないんだ。
だから――皆で背負う、それぞれの役割に対し皆で最善を尽くす。そうしなければ、こんな地獄みたいな戦争を戦い抜けやしない」
「――安田」
「そんな顔するな。今のは全部、土方さんの受け売りさ。
冥王星からの撤退戦で艦を喪った俺に、あの人はそう言ってくれたんだ」
冥王星救援作戦時に土方宙将が座上していたのが、安田が艦長を務めていた金剛型『ヒエイ』だった。だが、そのヒエイも既に亡い。艦隊主力の撤退を成功させる為の殿(しんがり)として外惑星圏で果てたのだ。
(そうだな、何を思い上がっていたんだ、俺は。
俺はキリシマ艦長として、己の本分と最善を尽くすだけだ)
吹っ切れた気分で山南は拳を固めると、宇宙防衛大学時代と同じように安田の肩を小突き返した。
「――頼むぜ、安田。
何としても俺たちの前まで敵を引っ張ってきてくれ。必ず俺が仕留めてやる。
むざむざとお前らを殺らせはしない」
「あぁ、昔っからお前の“腕”は信用してるさ。頼まれたよ。――それに、だ」
「なんだ?」
「お前のフネは作戦の要(カナメ)だ。危なくなったら俺たちが守ってやるよ」
そう言ってニンマリと笑う安田に山南も苦笑を禁じ得なかった。
「ぬかせ。こっちは自分の背中くらい自分で守れる。お前こそさっさと逃げないと、敵と一緒にぶっ飛ばしちまうぞ」
よぉー古代――そんな懐かしい呼びかけに古代守三尉が振り返ると、宇宙防衛大学時代の先輩である嶋津冴子一尉――突撃駆逐艦ヒビキ艦長――がひらひらと手を振りながら歩み寄ってくるところだった。
古代は、防衛大学の生ける伝説とも称されているこの女性士官の在学中、随分と目をかけてもらっていた(もっともその大半は、悪事発覚時の連帯責任担当だったが――)。
「今度はキリシマの“砲雷長”に大抜擢だって?とんだ大出世じゃないか」
「違いますよ、センパイ。“砲術長”です。公には存在しない臨時役職。
あだ名みたいなものですよ。正式には“艦長付砲術士”。
あー、ホンモノの砲雷長は艦長兼任です。
自分は――例の新兵器の速成教育を受けていますので」
「あれか・・・・・・。で、実際のところどうだ、使えそうか?」
「まだ何とも。
教育と言っても座学ばかりで、まだフルキャパでの実射すら行っていませんからね」
「そうか。しかし、残り少ない戦艦の艦長が砲雷長兼任とは、そりゃまた手荒い話だな・・・・・・」
見かけだけなら、国連宇宙軍でもトップ3に入ると評判の嶋津の美貌が僅かに曇る。
今や数隻しか残存していない戦艦クラスの科長が艦長兼任とは、宙自の人材枯渇もいよいよ深刻らしい――そんな嶋津の内心に気がついたのか、古代は努めて明るく言った。
「上官の数が少ないってのも悪くはないですよ。まぁ、風通しが良い分、カミナリもいきなり初弾命中ですが」
「違いない。
古代、『若おんじ』だの『“修”徳太子』だの、あだ名の印象に騙されるなよ。
そりゃあくまで『鬼竜』と比べての話だ。あのオヤジどもときたら――」
「――知ってます」
そう答えた時の古代の何とも言えない表情に、今度は嶋津が吹き出す番だった。
恐らく沖田提督謹製『説教後の無言酒盛り(地べた胡坐&差し&エンドレス)』や、山南艦長の反省会の名を借りた英国式茶会(極めて個性的な茶葉蘊蓄と戦術談義が磯風型の速射光線砲のような勢いで繰り出される独演会)にも招かれているに違いない。彼女自身、その洗礼を受けた経験があった――痛いほど。
しばらく二人して肩を震わせて笑った後、古代は少しだけ真顔に戻って言った。
「ところで・・・・・・ヒビキは復帰できそうなんですか?随分と酷いようですが」
「ん、さすがに――今回の作戦には間に合わないな。
だが、次のドンパチが始まるまでに、何とかこっちで曳船を見つけて月まで引っ張って帰るよ。今頃、副長がその段取りをつけている筈だ」
「さすがは石津教官」
「副長を知っているのか?」
「ええ、乗艦実習の際にお世話になりました」
宇宙防衛大学の乗艦実習で乗り込んだ突撃駆逐艦“アラシ”で、古代らの指導を担当したのが現ヒビキ副長の石津英二だった。決して口数の多い教官ではなかったが、宙雷屋らしい実直な態度と誠実な姿勢で学生たちの尊敬を集めていた。
『古代学生、中々宜しい。しかし戦場は生き物だ。それを忘れず、常に臨機応変にな』
最後の実技指導の際、そう言って肩を強く叩いてくれた事を今でもよく覚えている。
「――そうだったか。かく言うわたしは今でも世話になりっぱなしさ。
さすがは商船学校出の叩き上げだよ。あの交渉術にはどうしたって敵わない」
この時、月面で曳船探しに奔走していた石津が派手なクシャミをしていたかは定かではない。
語ることも尽き、暫し沈黙が二人を包んだ。
「・・・・・・古代、何があっても絶対に生きて帰るんだぞ。
無事に帰ったら、今度こそ宙自駆逐艦乗りの精髄を叩き込んでやる――とでも言うべきなんだろうが、そんなのガラじゃないしな。
とにかくお前は弟――進のことだけを考えろ。結局はそれが一番の御守になる」
「ありがとうございます。センパイも御無事で」
そんな言葉と敬礼を交し合い、二人は分かれた。
既に苛烈な実戦を経験している二人は、自分たちが口にした最後の言葉がどれほど難しいことか、よく分っていた。
●カ2号作戦参加戦力(日本国航宙自衛隊 第二空間護衛隊群を基幹に各国増援を加えた混成艦隊)
2193年5月時編成(※は隊旗艦)
〇主隊(沖田十三宙将直率)
・金剛型宇宙戦艦1(キリシマ※)
・村雨型宇宙巡洋艦6(トネ,ツクバ,ノシロ,スズヤ,イヅモ,カトリ)
〇直衛隊(隊司令:水谷信之三佐)
・磯風型突撃宇宙駆逐艦8
(フユヅキ※,ユキカゼ,テルヅキ,ユウヅキ,アキグモ,イカヅチ,アラシ,ナミカゼ)
〇支援隊(隊司令:安田俊太郎二佐)
・村雨型宇宙巡洋艦4(テンリュウ※,ユウギリ,ユウバリ,ユリシーズ/英王立宇宙軍)
・磯風型突撃宇宙駆逐艦14
(シキナミ,シマカゼ,カゲロウ,ユウグモ,オオナミ,カスミ
アサグモ,ユウダチ,スズカゼ,ワカバ,アマギリ,サザナミ
ナレースワン/タイ王国宇宙軍
トルニオ/フィンランド宇宙軍)

――『第二次火星沖海戦』へ続く――
お待たせしました!!
~火星沖2203~から半年、当初の公開予定からも更に2ヵ月近く遅れてしまいましたが、『第二次火星沖海戦』の前日譚である『幕間』が遂に公開です。
ニコニコ動画でもFGT2199さんによる最新予告も公開されます(^o^)
そしてそして、これらに続く『第二次火星沖海戦』の本編(MMD動画と原作文章)も、10月25日のMMD杯ZERO2の開催期間に合せて遂に公開です!!
いやー、ここまで本当に長かったです(^^;)
でも、それもあと一ヶ月かと思うと、少しばかり寂しくもなってきますね。
ブログの方をほったらかしにしている間に、2202の続編『宇宙戦艦ヤマト2205』が正式に告知されましたし、ヤマクル―の会報誌ではオリジナル版の復活篇前日譚(0章)たる『アクエリアス・アルゴリズム』の小説連載が予告されたりもしていました。
2199から心機一転して転がり始めたヤマトシリーズも、ここにきて更なる活況を呈し始めましたね(^o^)
我々ファンの二次創作も負けていられません♪
尚、この“幕間”では盟友EF12さんに快諾いただき、ヒビキ艦長にも顔出し(?)で登場いただきましたw
客演協力に快く応じていただきましたEF12さんには、改めて御礼申し上げますm(__)m
ではでは!一か月後の『第二次火星沖海戦』でお会いしましょう!!

地球の総力を結集した一大決戦――火星沖海戦は無残なまでの敗北に終わった。地球には未だ建造中や改装中、慣熟訓練中の艦艇も存在したが、火星沖で一どきに失われた戦力を思えば、焼け石に水としか思えなかった。
つまりそれは、宇宙レベルでいえば至近の地である火星にガミラス軍主力が展開し、地球本土へ直接侵攻を開始した場合、国連宇宙海軍にそれを食い止める実効的な手段は最早皆無であることを意味していた。
しかし、ここでまたしても地球人が目を疑うような事態が発生する――火星沖海戦後、火星圏を制圧したと思われていたガミラス軍が撤退したのである。
火星沖海戦序盤、空間障害物を利用した国連宇宙海軍の戦術は有効に機能し、ガミラス艦隊にかなりの損害を与えたものの、海戦後半に大規模なガ軍増援が戦闘加入したことで、海戦終了後もガミラス艦隊は未だ百隻以上の戦闘可能艦艇を保持していた。そしてそれだけの戦力があれば、制圧後の火星圏維持も容易であり、地球側の根拠地を接収するなどすれば、拠点構築にも困難はない筈であった。
しかし――ガミラス軍は撤退した。
当初、地球人たちはガ軍の撤退を何らかの欺瞞か次作戦に向けての予備行動ではないかと疑い、訝しんだ。しかし、いつまでも経ってもガ軍蠢動の兆候は確認できず、数週間が経過した後で、ようやく偵察用艦艇を火星圏に送り込むことを決定する。
警戒に警戒を重ねて派遣された偵察艦は、監視用衛星などの ガミラスの“置き土産”こそ発見したものの、宙域にガ軍潜伏を疑わせるような兆候を全く見出すことができなかった。また偵察艦は、自軍の通信周波数帯において極めて微弱な通信波やレーザー信号を複数傍受していた。確認の結果、それらは海戦中、大きな損傷を受けて航行不能や通信不能に陥った国連宇宙海軍所属艦艇たちであり、その数は意外なほど多かった。更に、完全に破壊されたと信じられていたグラディウス・ステーションも一部の機能は未だ生きており、健在な部隊が存在していることも同時に確認されている。
その報告に、国連統合軍司令部は久方ぶりに明るい空気に包まれ、宇宙海軍司令部に対して直ちに救援艦の派遣が命ぜられた。
しかし、それでも疑問は残った――何故ヤツらは引き上げたんだ?
その疑問に答えられる唯一の男――大ガミラス帝星国防軍第七五七空間機甲旅団長バルケ・シュルツ大佐にとって、その答はシンプル極まりないものだった。火星沖海戦における大佐の目的は、あくまで地球の機動戦力(主力艦隊)の殲滅であって、火星圏の制圧ではなかったからだ。
第二四重空間機甲旅団という増援を得て大勝利を飾ったものの、重機甲旅団は当初の予定通り引き上げられ(一部は既に次の任地である小マゼランへの移動を開始していた)、以降の地球攻略は元から存在する第七五七空間機甲旅団のみで行わなければならなかった。そして、火星沖海戦で被った損害も決して小さくない七五七旅団にとって、火星圏の掌握はもちろん、事後の地球・月の攻略を目的とした大規模攻勢など、戦力的に全く不可能な状況だった。
だが、そうした状況は海戦前から決定若しくは予想されていたものばかりであり、少なくとも大佐にとっては驚くような事態ではなかった。それどころか、現在の状況はシュルツ大佐と彼の幕僚団がデザインした大戦略そのものだった。
開戦以来の地球の抵抗の激しさを思えば、どれほど強力な増援(重機甲旅団)であれ、それが短期間の限定的な派遣に留まる限り、大規模戦闘(決戦)には勝利できても、粘り強い攻略戦が必要な敵首都星の制圧は難しい。それならばむしろ、決戦における完全勝利を徹底的に追及、増援部隊を積極的に用いて敵機動戦力を根こそぎにすることで敵の継戦意欲を破砕し、降伏勧告を受諾させる――それが大佐らの描いた戦略構想であった。
もちろん、制圧した火星圏に居座り、地球に対し軍事的プレッシャーをかけ続けた方が上記戦略にとって遥かに効果的であるのも間違いなかった。しかし方面軍からの増援が撤退した今、すり減らされた七五七旅団の戦力(稼働艦三十隻余)を火星と冥王星に二分するのは、あまりに危険であるとシュルツ大佐は判断した。
そんな危険を冒さずとも、火星沖海戦の大勝利をバックに、地球に対して揺さぶりをかけつつ降伏勧告を行えば、艦隊戦力という最も効果的な抗戦手段を失った地球は容易に陥ちる――その筈であった。
シュルツ大佐とその幕僚団によって築き上げられた戦略構想は極めて現実的且つ健全な判断から導きだされたもので、火星沖海戦の大勝利という戦術的成果も相まって、その実現性は非常に高かった。また、その実現性と確実性を更に高める為の“支作戦”が作戦参謀ヴォル・ヤレトラー少佐の主導で実行に移され、かなりの効果を挙げたことも地球に潜入中の工作員を通じて確認されていた。
地球に本戦略を打ち破ることが可能な現実的方策は殆どなく、ガミラス――いや、シュルツ大佐は本戦争(戦闘ではない)にチェックメイトをかけたも同然と思われた。
だが、完璧且つ完成直前と思われた大佐の戦略構想に思わぬところから待ったがかかる。敵からではない、他ならぬ彼らの上官――銀河方面軍作戦司令長官グレムト・ゲール少将からであった。
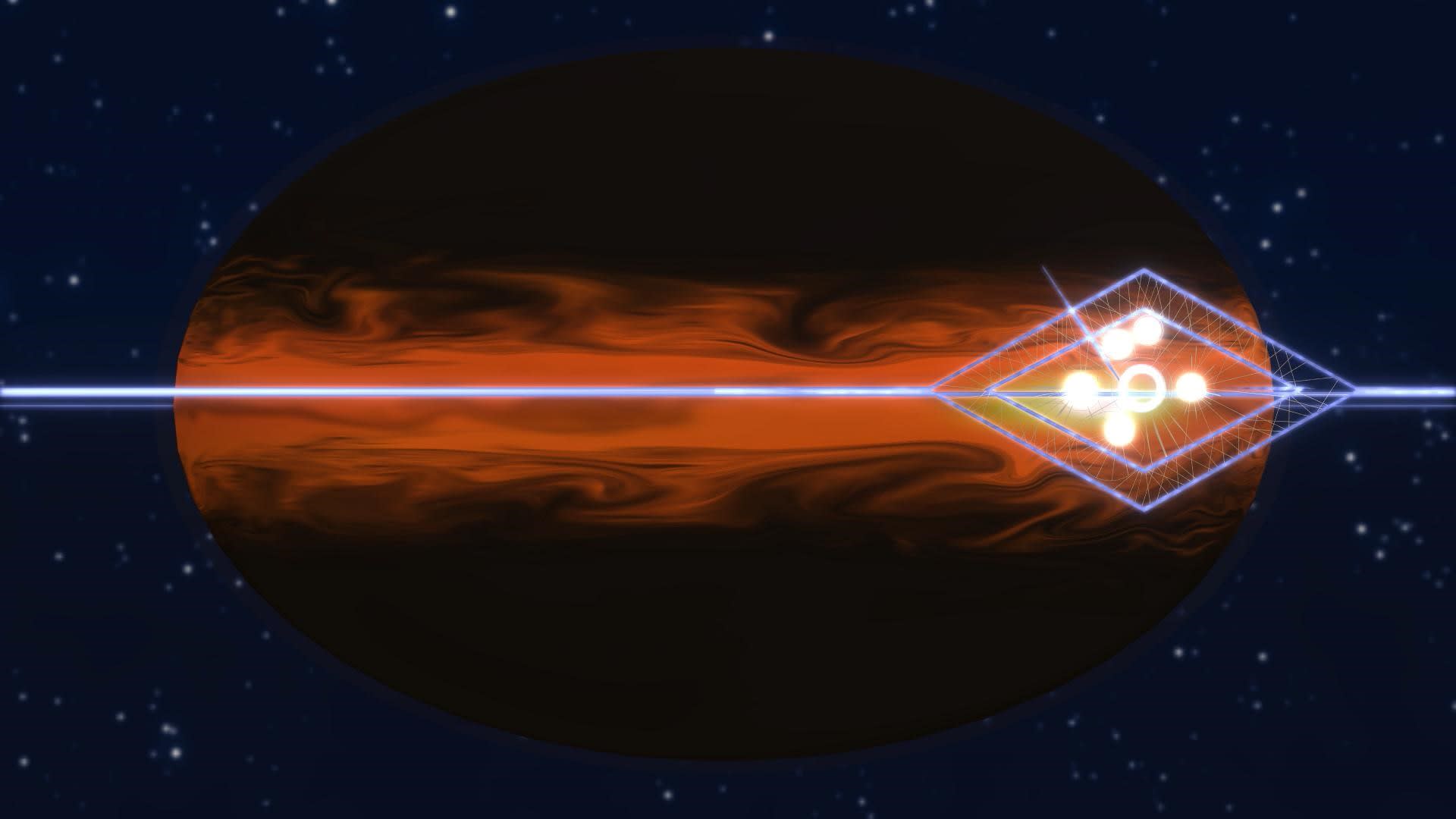
ゲール少将は歓喜していた。
長らく持て余し気味(殆ど存在を忘れるほど)だった重機甲旅団が、“自らの”完璧な作戦指導によって赫々たる戦果を挙げ、小マゼランへの転出に華を添えた。更に、自身が属する派閥の長であるゼーリック国家元帥からも直々にお褒めの言葉まで(『で、あるか』程度だが)賜った。これで、更に大きな戦果を挙げれば、本国への転属、いや栄転も夢ではない――少将の期待、いや野心は膨らむ一方だった。
そんな折に七五七旅団より上げられた、帝星国務省を通じた地球に対する降伏勧告という意見具申は、少将を激怒させるに十分だった。少将が望んでいたのは、降伏という確かではあっても地味な実績よりも、自らの栄転に値する見た目に派手な戦果――つまり、激戦の結果としての敵首都星の直接占領だったからだ。
具申に対する少将の返答は、それを目にしたシュルツ大佐が思わず『馬鹿な――』と絶句したとされるほど苛烈なものだった。
曰く――既に敵軍は先の大敗北によって意気消沈、残存戦力も僅かである。即刻、敵首都星攻略作戦を発起せよ。降伏勧告など、栄光あるガミラス軍人が発案すべき戦策に非ず。ガーレ・デスラー。
驚愕に打ちのめされたシュルツ大佐であったが、容易に引き下がることもできなかった。自身と幕僚団が築き上げた大戦略に絶対の自信があったことは勿論だが、純軍事的に地球の降伏が最早確実である以上、自らに忠誠を誓う部下たちの生命を危険に晒す必要性を全く認められなかったのである。
さすがにそれは公には口にできないにしても、現実問題として彼の手元には攻勢に出られるだけの戦力がなかった。七五七旅団は地球の降伏勧告受諾という戦略目標達成のために手持ちのリソースを完全に使い切っており、ゲール少将の求める“即時の攻勢発起”には少なくとも方面軍からの何らかの支援は不可欠だった。
シュルツ大佐は、まずは言を左右にして時間を稼ぎ、その間にゲール少将を翻意させるべく画策を図った。だが、本国への栄転への想いの強さ故か、少将を翻意させるのは容易ではなく、それどころか大佐が予想もしていなかった行動に出る。
突如、シュルツ大佐に命令不服従の疑いがあるとして、方面軍司令部への召喚命令を発したのである。しかも、命令は大佐のみならず旅団の主要幕僚全員に及んでおり、最早その狙いは明白だった。
シュルツ大佐が査問を受ける間、大佐の指揮権は停止され、旅団には旅団長代行が置かれることになる。ゲール少将はその代行者を意のままに操ることで、強引に攻勢を再開しようというのだ。
シュルツ大佐は自らの読みの甘さに臍を噛んだが、既に正式な召喚命令が発令されている以上、抵抗の余地はなかった。彼に可能であったのは、一分一秒でも早く旅団の指揮権を取り戻すべく、旗艦シュバリエルで方面軍司令部に出頭し、命令違反の事実などない事を証明することだけであった。
しかし太陽系――ガミラス人たちの言うところの『ゾル星系』――は、バラン星に設置された方面軍司令部までどれほど急いでも片道二ヶ月以上を要する辺境の地であり、その間に事態は大きく動くことになる。

「――陽電子衝撃砲?」
「はい、我々はショックカノンと呼んでいます」
後に地球と全人類を救った英雄と称えられることになる沖田十三提督が、最初に“新兵器”の概要説明を受けた際、そんなやり取りが交わされたとされている。この場面は、後にガミラス戦争や火星沖海戦が映画化・ドラマ化される際には必ずインサートされており、一般にも広く知られたシーンと言えるだろう。ただ、多くの作品において、沖田提督はこのやり取りだけで新兵器の全てを理解したかのように描かれているが、実際の状況はかなり異なるらしい。
開発技術者から一通りの概要説明を受けた後、宇宙物理学博士号すら有するこの歴戦の提督は、“新兵器”の構造、特性、制限、それらから導き出される現実的な運用方法に至るまでを長時間に渡り徹底的に技術者から聴取した。その様は、後に開発技術者の一人が『まるで試問か尋問のようだった』と述懐したほど容赦のないものであったが、同時に沖田提督の問いや指摘は極めて合理的且つ的確なもので、本ディスカッションを通じて、この新兵器に今後必要な改良点が浮き彫りになったと証言する技術者もいる程だ。
陽電子衝撃砲――通称:ショックカノン
後に地球防衛軍の主戦兵器の地位を獲得することになるこの新型艦載砲は、その名称からも明らかである通り、ガミラス軍の主戦兵器“陽電子ビーム砲”と基本的には同原理の兵器である。しかし、当時の地球の科学技術力では陽電子の生成はともかく、ガ軍の陽電子ビーム砲と同一の手法では十分な収束状態を実現することができなかった。結果、ガ軍よりも砲を大口径化してエネルギー量を稼ぎつつ、長大な砲身内で形成した電磁フィールドによってエネルギーを螺旋状に誘導、陽電子ビームが延伸する過程で更に収束率を向上させるという逆転の発想で、強引に射程と威力を引き上げていた。
その点、新型砲は機構やサイズ、エネルギー効率等、純技術的な洗練度ではガミラスよりも数段“遅れた兵器”であったが、大口径化と長砲身化の効能はそれを補って余り有り、開発技術者も一発あたりの威力と射程においてはガミラス軍の陽電子ビームを凌駕すると太鼓判を押していた。
だが、そうした強引な大威力化は他のスペックを犠牲にすることで達成されているのも事実であり、それ故の代償が存在した――それも、艦の死命を決しかねないほどの代償が。
『陽電子衝撃砲』を成立させ得るエネルギー量はあまりに膨大で、機関を全力稼働させても発射に足るエネルギーの充填には分単位の時間が必要であった。テンポの速い空間戦闘における分単位とは最早永遠にも近く、他艦の支援なしでは自艦の安全を確保しつつ連続発射を実現するのは事実上不可能と考えられた。また、陽電子ビームの螺旋誘導に必要な砲身も極めて長大であり、艦艇への搭載は主艦体そのものを砲身化する単装の軸線砲でしか不可能であった。
後に、開発技術者たちはこれらの問題点を様々な技術革新と画期的艦艇用機関――次元波動エンジン――の実用化によって解決することになるが、2193年時点においてそれらの問題点は、戦場で用兵家たちが運用の妙によって解決しなければならなかったのである。
そして、この未だ実用段階とは言い難いウェポンシステムの運用を任されたのが、開戦時の天王星沖海戦で戦傷を負い、この度ようやく復帰したばかりの沖田十三提督であった。
陽電子衝撃砲の試作砲は、まず金剛型宇宙戦艦最後の生き残りであるキリシマに搭載され、当初計画では数ヶ月間の実用テストの後、その結果をフィードバックした初期生産型が量産される予定であった。しかし、風雲急を告げる戦局はそれを許さず、キリシマでのテストを待たずして試作型をスケールダウンした増加試作品が急遽製作され、それらを装備した六隻の村雨型宇宙巡洋艦も沖田提督の指揮下に入ることが既に決定していた。
火星沖での大敗北後、地球各国政府の足並みは大きく乱れた。
地球にとって最後にして唯一の希望であった国連宇宙海軍は全滅し、遂に地球本土までもが侵略者の直接攻撃圏内に捉えられたことで恐怖に駆られた市民たちは、自国政府を激しく突き上げた。それに耐え切れず、非常任理事国を含む幾つかの国家が、国連で早期講和を唱え始めたのである。
未だ抗戦を諦めていない国家や人々――徹底抗戦派――からすれば、それは平和の美名を騙った紛れもない裏切り行為であったが、民主主義下においては許容された政治行為であり、民意の表明ではあった。
そして徹底抗戦派が最も憂慮したのが、早期講和派が公然化したことで、未だ徹底抗戦を明言している国家においても、国内に講和派が台頭してくることであった。もしそんな状況になってしまえば、国連及び常任理事国の強い指導で辛うじて維持されている地球規模の挙国一致体制は瓦解し、現状の劣勢が更に悪化するのは確実だったからだ。
事実、各国での世論調査の結果は講和派が急速に台頭しつつあることを示しており、徹底抗戦派の懸念は決して根拠のないものではなかった。
その点、こうした地球国家内での足並みの乱れは、ほぼはシュルツ大佐の狙い通りに進展していたと言えるだろう。しかも、地球攻略に向けて明快な大戦略を掲げたこの老獪なザルツ人大佐は、惹起した地球の混乱を更に拡大すべく次なる一手まで打っていた。
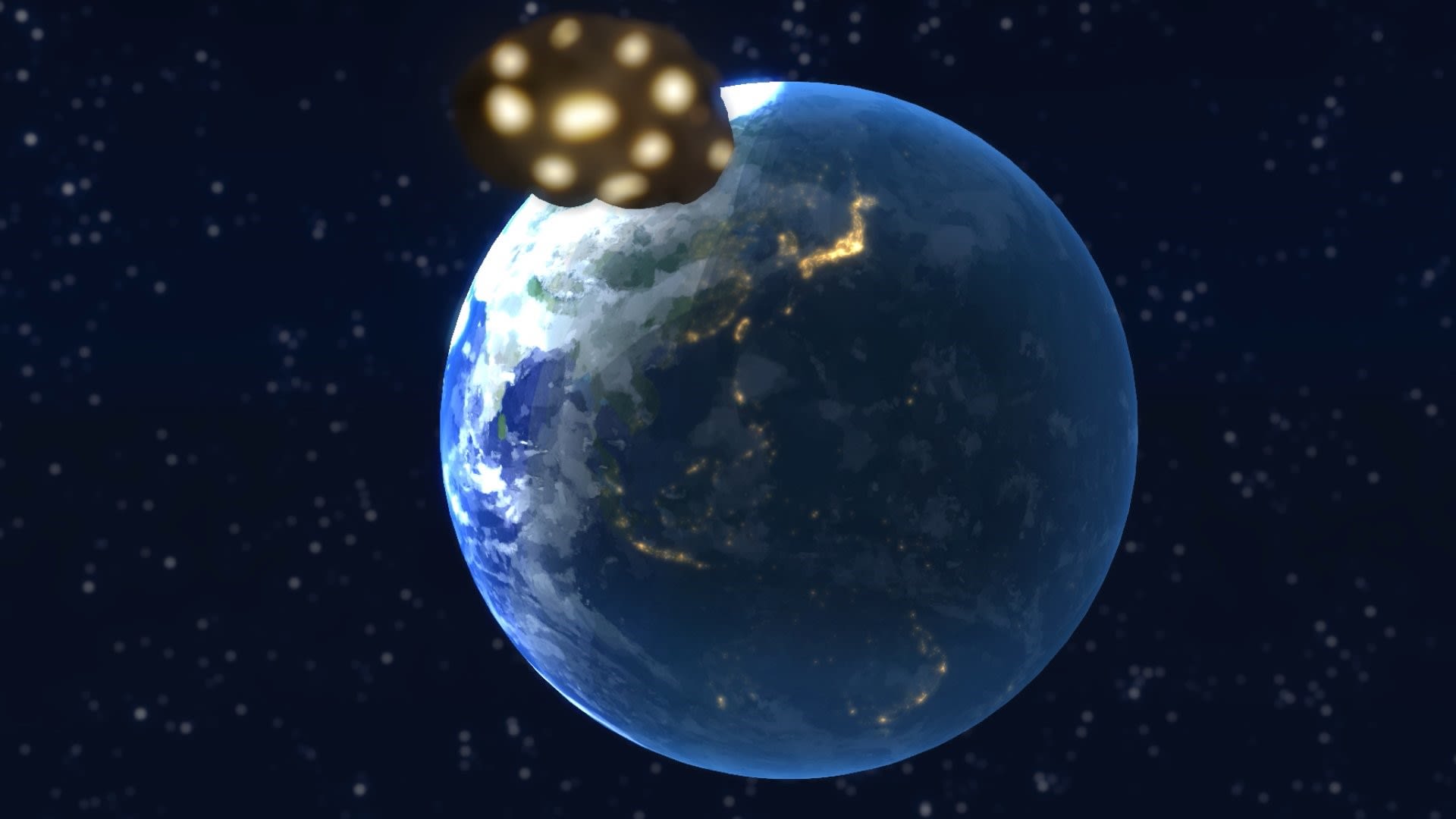
2193年4月12日、灼熱の火球と化した直径百メートル大の微惑星が地球に落下――後に『遊星爆弾』として怖れられることになる星間戦略爆撃の初弾である。
“爆弾”とはいえ、その実態はエッジワース・カイパーベルト天体に属する微惑星に、重金属充填による質量調整と耐熱用の簡易な表面処理を施しただけのもので、後の同種兵器のような生物兵器化――環境改造用植物の“種”が埋め込まれ、地球衝突後に飛散・発芽・胞子拡散する――は行われていなかった。また、爆撃が本格化する2194年以降のそれと比べれば比較的規模も小型であったが、それでもその威力は戦略級の熱核兵器にも匹敵した。
作戦参謀ヴォル・ヤレトラー少佐から、自然物を利用したこのロー・コスト兵器の上申を受けたシュルツ大佐は火星沖決戦後の“とどめ”として本兵器の採用と投入を決定、地球側の監視・警戒網が火星に向けて出撃するガミラス艦隊(七五七旅団)に引きつけられている間隙を突いて放出を果たしていたのである。
2193年当時、冥王星前線基地には未だ超大型陽電子ビーム砲『反射衛星砲』は設置されておらず、遊星爆弾第一号の初期加速は簡易なブースターによって行われた。更に、地球とのコリジョンコース設定も極めて慎重に行われた結果、地球圏への到達まで二ヶ月以上を要した
しかし、その間に行われた火星沖海戦と、その大敗による混乱から脱しきれていなかった国連宇宙海軍による察知は遅れに遅れ、気がついた時には遊星爆弾は既に木星軌道を通過していた。更に火星沖海戦で有力な機動戦力の大半を失っていた地球に有効な邀撃手段は残されておらず、国連軍による地球―月軌道での懸命の迎撃も空しく、遊星爆弾は地球への落着を果たす。
当初、遊星爆弾の落下地点はアメリカ合衆国ヴァージニア州と予測されていたが、国連軍の迎撃によって軌道が大きく変化し、結果的に爆弾が落下したのは遥か極東――日本国高知県南部――であった。
四国山地に属する山々とそれに源を発する多数の清流、それらが育んだ豊かな自然に彩られた古の土佐国は、この一弾によって無残に、そして完全に破壊された。破壊の一部は地殻を貫いてマントルにまで達しており、その後も長きに渡って深刻な地殻異常を引き起こすことになる。
遊星爆弾落着の事実とその光景は、発生した事象があまりに巨大であった為に報道管制など全く無意味であり、肉眼で本事象――真っ赤に灼けた巨大隕石が落下し、地上が眩い閃光に包まれる――を目撃した者の数は実に数百万人にも達した。更にネットワーク・インフラが発達した日本国内に落下したことも災いし、各種ネットワークを介した中継によって、世界中で数十億もの人々がほぼリアルタイムでこの凄惨な光景を目撃することになった。
当初、国連及び各国政府はこの事件を不運な隕石落下――つまりは自然現象と発表したが、それを信じるものは極僅かであり、多くの者が抗戦中の異星人の仕業であると確信していた。そしてその確信は、ガ軍に対する凄まじいばかりの恐怖へと容易に直結した。なぜなら彼らが敵に回した異星人は、軍人も民間人も関係なく数十万人を虐殺してしまうような無差別大量破壊兵器を――それも、現在の地球の科学軍事力では阻止困難な兵器を――平然と使用するような連中なのだ。
結果、強大且つ非道な敵に対する恐怖と、それに対してあまりに無力な国連や各国政府、軍への不信から、多くの市民が当時台頭しつつあった講和派へと流れることになる。彼らの多くが、開戦前には異星人の撃退を強く主張していたことを思えば、“変節”と評しても良い世論の変化だった。
徹底抗戦派の分析では、火星沖海戦の敗北発表後も民意は未だ七対三で抗戦派が優勢だったが、遊星爆弾の落下によってその比率は遂に六対四を切り、三ヶ月以内に民意は完全に逆転すると予想された。更に、この予想は現状で戦況が固定された場合のもので、更なるガミラス軍の攻勢や微惑星爆撃が実施された場合には、抗戦派と講和派の形勢は完全に逆転するとも考えられていた。
三ヶ月以内の反攻作戦――『カ2号作戦』――は、こうした戦略環境を受けて未だ徹底抗戦派が多数を占める国連宇宙防衛委員会で急遽決定された。
だが、決定こそ下されたものの、状況は最悪の一言に尽きた。
火星沖で機動戦力の大半を失ったことに加え、遊星爆弾の落下により各国政府の足並みの乱れは各国軍にまで及んでおり、国連統合軍に派遣した部隊の引き上げや、指揮系統からの離脱が相次いだからだ。
その為、反攻作戦は“政治的に信頼がおける国”の軍を主体にせざるを得ず、元より乏しい残存戦力を更に低下させることになった。しかも、これまで国連宇宙海軍の主力の地位を占めていた米・中軍は既に壊滅状態であった為、結果的に反攻作戦は比較的まとまった戦力を残していた日本国航宙自衛隊が主力とされた。
だがこの時、陸・海・空・宙の各自衛隊は遊星爆弾直撃による大被害への対応に忙殺されており、それは反攻作戦主力に任じられた航宙自衛隊すら例外ではなかった。現在も継続中の救難・救援活動からどうしても引き抜くことができない艦艇や隊員も少なくなかったのである。
結果、宙自単独では不足する戦力を補填する為に、国連宇宙軍を介した調整によって数ヶ国からの増援が加えられることになった。しかし当初は、編成が多国籍化することで指揮命令系統に不安が生じると宙自上層部が難色を示し、事実、日本隣国からの艦隊参加表明が“歴史”に係る厄介な政治問題を引き起こすという一幕もあった。
幸い、本作戦の編成主体である国連統合軍が馬鹿げた面倒を嫌った為、200年以上前の歴史を盾に非常識極まりない要求――艦隊指揮官は日本人以外とする、自国艦艇の指揮権の独立、連絡将校の受け入れ拒否――を送りつけてきた隣国に対しては、統合軍が簡潔且つ辛辣に艦隊参加を拒絶している。
曰く――貴国艦艇の能力・練度・士気、いずれにおいても本作戦への参加に能わず――と。
本顛末の唯一の救いは、半ば面罵するような国連統合軍の回答(意図的に一般にもリークされた)が各国にも広く知れ渡ったことで、生半可な覚悟と練度と装備では本作戦参加を表明することができなくなり、各国精鋭のみを集成した艦隊編成が可能になったことだけだった。
こうして、多少の軋轢こそ発生したものの、なんとか編成を完結した地球艦隊の指揮官には、戦傷から回復したばかりの沖田十三提督に白羽の矢が立てられた。
しかし軍務局は、開戦時の攻撃命令を拒絶して解任された沖田提督の指揮官就任に強く反対し、冥王星からの撤退戦で活躍した土方宙将(当時は航宙軍士官候補生学校長に就いていた)を推した。だが、他ならぬ土方宙将本人から頑として固辞された結果、渋々ながら沖田提督の就任を了承している。
反攻作戦決定後、慌ただしく招集された『カ2号作戦』準備会議には、作戦参加予定部隊の艦長以上の指揮官、新型砲搭載艦の砲雷長、航空隊幹部、そして沖田提督の強い要請で多数のオブザーバーが招かれており、その中には火星沖海戦で奮戦した突撃宇宙駆逐艦ヒビキ艦長の姿もあった。

ヒビキは海戦序盤においてガミラス艦二隻に大きな損傷を与えたものの、ガ軍重機甲旅団の戦闘加入後はデブリゾーンに立てこもっての耐久を強いられた。そして海戦最終盤、ヒビキは盾にしていたデブリごとガミラス軍の陽電子ビームに射抜かれてしまう――だが、彼女は沈まなかった。
こと防御においては脆弱極まりない突撃駆逐艦の被弾は即轟沈に繋がるケースが多いにもかかわらず、彼女が生き残ることができたのには、幾つかの幸運と必然が作用していた。
一つ目の幸運は、あまりに激しいガミラス艦隊の砲撃に、最早被弾は避けられないと判断した艦長の命令で残存魚雷と実体弾の全投棄、機関も完全停止の上、総員でのダメコン準備が発令されていたことだった。ヒビキの被弾は、それら全ての命令履行が確認された直後のことで、結果、誘爆などの二次被害を免れた彼女は一撃で爆沈するという最悪の事態を避けられたのである。
とはいえ、ガミラス艦の陽電子ビームは極めて強力であり、ヒビキは機関を完全に破壊された上に全電源も喪失、デブリゾーンの中を殆ど残骸のような姿で漂流することになった。
そして彼女の二つ目の幸運は、漂流の過程で他艦が仮泊地としていた大型デブリに接触できたことであった。元々そのデブリを仮泊地にしていた駆逐艦の消息は不明であったが(後に撃沈が確認された)、残されていた資材や消耗品を活用することで、ヒビキとその乗員たちは電源と通信機能を回復すると共に、救難艦の到着まで何とか生き延びることができたのである。
艦長以下乗員たちは大破したヒビキを何とか地球まで曳航し、修復しようと四苦八苦していたところを、艦長のみが急遽作戦準備会議に招聘され、不承不承この会議に加わっていた。
会議では、火星沖海戦時のヒビキのガン・カメラ映像が映し出され、艦長はその際の戦術状況を手始めに、自らが採った戦術意図と実施における過程と結果の説明を細部に渡って求められた。更に、彼女の説明に対しても沖田、土方両提督を筆頭に多数の質問が次々に浴びせられ、そのあまりの執拗さに、ヒビキ艦長が内心で辟易した程だった。
ようやくヒビキ艦長に対する質疑応答が終わると、今度は海戦後の火星沖で回収されたガミラス艦の装甲板が会議室に持ち込まれ、南部重工から出向中の素材技術者がその特性と破損状況の報告を行った。

火星沖海戦以前の戦いでは、いずれも戦闘後の戦場の支配権はガミラス軍が掌握しており、国連統合軍はガ軍艦艇の残骸や遺棄物資を回収することができなかった。しかし、火星沖海戦後にガミラス軍が火星圏から撤退したことで、初めてガ軍艦艇から脱落した部品や装甲板を回収することができた。回収物の解析は未だ緒に就いたばかりであったが、それでもこれまで完全な謎に包まれていたガ軍艦艇の防御上の特性が幾つも明らかにされていたのである。
最後に、艦隊砲術参謀がヒビキ艦長と素材技術者の報告を総括し、以下のように結論を取りまとめた。
・高圧増幅光線砲単独では、至近且つ同一箇所に集中して命中させない限り、ガミラス艦艇の装甲は射貫不可能
・ガミラス艦艇は、装甲表面に特殊なコーティングを施し、装甲強度と耐弾性を著しく高めている
・件のコーティングは、光線砲でも連続して命中させることで剥離が可能
・コーティング剥離後の装甲に対しては、光線砲よりも空間魚雷や高初速実体弾の直撃が有効
その報告に、会議室内は大きくどよめいた。これまで、よほどの僥倖に恵まれない限り、ダメージを与えられないと考えられていたガ軍艦艇の具体的且つ実戦的な撃破方法が初めて示されたからである。
それを端的に述べれば――攻撃艦は攻撃目標のガ軍艦艇に肉薄しつつ、高圧増幅光線砲の集中射撃にてガ軍艦艇の耐弾コーディングを除去、そこへ至近距離からピンポイントで対艦砲か空間魚雷を撃ち込む――というものであった。
開戦後、光線砲のあまりの威力不足から、ガ軍艦艇への攻撃は空間魚雷が主となっており、更に肉薄時にできるだけ自艦の存在と位置を秘匿する為、光線砲の砲撃は一層控えられる傾向にあったことを思えば、大きな戦術の転換と言えた。
攻撃の成功にはこれまで通り敵艦への肉薄が不可欠であり、砲撃による自位置と存在の暴露で攻撃難度は上がるが、敵艦にダメージを与えられる確度も飛躍的に向上するのは間違いなく、戦術の変更を指示された巡洋艦や駆逐艦の艦長たちの顔はいずれも明るかった。
そして更に、事前に沖田提督とショックカノン搭載艦の幹部にのみ開示されていた新型砲――ショックカノン――の存在が会議参加者に明らかにされたことで、作戦準備会議の雰囲気は目に見えて変化し始めていた。
――これならば、勝てるかもしれない。
そこにあったのは、長らく忘れていた勝利の予感であり、感触だった。ほぼ無敵と思われたガミラス艦艇を撃破可能な戦術と新兵器の存在はそれ程のインパクトを持っていた。
彼らの大半は、これまでの戦いで多くの仲間――上官や部下、同期――を喪っており、中には四国南部への遊星爆弾落下によって肉親や友人まで亡くした者もいる。いずれの会議参加者も表面上はヴェテラン軍人そのものという冷静さを維持していたものの、そのぎらつくような瞳の輝きは、復仇の機会を渇望し、それを目前にした者に特有のそれであった。
だが、そうした会議室の空気を一人の男が変えた。
その男――土方竜宙将は沖田提督から発言の許可を得ると立ち上がった。その眼光は指揮下の艦隊乗員や候補生たちから奉られた“鬼竜”という異名そのままに、どこまでも鋭い。
彼もまたオブサーバーとして会議に参加していたが、本作戦の立案にあたり、旧友である沖田提督に強く請われ、実質的には作戦参謀としての役割を担っているという専らの噂であった。
彼は、その噂を自ら肯定するように会議出席者を睥睨しつつこう言い放った。
「諸君らには今一度思い出してもらいたい。
火星沖でも、我々は勝利を確信した。
しかしその確信は、敵の増援投入によって粉微塵に打ち砕かれた。
――今回も同じだ。
我々の勝機は、数が限られ、未だ不完全な新兵器と、危険極まりない肉薄戦術にしかない。
それらの優位はあまりに脆弱であり、圧倒的に優勢な敵軍はそれを容易に覆し得る――それを絶対に忘れてはならない」
醸成されつつあった興奮と熱気が消え、再び水を打ったように静まり返った会議室に土方宙将の声だけが神託のように響く。
だが、彼の“役割”は会議出席者の楽観を引き締めることだけではなかった。むしろ、ここからが本題だった。

「我々は火星沖で敗れた。だが、我々にはまだ戦う力が――新たな力がある。
そして、敵はまだ“それ”を知らない。
今次作戦『カ2号』はその奇襲効果を最大限に利用する」
宿将の瞳に込められた決意の強さに、会議参加者全員が威儀を正して彼の次なる言葉を待った。だが、続いて彼の口から語られた作戦構想は、あまりに破天荒なものであった――。
「本当によかったのか、これで」
「ああ。この役は今の俺にしかできん。こんな綱渡りのような作戦を完遂するには、艦隊全員がお前の命令に従って一糸乱れずに行動する必要がある。
その為には、非情な作戦を立案し、押し付ける汚れ役が必要だ。そんな役は、安全な後方で教師の真似事をしているような男にしか務まらん。
――気に病む必要などない。もしお前と俺の立場が逆なら、お前はどうした?」
「すまんな。しかし・・・・・・安田君は全て気づいていたようだが」
「あぁ、奴とは付き合いが長い。目端も利く。だから一番危険な任務を任せた」
「彼は分っているよ。それがお前の信頼の証だということを」
「そうだな・・・・・・」
既に会議が散会して十五分が経過していた。会議参加者の大半は退室し、残っているのは何らかの打合せをしている者たちだけだ。
沖田の視線が出口に向かう一人の士官を捉えた。土方もつられるようにそちらを見る。
艦長用制服に身を包んだ若手士官――腕章には『TERUZUKI』とある――は二人の視線に気がつくと立ち止まり、ピシリと敬礼をささげた。その瞳には、上官に向けた敬意というだけでは説明できない真摯さと親しみがある。
沖田と土方が揃って答礼を返すと、士官は待たせていた副長を連れて足早に立ち去った。その後ろ姿をじっと凝視している親友の姿に、土方は微かな羨望と共に、消しようのない胸の痛みを覚えた。
だが、今の彼にその痛みを吐露することは許されない。だからこそ、彼は言った。
「――沖田、生きて帰ってこい。どんなことがあっても、必ずだ」
そんな同期二人を遠くから眺めている別の二人がいる。世代こそ違うが、彼らもまた同期だった。
「親父ドノたちの苦労は絶えん、ってところか」
どこか諧謔を感じさせる口調のテンリュウ艦長 安田俊太郎二佐に、キリシマ艦長 山南修二佐が噛みついた。
「バカ野郎。どう考えても、この作戦で一番苦労するのは貴様だろうが。
自分から貧乏クジを引きやがって。」
普段のシニカルな物言いを好む山南を知る者からすると、その口調は随分と荒々しく感じられたが、そこは勝手知ったる同期の仲、安田の返答も慣れたものだった。
「任せておけよ。こういう役は得意だ。知っているだろ?
貴様に乗せられた俺が、何度女の子に声をかけて、何度貴様の前まで引っ張ってきたことか」
「ふん、率は精々四分六だったがな――」
「それを言うな。それに、俺の引いたクジなんてまだまだ序の口さ。
増援で送り込まれる航空隊には、訓練中の学生までいるって話だ」
「本当か?それは」
山南は目を剥くと同時に慄然とした。
――俺たちは、本来は守るべき半人前の子供たちまで動員してこの戦争を継続してようとしているのか?
「なんでも一人は、教官すら叩き落すような凄腕らしいが・・・・・・」
そう続ける安田も釈然としないのは同様らしい。しかし、一艦を預かる指揮官として、既に動き始めた作戦に対する批判は厳に慎まなければならない。
山南は内心の屈託を断ち切るように、両手で制帽を被り直した。
「しかし尾崎のこともある。貴様も気をつけろ。
で・・・・・・あいつの容態は?」
「こっちに来る前に軍病院に寄ったが、まだ意識が戻らん。ここ二、三日がヤマらしい」
「・・・・・・そうか」
先の火星沖海戦では、彼らのもう一人の宇宙防衛大学同期である尾崎徹太郎二佐が重傷を負っている。
尾崎は、キリシマと同じ金剛型のネームシップ『コンゴウ』の艦長を務めていたが、海戦終盤のガミラス軍の攻勢――メルトリア級を主力とした突破戦闘――に浮足立つ友軍を後目に孤軍奮闘、複数艦での近距離集中砲撃によってガミラス艦数隻に無視できない損害を与えていた。

しかし、海戦の帰趨を覆すことは叶わず、最後まで奮戦したコンゴウもまた激しく損傷し、遂には総員退艦命令が発せられるに至る。艦長の尾崎は艦内に取り残された乗員がいないかを確認していた際、発生した爆発に巻き込まれ重傷を負ったという。幸い、他の乗員たちによって救助された彼は急ぎ地球に後送されたものの、未だその意識は戻っていない。
せめて俺が、俺のキリシマが参戦していれば――山南の心中にはそんな忸怩たる想いがある。もちろん、内惑星戦争以来の豊富な実戦経験を有する彼は、いくら期待の新型砲を装備したキリシマといえど、たった一隻であの戦いをひっくり返せたとは毛ほども思っていない。しかしそれでも、キリシマの参戦によって一人でも多くの戦友を、一隻でも多くの友軍を救えたのではないかという想いを抱かずにはいられないのだ。
その点、彼はこの過酷極まりない戦況の中にあっても、未だ指揮官としての責任と人間としての優しさ、良識を維持している漢だった。
とはいえ、そんな彼の内心にも消しようのない怒りがある。だが、その怒りは敵軍に対してよりも、寧ろ自らと友軍――その上層部――に向けられたものだった。
確かに地球艦隊の戦力は、個艦レベルで敵に対して圧倒的に劣勢だ。だが、全く無力という訳ではない。
火星沖海戦では、その格差を少しでも縮めるべく、大規模な空間障害を設置するなど、局所的な戦術上の優位を獲得すべく様々な努力が払われた。更に、文字通り『根こそぎ』というレベルで全地球圏から艦隊戦力が抽出され、敵に数倍する戦力が揃えられていた。
だが――本当にそれだけで十分だったのか?艦隊や司令部のお偉方は、本当に最善を尽くしたと言えるのか?
世界中からかき集められた戦力にしても、もっと有効な運用が可能だったのではないのか?かき集めた物量に満足し、それを過信した結果、戦術面での工夫が徹底しなかったのではないのか?
尾崎たちの奮戦と彼らが達成した戦果は、失敗に終わった冥王星救援作戦時に土方宙将が効果を証明した戦術によって成し遂げられたもので、他の地球艦隊でも十分に実践可能だった。だが、実際にはそうはならず、ガ軍の増援艦隊がデブリ・バリアーを突破した時点で地球艦隊は完全に動揺、その後は個艦単位の場当たり的な防御戦闘しか行うことができなかったという。
せめて、戦隊単位の集中砲撃戦術が徹底できていれば、自らの損害はともかく、敵軍に更なる出血を強いることができていたかもしれない。そこに俺のキリシマが加わっていれば、あるいは――。
「――山南、お前の悪いクセだ。何でもかんでも一人で抱え込むな」
不意に肩を小突かれ我に返ると、先程までとは対照的な表情を浮かべた安田が山南を見据えていた。
「確かに俺たちは艦を預かる指揮官だ。だが、俺たちだけで艦を背負っている訳じゃない。
幹部も乗員も、若手もヴェテランも、皆それぞれ艦を背負っているという気概を持っている。
責任とは違う。心構え、気構えみたいなものさ。
俺たちの上には、沖田さんや土方さんだっている。
艦も艦隊も、この戦争だって同じことさ。どれもこれも個人が背負いきれるほど軽くはないんだ。
だから――皆で背負う、それぞれの役割に対し皆で最善を尽くす。そうしなければ、こんな地獄みたいな戦争を戦い抜けやしない」
「――安田」
「そんな顔するな。今のは全部、土方さんの受け売りさ。
冥王星からの撤退戦で艦を喪った俺に、あの人はそう言ってくれたんだ」
冥王星救援作戦時に土方宙将が座上していたのが、安田が艦長を務めていた金剛型『ヒエイ』だった。だが、そのヒエイも既に亡い。艦隊主力の撤退を成功させる為の殿(しんがり)として外惑星圏で果てたのだ。
(そうだな、何を思い上がっていたんだ、俺は。
俺はキリシマ艦長として、己の本分と最善を尽くすだけだ)
吹っ切れた気分で山南は拳を固めると、宇宙防衛大学時代と同じように安田の肩を小突き返した。
「――頼むぜ、安田。
何としても俺たちの前まで敵を引っ張ってきてくれ。必ず俺が仕留めてやる。
むざむざとお前らを殺らせはしない」
「あぁ、昔っからお前の“腕”は信用してるさ。頼まれたよ。――それに、だ」
「なんだ?」
「お前のフネは作戦の要(カナメ)だ。危なくなったら俺たちが守ってやるよ」
そう言ってニンマリと笑う安田に山南も苦笑を禁じ得なかった。
「ぬかせ。こっちは自分の背中くらい自分で守れる。お前こそさっさと逃げないと、敵と一緒にぶっ飛ばしちまうぞ」
よぉー古代――そんな懐かしい呼びかけに古代守三尉が振り返ると、宇宙防衛大学時代の先輩である嶋津冴子一尉――突撃駆逐艦ヒビキ艦長――がひらひらと手を振りながら歩み寄ってくるところだった。
古代は、防衛大学の生ける伝説とも称されているこの女性士官の在学中、随分と目をかけてもらっていた(もっともその大半は、悪事発覚時の連帯責任担当だったが――)。
「今度はキリシマの“砲雷長”に大抜擢だって?とんだ大出世じゃないか」
「違いますよ、センパイ。“砲術長”です。公には存在しない臨時役職。
あだ名みたいなものですよ。正式には“艦長付砲術士”。
あー、ホンモノの砲雷長は艦長兼任です。
自分は――例の新兵器の速成教育を受けていますので」
「あれか・・・・・・。で、実際のところどうだ、使えそうか?」
「まだ何とも。
教育と言っても座学ばかりで、まだフルキャパでの実射すら行っていませんからね」
「そうか。しかし、残り少ない戦艦の艦長が砲雷長兼任とは、そりゃまた手荒い話だな・・・・・・」
見かけだけなら、国連宇宙軍でもトップ3に入ると評判の嶋津の美貌が僅かに曇る。
今や数隻しか残存していない戦艦クラスの科長が艦長兼任とは、宙自の人材枯渇もいよいよ深刻らしい――そんな嶋津の内心に気がついたのか、古代は努めて明るく言った。
「上官の数が少ないってのも悪くはないですよ。まぁ、風通しが良い分、カミナリもいきなり初弾命中ですが」
「違いない。
古代、『若おんじ』だの『“修”徳太子』だの、あだ名の印象に騙されるなよ。
そりゃあくまで『鬼竜』と比べての話だ。あのオヤジどもときたら――」
「――知ってます」
そう答えた時の古代の何とも言えない表情に、今度は嶋津が吹き出す番だった。
恐らく沖田提督謹製『説教後の無言酒盛り(地べた胡坐&差し&エンドレス)』や、山南艦長の反省会の名を借りた英国式茶会(極めて個性的な茶葉蘊蓄と戦術談義が磯風型の速射光線砲のような勢いで繰り出される独演会)にも招かれているに違いない。彼女自身、その洗礼を受けた経験があった――痛いほど。
しばらく二人して肩を震わせて笑った後、古代は少しだけ真顔に戻って言った。
「ところで・・・・・・ヒビキは復帰できそうなんですか?随分と酷いようですが」
「ん、さすがに――今回の作戦には間に合わないな。
だが、次のドンパチが始まるまでに、何とかこっちで曳船を見つけて月まで引っ張って帰るよ。今頃、副長がその段取りをつけている筈だ」
「さすがは石津教官」
「副長を知っているのか?」
「ええ、乗艦実習の際にお世話になりました」
宇宙防衛大学の乗艦実習で乗り込んだ突撃駆逐艦“アラシ”で、古代らの指導を担当したのが現ヒビキ副長の石津英二だった。決して口数の多い教官ではなかったが、宙雷屋らしい実直な態度と誠実な姿勢で学生たちの尊敬を集めていた。
『古代学生、中々宜しい。しかし戦場は生き物だ。それを忘れず、常に臨機応変にな』
最後の実技指導の際、そう言って肩を強く叩いてくれた事を今でもよく覚えている。
「――そうだったか。かく言うわたしは今でも世話になりっぱなしさ。
さすがは商船学校出の叩き上げだよ。あの交渉術にはどうしたって敵わない」
この時、月面で曳船探しに奔走していた石津が派手なクシャミをしていたかは定かではない。
語ることも尽き、暫し沈黙が二人を包んだ。
「・・・・・・古代、何があっても絶対に生きて帰るんだぞ。
無事に帰ったら、今度こそ宙自駆逐艦乗りの精髄を叩き込んでやる――とでも言うべきなんだろうが、そんなのガラじゃないしな。
とにかくお前は弟――進のことだけを考えろ。結局はそれが一番の御守になる」
「ありがとうございます。センパイも御無事で」
そんな言葉と敬礼を交し合い、二人は分かれた。
既に苛烈な実戦を経験している二人は、自分たちが口にした最後の言葉がどれほど難しいことか、よく分っていた。
●カ2号作戦参加戦力(日本国航宙自衛隊 第二空間護衛隊群を基幹に各国増援を加えた混成艦隊)
2193年5月時編成(※は隊旗艦)
〇主隊(沖田十三宙将直率)
・金剛型宇宙戦艦1(キリシマ※)
・村雨型宇宙巡洋艦6(トネ,ツクバ,ノシロ,スズヤ,イヅモ,カトリ)
〇直衛隊(隊司令:水谷信之三佐)
・磯風型突撃宇宙駆逐艦8
(フユヅキ※,ユキカゼ,テルヅキ,ユウヅキ,アキグモ,イカヅチ,アラシ,ナミカゼ)
〇支援隊(隊司令:安田俊太郎二佐)
・村雨型宇宙巡洋艦4(テンリュウ※,ユウギリ,ユウバリ,ユリシーズ/英王立宇宙軍)
・磯風型突撃宇宙駆逐艦14
(シキナミ,シマカゼ,カゲロウ,ユウグモ,オオナミ,カスミ
アサグモ,ユウダチ,スズカゼ,ワカバ,アマギリ,サザナミ
ナレースワン/タイ王国宇宙軍
トルニオ/フィンランド宇宙軍)

――『第二次火星沖海戦』へ続く――
お待たせしました!!
~火星沖2203~から半年、当初の公開予定からも更に2ヵ月近く遅れてしまいましたが、『第二次火星沖海戦』の前日譚である『幕間』が遂に公開です。
ニコニコ動画でもFGT2199さんによる最新予告も公開されます(^o^)
そしてそして、これらに続く『第二次火星沖海戦』の本編(MMD動画と原作文章)も、10月25日のMMD杯ZERO2の開催期間に合せて遂に公開です!!
いやー、ここまで本当に長かったです(^^;)
でも、それもあと一ヶ月かと思うと、少しばかり寂しくもなってきますね。
ブログの方をほったらかしにしている間に、2202の続編『宇宙戦艦ヤマト2205』が正式に告知されましたし、ヤマクル―の会報誌ではオリジナル版の復活篇前日譚(0章)たる『アクエリアス・アルゴリズム』の小説連載が予告されたりもしていました。
2199から心機一転して転がり始めたヤマトシリーズも、ここにきて更なる活況を呈し始めましたね(^o^)
我々ファンの二次創作も負けていられません♪
尚、この“幕間”では盟友EF12さんに快諾いただき、ヒビキ艦長にも顔出し(?)で登場いただきましたw
客演協力に快く応じていただきましたEF12さんには、改めて御礼申し上げますm(__)m
ではでは!一か月後の『第二次火星沖海戦』でお会いしましょう!!















