みなさま、ご機嫌はいかがでしょうか?
横浜では昨日より、
「ジャパン インターナショナルボートショー2012」が開催されています。
私も、早く見に行きたいのですが・・・
昨日は月末/月初の事務処理で・・・X
今日は・・・昨日電話があって、「明日行って(来店して)いいですか?」
と言われたので、「修理かな?」とお待ちしていたので、
結局、明日3/3(土)になりました。
行ってきま~す。
さて本日は船外機のクラッチについてです。
船外機は前進、後進にシフトした場合、「ガリガリ」みたいな
独特の音がすることがありますね。
わざとゆっくりシフトレバーを倒しておくと、「ガリガリガリガリガリガリ・・・ドン」みたいな・・・
船外機の多くは「ドッグクラッチ」というシステムを採用しています。
(BF2Dは遠心クラッチなので、今回の話には該当しません!)
まさしく「噛みつくような」クラッチです。
写真の3つのギヤに囲まれている、真ん中の部品が「それ」です。
船外機が始動すると、3つのギヤも常時回転を始めます。
そこで、「ドッグクラッチ」が前後に(この写真では左右に)スライドすることで、
プロペラシャフトに動力が伝わります。
(プロペラシャフトとドッグクラッチはコンビです)
写真では見やすいように、片方のギヤをわざとずらしています。
右側の写真が前進状態、左は後進状態にクラッチがつながった状態です。
ドッグクラッチがどっちらにスライドするかで、プロペラシャフトの
正回転もしくは逆回転するかが決まります。(前進後進)
もう少しスライドを見やすくすると・・・
それぞれスライド方向に、「ベベルギヤF」および「ベベルギヤR」
があります。それぞれ前進、後進を伝えるギヤです。
ベベルギヤは常時、FとRは逆に回転しています。
前進、及び後進の担当で、クラッチとつながる部分の「ツメ」の
数が違う場合が多いです。(前進担当の方が多い)
写真はBF90ATのものですが、前進は6ツメですが、後進は3ツメです。
使用頻度の違いからでしょうか?
(誰からも詳しく聞いたことが無いので・・・・)
また、前進側の6つの各ツメの山の形状は、片方が引っかかり、
片方は引っかからないような、工具の「ラチェット」のような
運動をするように作られているのが、わかるでしょうか?
たとえが陸上で(エンジンは停止)クラッチを前進に入れておき、
プロペラを手で回そうとすると、片方の回転は回りませんが、
逆方向は「カチッ、カチッ」と音が鳴って、回転する場合が多いです。
(該当しない船外機も、あります・・・・・)
これは、たとえば前進で全速で走行していて、急にスロットルをOFFに
したとき、ボートは行き足(惰性)で何メートルも前進しますが、そのとき
水中では、プロペラも船体が前に進めば進む分、水に逆回転させられて、
ぐるぐる回ります。
「バックトルク」とかいったと思うのですが、そのままプロペラの回転が
エンジンやクランクに伝わるといけないので、ラチェット運動させて
バックトルク?を逃がしています。
なお、こういった動力を伝達するギヤは、その歯のかみ合い具合はすごく繊細で、
入ってるケース(ロワケース)やギヤの加工具合で0.1mmとか誤差が出るのですが
それを組み付けるとき、「シム」というすごく薄いワッシャを、ベアリングやギヤの間に
入れて、ギヤの歯の噛み具合が設定どおりになるように調整します。
このシムは、BF90Aなら0.10mm、0.15mm、0.30mm、0.50mmとかありまして、
それぞれ1枚から数枚組み合わせて数箇所に入れて、調整します。
少し、例を出すと・・・・・かなり極端に表現していますが・・・・
ピニオンギヤに対して、ベベルギヤが上にずれたり、下にずれたり、
歯同士の当たる面積が減る→耐久力が落ちる。
と、なりまして・・・・そのうちギヤが破壊される可能性が大です。
「シム調整」と言うのですが・・・船外機の修理でもっとも大変な部分だと
思います。
ここは、絶対にプロの「サービスマン」に任かせましょう。
さて、今回のドッグクラッチですが、仕組みがわかりましたでしょうか?
わかれば、シフト時に「ガリガリ」言うのも、「エンジンの回転を落としてから、
シフト操作しましょう(バーハンモデル、リモコン2レバーモデル)」と言われるのも
納得できると思います。
あと、単純な仕組みなだけに、高馬力船外機になると、クラッチを入れたり、抜いたり
するときに、トルクが掛かり過ぎて「抜けへん」「入らへん」が起こりそうですが、
賢い船外機は、クラッチがドッキングする瞬間だけプラグのスパークを
間引いたりしてアシストするようにプログラムされています。
また、とあるメーカーではプロペラの中のゴムブッシュの硬さの違うものが
あるそうで、クラッチのドッキング時のショックを吸収することで
ドッキングし易く考えているものもあるとか、聞いたことがあります。
(違う理由も含まれているかも知れませんが・・・)
なお、ドッグクラッチ、寿命の長~い長~い消耗部品?です。
この寿命をもっと長くするには、ギヤオイルを必ずメーカー指定の周期で
交換することです。
ホンダ船外機の場合は、BF5A~BF225Aの場合、「6ヶ月又は100時間の早い方」
でのギヤオイルの交換を指定しています。
ちなみにBF2Dは、「6ヶ月又は50時間の早い方」です。(ドッグクラッチではないですが)
宜しくお願いします。
話は変わりますが、本日は、HONDAの新型の・・・作業着を・・・・
初めて着ました。
「サロペット」型と言うのでしょうか?
「ツナギ」型より購入価格は高いのですが・・・
すごく動きやすく、使いやすいです。Uさん!
「これ、めっちゃええわぁ~!」
ちょっとのことで、うれしい今日でした・・・・





























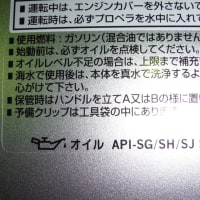

一例だけ出しておきますと、とあるメーカーさんの50馬力の船外機のクラッチ交換の場合シム調整無しの部品交換は3時間、シム調整込みの場合は4.5時間となっております。
この時間工数に、お取引のあるマリンショップの時間工賃を掛けると、
基本の工賃がわかります。あと部品代がプラスになります。
ロアギヤケース分解には、必ずギヤオイルの交換が追加になります。
また、基本工数には塩噛みなどのネジが外れない、折れたなどのトラブルは入っていませんので、不測のトラブルがあると、割り増しになります。(長期ノーメンテの場合、トラブル発生率は高いです。普段からのメンテナンスをお勧めします)
上記に、持込修理でなく、出張修理なら交通費が加わると思います。
Kさんのエンジンはクラッチにトラブルがあるのですか?
少し心配ですね?ギヤオイルを抜いて、オイルの状態である程度診断できる場合があります。
宜しくお願いします。
シフトショックについてご教示お願い致します。
BF150A 2レバーハンドルで2ステーションです。
ギヤチェンジ時のシフトショックが大きか感じます。
2007年製です。
アワメーターでおそらく.600時間位です。宜しくお願い致します。
実際に見てみないと判らないと前置きした上で・・・・・・
シフトがつながるときにショックが大きい場合、メーカーが
設定しているエンジン回転数より高い回転でクラッチが
つながっている場合が多いです。
2レバーの場合、スロットルケーブルの長さの調整が甘いとアイドル時の回転が高くなる場合が考えられますので、
一度、リモコンケーブルの長さが適正であるか確認を
お勧めします。
スロットルケーブルを確認しましたが、目一杯戻ってます。
ギアを変えるときに機械的にスイッチがありますが、スイッチの故障でのシフトショックは、あり得ますでしょうか?
ご教示お願い致します。
ケーブルが戻っているかも確認必要ですが、シフトが入るときのエンジン回転数が適正かどうかで判断します。
ケーブルが戻っていても他の原因でシフトインのときの回転が高い場合は、ショックが大きくなります。
2次エアの吸い込み、スロットルボディーのベースアイドルの調整不足なども原因になる場合があります。
「ギアを変える時の機械的スイッチ」とは、なにのことを
言われていますでしょうか?
ニュートラルスイッチのことなら、シフトIN/OUTのショックにはほとんど関係ないと思います。