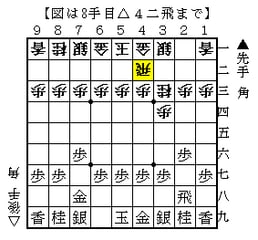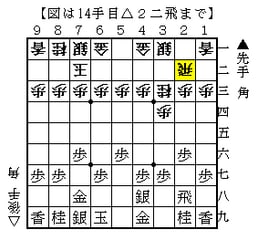まだ、H20度の将棋年鑑の棋譜並べ(データベース化)をしていないので、今日は、ゆっくり棋譜並べでもしようと思います。
プロの棋譜は難しいので、理解は出来ないと思いますが、楽しみながら、棋譜並べをしようと思います。
===== 2008/11/24 17:50 追記 =====
竜王戦の1組を10局を入力していました。
羽生さんが後手で中座飛車を指しているのは、少し意外な感じがしました。
トッププロは、自分の棋風を持っているイメージが残りました。
勝つとは何か・・・? 考えさせられます。
トッププロの将棋を見ていると、将棋の本質は何なのか?
何だか、戦法うんぬんではなく、将棋の本質を常に考えているイメージがあります。
私には理解できない領域のような感じがしました。
数学で言えば、数学の抽象理論を考えて、ただ、それを実装しているイメージがあります。 それに、似ている感じでした。
なんだか、不思議な感覚です。
プロの棋譜は難しいので、理解は出来ないと思いますが、楽しみながら、棋譜並べをしようと思います。
===== 2008/11/24 17:50 追記 =====
竜王戦の1組を10局を入力していました。
羽生さんが後手で中座飛車を指しているのは、少し意外な感じがしました。
トッププロは、自分の棋風を持っているイメージが残りました。
勝つとは何か・・・? 考えさせられます。
トッププロの将棋を見ていると、将棋の本質は何なのか?
何だか、戦法うんぬんではなく、将棋の本質を常に考えているイメージがあります。
私には理解できない領域のような感じがしました。
数学で言えば、数学の抽象理論を考えて、ただ、それを実装しているイメージがあります。 それに、似ている感じでした。
なんだか、不思議な感覚です。