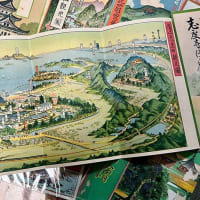今日の西日本新聞は1面を含む計4面に昨日の「地域と語ろう隊」懇談会の
内容が記載されていた。また、マンション計画を打ち出していた建設会社が、
地域の意見を取り入れ計画変更に応じる姿勢を見せた旨も掲載され、改めて新
聞の力を実感している。
現在のようなメディアや情報伝達手段が発達した時代でもこうなのだから、
吉田初三郎が活躍した時代の新聞の影響力は今以上だったかもしれない。そう
考えると、初三郎自らが残した6冊・3千近くの新聞記事スクラップは、その
まま当時の初三郎の影響力を表していると考えるべきだろう。
西日本新聞の前身、福岡日日新聞は全国紙である朝日、毎日に継ぐ3回も
長期新聞連載を初三郎に依頼している。時期的には国立公園法が成立し、各地
で国立公園候補地への名乗りが上がった時代に集中しているが、当時、鉄道省
国際観光局の委嘱絵師でもあった初三郎は、論客としても引く手あまただった。
以前も記したが、中でも「国立公園として九州の価値」という21回にわた
って連載された九州全土の観光開発・産業開発への視点は、70余年を経た今
だからこそ読むべきものである。同時代には他にも鳥瞰図や観光案内を手がけ
るものは多かったのだが、その元祖である初三郎が他の亜流作家と決定的に違
ったのは、歴史・文化・通俗を含めた豊かな教養のもとに現地に残る伝説や逸
話を上手く鳥瞰図やポスター、表紙画などのデザインへ昇華し、さらにその地
に眠る観光資源を掘りおこす、見抜く目線を持っていたからに他ならない。
今、私も含めて観光用の絵地図やマップを描く際、イラストレーターや作家
さんがどれくらい郷土のことを理解して描いているであろう。普通のイラスト
レーターであれば、市が発行する観光案内などを参考に現地へも赴かずに描く
方も多い。写真資料などは初三郎当時とは比較できないほど豊富になっている
ので、それでも描けるかもしれない。
しかし、実際に現地を訪れ、その土地が持つ独自の空気や匂いなど五感全て
で感じることは大切である。表現者=画家と職業作家の違いがそこにあると、
私は考えている。その土地の古老や知識人に会い、実際に旅館や神社などを尋
ね、足で歩いて踏査取材し作品を描き続けた初三郎は、はたして職業作家だと
言い切れるのか?
確かに仕事として作品を描いたが、多くの作品が今も観る人の興味を引きつ
けるのは、作品のベースにあるのが精神性・知識・教養であるからこそ。その
土地の郷土史家など研究者をも虜にしてしまう初三郎鳥瞰図には、画家・芸術
家の魂が込められている。
表面的な画法や色彩の使い方ばかりにとらわれ、印刷技術による大量生産品
だからと、画家としての価値を見いだせない人にこそ、初三郎が残した日記や
新聞スクラップ等の諸資料をみてほしい。友禅絵師を経て洋画家をめざした初
三郎は日本画の技法で鳥瞰図などを描きながらも、正式に日本画を学んでいな
い。逆に友禅染めや洋画の技法を作品に取り入れ描いた鳥瞰図も多く、それら
は絹本原画を観て初めて知ることができる。
洋画家としては挫折者、日本画家としては亜流とみられた初三郎は、自身の
作品が本当に評価されるのは50年、100年と時間が経ってからであると、
自分で意識していた。だからこそ作品を高い画絹に高級な外国産顔料を多様し
後世へ残るように配慮した。また、日記にしても新聞スクラップにしても、自
分の記録を誰かが見る前提でまとめられている。自分が存在した証を、後世の
誰かが活用してくれてこそ、初三郎が報われるように思う。
誰が見ても、初三郎は「オンリーワン」の「美の国日本」を描き続けた画家
であり、彼の功績を鳥瞰図という一分野としてではなく、観光学、都市科学、
環境学、情報科学など学問の諸分野で研究が進むことを願う。慶應義塾大の初
三郎を取り上げた情報環境の研究はとても興味深い。
今日の写真は、吉田初三郎作「網走市」観光案内板(昭和24年)。
戦前から昭和30年代にかけて、初三郎はこのような全国各地の観光案内板の
制作も手がけた。現物は風化し現存しないであろうが、写真などがもっと
見つかるといいのだが…。
内容が記載されていた。また、マンション計画を打ち出していた建設会社が、
地域の意見を取り入れ計画変更に応じる姿勢を見せた旨も掲載され、改めて新
聞の力を実感している。
現在のようなメディアや情報伝達手段が発達した時代でもこうなのだから、
吉田初三郎が活躍した時代の新聞の影響力は今以上だったかもしれない。そう
考えると、初三郎自らが残した6冊・3千近くの新聞記事スクラップは、その
まま当時の初三郎の影響力を表していると考えるべきだろう。
西日本新聞の前身、福岡日日新聞は全国紙である朝日、毎日に継ぐ3回も
長期新聞連載を初三郎に依頼している。時期的には国立公園法が成立し、各地
で国立公園候補地への名乗りが上がった時代に集中しているが、当時、鉄道省
国際観光局の委嘱絵師でもあった初三郎は、論客としても引く手あまただった。
以前も記したが、中でも「国立公園として九州の価値」という21回にわた
って連載された九州全土の観光開発・産業開発への視点は、70余年を経た今
だからこそ読むべきものである。同時代には他にも鳥瞰図や観光案内を手がけ
るものは多かったのだが、その元祖である初三郎が他の亜流作家と決定的に違
ったのは、歴史・文化・通俗を含めた豊かな教養のもとに現地に残る伝説や逸
話を上手く鳥瞰図やポスター、表紙画などのデザインへ昇華し、さらにその地
に眠る観光資源を掘りおこす、見抜く目線を持っていたからに他ならない。
今、私も含めて観光用の絵地図やマップを描く際、イラストレーターや作家
さんがどれくらい郷土のことを理解して描いているであろう。普通のイラスト
レーターであれば、市が発行する観光案内などを参考に現地へも赴かずに描く
方も多い。写真資料などは初三郎当時とは比較できないほど豊富になっている
ので、それでも描けるかもしれない。
しかし、実際に現地を訪れ、その土地が持つ独自の空気や匂いなど五感全て
で感じることは大切である。表現者=画家と職業作家の違いがそこにあると、
私は考えている。その土地の古老や知識人に会い、実際に旅館や神社などを尋
ね、足で歩いて踏査取材し作品を描き続けた初三郎は、はたして職業作家だと
言い切れるのか?
確かに仕事として作品を描いたが、多くの作品が今も観る人の興味を引きつ
けるのは、作品のベースにあるのが精神性・知識・教養であるからこそ。その
土地の郷土史家など研究者をも虜にしてしまう初三郎鳥瞰図には、画家・芸術
家の魂が込められている。
表面的な画法や色彩の使い方ばかりにとらわれ、印刷技術による大量生産品
だからと、画家としての価値を見いだせない人にこそ、初三郎が残した日記や
新聞スクラップ等の諸資料をみてほしい。友禅絵師を経て洋画家をめざした初
三郎は日本画の技法で鳥瞰図などを描きながらも、正式に日本画を学んでいな
い。逆に友禅染めや洋画の技法を作品に取り入れ描いた鳥瞰図も多く、それら
は絹本原画を観て初めて知ることができる。
洋画家としては挫折者、日本画家としては亜流とみられた初三郎は、自身の
作品が本当に評価されるのは50年、100年と時間が経ってからであると、
自分で意識していた。だからこそ作品を高い画絹に高級な外国産顔料を多様し
後世へ残るように配慮した。また、日記にしても新聞スクラップにしても、自
分の記録を誰かが見る前提でまとめられている。自分が存在した証を、後世の
誰かが活用してくれてこそ、初三郎が報われるように思う。
誰が見ても、初三郎は「オンリーワン」の「美の国日本」を描き続けた画家
であり、彼の功績を鳥瞰図という一分野としてではなく、観光学、都市科学、
環境学、情報科学など学問の諸分野で研究が進むことを願う。慶應義塾大の初
三郎を取り上げた情報環境の研究はとても興味深い。
今日の写真は、吉田初三郎作「網走市」観光案内板(昭和24年)。
戦前から昭和30年代にかけて、初三郎はこのような全国各地の観光案内板の
制作も手がけた。現物は風化し現存しないであろうが、写真などがもっと
見つかるといいのだが…。