《『書道全集 中国篇』を通読して 要約篇その4中国4》
4中国4 東晋
凡例に記してあるように、本巻は、東晋のはじめからその滅亡に至るまで(317-420)の104年間の書蹟を収めている。この巻では、二王の書蹟を中心として取り扱い、併せて石刻を収めている。
中国書道史4 神田喜一郎
まず、神田喜一郎は、東晋の王朝について次のように説明している。
東晋の王朝は、南渡の喪乱にあたって江南地方に移住した門閥貴族によって支持され、その政治上の枢要な地位は、ほとんど彼らによって独占された形であった。元帝のときの王導をはじめとして、桓温、謝安など名族出身の丞相が相ついで権柄を握り、内治、外交ともに治績があげられていった。彼らは北方の旧領土の回復を念願したが、実現しなかった。しかし江南土着の豪族を懐柔し、この地方の経済力を背景として、新しい佳麗な文化を発展させた。
江南に再建された東晋の王朝政権を掌握した門閥貴族の中で、とりわけ名門とよばれたものに琅邪の王氏がある。中国の書道の歴史の上において、書がもっとも発達したのは東晋であると考えてよいと神田はみているが、その東晋の書道においてもっとも偉大な貢献をなしたのは、この琅邪の王氏の一族である。
ところで、今日一般におこなわれている楷書、行書、草書の三つの書体は、三国西晋のころから普通に用いられるようになり、篆書や隷書は特殊な場合にのみ用いられるにすぎなかった。東晋の初めになってから、江南に移住した貴族の間において、この普及された三つの書体が、さらに芸術的な美しさにみがかれていった。彼らの間にとりかわされた尺牘には、行書や草書または行草をあわせた書体によって、「飄として浮雲のごとく、矯として驚龍のごとし」と批評されたような美しい書がしたためられた。また時に著名な詩や文章を新しい楷書の体に清書して、その清絶さを称讃することもおこなわれた。
このように、楷、行、草の書芸術としての美しさが完成の域に到達した。この偉大な事業をなしとげた天才こそ、古来書聖と仰がれる王羲之その人であった。ここにおいて中国の書は一時期を画し、こののち中国の書体は一つの美の標準をもつことになった。
さて、その王羲之は琅邪の名族王氏の出身で、南渡のときの功臣王導の従子にあたる。あざなは逸少といい、かつて右軍将軍という官についたことがあるので、王右軍と称された。その生卒年月については、いろいろ異説があるが、西晋の懐帝の永嘉元年(307)に生まれ、東晋の哀帝の興寧3年(365)、59歳で没したというのがほぼ正確に近いものと、神田は考えている。
王羲之は45歳のときに、右軍将軍、会稽の内史となり、任地におもむいた。この会稽というところは、春秋時代の越の古都で、今の浙江省の紹興市にあたり、美しい山水の風景にめぐまれた土地である。
彼はここに4年間、在任し、永和11年(355)に官を辞した。その後もこの地で優遊自適の生活を送り、その一生涯を終えた。
さて、王羲之は伝説によると、八分、隷、行、草書、飛白など各体の書をよくし、とりわけ隷書(すなわち楷書)をよくし、古今第一と称ばれていたといわれるが、今日彼の書蹟として伝えられているものは、すべて楷、行、草の三体に限られている。この点について、神田は次のように推測している。この頃、この三体の書がまだ十分成熟していなかったのを、王羲之が初めてこれを芸術的に立派な書体にまで完成することに心血をそそいで努力したからであって、その他の書体は実際あまり書かなかったのであろうというのである。ともあれ、現に彼の書蹟として伝えられているものも、すべてこの三体に限られている。
次にその代表的な作品をとりあげてみよう。
まず楷書で書かれたものとしては、
1.「楽毅論」(図1-5)
2.「東方朔画賛」(図6, 7)
3.「黄庭経」(図8, 9)
がある。この中でも「楽毅論」は王羲之の正書の第一等のものとして、古来もっとも著名な法帖である。これはすでに梁王朝のときに模本がつくられて、人々の間に珍重され、また臨書されている。中国のみならず、日本の正倉院に尊蔵される光明皇后の「楽毅論」(9巻図42, 43)も、古く日本に伝えられた模本によって臨書された。このことから考えても、この法帖がいかに名蹟として重んぜられていたかがよくわかる。
そして行書には、とくに名高いものとして、
4.「蘭亭序」(図12-27)
5.「集王聖教序」(8巻図50-57)
がある。「蘭亭序」は永和九年(353)王羲之が47歳のとき、3月3日の佳節に、当時、会稽の内史をしていた彼が同地方の名所である蘭亭に、名士および一族など41人を招いて、みそぎをおこない、曲水に杯を浮かべて、宴遊の雅会を催したとき、おのおのが作った詩をあつめて一巻としその巻首に王羲之みずから毫を揮うてかいた序文である。これは王羲之の会心の作であったといわれるものである。
しかし、その原本は唐の太宗の時まで伝えられていたが、太宗が崩御するとともに、その昭陵に殉葬されて、この世からすがたを消してしまったといわれている。したがって、現在「蘭亭序」として伝わっているものは、唐代において、臨模したり搨模したりしたものである。それには欧陽詢、虞世南、褚遂良の臨模したといわれるものや、搨書人の趙模、馮承素(ふうしょうそ)などによって搨模されたものなどが伝えられている(図12-23)。そしてその伝本の種類によって書風の異なったものが幾通りもあり、「蘭亭序」は王羲之の書としては必ずしも信用できないところがある。しかし、その成立した由来が風雅であるために、昔から王羲之の書として特に賞美されている。
宋代以後になると、各種の伝本にもとづいて石に刻された無数の拓本が流布するようになったが、そういう拓本の中でも定武本(図18, 19)と神龍半印本(図26, 27)はもっとも伝来も古く、代表的なものとして知られている。
一方、「集王聖教序」というのは、唐の高宗の咸亨3年(672)に僧懐仁が勅令を奉じて
宮中に秘蔵された王羲之の多くの筆蹟の中から文字をよせあつめて、聖教序の原文をあたかも王羲之が書いたかのようにしたてて、それを碑に刻したものである。その原碑は今日なお残存していて、王羲之の行書をうかがうには、「蘭亭序」よりも字数が多く、拠り所にした原蹟にもよいものがあったと考えられており、かえって信頼するに足る貴重な資料とされている。
さて、草書には名高いものとして、「十七帖」(図46-57)がある。これは王羲之の尺牘29通ばかりをあつめて一巻とした法帖である。
その「十七帖」と名づけられているのは、最初にかかげられた尺牘が十七日云々という文句ではじまるのにもとづいている。もとよりその真蹟は今日すでに佚して伝わらない。ただ唐代の初め官立の学問所の弘文館における学生の書を学ぶ手本として搨模されたものにもとづいて後になって模刻した拓本が残っていて、ほぼその原蹟の面目を想像しうる。
この法帖に用いられている書体は単に草書といっても、今日の草書とは異なり、いわゆる独草体とよばれる種類のものである。つまり、一字一字がおちついて単独に書かれ、時には二字ほど続けて書くこともあるが、後に唐代になって発達した張旭(8巻図98, 99)とか懐素(9巻[ママ]図72-75)のような連綿体の草書とは性質が別のものである。
その他、南唐李氏の刻本に擬せられている「澄清堂帖」(図58-67)は、内容も比較的精選されており、刻法も良好であり、王書の鑑賞には欠いてはならないものである。
以上が、王羲之の書蹟として一般にもてはやされてきた主要なものである。しかし、これらはいずれも肉筆そのままのものではなく、転々と模写され翻刻されたりしていくうちに、原蹟の精彩を失って、かなり感じのかわったものになっている。
ところが、日本には幸いなことに、古くから王羲之の真蹟の搨模本が伝わっていて、それによって以上のものでは知られなかった王羲之の真面目をうかがうことができる。
すなわち、王書の至宝とされている次の二帖がそれである。
1.「喪乱帖」(図28-31)
2.「孔侍中帖」(図32, 33)
これは唐代あるいはそれを遡る六朝時代に王羲之の肉筆から精密な方法をもちいて搨模してつくられたものである。だから王の真蹟にもっとも近いものと考えてよく、現在、日本に伝来したものには、これほど立派なものは一つとして見当らない。
ただ、「奉橘帖」(図34,35)とか、乾隆帝の内府に秘蔵されて、三希堂法帖に刻された「快雪時晴帖」(図36)や、のちになって日本に舶載された「遊目帖」(図39-41)などのたぐいがあるくらいである。
また明代の集帖の真賞斎帖に刻された「袁生帖」(図72)、「姨母帖」(図73)、「初月帖」(図74)や、余清斎帖に刻された「思想帖」(図77)、「遅汝帖」(図78, 79)なども直接筆蹟から模刻したものであるといわれる。しかし、神田によれば、これらはやはり「喪乱帖」と「孔侍中帖」には劣っているという。つまり現在ではこの二帖こそ王書の無上の神品と称してよいとする。
さて、王羲之の完成した楷、行、草三体の書はもとより彼が名族の出身であるだけに、そのすがたはいかにも貴族的で、高い香気をはなち、典雅端正である。その上、王羲之の性格から発した縹緲たる仙気とでもいうようなものが揺曳していて、それまでの書とは全く異なった一種の風格がそなわっていると神田はみている。これがその当時はいうまでもなく、さらに後世にいたるまで久しく書法の典型として、ほとんど絶対といってよいほどの権威を維持してきたのは当然であるとする。
ところで王羲之には7人の男子があった。これら7人の中で末子の王献之がもっともすぐれていたことは六朝時代から定評のあったところである。現に『淳化閣帖』を見ても、巻6, 7, 8の王羲之についで、巻9, 10と2巻にわたって編纂されている。
その王献之はあざなを子敬といい、東晋の康帝の建元2年(344)に生まれ、没年については孝武帝の太元11年(386)と太元13年(388)の両説がある。
その書はすでに在世のころから著名であったらしく、『晋書』によれば、桓玄が王羲之と王献之の書を1巻として、座右において愛玩していたという。また南朝宋につかえた虞龢の「論書表」にも「晋末の二王、英と称す」とあり、王献之を父羲之と併称して二王とよんでいる。
王献之の現在伝えられている書蹟も、やはり父羲之と同じく、楷、行、草の三体に限られている。楷書としては、「洛神賦」(図90, 91)がある。これは魏の曹植の名文として知られた洛水の女神のことを賦した文章を書いたものである。
草書の代表的なものとしては、
「中秋帖」(図96)
「地黄湯帖」(図92, 93)
「鴨頭丸帖」(図97)
がある。「中秋帖」は王羲之の「快雪時晴帖」(図36)および王珣「伯遠帖」(図106)とともに乾隆帝の秘蔵した3つの希宝の1つで、あわせて「三希堂法帖」に刻されているので知られている。
「地黄湯帖」と「鴨頭丸帖」はともに『淳化閣帖』に刻されて名を知られているが、「地黄湯帖」はその搨模本が伝存し、「鴨頭丸帖」には明のとき呉廷が原蹟と称せられるものにもとづいて「余清斎帖」に模刻したものがある。
王献之は父王羲之の衣鉢をよく伝えたが、その書風は概して父よりも自由で、その上妍媚なところに特色を発揮しているが、一面においては父の書に見るような骨力に欠けるという憾みがあった。しかしその書風は父よりもさらに広く南朝貴族の間に流伝し、宋の羊欣
、謝霊運をはじめとして、その影響を受けたものは少なくない。
琅邪の王氏の一族は、王羲之、王献之父子をのぞいたほかの人々も、たいていは書をよくしたといわれる。王導は魏の鐘繇と衛瓘から出て行草をよくし、晋の南渡のとき鐘繇の「宣示表」をふところにしのばせて戦禍を逃れたといわれるほどの書の愛好家であった。その子の中では王洽(図104)が特にすぐれており、かつて王羲之が、「洽の書は自分に劣らない」といって称揚したそうだ。
最後に神田は「東晋の石刻」について言及している。西晋においては、石刻の残存するものはきわめて乏しかったが、東晋になると、立碑の禁令はさらに徹底したとみえて、石刻の見るべきものはほとんど絶無といってよいくらいである。だから東晋においては、石刻としてはただわずかに2、3のものが知られているにすぎない。
その一つが「爨宝子(さんぼうし)碑」(図110, 111)である。これは太亨4年=義熙元年(405)に、雲南地方の爨宝子の墓地に立てられた記念碑である。彼が生来の美徳を備え弱冠にして建寧太守となり、しかもわずか25歳で世を去ったことを悲しみをこめて伝えている。隷書から楷書に移行する過渡期のもっとも代表的な書とされる。ともかく王羲之がかの流麗な書風を完成したのちにおいても、雲南の辺境では、なおこうした一時代古い西晋風の、しかも田舎じみた書が行われていたと、日比野丈夫は付言している(日比野丈夫、図版解説、199頁~200頁参照のこと)。
ともあれ、この「爨宝子碑」は、宋の大明2年(458)に建てられた「爨龍顔碑」(5巻図4-13)とともに、二爨の碑とよばれて北碑を愛する人たちにも喜ばれているものである。この碑は、文化の中心からはるかに離れた雲南地方に伝わったものであり、建碑の年代は東晋の終わりに近い頃のものであるが、辺鄙な地方においてつくられたためか、二王の書法の影響は全く認められず、漢隷の八分の技法を誇張したような、きわめて素樸なすがたをなしていると神田は解説している。
神田は東晋の中国書道史について、次のような結語を記している。中国の書法は王羲之、献之父子の出現によって一変することになった。この二人の天才的な技能とめざましい努力によって、はじめて楷、行、草の三体が完成の域に達し、独立した書芸術としての地位を確立した。
このように芸術作品としてすぐれた書が現われるとともに、その題材の上においても、例えば王羲之が夏侯玄の「楽毅論」や夏侯湛の「東方朔画賛」をかき、王献之が曹植の「洛神賦」をかいているように、文学または歴史に関する文章をとりあげることによって、新生面を開いている。
また日常往復の尺牘にも洒脱な草書芸術の新境地を展開して、論評をこのんだ当時の士人の間に賞玩に供した。そしてそれによってますます書の芸術性がみがかれていった。こうして書芸術の鑑賞法が次第に高まっていくにつれて、書道の本質を理論的に探求したり、書品の優劣上下を品第したりする傾向がさかんになってきたことは、中国の書道史の上において看過することのできない大きな現象であると神田は捉えている。
やがて梁代になると、袁昻の「古今書評」とか庾肩吾の「書品」のような書に関する専門の評論書が著わされて、書が詩文とあいならんで、立派な一個の芸術として重んぜられるようになってくる。こうした情勢をつくりだす基盤を築いた二王の功績は偉大であったと神田は理解している(神田、1頁~11頁、199頁)。
王羲之とその周囲 外山軍治
前述したように、王羲之の家は琅邪の王氏といって、山東臨沂の名家であった。この一族が声望をえたのは東晋に入ってからのことで、それは王導が建康において司馬睿を擁し、江南土着の豪族の勢力を結集し、晋室再興の大事業をなさしめたことによる。
王羲之の父の王曠は、この王導の従弟にあたる。『晋書』の王羲之伝にはその冒頭に「王羲之あざなは逸少、司徒導の従子なり」といっている。
前述したように、王羲之の生年については、その没年とともに諸説あって一定しない。この生没年について、外山は詳しく解説している。
1.その享年については、主として『晋書』列伝の59歳説が信じられているようである。「右軍集」の題衛夫人筆陣図後の最後に、「時に年五十有三、永和十四年四月十三日書」とあるから、これによって逆算すると、恵帝の光熙元年丙寅(306)に生まれ、哀帝の興寧2年甲子(364)に没したことになる。しかし永和という年号は12年で終わり、永和14年という年はない。これは偽託であることが明らかで、したがってこの説は信ずるに足りないと外山はみなす。
2,次に羊欣の「筆陣図」に、「羲之三十三歳にして蘭亭叙を書す」といっている。これによって推定すると、元帝の太興4年辛巳(321)に生まれたことになる。ところがこれを信ずると、王羲之列伝の記事と符合しない点が生ずる。すなわち、列伝には、王羲之が13歳で周顗(しゅうぎ)に謁したという記載があるが、その周顗は太興4年の翌永昌元年(322)に没しているから、王羲之はまだ生後1年になるかならないかで、周顗に謁したことになるわけである。銭大昕の『疑年録』に、太興4年辛巳(321)に生まれ、太元4年己卯(379)に没した、としているのはこの羊欣の「筆陣図」によったものであるが、上記のような理由で直ちにこれに従うことはできない。
羊欣は宋の人で、王献之に書法をならった人であるから、もっとも正しい記録を残すはずの人である。しかし王羲之と周顗との関係は『世説新語』汰侈篇にもみえていて、全然無視してかかることもできないので、この点が落着しない限り、この説には従い難いとする。
3.唐の張懐瓘の『書断』には、王羲之は升平5年(361)に卒したと書いている。宋の黄伯思の『東観余論』の「跋瘞鶴銘後」の条には、『書断』の説を採り、『晋書』列伝の59歳説から推して、晋恵帝太安2年癸亥(303)に生まれ、穆帝升平5年辛酉(361)に没したとしている。
4.この説について、魯一同の『右軍年譜』は次のようにいう。右軍集に桓公以江州還台帖があるが、桓温が江陵から入朝したのは興寧2年(364)7月のことであり、その鎮を姑孰に移したのは興寧3年2月である。
ここにおいて固く内録を譲り、揚州を遙領したが、この事実を還台といったもので、升平以前にはかつて還台のことはなかったのである。
したがって右軍集の桓公以江州還台帖は、興寧3年2月以後の筆であり、王羲之は升平5年以後、少なくとも4年、すなわち興寧3年まで生存したことが明らかであると魯一同はいう。
魯一同はさらに次のようにいっている。
郗曇は升平5年に卒したが、『晋書』の郗愔伝には、愔は曇が卒してから、ますます処世の意なく、郡(会稽郡)にあって優遊し、姉の夫王羲之、高士許詢と心を棲まし穀を絶ち、黄老の術を修めたことを載せており、また『世説新語』には右軍が王敬仁(名は脩)、許玄度(名は詢)とよく交わったこと、この両人が王羲之よりもさきに没したことが知られることなどを指摘し、これらのことを綜合すると、王羲之は郗曇と同年の升平5年に没したとは考えられない、といっている。
この魯同一の批判について、外山は大体当っているとみなしている。なお、王敬仁は永和12年5月13日、王羲之が「東方朔画賛」(図6, 7)を写し与えたという人物で、『書断』によると、升平元年(357)、24歳で没したとなっている。
また『右軍年譜』によると、「十七帖」の中に「足下今年政(まさ)に七十なるか。(中略)吾、年耳順に垂んとす」という言葉がある(図48, 49)
これは王羲之から周益州(名は撫)におくった書と考えられているが、周撫は蜀に鎮すること20年で、興寧3年(365)6月に卒した人である。この書に、年耳順に垂んとすといっているから、そのとき王羲之はまさに59歳であったわけである。
それで王羲之の卒もまた興寧3年の後に至ることをえない、という推定を下している。59歳は『晋書』王羲之伝の説とも一致する。この点について魯同一は力をえたものであろうとし、この魯同一の説が現在のところ、もっとも妥当な説のように思うと、外山は考えている(神田もこの説である、3頁参照のこと)。
王羲之が興寧3年(365)に没したとして逆算すると、永嘉元年(307)、司馬睿が建康に鎮した年に生まれたことになるわけである。
5.このほか、姜亮夫の「歴代人物年里碑伝綜表」によると、太安2年(303)に生まれ、太元4年(379)に没したとしている。ただ、そうすると77歳まで生存したことになるが、その論拠を知ることができないと外山は否定している。
以上の王羲之生没年の諸説を整理すると、次のようになる。
1.「王羲之題衛夫人筆陣図後」
光熙元年(306)~興寧2年(364) 59歳
2.羊欣の「筆陣図」→銭大昕の「疑年録」
太興4年(321)~太元4年(379) 59歳
3.張懐瓘の「書断」→黄伯思の「東観余論」
太安2年(303)~升平5年(361) 59歳
4.魯一同の「右軍年譜」
永嘉元年(307)~興寧3年(365) 59歳
5.姜亮夫の「歴代人物年里碑伝綜表」
太安2年(303)~太元4年(379) 77歳
次に外山は王羲之が薫陶を受けた人物について考察している。王羲之は幼にして父に死別し、母兄の訓育をうけたという。王羲之が永和11年(355)3月、会稽内史を辞するときにかいた「祭墓文」に「羲之不天、夙に閔凶に遭い、過庭の訓を蒙らず、母兄に鞠育せられ、漸く庶幾するを得たり」といっている。
ところが、この母兄については『晋書』その他にも記すところがない。この点について、外山は姚鼐の「愔抱軒法帖題跋」が興味ある考えを出しているとして、詳述している。
同書の王廙の妻の条と兄霊柩垂至帖の条とにおいて、王羲之の兄として王籍之という人物を姚鼐は想定した。
叛乱をおこした王敦の敗死後、この乱に関係した王彬(おうひん)と兄の子の安成太守王籍之は罪に問われ、王籍之の方は建安(福建省)に徙されてそこで没した。謫徙の人であるから帰葬することができなかったので、隔絶すること30年、つまり王羲之51歳になってはじめて、乞うてその兄の柩を返葬することができたと姚鼐は考えた。
王羲之の帖に、「慈蔭幽絶して、卅年に垂んとす」(「建安帖」、図85)とか、「慈顔幽翳して、三十年に垂んとす」とあるのは、このことを指すものと姚鼐はみなした。
この姚鼐の説に対して、外山は次のように批評している。王籍之は『晋書』王彬伝によると、彬の兄の子となっている。王彬の兄といえば、王羲之の父の王曠か、叔父の王廙(図108)などのことである。何故、何某の子と明確に書いていないのか、この間の事情はわからないとしながらも、この王籍之を王羲之の兄にもってくるのはよい着想であると外山はいう。ただ、姚鼐は王羲之の没年を興寧3年(365)ではなく、升平5年(361)としている点はなお検討を要するし、王籍之だけは許されないで、建安(福建省)に徙され、そこで死んだというのは、姚鼐の考えであり、臆測に過ぎる嫌いもないではないと外山はコメントしている。
この点、「建安帖」(図85)の図版解説をした中田勇次郎の批評も紹介しておこう。この「建安帖」は王羲之の兄の霊柩と見てよいようであり、王羲之が30年前に死別した兄の霊柩が長らく建安の方にあったのが、今度こちらの方へうつされたことを報知した手紙ということになると、中田も解している。この兄というのが、姚鼐の「法帖題跋」の説では、王籍之をさすが、「琅邪臨沂王氏譜」では王籍之は彬の兄の子となっていて、王羲之の実兄ではない。そこで姚鼐の説は一説として参考にとどめておくと中田は断っている(中田、図版解説、189頁~190頁参照のこと)。
話を元に戻そう。少年時代の王羲之を庇護した人としては、宰相周顗、叔父の王廙、父と従兄弟の間柄にある王導、王敦らがあった。そのうち、王廙は、衛夫人とともに王羲之の書の上にもっとも大きな影響を与えた人として考えられている。王羲之は永嘉元年に生まれたという説に従うと、その時、すでに16歳になっていたから、十分その影響をうけることができたはずである。王導、王敦からも一族のホープとして大いにその将来が期待されたらしい。
ところで、王羲之はそのうち郗鑒の女を娶った。名は璿(せん)といった。郗鑒は高平金郷(山東省)の人であった。
『世説新語』雅量篇には、この婿えらびの経緯を記していて、それが有名な話になっている。京口(江蘇省鎮江)におった郗太傅(郗鑒)が門生を遣わして王丞相(王導)に書をおくり、女婿を求めた。丞相は郗の信君(使者)に語げ、東廂に往って任意にこれを選べ、といった。門生が帰って郗に報告していうことには、王家の諸郎はみなりっぱであるが、婿さがしにきていると聞いてみな堅くなっていた。ただ一人だけ東床上に坦腹して臥し平気にしているのがいたと。郗公がいうには、これこそもとめる婿がねだ、といって、たずねてみるとこれが王羲之であった。そこで女を嫁入らせた、と。
その注に引いた王氏譜によると、郗鑒の女、名は璿(せん)といい、王羲之との間に七男と一女とをもうけた。そして王羲之はまたその末子王献之のために郗曇(夫人の弟)の女を娶ったので、王、郗両家はのちに重縁になった。
王羲之の官歴について、外山は述べている。その第一歩は秘書郎からはじまった。そして咸和9年(334)、28歳のとき、征西将軍庾亮の請によってその軍府の参軍となり、武昌に赴いた。庾亮は元帝の中興の業をたすけ、蘇峻の乱のとき、征西将軍となって長江上流の鎮撫にあたった人である。
王羲之が章草をもって庾亮に答えたのをみた亮の弟の庾翼が、深く歎服して、書をおくって、次のようにいった。
「吾、昔伯英(張芝)の章草十紙を有したが、過江顚狽、ついに乃ち亡失せり、常に好迹の永えに絶えたるを歎きしところ、忽ち足下が家兄に答えたる書をみたるに、煥として神明のごとく、頓みに旧観に還る」と。
兄の庾亮も草、行を善くしたと伝えられるが、書名は庾翼の方が高く、隷、行を善くし、若い時分には王羲之と比肩したといわれる。のち王羲之の名が高くなってからも、庾翼はこれに服さなかったが、王羲之が庾亮に与えた書をみてはじめて王羲之に服したと伝えられる。
書人としての王羲之の輪郭が次第にはっきりしてきた時期、および王羲之の政治上の意見が次第に明確になってくる時期は、おそらく庾翼がこの書を送った頃であったと外山は推測している。
咸康4年(338)、王導が丞相となり、郗鑒が太尉、庾亮が司空となった。この頃、王羲之は王導からたびたび建康政府に入れといわれたが辞退したという。これは後年殷浩に報じた書にみえている。殷浩は会稽王昱がその相談役にした人物で揚州刺史であった。王羲之はこの殷浩に嘱望されて輔軍将軍に推された。このときに答えたのが、この殷浩に報ずる書である(魯一同によれば、永和2年(346)に書かれた)。
そこには、もとより廟廊の志のないことをいい、「兒娶り女嫁してより、すなわち向子平の志を懐き、しばしば親知とこれを言うこと一日にあらざるなり」といっている。
子供たちがそれぞれ成人した上は、官界を去って悠々自適の生活に入りたいというのがその素志であるという。王羲之は天師道(五斗米道)に熱心であったというから、自然に遊び、服食養生の道を楽しみたいというのが本心であったと思うが、それだけの理由で建康政府に入ることを望まなかったとは外山には思われないという。
その理由として、王羲之は中央政府に入ることは望まないが、地方官として外に出ることならば嫌うところではないと、殷浩に報ずる書で記している点を指摘している。そこには「もし駆使を蒙らば、漢隴巴蜀もみな辞せざるところである」とある。
王羲之にとっては、中央政府部内の空気に入りきれないものがあったのではないかと外山は推測している。つまり姑息な平和をたのしみ、わが身の栄達、家門の繁栄をのみ望む人々が集まり、遊惰な気分がみなぎっているような中央政府へ入る気がしなかったのではなかろうかという。
ところで『世説新語』言語篇に、王羲之が謝安とともに冶城に登って四周を眺望しながら語り合ったことが書かれている。このとき王が謝にいって曰く、
「いま四郊に壘多し、よろしく人々自效すべきに、虚談務を廃し、浮文要を妨ぐ。おそらくまさによろしきところにあらず」と。
このような王羲之のきびしい気持ちが建康政府部内の空気にあわなかったと外山はみている。
また『世説新語』には、「高爽にして風気あり、常流に類せず」とか「風骨清挙」とか王羲之を評したいろいろな言葉がある。この点からも常人とは違った気骨の持ち主であったことが知られ、このようなきびしい気持ちと、世俗を避けて隠遁したいという気持ちとが、いつも背中あわせになっていたと外山は解している。
それでも王羲之は一時建康政府に入ったが、永和7年(351)、45歳のとき、右軍将軍、会稽内史として会稽郡山陰県に赴任した。会稽郡は、土着の豪族の数も多く、食糧も豊富であり、江南第一の形勝の地であったが、王羲之はここで4年間在任する。
この地には、謝安(図109)、道士許詢、僧支遁など各界の名士も多く住んでおり、名士や土着豪族と交わりながら、会稽内史としての職責を果たした。その交友の広いことは、永和9年(353)3月3日、蘭亭に集まって、禊を行った人々の顔ぶれを一見しただけで十分であろう。
王羲之が病と称して会稽内史を辞したのは永和11年(355)49歳である。ただ王羲之の会稽住まいは退官後の方がむしろ長く、その死に至るまでの10年間があった。これは王羲之がその素志の通り余生を楽しんだ期間である。山水の遊びを尽くし、釣糸をたれてたのしみ、また道士許邁とともに服食を修め、東南の諸郡を徧遊した。山陰の一道士に「道徳経」を写して与え、好鵝と交換したというのもこの間のことである。しかし彼は全く世を捨てたわけではなく、政治の動き、ことに北方政策に関心を抱いていた。例えば、永和12年(356)、桓温による洛陽の回復、琅邪に存在する王氏の祖先の墳墓の修復の報に歓喜し(図66, 67)、そしてその後幾ばくもなく前燕の進出のために、旧京、先墓の再び失陥したことを嘆き悲しんだ(図28-31)。
ここで、356年、桓温による洛陽の回復のことを伝える書をみておこう。「王略帖」(澄清堂帖、紫藤花館本)によれば、
「知虞師春。桓公以至洛。即摧破羌賊。賊重命。想必禽之。王略始及舊都。使人悲慨深。此公威略實著。自當求之於古。真可以戦。使人嘆息。」(後略)
この帖は、「桓温が洛陽に至って羌賊すなわち姚襄を撃破した。賊は命を重んじている。きっとそれを捕虜にしていることとおもう。今までしばしば北伐して奪還しようとした旧都洛陽が、はじめてわが王朝の領土となり、まことに感慨無量である。この桓公の威略はまことにすばらしいもので、このような人物は現代にはなく、当然、古に求むべきである。まことに恐るべきことで、感嘆させられる」という。
先述したように、桓温が姚襄を破って伊水に至ったのは永和12年(356)8月のことである。東晋の人士がひとしく抱いていた北土回復、旧都奪還の念願がひしひしと文字の上にあらわれ、その奪還した時の喜びが目の当たりに浮かぶようである。
この点に関して、中田勇次郎は次のようにコメントしている。
「手紙というものが単に文学作品でなく、現実の社会に根をおろした切実なものであることがこれによってよく示されているとともに、当時第一の書人であった王羲之によってこのような史実がありありと伝えられていることはまことに興味のふかいことである。」
(中田、図説解説「図66, 67 王略帖」、181頁~182頁参照のこと)。
話は元に戻し、外山軍治は王羲之について北方回復を忘れえない点では、もっとも北方豪族の気概をもった人物として理解している。そして同時に会稽で優遊するにふさわしい文雅の士でもあったと捉えている。東晋特有の優美な中に、気骨を感じさせる人物であった。
王羲之とその子供たちと比較して、王羲之は、骨っぽく、そして毅然たるものをもっていたと外山はみている。王羲之の子たちはその数も多いが、何となく線が細く、家庭生活においても、少しく乱れがみられた。例えば、第七子の献之にしても、はじめ母の弟にあたる郗曇の女と結婚したが、のち離婚して新安公主に尚した。離婚は東晋貴族の間ではさして珍しくなかったようだ。
しかし、献之が後年病気になったとき、離婚した前妻のたたりであろうか、と恐ろしがったりしているのは少々だらしないと外山は評している。
また、次男の凝之は会稽内史となり、会稽に住んだが、父ゆずりの五斗米道にこり過ぎて、孫恩が会稽に攻めよせたときに防備を施さず、命をおとすという情けない人物であった。その妻の謝道蘊は、才女のほまれが高かったが、凝之は、この夫人からも馬鹿にせられていたことが『世説新語 賢媛篇』に見えているそうだ。ともあれ、王羲之の子供たちは家範を得たがそれぞれ特徴があり、凝之はその韻をえ、操之はその体をえ、徽之はその勢をえ、渙之はその貌をえ、献之はその源をえたといわれる(外山、12頁~19頁、203頁)。
二王法帖の系譜 中田勇次郎
中国の伝統的書芸術の最高権威と称せられているだけあって、王羲之、王献之父子の伝存する書蹟は、夥しい数にのぼっている。そこで中田勇次郎はその数多くの法帖について、その書蹟の研究資料としての大体の系統を立てることを試みている。とりわけ、唐宋二王朝における法帖の資料の主要なものを検討している。
唐王朝にはかなり多数の二王の書が、王室を中心にして閲玩し、収蔵されていたようだが、その内容が実際どんなものであったかについては、記録の上には詳しくあらわれていない。幸いに、褚遂良の撰んだ「晋右軍王羲之書目」および張彦遠の録した「二王書語」(「右軍書記」と「大令書語」よりなる)の2つの文献によって、その一部をうかがうことができる。以下、中田の解説をまとめてみよう。
1.褚遂良の「晋右軍王羲之書目」
これは唐太宗の貞観年間(627-649)に褚遂良が禁中において王羲之の書蹟を臨写したときに録出しておいた法帖目録である。一に貞観目録ともよばれている。
内容は正書は5巻14帖あり、「楽毅論」(図1-5)を第一とし、「黄庭経」(図8, 9)、「東方朔画賛」(図6, 7)がこれにつぎ、魏の鐘繇の書を臨したといわれる「墓田丙舎帖」(3巻図114)、「宣示表」(3巻図107-110)などを列挙している。
行書は58巻266帖あり、「蘭亭序」(図12-27)を第一とし、第二以下には多く尺牘を載録している。この中には有名な「孔侍中帖」(図32, 33)が含まれているし、「奉橘帖」(図34,35)、「快雪時晴帖」(図36)などもあり、「官奴帖」(図82-84)にあたるものもあり、「右軍書記」の中に見えるものもかなり多い。
撰者の褚遂良は王書の真偽の鑑定についてはもっとも精審であり、その識別には一つとして舛誤はなかったと称せられているほどである。だからこの書目も彼の観賞した王書の中から真蹟として疑いのない名品を録出したものと考えられる。したがって、この書目こそは王書の研究の第一位に置かれるべき貴重な資料であると中田はみている。
ただ、この書目においては各法帖のはじめの数句が書きとどめられているだけで、全文が明らかではないので、正確にはその内容がわからないのが遺憾であるという。しかし概して日付と名の書き出しではじまる尺牘の形式のものが多く、単に王書の断簡零墨といったようなものではなく、書式の完備し、もちろん書も立派な法帖が選択されていると中田は想像している。
2.「二王書録」
二王の法帖を集録したもので、「法書要録」に収録され、「右軍書記」と「大令書語」よりなる。「右軍書記」は張彦遠が好事者に王羲之の草書を知らせるために集録したもので、「貞観書目」の正行体に対して、草書のものをこれによってうかがうことができる。内容は主として相聞の尺牘であって、巻頭に有名な「十七帖」を掲げており、集録した法帖の合計が465帖あると巻末に記しているが現存のものはその数に達しない。
しかし古い時代における一人の人物の尺牘がこのように多数伝わっていることは珍しいことで、ことにこの書記では法帖の全文がそのまま釈されていて、王羲之の日常生活が生きた通俗の文字資料として目の当たりに展開され、彼の人となりを各方面から観察できることは、王書の研究にとっても、この上もないありがたいことであると中田はみている。
一方、王献之の「大令書語」は帖数もきわめて少ない。ただ、梁の鑑定家の徐僧権や唐代における二王の収蔵家の鐘紹京などの押署のあるものがあることは注目を要するという。
3.「十七帖」
「右軍書記」の巻頭にかかげて、唐太宗の蒐集品の中でももっとも著名なものであるといっている。貞観年間の秘府における草書帖の装背の式どおり、長さ1丈2尺とし、107行、942字すべて23帖よりなり、貞観2字の小印と、開元2字の小印があり、跋尾に当時の大臣の名が列記されていたという。
「十七帖」の名称は巻首に「十七日」という字があるのでそれを取って名づけられたものである。現在伝わっている「十七帖」は唐模本によったとおもわれる刻本で、帖数は29帖ある。
「右軍書記」の記載より6帖多く、のちに勅字と「付直弘文館臣解无畏勒充館本、臣褚遂良挍無失、僧権」の21字とがある(挿51)。すなわち直弘文館の解无畏に模勒させて、館に出入する子弟の書の手本に充てたものであり、褚遂良の校定を経ている。僧権は梁の徐僧権が合縫にしるした押署であり、梁王室から伝来した証左と考えられる。
ところで、この後記はまず勅押が唐玄宗の「鶺領頌」(8巻図92、93)にあるのと同筆といってよいくらい似ているので、その下にかかれた跋と僧権2字の位置なども、ことさらに配置したようで、刻本にするときに作為したような気味があると中田はみている。ただ、「右軍書記」より多い6帖の中には、『淳化閣帖』に刻入されているものがあり、いきおい閣帖より以前にあったものと考えるのがよく、またこの6帖の書風も内容も他の帖と決して不調和ではないので、「右軍書記」の本よりのち、『淳化閣帖』より以前においてこのような形式のものが作られていたと中田は推定している。
この帖はその手紙の文章も趣旨ももっともよく王羲之という人物を知るに役立つところがあり、しかもその書は彼の草書の典型として第一位におくべきであろうと中田は位置づけている。
4.「伝藤原行成臨王右軍尺牘」
日本に伝来した王羲之の法帖に「喪乱帖」(図28-31)と「孔侍中帖」(図32, 33)があることは衆知のとおりである。「孔侍中帖」は「貞観書目」に収録されているもので、中国においてもその由緒の正しいものであることが考えられる。
この二帖のほかに、やはり「東大寺献物帳」(9巻図48, 49)に搨模本によって臨書したとおもわれるものに伝藤原行成筆の「王右軍尺牘十二帖」がある。「秋萩歌巻」(12巻図30, 31)の巻尾にあるもので、王の尺牘を行成風の筆致で臨書したものである。
5.「宝真斎法書賛所載唐模王右軍尺牘」
宋の岳珂の「宝真斎法書賛巻七」に載せられている王羲之の尺牘で、10帖あったというが、今、刻本で見られるのは「遣言帖」「河南帖」の2帖だけである。
次に宋代における二王の法帖を見てみよう。この時代の法帖はすべて刻本の形式で伝えられているので、原本を模勒して鐫刻し、さらにそれを拓本にとるという3段の工程を経ている。だから、唐代およびそれ以前における搨模本のような華潤さに乏しいという難点がある。その代表的なものは『淳化閣帖』である。閣帖が刻されてからのちも、多くの刻本や集帖があらわれたが、今日伝えられているのは閣帖のほかに「大観帖」「絳帖」「汝帖」「鼎帖」「宝晋斎法帖」「二王帖」などで、大半は亡佚してしまっている。ここでは二王の法帖をこれらの諸本の中から拾っている。
6.『淳化閣帖』
宋の太宗の淳化3年(992)、翰林侍書王著に命じて内府の名蹟を模勒上石せしめた法帖である。全10巻あり、その中、巻6, 7, 8に王羲之、巻9, 10には王献之を収めている。
内容から見ると、「貞観書目」や「二王書録」などに載せられているものもあるが、前代の
名蹟を精選したものではなく、これ以外の著名なすぐれた筆蹟がのちの増補した刻本にあらわれてくる。
そのうえ全帖にわたって偽蹟とおもわれるものが多数その中に交じっている。これについては宋の米芾と黄伯思が一々の法帖の真偽を鑑別した。さらに清朝になって、王澍が「淳化秘閣法帖考正」をあらわし、諸方面からの考証を詳細にした。
7.「絳帖」
北宋のとき潘師旦が『淳化閣帖』を増損して翻刻した集帖である。夙に欧陽脩の「集古録跋尾」に見えているもので、現存する翻刻本ではもっとも古いものである。前後各10巻よりなり、前巻の第6, 7、後巻の第3, 4, 5, 6が王羲之、前巻の第8, 9, 10、後巻の第7が王献之となっている。後帖の第3, 4, 5, 6は東京の書道博物館に所蔵されている。
8.「汝帖」
大観3年(1109)8月、河南汝州の郡守王宷が刻した集帖である。すべて12巻あり、第6巻に二王の尺牘と「洛神賦」が刻されている。本来この法帖は『淳化閣帖』や「秘閣続帖」から雑取してつくられたものであるが、現存する拓本は文字が漫滅してほとんど鑑賞には堪えないという。
王羲之は「想無悪帖」以下10帖を収めている。すべて閣帖に載っていないもので、「姨母帖」と「初月帖」は「万歳通天進帖」の中にある名品であるが、その他の帖とともに「秘閣続帖」から取ったものと中田は推測している。「姨母帖」を除く他はすべて今の「澄清堂帖」に見られるのも注意すべき点であるという。王献之の尺牘は「授衣帖」「東家帖」「月終帖」の3種で、いずれも閣帖に刻されているものである。
9.「鼎帖」
紹興11年(1141)、鼎州(湖南)の郡守張斛が『淳化閣帖』のほかに「元祐秘閣続帖」、「潭帖」「絳帖」「汝帖」などを合せて刻したといわれる集帖である。現在その残本第10から第15に至る6帖を存し、東京書道博物館に所蔵されている。
10.「宝晋斎法帖」
南宋の宝祐年間(1253-1258)、無為郡(安徽)の通判をしていた曹之格が刻した集帖である。すべて10巻よりなり、巻1から巻6までは王羲之、巻7, 8は王献之を収めている。宝晋斎は米芾が晋の謝安の「八月五日帖」および王羲之の「王略帖」を手に入れてその書斎に名づけた号といわれる。米芾が無為の太守となったときに、この地で晋帖を刻したことがある。曹之格は宝晋斎のあとをついで米芾の刻帖に基づいて晋帖を主とした集帖10巻を編して刻し、「宝晋斎法帖」と名づけたものと中田は推測している。
この帖は米の臨書という説もあるが、中田はこの説を否定し、やはり原蹟または原帖からの模刻であろうとする。この中には「王略帖」をはじめとして、「貞観書目」に見える「期小女帖」など、めずらしい法帖がある。米の臨本は「戯鴻堂帖」巻14に7帖刻されているが、この帖に比べると米の筆癖が出ていて、「宝晋斎法帖」が米臨でないことがよくわかると中田は強調している。
11.「二王帖」
南宋の許開が清江(湖北)の太守をしていたときに刻した集帖である。上中下3巻よりなり、王羲之は上巻に56帖、中巻に50帖を収め、王献之は下巻に44帖を刻している。『淳化閣帖』のほか、「宝晋斎旧帖」「絳帖」などから集めて刻したもので、各帖にその依った帖名をことわっており、のちに「二王帖目録評釈」がついているので、研究に役立つところが多いという。
「石脾帖」「愛鵞帖」「筆精帖」などは他の集帖ではあまり多くは見られぬ珍しいものである。中でも「筆精帖」は「澄清堂帖」(戯鴻堂帖本)にも載ってはいるが、もと米芾の「書史」にも見え、貞観の印記のあったという名蹟である。
12.「澄清堂帖」
王羲之の尺牘を集刻した法帖の残巻で、現在では5巻まで知られている。すぐれた法帖によって精刻していると思われる点においては類例のないよい集帖であるという。大体の形式は第1巻から3巻までは『淳化閣帖』に相当し、第4, 5巻は閣帖以外の法帖を収めていると中田はみている。また閣帖の部分は米芾と黄伯思が偽蹟と鑑定したものをほとんどそのまま刪除したかのようになっていることから、米、黄二氏より以後にその意見を参照して編せられたと中田は推測している。
以上、唐宋二王朝における法帖の資料の主要なものを中田は検討している。二王の法帖の資料の中で、もっとも基礎的なものは「喪乱帖」「孔侍中帖」のように由緒の正しい搨模本を第一とすべきであるが、文献の上からは褚遂良の「貞観書目」における正行体の書と、「二王書語」における草書がもっとも大切であると中田はいう。
特に「貞観書目」に載っているものはもっとも信頼すべきものであろうとする。ただ草書のものは数もおびただしく、あるいは南朝貴族が学書したものや戯習したものが交っているかもしれないので、各帖について諸方面からの考究が必要であるという。
ところで宋代になると模刻の形式をとるために真蹟の精彩が失われる。『淳化閣帖』には五代の宮廷人の倣書したという偽蹟が混入しているといわれているが、米芾や黄伯思があらわれて精審な鑑別をおこなうころから、鑑賞が更に進んできて、閣帖に取り入れられなかったすぐれた法帖が見出されて、官私の集帖に模刻されていった。
けれども刻本のものは結局肉筆には及ばないという嫌いはあった。しかしながら、正しい真蹟によって、これらの不足を補って原蹟を想定することにより、これらの刻本のものにもその書の美しさを還元し、こうして伝えられた資料をよりよく生かしてゆくべきであろうと中田は主張している。
最後に、これらの資料を書風の上から簡単に大別すると、
1.「姨母帖」(図73)のような一見未熟とおもわれるものを一類とする
2.「喪乱帖」(図28-31)、「孔侍中帖」(図32, 33)にほぼ合致するもの、またはそれに近いものを一類とする
3.「十七帖」(図46-57)に似ているものを一類とする
4.「初月帖」(図74, 75)「遠近清和帖」(図64)のような「十七帖」よりもいくらか放逸な草書のものを一類とする。
5.「思想帖」(図77)や「裹鮓帖」(挿44)のような技巧的で趣味のゆたかなものを一類とすることでできるのではないかという
そしてこの書風の区分は「羲之」二字の署名の結体用筆によってある程度まで見分けることができるとする。このように書風を類別することによって、上記の諸資料をまた各法帖について識別することができると中田は考えている。
二王の法帖の系統を立てるには、このほか尺牘の書式、材料、用語、内容にもられた史実、ひいては二王の人物にも及ばねばならないと残された課題を付記している(中田、20頁~36頁)。
押縫について 内藤乾吉
内藤乾吉は本巻で担当した王羲之の書の解説の中で、しばしば押縫のことに言及しているが、解説の中で十分説明することができなかったので、ここに補説を記している。
唐以前の書道の研究には必須の文献である「法書要録」を読んだ人には押縫については説明するまでもないことだが、近来は書道の専門家でも、こうした書物を敬遠し読まないで議論する人があるので、ここで内藤は説明しておきたいという。
押縫というのは、縫すなわち絹や紙のつぎめに押署する、すなわち署名をすることである。その目的は、今日、証文が2枚以上になると割印をするのと同じで、前紙と後紙が連続して分離すべきでないことを証し、差しかえなどの詐欺行為を防ぐにある。したがって押縫は本来は公私の法律文書に施された方法である。
内藤は西本願寺の大谷探検隊が西域からもたらした唐代の官文書を調査したが、それら官文書には数多くの押縫の例が見られ、古法帖の押縫研究に参考になることがわかったという。
その官文書は主として唐の開元、天宝(713-756)頃までの敦煌県、西州都督府、高昌県で処理・保管された官文書であった。そこには、一つの文書の用紙が2枚以上にわたって、貼りつぎの必要のある場合、および当時の官文書の整理保管の方法として、多数の文書を今日のように綴り込みにせずして、次々に貼りついで巻子として保存した。その貼りつぎをする場合には、みなその文書処理の責任ある官吏が押縫をしている。
その押縫は紙背にしている場合が多く、原則としては紙の下端から約5, 6糎のところにしている。押縫の署名は、姓を書かずに名の一字を書き、2字名の場合もその中の1字だけを書いている。このような唐代の官文書の押縫の方法はおそらく六朝時代から継承されたものであろうという。
また日本の正倉院の古文書にも同様の押縫があり、これは中国の方法を継承しているものであるという。法帖に押縫があるのは、何通かの帖を巻子に仕立てて整理保存する場合に、官文書の整理保存の方法が応用されたものであるとみている。王羲之その他の法帖に見える押縫は「法書要録」などに見える記録によると、みな法帖の整理を命ぜられた官吏のものである。つまりそれらの官吏が法帖を整理する場合に、官文書の整理保存法に準じた方法を取ったものとみなしている。
ところで「法書要録」には、六朝時代および唐代に朝廷が古法帖を蒐集整理したことに関する記録が載っている。その記録に見える法帖整理担当者の名には、梁では徐僧権、唐懐充、姚懐珍、満騫、朱异、沈熾文、隋では江総、姚察がみえる。これらの人々は整理された巻の跋尾に署名したことは勿論、その大部分の人は巻中の押縫をもしたであろうと内藤は推測している。
そして内藤は王羲之と王献之の法帖にみえる押縫の例を挙げている。例えば、「蘭亭序」の「僧」(挿49, 50)、「喪乱帖」(図28-31)の「僧権」(図28)と「珍」(図30)、「奉橘帖」(図34, 35)の「僧権」「懐充」「察」、「万歳通天進帖」中の王献之の「廿九日帖」(図102)の「僧権」である。
そして内藤は「喪乱帖」(図28-31)の図版解説においても、この点について詳述している。
御物の「喪乱帖」は、前田家の「孔侍中帖」(図32, 33)とともに、現存する王羲之書の摹
本中での第一級品である(実際、全集第4巻、中国4東晋の附録は、この二帖の搨模本である)。
その第1行の「之極」の右側にやや薄れて見えているのは「僧権」という字の左半である。これは梁の徐僧権の押縫をそのまま摹したものである。ここは原本では、紙縫のところで紙が破断されていたために、「僧権」の文字の左半だけが残っているという。その紙の破れ目を写した細い線が、乱の字の末筆から下へかけて認められる。そしてこの僧権の押縫は「奉橘帖」(図34,35)の中の「平安帖」(図34)に見えるものと全く同じ形をしている。
また第9行の「良不」と第10の「拝」の間にある字は、おそらく姚懐珍の押縫で「珎」の形が少し崩れたものと内藤はみている。
徐僧権も姚懐珍も梁の時に内府の法帖の整理を命ぜられ、法帖の首尾や縫に押署した人々であることは「法書要録」その他に見えている。例えば「法書要録」の「右軍書記」の中の「足下晩…」の条には、「前辺僧権、後辺珍」と記してあって、僧権と珍とが同じ帖に押縫をしている例のあったことが知れると内藤は解説している(内藤、図版解説「喪乱帖」、164頁、参照のこと)。
さて、法帖に押縫をしたのは大体に隋までで、唐の太宗が貞観中に整理させたものには、縫に貞観の印を押し、開元の時には開元の印を押した。
官文書に押縫をすることは何時まで続いたかは詳かにしないが、宋代になると押縫というものに対する認識が漸く乏しくなっているという。例えば、黄伯思の「法帖刊誤」第九王大令上に、法帖の摹刻には往々原本では行傍にある字を行中に入れている場合があることを指摘し、それらは文意の上では別に差支えのないものもあることを述べている。
その後、黄伯思は次のように述べている。引用が長くなるが、記しておく。
「蘭亭敍を読むものが、不知老之将至の傍にある僧の字を、王羲之が曽字を誤書したものと考えて、かりにそれを行中に摹入したとしたら、これは不都合である。大体、古の蘭亭敍は元来二十八行で、第十四行のところに至って行間が特に広いのは、紙のつぎめに当るからであって、知の字(不の字の誤りか)がたまたまこの行の末にあることとは無関係である。梁の舎人徐僧権がその傍に名を書いたが、当時これを押縫といった。梁の御府中の法書はおおむねこの通りである。この帖は僧字の下にその権字を失ったものである。
近世の人がこれを知らずして、僧は曽の誤りであるといい、よって曽不知老之将至と読むのは間違いである。そのことは「晋史」の王羲之の本伝および「法書要録」第十巻(右軍書記)にはみなこの敍を載せているが、ただ不知老之将至とあって曽字はないところから見てもわかる」といっている。
なお僧字を曽の誤りと見る説は蘇東坡の「書摹本蘭亭後」(東坡題跋巻四)に見えていると内藤は付言している。
「蘭亭序」の僧字が押縫であることはもはや言うまでもないことであるが、そうすると開 皇本や定武本(挿49, 50)のように僧字のある「蘭亭序」は、やはり梁の内府を通って来た本をもとにして、それを忠実に伝えているということになると、内藤は理解している(内藤、37頁~40頁)。
別刷附録 王羲之 喪乱帖 孔侍中帖
最新の画像[もっと見る]













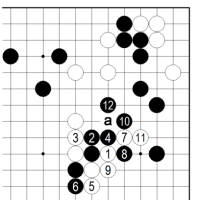






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます