
どんな練習の仕方だとしても、「習うより慣れろ」という言葉があるように効果があるのだと思います。アマチュアの場合は普段の仕事があって、楽器をさわる時間が制限されているわけですし、とにかく楽器を出来るだけ毎日さわっている時間がほんの数分だとしても、その勘を鈍らせないために重要な事でしょう。
ただ楽器を演奏するレベルを向上させたいと思った時に、その方法は短時間でより効果のある方法の方が嬉しいですし、その人なりの方法をあみ出すのも楽しい事かも知れません。
そこで今日は、私のエチュードの練習の仕方を少しだけお話しします。
私も学生の頃は、とにかく時間をかけて課題のエチュードを何回も、(所謂根性で)止まらないように練習する事を第一に練習していたように思います。曲の最初から最後までとにかく通してゆくのです。何回もつまずく所は、取り出して集中練習をしてました。このやり方も悪くはないですが、効率的かどうか?はよくわかりません。
もう少し、1曲のエチュードを今後の自分の血となり肉とするために練習する方法をある時期に変えました。私には効果があった方法なので、これから書きます。
まず、練習しようと思ったエチュードの曲全体(譜面)をよく眺めます。そこで、このエチュードは何を練習者に学ばせたいか?よく考えることです。スピッカ~トだったり、重音だったり、レガ~トだったり、音飛びだったり、曲によって求めていることが違うと思います。
その作曲者の方針を推測出来たら、それを頭に入れながら練習し始めます。
曲を最初から眺めて、ひとくくり~それは第一主題だったり、解決までの音楽の場所だったりします。~だけを暗譜するまで練習します。写真が小さいですが、例えば左側のペ~ジの4段目位までだけとにかく弾けないところが無くなるまで練習します。このエチュードで求められる技術的要求はここまでの間にほとんど網羅されているのです。
最初から最後まで通すやり方よりも、最初の部分をまずクリアにする方法の良い所は、そのエチュード全体の理解がよりすすむところです。その4段目までを暗譜する位まで練習を終えた後の音楽は、エチュードの場合はほとんど展開していかないので、同じ技術の応用です。
なので、最初の4段目まで演奏出来れば全部を演奏出来るようになるのがよりはやく感じます。最初は1ペ~ジ半もある長いエチュードだと思っていたのが、たった4段だと思う事で、気持ちが楽になるでしょう??
最初の4段目を暗譜する頃には、早く次の所にいきたいと欲求も高まるかと思います。
私は普段こうやってエチュードを練習していきます。
ただ楽器を演奏するレベルを向上させたいと思った時に、その方法は短時間でより効果のある方法の方が嬉しいですし、その人なりの方法をあみ出すのも楽しい事かも知れません。
そこで今日は、私のエチュードの練習の仕方を少しだけお話しします。
私も学生の頃は、とにかく時間をかけて課題のエチュードを何回も、(所謂根性で)止まらないように練習する事を第一に練習していたように思います。曲の最初から最後までとにかく通してゆくのです。何回もつまずく所は、取り出して集中練習をしてました。このやり方も悪くはないですが、効率的かどうか?はよくわかりません。
もう少し、1曲のエチュードを今後の自分の血となり肉とするために練習する方法をある時期に変えました。私には効果があった方法なので、これから書きます。
まず、練習しようと思ったエチュードの曲全体(譜面)をよく眺めます。そこで、このエチュードは何を練習者に学ばせたいか?よく考えることです。スピッカ~トだったり、重音だったり、レガ~トだったり、音飛びだったり、曲によって求めていることが違うと思います。
その作曲者の方針を推測出来たら、それを頭に入れながら練習し始めます。
曲を最初から眺めて、ひとくくり~それは第一主題だったり、解決までの音楽の場所だったりします。~だけを暗譜するまで練習します。写真が小さいですが、例えば左側のペ~ジの4段目位までだけとにかく弾けないところが無くなるまで練習します。このエチュードで求められる技術的要求はここまでの間にほとんど網羅されているのです。
最初から最後まで通すやり方よりも、最初の部分をまずクリアにする方法の良い所は、そのエチュード全体の理解がよりすすむところです。その4段目までを暗譜する位まで練習を終えた後の音楽は、エチュードの場合はほとんど展開していかないので、同じ技術の応用です。
なので、最初の4段目まで演奏出来れば全部を演奏出来るようになるのがよりはやく感じます。最初は1ペ~ジ半もある長いエチュードだと思っていたのが、たった4段だと思う事で、気持ちが楽になるでしょう??
最初の4段目を暗譜する頃には、早く次の所にいきたいと欲求も高まるかと思います。
私は普段こうやってエチュードを練習していきます。










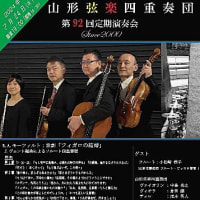















チケットも高くなりましたが……(笑)
ショパンのピアノもいいけれど、絃が寂しかったですね。
今回はシューマンの室内楽に標準を当てて聴いてきました。
ピアノトリオ+ビオラとSQメンバー(ライプチッヒSQ)+ピアノでピアノ四重奏曲を聴き比べてきました。どちらもよかったですよ。山形Qさんもそのうちおねがいしますね~~(文翔館議場ホールにピアノありますね?)
付け忘れましたが第3楽章で、チェロC線をBに落とす(Bのオクターブ重音)のとそのまま(Bのみの単音)の二通りありました。途中でチェロが変なことを始めるより演奏会ではそのままのC線でおかしくないと思います。そういえば、一週間後に上野の奏楽堂で同じ曲の演奏会チケットがあり、それも楽しみです。
ライプチッヒSQのシューマンの第2番を聴きました。リズムが大変ですね?でもシューマン特有の抑揚・アクセントとは別に第一拍目にしっかりと強拍があります。この後で1stVLNのアルツベルガーさんとVlaのバウエルさんとあの国際フォーラムでは敵視されているB館「ニコチンルーム」で一緒になり二言三言拙い英語で喋ってきましたが、バウエルさんとらびおさんは歳背格好ともほぼ同一ですね~~アルツベルガーさんは中爺さんと同年くらいと思いますが、身長は高いですね。二人ともニコチン愛好者でそれも同じですかね?特にシューマンの後ではストレスたまりますね。(笑)
ということで、第一拍目に強拍がないと曲にならない(だけどベートーベン後期SQはどうなるんだか……)ことがはっきりわかりました。
以上、LFJ(ラ・フォル・ジュルネ)2010特派員からでした。
ゴールデンウィークをお楽しみのようですね。
学生の頃~つい20年位前ですが・・・、弦楽四重奏をやる人達、聴く人達にとって、このシューマンやメンデルスゾーンなどはマイナ~な曲でした。ところがCD時代になって、録音する団体が増えてきたこともあって、主要な団体さん達のレパ~トリ~になってきたので、随分メジャ~な曲のイメージになったように思えます。ただシューマンは、ペーター版などしか譜面が出ていないので(ヘンレとかの原典版が出ればかわると思います)あまり実演に接する機会が無いので貴重な体験でしたね。
とくに第2番は、ほとんどの団体が毛嫌いするので貴重中の貴重な体験だったのでは??
最近は、強拍・弱拍の考え方が数年前と変わってきているように思えます。もちろん昔からあったのでしょうけど、前はもう少し長いフレ~ズをとって、フレ~ズ内で出来るだけ拍感が無いように演奏してましたもの・・・。
今は短いフレ~ズの取り方をして、強拍弱拍を意識して演奏する人が増えたのではと推測しています。ピリオドの方からの影響ですかね?私にもよく分かりません。
シューマンはこの秋口に演奏するので楽しみです。