
25年度決算審査のため、
財政の本を参照しながら分析しています。
参考図書をご紹介します。
(財政の入門書)
入門用にはこんな本があります。
「超入門 自治体財政はこうなっている」学陽書房。
基本的な言葉や仕組みについて、簡潔に説明しています。
2002年発行で少し古いですが良い本だと思います。

目次の初めの部分をご紹介します。
1 自治体財政の基本
1 なぜ税金を払わなければならないの
2 自治体はくにからお金をもらっているの
3 お金に色があるって本当
4 財政が硬直化するってどういうこと
5 どうすれば財政状況が良いか悪いかわかるの
など

(市町村財政の分析)
「習うより慣れろの市町村財政分析」自治体研究社2007
各自治体は財政状況について「決算カード」と言う資料を作ります。
自治体によってはホームページに掲載していませんが、
総務省のホームページには全自治体の決算カードが載っています。

この決算カードをどのように読めばよいのか、分析すればよいのか
などを解説しているのがこの本です。

参考ブログ
・財政分析の視点
・予算の分析
(監査の視点から)
関西学院大学教授で英国勅許公共財務会計士の石原俊彦氏が書かれた
「地方自治体のパブリック・ガバナンス」が勉強になります。
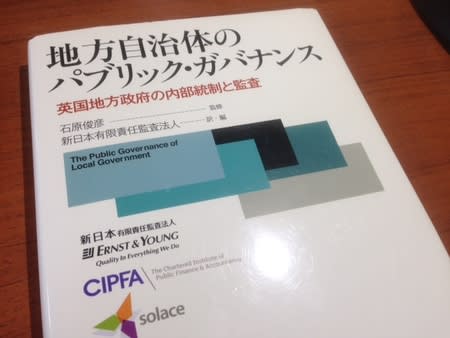
私は群馬県庁に勤務しながら、
高崎経済大学大学院の地域政策研究科で学びました。
(夜間と土曜日の昼間に授業があります)
同じように、石原教授のもとで関西方面の市役所や県職員が
働きながら大学院生として学んでおり、
今年に入って次々と現役の自治体職員から
英国勅許公共財会計士が誕生しています。

石原教授の研修を受けたときのブログはこちらです。
・センスは時代に先行する
・地方自治体のための予算編成と予算管理のすすめ方 パート1
・自治体予算等の研修報告 パート2
(財政健全化法)
いわゆる財政健全化法に関しては
「自治体財政健全化法 制度と財政再建のポイント」学陽書房2008。

法律の趣旨や、監査体制、情報開示、財政規律の確立など書かれています。
最終章では、財政健全化法と地方自治の精神との関係や、
過疎地の病院は閉じればいいのか、議会議員の役割、などにも触れています。
この法律の目的は、地方自治体の財政破綻の予防です。
財政指標により、財政の悪化を把握した場合には、
自治体の自主的な改善努力により、財政の健全化を保つことが期待されます。
健全化法では、地方公共団体(都道府県、市町村等)の財政状況を
客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するため、
4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。
●実質赤字比率
地方公共団体の「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、
その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。
●連結実質赤字比率
公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に
生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。
●実質公債費比率
地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、
その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。
●将来負担比率
地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、
その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。
(国の財政は大丈夫か?)
ここまで地方財政の健全化についておさらいしていて
ふと気になったのは国の財政。本日のメインです。
地方自治体に対して、財政健全化指標を公表するように定め、
財政の悪化に早めに気付いて対応するように求めていながら、
1000兆円を超える借金を抱えた国の財政の方は大丈夫なのか?
仮に、地方自治体に使われている財政の健全化指標を
国の財政に当てはめたら、どれくらいの評価になるのか。
自分で大まかな計算をしてみようと思いましたら、
すでに財務省自身で試算した資料が公表されていました。
実質公債費比率で比較したものです。(19年度決算データ)
こちらの資料の31ページです。

この資料の左をアップして、私が一部加工したのが次の資料です。

財政再生基準を超えると、財政再生団体となります。
現在、全国で財政再生団体なのは北海道夕張市。
この時点の資料では長野県王滝村は、
もっと悪い状況ですが、血のにじむような努力で
なんとか財政再生団体の指定は回避したようです。
さて、一番問題なのは国の財政。
財政破綻した北海道夕張市でさえ40%弱なのに、国は約80%。
実質公債費比率が25%を超えると、
サッカーなら要注意のイエローカード。警告です。
そして、35%を超えると、レッドカード。
実質的に財政破綻とみなされ
財政再生団体とされます。
この指標が財政力を的確に評価しているならば、
自治体よりも先に国の方が財政破綻してもおかしくありません。
国は夕張市のような財政再建の努力をしているでしょうか。
消費税を8%に値上げしても、財政は更に悪化しています。
自治体関係者は、本気で国の財政破綻に備えなくてはなりません。
(参考)夕張市長の講演(もと東京都から応援派遣された職員)
行政のサービスは住民にとって空気みたいな存在。
薄くなってこないと気づかない。
行政や議会は、時代に応じて柔軟に変化すべし。
夕張市へ派遣された初日に驚いた。今思うと考えが実に甘かった。
都から応援に行ったので、おそらく初日は仕事は早めに終わって、
歓迎の宴会くらいあるだろうと思っていた。
しかし、夜6時なっても夕張市の職員はだれも帰らない。
そのうちみんなベンチコートを着て、
薄手の手袋をしてパソコンを打ち始めた。
外は零下17度くらいだが、夕方5時には役所の暖房が切ってあるからだ。
東京から来た私たちは、スーツだったので寒さに震えた。
夕張市の職員は誰も帰らない中で、寒さに耐えられず夜10時に
「早退させていただきます」と先に帰らせてもらった。
(参考ブログ)
・このままでは10月末に財政破綻 自治体は対策立てよ!(2012年)
・国の財政破綻に関する市長の所見(2012年)
・公務員を受験するにあたって(2013年)
・景気がいい、悪いの次元ではない(2013年)
・国の財政 藤巻健史のプロパガンダ(2014年)
財政の本を参照しながら分析しています。
参考図書をご紹介します。
(財政の入門書)
入門用にはこんな本があります。
「超入門 自治体財政はこうなっている」学陽書房。
基本的な言葉や仕組みについて、簡潔に説明しています。
2002年発行で少し古いですが良い本だと思います。

目次の初めの部分をご紹介します。
1 自治体財政の基本
1 なぜ税金を払わなければならないの
2 自治体はくにからお金をもらっているの
3 お金に色があるって本当
4 財政が硬直化するってどういうこと
5 どうすれば財政状況が良いか悪いかわかるの
など

(市町村財政の分析)
「習うより慣れろの市町村財政分析」自治体研究社2007
各自治体は財政状況について「決算カード」と言う資料を作ります。
自治体によってはホームページに掲載していませんが、
総務省のホームページには全自治体の決算カードが載っています。

この決算カードをどのように読めばよいのか、分析すればよいのか
などを解説しているのがこの本です。

参考ブログ
・財政分析の視点
・予算の分析
(監査の視点から)
関西学院大学教授で英国勅許公共財務会計士の石原俊彦氏が書かれた
「地方自治体のパブリック・ガバナンス」が勉強になります。
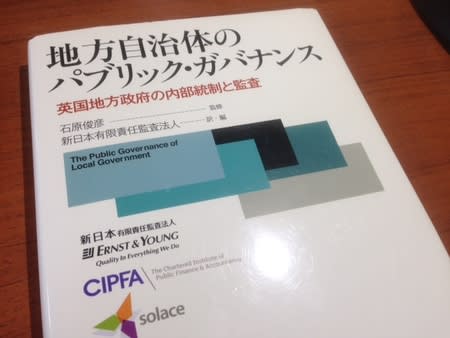
私は群馬県庁に勤務しながら、
高崎経済大学大学院の地域政策研究科で学びました。
(夜間と土曜日の昼間に授業があります)
同じように、石原教授のもとで関西方面の市役所や県職員が
働きながら大学院生として学んでおり、
今年に入って次々と現役の自治体職員から
英国勅許公共財会計士が誕生しています。

石原教授の研修を受けたときのブログはこちらです。
・センスは時代に先行する
・地方自治体のための予算編成と予算管理のすすめ方 パート1
・自治体予算等の研修報告 パート2
(財政健全化法)
いわゆる財政健全化法に関しては
「自治体財政健全化法 制度と財政再建のポイント」学陽書房2008。

法律の趣旨や、監査体制、情報開示、財政規律の確立など書かれています。
最終章では、財政健全化法と地方自治の精神との関係や、
過疎地の病院は閉じればいいのか、議会議員の役割、などにも触れています。
この法律の目的は、地方自治体の財政破綻の予防です。
財政指標により、財政の悪化を把握した場合には、
自治体の自主的な改善努力により、財政の健全化を保つことが期待されます。
健全化法では、地方公共団体(都道府県、市町村等)の財政状況を
客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するため、
4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。
●実質赤字比率
地方公共団体の「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、
その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。
●連結実質赤字比率
公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に
生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。
●実質公債費比率
地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、
その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。
●将来負担比率
地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、
その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。
(国の財政は大丈夫か?)
ここまで地方財政の健全化についておさらいしていて
ふと気になったのは国の財政。本日のメインです。
地方自治体に対して、財政健全化指標を公表するように定め、
財政の悪化に早めに気付いて対応するように求めていながら、
1000兆円を超える借金を抱えた国の財政の方は大丈夫なのか?
仮に、地方自治体に使われている財政の健全化指標を
国の財政に当てはめたら、どれくらいの評価になるのか。
自分で大まかな計算をしてみようと思いましたら、
すでに財務省自身で試算した資料が公表されていました。
実質公債費比率で比較したものです。(19年度決算データ)
こちらの資料の31ページです。

この資料の左をアップして、私が一部加工したのが次の資料です。

財政再生基準を超えると、財政再生団体となります。
現在、全国で財政再生団体なのは北海道夕張市。
この時点の資料では長野県王滝村は、
もっと悪い状況ですが、血のにじむような努力で
なんとか財政再生団体の指定は回避したようです。
さて、一番問題なのは国の財政。
財政破綻した北海道夕張市でさえ40%弱なのに、国は約80%。
実質公債費比率が25%を超えると、
サッカーなら要注意のイエローカード。警告です。
そして、35%を超えると、レッドカード。
実質的に財政破綻とみなされ
財政再生団体とされます。
この指標が財政力を的確に評価しているならば、
自治体よりも先に国の方が財政破綻してもおかしくありません。
国は夕張市のような財政再建の努力をしているでしょうか。
消費税を8%に値上げしても、財政は更に悪化しています。
自治体関係者は、本気で国の財政破綻に備えなくてはなりません。
(参考)夕張市長の講演(もと東京都から応援派遣された職員)
行政のサービスは住民にとって空気みたいな存在。
薄くなってこないと気づかない。
行政や議会は、時代に応じて柔軟に変化すべし。
夕張市へ派遣された初日に驚いた。今思うと考えが実に甘かった。
都から応援に行ったので、おそらく初日は仕事は早めに終わって、
歓迎の宴会くらいあるだろうと思っていた。
しかし、夜6時なっても夕張市の職員はだれも帰らない。
そのうちみんなベンチコートを着て、
薄手の手袋をしてパソコンを打ち始めた。
外は零下17度くらいだが、夕方5時には役所の暖房が切ってあるからだ。
東京から来た私たちは、スーツだったので寒さに震えた。
夕張市の職員は誰も帰らない中で、寒さに耐えられず夜10時に
「早退させていただきます」と先に帰らせてもらった。
(参考ブログ)
・このままでは10月末に財政破綻 自治体は対策立てよ!(2012年)
・国の財政破綻に関する市長の所見(2012年)
・公務員を受験するにあたって(2013年)
・景気がいい、悪いの次元ではない(2013年)
・国の財政 藤巻健史のプロパガンダ(2014年)

























国土と地方自治体では、税制など異なりますが、
税収力に対する借金の大きさはおよそつかめると思います。
近年の日本の国の予算は、
税収より借金による収入のほうが大きいという異常な状態が
何年も続いています。
自治体なら、とうに破綻しているレベルですが、
日銀が国債を買い支えているので、
長期国債の金利上昇さえ押さえ込まれていると理解しています。