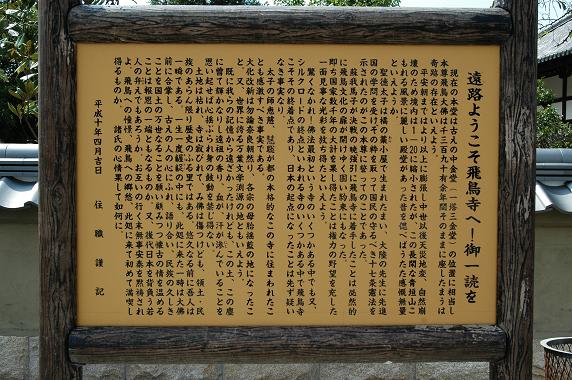9月28日~29日に「奥飛騨」周辺(乗鞍岳、上高地、飛騨高山など)の散策をしてきた。
今回はこの時の状況を・・・「奥飛騨」周辺の散策からUPしますが、第一回目として「乗鞍岳」からUP・・・
「乗鞍岳」は岐阜県と長野県の県境に位置し、多くの峰と湖沼・平原を持つ火山群の「総称」・・・最高峰の「剣ヶ峰」は3026mあり、その他も殆どが3000m級の峰となっている。
また、「乗鞍岳」は国立公園の「特別保護地域」に指定され、特別天然記念物の「雷鳥」をはじめ、珍しい高山植物(コマクサなどの)貴重な自然が多く残されている。
その他、湖沼としては山頂近くの「権現池」や「大雪渓」などでも有名な「乗鞍岳」として人気を集めている。
尚、「乗鞍岳」には東京大学・宇宙船研究所・附属「乗鞍研究所」が設置されており、「高山に於ける宇宙船観測研究」が行われていることでも知られている。
こんな高山だが、「乗鞍スカイライン」などを利用することによって、山頂近くの「畳平」まで行くことが出来る・・・しかし、「マイカー規制」があり、一般の「乗用車」では乗り入れることが出来ず、「バス」などへの「乗り換え」が義務づけられている。
「畳平」近辺は、まだ9月なのに「紅葉」が始まっており、10月末になると「冬支度」の季節に入る・・・今回は「はい松」の中の「紅葉」の様子もUPします。
その他、「乗鞍岳・畳平」周辺からの「紅葉」、「乗鞍岳最高峰・剣ヶ峰」、「権現池」、「大雪渓」、「東大・乗鞍観測所」などをUP・・・

乗鞍岳の最高峰・「3026mの剣ヶ峰」と「大雪渓」

山頂近くの「権現池」と「雪渓」・・・山の上に「東大・乗鞍観測所」

山頂近くの「権現池」

東京大学・宇宙線研究所「乗鞍観測所」の全景

乗鞍岳・山頂付近の「紅葉」①

乗鞍岳・山頂付近の「紅葉」②・・・スカイライン「はい松」の中の「紅葉」
今回はこの時の状況を・・・「奥飛騨」周辺の散策からUPしますが、第一回目として「乗鞍岳」からUP・・・
「乗鞍岳」は岐阜県と長野県の県境に位置し、多くの峰と湖沼・平原を持つ火山群の「総称」・・・最高峰の「剣ヶ峰」は3026mあり、その他も殆どが3000m級の峰となっている。
また、「乗鞍岳」は国立公園の「特別保護地域」に指定され、特別天然記念物の「雷鳥」をはじめ、珍しい高山植物(コマクサなどの)貴重な自然が多く残されている。
その他、湖沼としては山頂近くの「権現池」や「大雪渓」などでも有名な「乗鞍岳」として人気を集めている。
尚、「乗鞍岳」には東京大学・宇宙船研究所・附属「乗鞍研究所」が設置されており、「高山に於ける宇宙船観測研究」が行われていることでも知られている。
こんな高山だが、「乗鞍スカイライン」などを利用することによって、山頂近くの「畳平」まで行くことが出来る・・・しかし、「マイカー規制」があり、一般の「乗用車」では乗り入れることが出来ず、「バス」などへの「乗り換え」が義務づけられている。
「畳平」近辺は、まだ9月なのに「紅葉」が始まっており、10月末になると「冬支度」の季節に入る・・・今回は「はい松」の中の「紅葉」の様子もUPします。
その他、「乗鞍岳・畳平」周辺からの「紅葉」、「乗鞍岳最高峰・剣ヶ峰」、「権現池」、「大雪渓」、「東大・乗鞍観測所」などをUP・・・

乗鞍岳の最高峰・「3026mの剣ヶ峰」と「大雪渓」

山頂近くの「権現池」と「雪渓」・・・山の上に「東大・乗鞍観測所」

山頂近くの「権現池」

東京大学・宇宙線研究所「乗鞍観測所」の全景

乗鞍岳・山頂付近の「紅葉」①

乗鞍岳・山頂付近の「紅葉」②・・・スカイライン「はい松」の中の「紅葉」