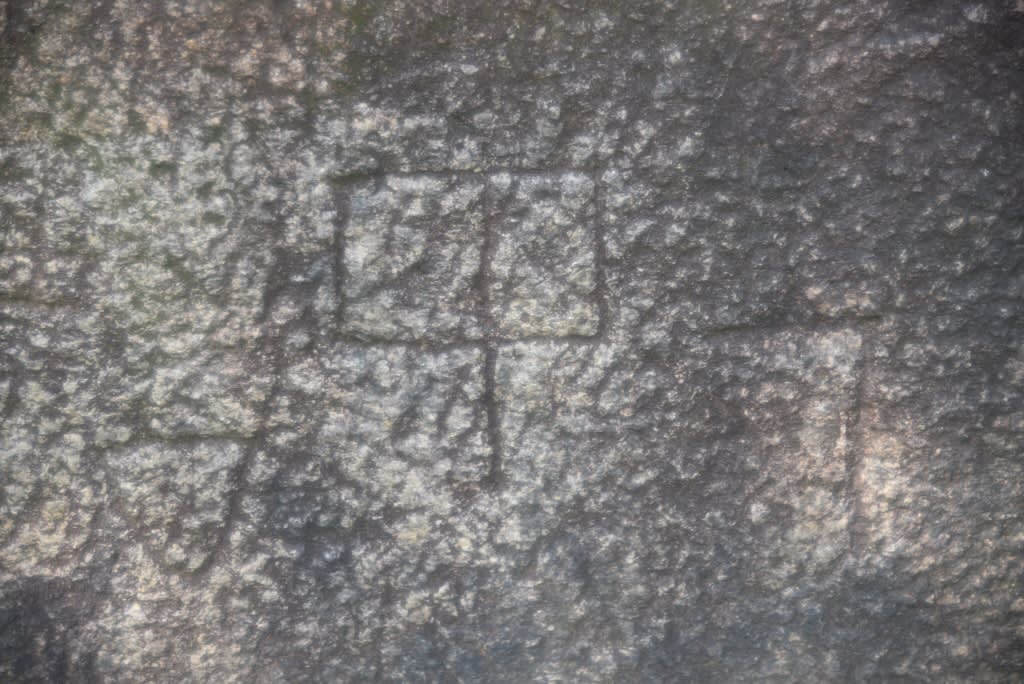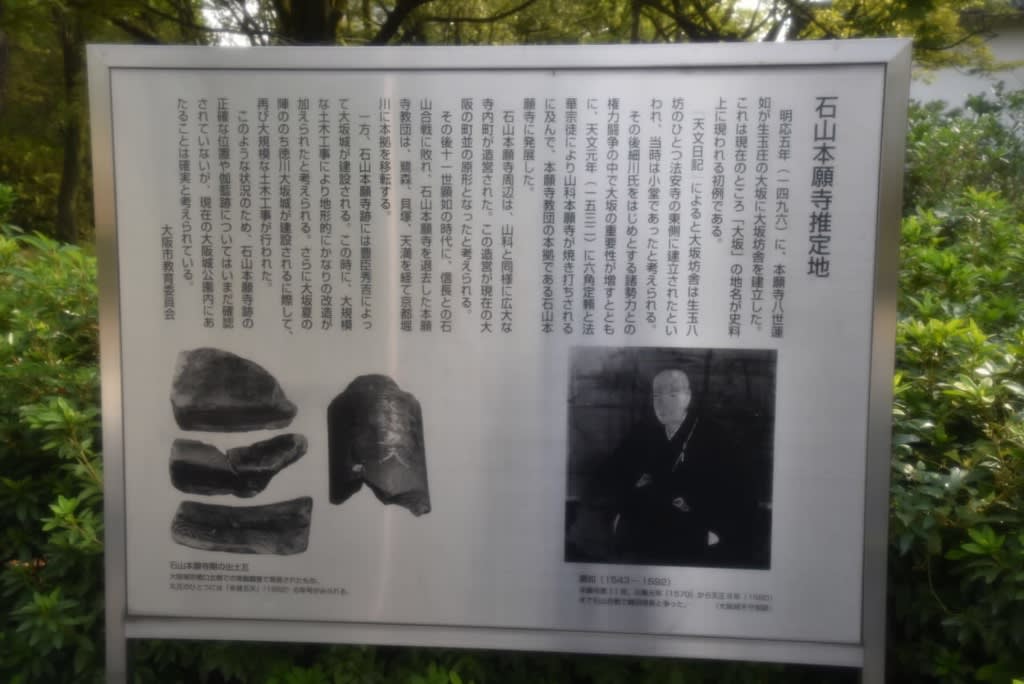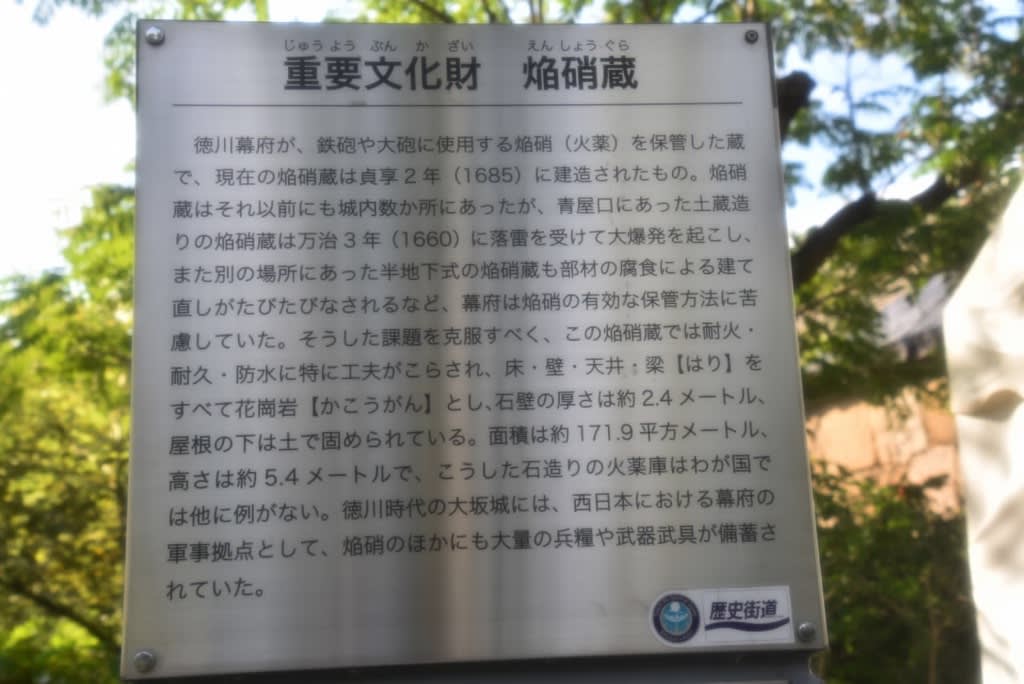昨日(11月7日) 大阪城の秋巡りに最高のお天気です。
桜、けやき、銀杏がそろそろ見頃です
午前は、玉造口から、午後は京橋口方向からが私は好きです。
午前と午後
⑴朝、JR森ノ宮駅から、大阪城玉造口へ







⑵午後、京橋口周辺から。夕陽も最高です。






チョット 御座船に乗ってみた



天守閣を見上げて



秋晴れの散策はいいですね


大阪城の外堀周辺の散歩でした。
何度も訪れていますが、その度に表情と言うか風情というか景色は違います
冷え込みもこれから、漆の木(少ないですが〜)もうすぐ真っ赤になるでしょう
2016.11.7 大阪城外堀周辺にて
桜、けやき、銀杏がそろそろ見頃です
午前は、玉造口から、午後は京橋口方向からが私は好きです。
午前と午後
⑴朝、JR森ノ宮駅から、大阪城玉造口へ







⑵午後、京橋口周辺から。夕陽も最高です。






チョット 御座船に乗ってみた



天守閣を見上げて



秋晴れの散策はいいですね


大阪城の外堀周辺の散歩でした。
何度も訪れていますが、その度に表情と言うか風情というか景色は違います
冷え込みもこれから、漆の木(少ないですが〜)もうすぐ真っ赤になるでしょう
2016.11.7 大阪城外堀周辺にて