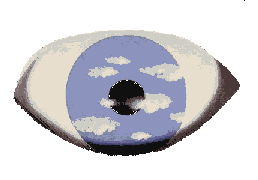おいでよ立可ちゃん・温泉編 立可の視野には、よくひきしまった満月を頂点に置いた巨大な山が、のしかかるように、圧迫感を伴って、ずどんと存在していた。月は肉眼には捕らえられぬ程の猛スピードで、太陽の光を反射し、狂った様に瞬いていた。フィルムにすれば何億コマか?何兆コマか?気の遠くなるスピードだ。脳髄から快楽物質がきゅるきゅる全身に飛び出す。 休日を利用して仲間たちと一泊二日の温泉旅行に出掛けた立可は旅館での濁水にとっぷりとつかりこんだような、けたたましいバカ共の宴会についに耐えきれなくなり、胸の片隅に突然にして、ひょっこりと吹き出してきた妙なセンチメンタルと元来の孤独癖に誘われて、こっそりと旅館を抜け出して電灯のたぐいの全くない狭い山道を歩いてみることにしたのだ。 ピンとはりつめた月下の冷たい緊張は彼の全神経を、微動だにしない一本の心の琴線に 徹底的に集中させた。立可は、宴会の俗っぽい汚濁の波が静まり返り浄化されていくのを感じ、宴会場で卑しいカタルシスを演じる友人たちと、きっぱりと、画然と、隔てられた月下の自分を再発見した。この感覚は過去にも幾度と無く味わったものだ。
立可は、逆光で真っ黒に染まった威容の山に向かい合い、静かにさくさく背を曲げて歩いていった。土を踏みしめる自分の音が静寂をさらに盛りたてていると思った。 歩きながら、次第に立可は、未だかつて経験した事のない不思議な感覚にとらわれていった。身体が背筋の下方からアイスクリームのように溶け流れてゆくようだった。その感覚を物理現象化するならば、巨大化したもう一人の自分が、山々を淋しげにひたひた歩く自分自身を、ちょうど月の位置からジッと俯瞰している感じだ。夜闇はもう一人の自分の巨大な影なのだ。そう思うと立可は“ゾッ”として、しばらく足を止め、耳をすまして眼を見開き、本当の自己の存在を五感全開にして確認せねばいられなかった。
立可は自分自身の巨大化の幻想を頭の中から振り解き、あらためてこのあまりにも日常とかけ離れた異様な状況に驚いた。彼は一瞬、眼を大きく見開き身体を硬直させ、“あっ”と一言もらした。 その円形の光の中央に揺れる枯れた雑草の間から、青白く薄い光を滲ませて輝く何物かの存在に気づいたのだ。 それは燈籠だった。しかも、その中で煌々とゆらめく微かな炎の存在をも感じたのだ。 “鬼火じゃないか?” 立可は最初、そう思った。昔、祖父の墓で見た青白い魂の輝きを思い出した。しかし、それは違った。確かにろうそくの、ゆらゆらとしたあの妙に心細い儚げな光だった。盆の落とし物?と考えるとり先に、意表をつく何かその演出的で非現実的な出現状況に立可は恐怖した。氷水を浴びせられたように顔から中心に全身の筋肉がひきつった。 しばらくジッとその燈籠を見ているうちに、立可は突然、背後に得体の知れない巨大な恐怖を感じ、弾かれたように振りむいた。鋭い風が鼻の下をスーッと通り過ぎた様に感じた。しかし、そこには、ただ虚ろな野原がブルーのセロハンを透して見たように彼の視野の底に静かに横たわっていた。彼は洋服の庇護から露出し行き場無く彷徨う自分のか弱い手の不安定な存在がたまらなく気になりはじめ、すばやく外気からポケットの中の暖かい空間にしまい込んだ。しばし頭を空白化させた感情がポケットの中で庇護され暖まっていく手と共に穏やかになっていくと、今度はやけに、はっきりと思考が活動を開始した。 “夏、誰かが捨て置いたのだろう。この情景は見事な偶然の神秘的産物に違いない。ろうそくの火は錯覚だろう” 立可は再びゆっくりと振り向き雲のカーテンにすっかり月の照明を消されて、ただの暗闇の中にひっそりと姿をのぞかせている朽ちた燈籠を見た。灯りの痕跡は全くなく、それは古びた髑髏のように破れて開いた上方の穴から立可を見返していた。やはり錯覚だった。 風が出て枯れ草を、死んだ子供がうめくように騒がせ始めた。 立可は、もう、すっかり平静を取り戻し、じっくりともう一度あたりの荒涼とした風景を観察し始めた。見れば見るほど、この冷たい青闇の情景は立可に、どこか奥底で人間の心を惑わすような不可解な印象を与えた。 狐狸の奸計か?の類いを考えに入れないわけにはいられなかった。かといって特に、この燈籠を中心に渦巻く眼前の月野原の世界には具体的な奇異は何一つ見つからないのだ。しかし、やはり、そこには何か立可の潜在的な意識野を波立たせる不可解なものが在るように思われた。肉眼では決して捕らえることの出来ぬ、その何か霊的ともいえる奇妙な信号を立可は魂の律動に変調をきたそうとする何らかの害意のように感じていた。 何者かが異形の不安という有害物を、何かの「終わり」の予告として立可の中へ注ぎ込んでいるように思われた。 “今、終わりは始まったよぅ” そんな声を内奥のどこかで、立可は聞いたような気がした。 立可は深呼吸をし、ポケット中のハイライトを取り出しマッチで点火した。マッチの赤い小さな灯りは立可の次の行動に一つの示唆を与えた。それは立可がおよそ考えもしなかった事だった。マッチの小さな灯りは立可に、こう示唆していた。 “燈籠の内部に点火せよ・・・” それは立可にとって強烈な誘惑と化して、次の瞬間、ぐわぁっと襲いかかってきた。抗う事も出来ず、立可は、紙のような枯れ草を踏みつけながら、そろそろと操られるように小さな竹製の物体に近づいていった。月は、すっかり姿を隠していた。延々と続く大蛇の胴体のような雲の群れが当分の間、地上を漆黒に染め続けるはずだった。
火は微かなシュという音と共に立可の足元に転がる燈籠を白く浮きたたせた。 立可は速やかに小さく燃え上がる炎を破れた紙の内側へ投じた。わずかな火は籠の内部に達すると同時に、ぱっと破裂したかのように、一瞬にして全体に燃え広まった。立可は目を剥いた。それは、彼の心に強大な空白と不安を生じせしめた。彼は事態を明確に把握できず、ただこの思いがけぬ火勢の発露に驚愕していた。何故か、この炎は全ての生命を焼き尽くす深遠なる神々の劫火のように思えた。 立可は、いきなり後方にはじき飛び、今や回りの枯れ草まで浸食し始めた燈籠の炎の舌を不動のまま見つめていた。熱い空気が立可を包み、ますます彼の感情を熱く高ぶらせた。火の手は、瞬く間に大きくなり、見事に風景を鮮やかな輝きに満たしていった。 それを見つめていると今度は立可の顔に不思議な安堵と充実の表情が宿ってきた。燃えてる。燃えてる。とても綺麗。頭の中が快感でジンと痺れ、自然にグッグッグッと笑い声がもれだし、うれし涙までこぼしていた。
「みんな、焼け死んじまえ」と彼はうれしそうにポツンとつぶやき猛スピードで国道に飛び出し、安全圏に去って行った。 そして、これが立可の聖なる放火の始まりだった・・・・・ |
kipple