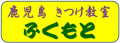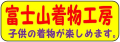6月7日(木)、「はかた伝統工芸館」で午後1時から
「きつけ塾いちき」は、いつもお世話になっている「はかた伝統工芸館」で、着付けショーを開催いたします。
今回の内容は、「京の雅と、博多の粋」と題して、博多の芸妓と京都の芸妓の着付けをご覧頂きたいと思います。
京都と博多の芸妓は、帯結びが違います。使う帯も違います。
博多と京都の芸妓の違いも、楽しみにご覧くださいませ。
工芸館の二階で行う予定です。
午後1時には開始致しますので、時間の遅れないようにお越しくださいませ。
心よりお待ち申し上げております。
なお、お問合せは、
「はかた伝統工芸館」
〒812-0026 福岡市博多区上川端町6−1(櫛田神社横) 092-409-5450 開館時間/10:00~18:00(入館は17:30まで) 
襦袢(じゅばん)は外来(ポルトガル)語。
16世紀の後半に、ローマに派遣された使節団が、帰路のインドで宣教師から贈られた下着を「ジバオ」(gibao)といい、これがジュバン(襦袢)になったわけです。
「ジバオ」(gibao)はポルトガル語で、はじめは袖なしの上半身だけの下着だったようです。ですから襦袢は造語です。
その後、下半身の裾除け(蹴出し)も出現し、二部式になってきます。上下の一部式の長襦袢の歴史はその後に現れてきます。
余聞ですが、キセル、コップ、タバコなども、ポルトガル語であることはご承知の通りです。
踊りの襦袢は二部式がいい…
それでは、舞踊の襦袢の話に移ります。
着せている衣裳方からすると、一部式の長襦袢は、かなり不便ですし、きれいに仕上げられません。
踊りの衣紋を大きく抜くと、一部式では裾が上がってしまいます。
また、体型が違うと、一部式では衿がきれいに合いません。
二部式は、上下が分かれているので、衣紋や衿に関係なく、裾の長さも合わせられるし、少々体型が違っても、衣紋と衿がきれいに合わせられます。
かなり、ふくよかな方でも、襦袢の脇の縫い目を解くことで、充分に衿合わせが出来るわけです。
動きについても二部式は自由です。
東京の松竹や、京都の衣裳店の襦袢は、例外なく二部式になっているのは、そうした理由からだと思われます。