The Atlantic Monthly on mercenary child-retreivers, mentions Japan
Posted by debito on October 17th, 2009
有道ブログである。
Hi Blog. Here are the lengths people will go to if there is no legal framework to enforce international child abductions: even hire a professional to retrieve your child. From The Atlantic Monthly November 2009, courtesy of Children’s Rights Network Japan. This is it, the big leagues.
Congratulations, left-behind spouses. You’ve hit a home run with this issue.・・・・You’ve put Japan into the international spotlight over a problem just as long-suffering as racial discrimination in Japan.I guess Chris had to get arrested before it would happen, alas.
It will probably will get the GOJ to sign the Hague. Getting us to enforce it, however, is another matter. Keep on it. Arudou Debito in Kyoto
子供の連れ戻しについて、法的枠組みがないと、こうなる。おめでとう、取り残された親御さん、日本の差別問題が国際的な脚光浴びるようになろうが、そうなるには、クリスが逮捕までされてしまった。 日本政府にハーグに締結させることになるだろう、執行するか、どうかは別にして、・・・・として、すごい記事を紹介している。
さらっと読む。
If your ex-spouse has run off and taken your children abroad, and the international legal system is failing to bring them back, what are you to do? One option is to call Gus Zamora, a former Army ranger who will, for a hefty fee, get your children back. Operating in a moral gray area beyond the reach of any clear-cut legal jurisdiction, Zamora claims to have returned 54 children to left-behind parents. Here’s the story of number 55.
倫理的にはグレーゾーン、法的には、管轄外の領域で、元軍隊のレンジャーに取り戻しをはかってみたら、という記事である。
The Atlantic Monthly on mercenary child-retreivers, mentions Japan
Posted by debito on October 17th, 2009
debito.org/?p=4761
魚拓1魚拓2魚拓3魚拓4
日本関連場所をみてみると、
A successful snatchback is only the beginning of the journey. Sometimes, the child doesn’t want to go. Early this year, Gus says, an American father agreed to pay him $70,000 to recover his 10-year-old daughter from Japan, assuring him that the girl would acquiesce. Gus went to the Philippines to prepare an escape route by boat. He then flew to Tokyo and, accompanied by the father, hustled the girl into a van as she left home. “That little girl screamed bloody murder,” Gus told me. “She was beating at the windows. Contrary to everything we’d been told, she definitely did not want to go.” After a day of unsuccessfully trying to calm the girl down, he released her. (He says he received half of his fee up front; he wasn’t paid the remainder.) Gus says he would never snatch an unwilling child―though he also describes recoveries in which a resistant child grew more willing over time.
10才の日本人の少女を連れ出そうとしたところ、金切り声をあげられて、窓はどんどん叩く、アメリカ人父親から言われたこととは違い、少女は帰りたくなんてなかったんだ、という。その後釈放してあげたそうだ。
----すさまじいケースである。
次は、日本国内のベンダさんのケースである。
」
The predicament of Walter Benda is typical. In 1995, he was living with his wife of 13 years in her home country of Japan. According to Benda, he wanted to return to the U.S. and she did not. One day, she disappeared with their two daughters. “Please forgive me for leaving you this way,” she wrote in a note she left. The Japanese police, Benda says, would not investigate what they viewed as a family matter; it took him three and a half years to find the girls. He never won visitation rights. “It took a couple of years before the courts even interviewed my children,” he recalls. “By that time, they’d been brainwashed and didn’t want to see their father.”
13年間日本で暮らし、アメリカに帰国したかったが、日本人の奥さんは嫌だといった。ある日、娘と、「こんな形でお別れでごめんね」と置き手紙をして、出て行った。ベンダ氏によると、日本の警察は家族内のことに手を出すこともなく、また、面接権も取れなかった。何年かして、裁判所は子供と面会したが、そのころには、洗脳されていて、父親には会いたくない、といっていた、という。
この少女たちを拉致したのか、どうかは書いていない。
ーーー日本国内のケースでハーグとは関係ない。洗脳されたか、どうかはわからない。面接権が認められなかった理由も書いていない。
Sometimes even countries that have agreed to the Hague Convention are no better. For instance, the State Department has more than 500 open cases involving 800 children abducted to or retained in Mexico. The convention has no enforcement mechanism; it’s up to the judicial system of a member nation to make its court’s decision stick. According to the Hague’s own statistics from a 2003 study, only 51 percent of all applications end with the child’s return to the left-behind parent. When the abducting parent does not consent to give up the child, judges take an average of 143 days to order a return―a far cry from the six weeks mandated by the convention. (Costa Rica, which agreed to the convention in 1998, did not respond to the Hague survey, so it is not included in these statistics.)
Gus Zamora, for his part, is generally dismissive of what he calls “the Vague Convention.” But he’s seen it work. In 2004, Hal Berger’s then-wife abducted their son from California to South Africa. A year later, he filed a Hague application, spending hundreds of thousands of dollars in legal fees and eight months in South Africa during the litigation; finally, South Africa’s Supreme Court ordered the boy’s return to the U.S. Berger, his estranged wife, and their son flew back together on the same plane. But 10 months later, she took off with the son again, using fake passports to return to South Africa. Berger went back to the South African courts―but this time he hired Gus, in case the courts ruled against him, or his estranged wife fled a third time. After spending hundreds of thousands more, a night in jail, and more than a month in Africa, Berger won his case in the South African courts in December 2007 and flew home with his son.
すごいのは、ハーグ条約締結国間でもこうした拉致をしている。
Todd considered filing a Hague application with the State Department, but he was skeptical that it would amount to anything because he distrusted what he dismissed as the corrupt legal system in Costa Rica.
ある人など、ハーグ締結国でも、その国の法の運用が信頼できないから、こどもを拉致せんとこの元軍人に依頼した、というのである。
こうした記事のケースがどのようにハーグ締結と関係するのか定かではない。日本のケースでは、ハーグと仮に関係しても、残酷な拉致のケースと、ハーグとは関係ないケースである。
他のケースでも、ハーグ締結国でも相手国が信用できなければ、こうしてくれるわ、というマッチョな脅しのような記事ではないか?
遵法精神などあったもんじゃない。しかもあのクリスはあたかも英雄である。
ハーグに締結してもしなくても彼等を満足させることは永久に無理そうである。
関連投稿
Christopher Savoie: vs Noriko
(日本人記者にはお勧め、海外での報道で、明らかになっている部分をまとめています。・・・英語ですが・・・)
クレイマークレイマー
2ちゃんねる的記事 1
Savoie vs Noriko
サボイ氏の事件 noriko vs Chris
裏をとって、ジャーナリストさん
メディアさん、おもしろうなネタだよ!!
米政府 日本人拉致未遂事件関与か?
誘拐合戦
更新 CNN Kyung Lah の迷走記事。
釈放
これハーグ?











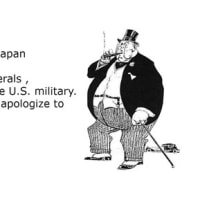
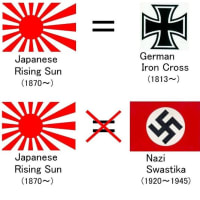
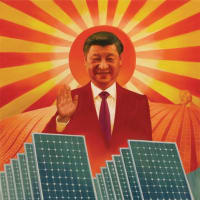
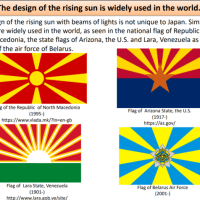




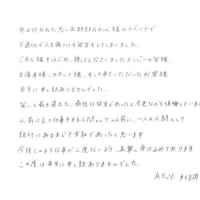
辞書を引き引き読んでみました。
http://travel.state.gov/family/abduction/resources/resources_4308.html
ここの2009年版の11ページを見てみますと・・・
2008年度にアメリカから外国へ連れ出されたケース
メキシコ 316件 533人
カナダ 57件 83人
イギリス 41件 52人
日本 37件 57人(ハーグ未加盟)
インド 35件 45人(ハーグ未加盟)
ドイツ 34件 49人
ドミニカ 25件 39人
(以下略)
子どもがアメリカに戻された人数
メキシコ 92人
カナダ 34人
イギリス 16人
ドミニカ 11人
ドイツ 10人
外国からアメリカに連れ込まれたケース
メキシコ 121件 174人
ドイツ 27件 36人
イギリス 21件 31人
カナダ 19件 27人
フランス 13件 16人
子どもがアメリカから外国に戻された人数
(調べきっていません。どなたか教えてください。)
よくわかったのは、日本が拉致大国といわれるほど事件数が多くないということでした。また、アメリカから距離が遠くなるほど、返還率も低くなるということと、どこまで行っても民事面(Civil Acpects)の条約であることでした。
あと、私が探し出せないだけだと思いますが、アメリカから他国に出国した人数がわかりません。ここのところをもう少し深く考えてみたいと思います。
参考までに。
During FY 2008, CI was notified of 1,082 new
outgoing IPCA cases involving 1,615 children.
Of these, 776 were abductions to Convention
partner countries. All but two of the ten
countries with the highest incidence of reported abductions (Japan and India) are Convention partners. These ten countries accounted for 602 cases: Mexico (316), Canada (57), the United
Kingdom (42), Japan (37), India (35), Germany (34), the Dominican Republic (25), Brazil (21), Australia (18), and Colombia (17). The number of new outgoing IPCA cases has increased substantially in the last three years, from 642 (FY 2006), to 794 (FY 2007), and now 1,082 (FY 2008). CI received 344 Convention applications concerning abductions to the United States, involving 484 children, in FY 2008. The topfive countries with the highest incidence of
reported abductions from the foreign country to the United States were Mexico (121), Germany (27), the United Kingdom (21), Canada (19), and France (13).
In FY 2008, CI assisted in the return to
the United States of 361 children who were
wrongfully removed to or wrongfully retained in other countries. Of these, 248 (69%) were returned from countries that are Convention partners. The countries accounting for the greatest number of returns were Mexico (92),
Canada (34), the United Kingdom (16), the
Dominican Republic (11), and Germany (10).
Moreover, 210 children wrongfully removed
to or wrongfully retained in the United States
from a foreign country were returned under
the Convention to their countries of habitual residence during FY 2008.
The report discusses the human and social
cost of IPCA, the consequences for children
and left-behind parents, and the role of nongovernmental organizations.
Convention partner countries are evaluated
for compliance in three areas: Central
Authority performance, judicial erformance,
and law enforcement performance. Honduras
is evaluated as “Not Compliant.” Seven
countries are evaluated as “Demonstrating
Patterns of Noncompliance:” Brazil, Chile,
Greece, Mexico, Slovakia, Switzerland, and
Venezuela.
Finally the compliance report provides a
summary of 67 applications for return of
an abducted child under the Convention
(sometimes referred to in this report as
“Hague return applications”) from 14
countries. These applications were filed prior to April 1, 2007, and remained unresolved after 18 months from the date of filing, as of September 30, 2008
子どもがアメリカから外国に戻された人数
(調べきっていません。どなたか教えてください。)
→
Title Statistical Analysis Part II: National Report United States
http://hcch.e-vision.nl/upload/stats_us.pdf
ちょっと古い(1999年)ようですが、
Overall, 52% of applications made to the USA ended in the child being returned
either by a court order or voluntarily which is marginally above the global rate of 50%.
210の申し立てがあり、
52%が帰還しているようです。
おもしろいのは、
自発的帰還が59
裁判での帰還が50だそうです。
それ以外は却下、取り下げ、係争中などのようです。
、アメリカから他国に出国した人数がわかりません
→
こっちのほうがでているかな? Page10
ABDUCTION STATISTICS
Outgoing Cases – Abductions from the
United States
4 In FY 2008, the USCA assisted many LBPs
in the United States with ongoing cases and
responded to 1,082 new IPCA cases involving
1,615 children. Of these cases, 776 involved
children wrongfully removed to or wrongfully
retained in countries that are parties to the Convention.
アメリカのこの機関が援助したケースでは、アメリカからの出国は、1615、このうち776ケースが、ハーグ締結国に拉致されたケース。
In FY 2008, the Department assisted in
the return to the United States of 361
children who were wrongfully removed to or
wrongfully retained in other countries. Of
these children, 248 children were returned
from countries that are Convention partners
with the United States, accounting for 68.7
percent of the returns in FY 2008.
4 In FY 2008, 210 children wrongfully removed
to or wrongfully retained in the United States
were returned under the Convention to their
country of habitual residence
2008年には、361のアメリカへの帰還ケースを援助して、そのうち248(68.7%)はハーグ締結国からの帰還
アメリカに拉致されたケースでは、210ケースハーグ締結国に帰還させた、とあります。
ハーグ締結に際して、共同親権などの法整備が問題になってくると思いますが、これもかなり要件をつめないと泥沼状態になる可能性もある。
また、強制面接にしても、然りで、子供の意向を汲むのは当然として、やはり、具体的な方策を整備しておかなくてはいけない。
単純に外交上のアメリカにこづかれるから、というのでは、混乱を産むだけだろう、と思います。
そこの部分は追いついていませんので、後で読ませていただきます。
さて本題、マスコミにや別居親系の当事者団体が、共同親権とハーグ条約の位置関係について誤解していることです。
今年の5月のアメリカ大使館のハーグ条約についてのセミナーは私も参加してきましたが、大使館がはっきり言っていることは
『ハーグ条約は、締結国も単独親権の時代に制定されていますから、単独親権でも批准することになんら問題はありません。』ということです。
ハーグ条約の法整備については、『Civil Acsepts(民事面に)』の部分について、どのように対応するかです。
ここからは私見ですが、ハーグ条約絡みの法整備について、もっとも大きなのは裁判所の管轄です。
現在の国内法では、親子に関する審判の場合は『子の住所地を管轄する家庭裁判所』とされており、住居の居住期間は考慮されていません。
(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_02_4.html )
養育費や面接交渉では、調停前置主義を採用しており、まずは相手方(被告)の管轄する家庭裁判所で対応することになっています。
(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_03_4.html )
これを、ハーグ条約制定時には、子の前1年間の居住していた住所地の管轄する家庭裁判所と変更する必要があります。現実問題としては、『ただし、ハーグ条約に基づく申し立てが中央機関より届いているときは・・・』という但し書きを設けることが一番重要かもしれません。
それから、ハーグ条約の実務に『子の強制的な引き渡し』という項目が入っていますし、たとえば日米犯罪人引渡条約でも、自国民を相手国に引き渡す義務を負わないと明記されていますので、民事で強制引き渡しを実施できるのかという点で、さらに要件を詰める必要があります。
取り急ぎ…
ありがとうございます。
なるほど、ハーグ、共同親権、強制面接など、セットで語られる場合が多いので、私も誤解しておりました。
とすると、ご指摘のように、
「民事で強制引き渡しを実施できるのか」というところの法整備ということなんでしょうね。
↑意味が逆に取り違えるような書きこみ、申し訳ございません。
大阪市立大学の法哲学ゼミ2006年度報告書が、わかりやすく翻訳されていますので、ここから引用します。(コピペができないので、打ち込みました)
http://philolaw.hp.infoseek.co.jp/resume/2006/report2006m.pdf の10ページ
3 批准国における条約適用時の義務
a)いずれの締約国も、子の条約に負う義務を履行するため、中央当局を指定する。
b)中央当局は、子の迅速な返還を確保するため、及びその他の目的を実現するため。互いに協力し、かつそれぞれの区の権限当局間の協力アをする。
c)中央当局は、次の事項を行うため、直接または代理機関を通じて適切な処置を取る。
1.奪取された子の所在を発見すること。
2.仮の処置を取り(取らせ)、子に及ぶ今後の危険を防ぎ、又は理解関係人に及ぶ今後の損害を防ぐこと。
3.子の任意の返還を確保、又は示談による紛争の解決に便宜を与えること。
4.適当とされる場合には、子の社会的背景に関する情報を交換すること。
5.この条約の実施に関連する自国の国内法につき一般的な情報を提供すること。
6.子の返還を受けるために相当と認める場合には、面接権の内容を定め、又は開始するための便宜を与えること。
7.相当と認める場合には、弁護士の参加も含め、訴訟上の救済及び助言を与え、又は開始するための便宜を与えること。
8.必要かつ適当な行政上の手続きをとり、子の無事な返還を確保すること。
9.この条約の実施に関する情報を交互に交換し、できる限り、適用の障害となるものを取り除くこと。
つまり、『強制的に子の返還を実施する』とは、義務の中に書かれていないのです。
取り急ぎ・・・
あと、アメリカ国内の法律からすれば、強制返還があたりまえなので、その常識を押し付けようとしているとか。
ハーグは80年代に作られたものであり、2009年版に修正しようという動きもあるんですが、そちらのほうでは、どのように修正したがっているのかは、読んでいませんので、わかりませんが、そういったことの変更を求めているのかもしれないですね。
国際的に日本での裁判の管轄が認められ、日本でも日本人の裁判官によって、ハーグ条約に基づいて裁判が行われるわけですから、「同情」も入ってくるでしょうし(アメリカの裁判との一番の違いだと思います)、そしてその判決が両国で有効というのは、母子を保護するためとして考えると、必要ともいえるでしょうね。
条約の批准を求めるのは出来るが、個々の具体例に踏み込むと内政干渉になるので訴えることが出来ず、ハーグ条約批准を声高に訴えることしか諸外国は出来ないのです。