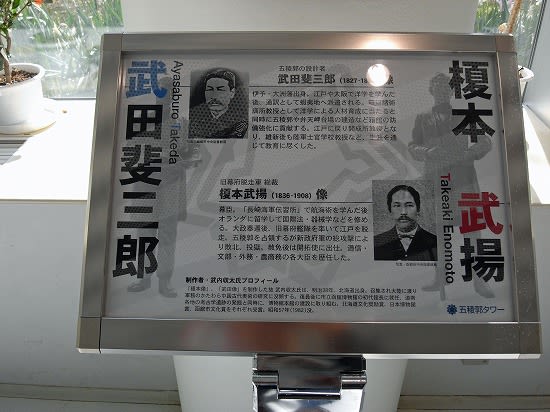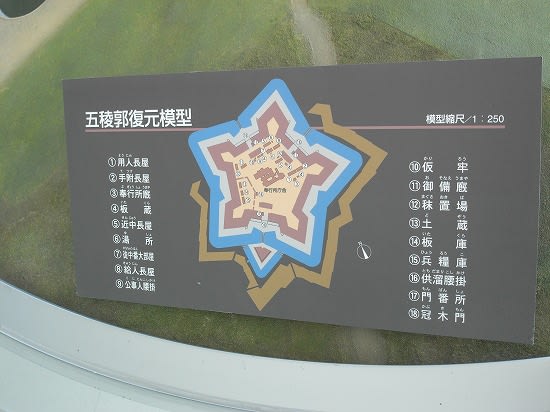2015年5月18日(月) 晴 (えりも町・民宿 仙庭~広尾町・広尾キャンプ場)

6時40分、民宿の女将さんと連泊の同宿者に見送られて、出発。

旗を振って見送られたのは初めて。むかしのユースホステルの名残かな。女将さんからおにぎりを貰った。女将さんの話では、冬はほぼ半年の間お客は来ない。吹雪と強風で建物が壊れるのではないかと怖くなってしまう。シーズン中も若い人はほとんど来ないし、相部屋は好まれない。そもそも若者が昔のようには旅をしなくなっているのではないか。遠からず、宿を閉めようと思っている、大分県に戻って小さな宿をやってみたい、と。一つの時代が過ぎ去っていく、ということか。寂しいかぎり。
晴れて、風弱し。「海岸緑化造成地」や、クロマツやハンノキの人工林、保安林など、両側が防風林に挟まれた道道34号線を行く。





7時15分、道路上にキタキツネ。

(拡大)

自動車はほとんど通らず。空は抜けるように青く、左手の日高山脈の山々(山頂の建物は自衛隊日高駐屯地)、

右手の海もくっきり見える。




牧場もあり。こちらを見つめる牛たち。

8時、北緯42°地点の碑。

観音堂(左)と、一石一字塔(右)。

一石一字塔は、海難事故犠牲者の供養と航海の安全祈願のため一八〇六年に建立された、と。

右手の百人浜の展望台は、修繕工事のため使用不可。

真下まで行って見たが、案の定上れず。

左、悲恋沼というロマンチックな名前の沼と、日高山脈南部の山々(山座同定はできず)。

悲恋沼は、和人の若者とアイヌの娘の悲恋の伝説による。
振り返れば、稜線に自衛隊駐屯地遠く。

8時55分、こんどは馬の牧場。

国道336号線(襟裳国道)に合流し、庶野漁港を見て行く。襟裳岬の東側にも昆布乾燥場あり。

10時10分、回り込んだところに「これより黄金道路」の碑。


前方に、断崖絶壁ゆえ巨額建設費投下の「黄金道路」。


10時15分、フンコツトンネル、

10時20分、白浜トンネル(622m)、

岩礁。

咲梅トンネル(473m)過ぎて、

「北海道で一番長い道路トンネル」の、えりも黄金トンネルへ。


4941mを62分で通過。1時間以上トンネルの中にいると、体は冷えきってしまうし、

気晴らしに懐メロを歌いながら行くが、ちょっと気分が変になる感じ。
出たところのバス停で、おにぎり休憩。
しばらく日に当たりながら歩くことの有難味を感じつつ行き、
12時5分、猿留川。

川の名の由来――永田地名解によると、サロルン・ウシ(鶴多き処)あるいはシャリオロ(湿沢の処・葦原の処)が語源であろうとされている。

落石・崩壊防止のネット状の補強と「津波注意」警告板。

12時20分、荒磯トンネル。

12時30分、目黒トンネル。トンネルは舗装中で、隣の覆道を行く。

覆道内で、チャリで日本一周中の京都の大学生に出会い、キャンデーをあげた。お互い頑張ろうとエール交換。
さらに行くと、車が停まり、男性が、帯広に行くから広尾まで乗せてくれる、とのこと。甘える。
彼は昆布専門の漁師。他の人は昆布の他にカレイ、エビ、ツブガイなどの漁をする。黄金道路が開通する以前は内地に出稼ぎに行ったが、開通後は地元で食べていかれるようになった、とのこと。
13時、広尾町に入る。

13時30分、フンベの滝で停まってもらい写真を撮る。彼の話では、昔はナイアガラの滝のように一面に流れ落ちていたのだが、徐々に水量が減ってしまった、と。



13時40分、黄金道路終点で降ろしてもらい、お礼を言って別れた。


炎天下の広尾の町中を行き、途中の歯医者で差し歯を直してもらう。運悪く昼休み中で1時間ほど待たされたが、自動車に乗せてもらったので埋め合わせ。暑い中を歩いてきたので、待合室の冷房も気持ちよかった。今日は北海道中で広尾が一番高温だった、と事務員の女性が言っていた。(※歯科治療費は計算外)
15時30分、十勝神社にある、北海道に初めてできた道の記録「東蝦新道記・彫字板」。

その後は、楽古川を目指し、
16時5分、楽古川上流側、

河口側。

川の名の意味――猟虎(らっこ)が流れ寄りつく川

川の先の表示に従って右折。キャンプ場へ。
「日本一のエンレイソウの群落地」で、大木の根元に白い大輪のエンレイソウが盛りだった。


16時30分、キャンプ場はまだ営業しておらず、キャンプ場横の草地に設営。宿泊、無料。
2015年 第48日(佐多岬より110日)
歩数 51163歩 (佐多岬より累計 5641927歩)
距離 48.5㎞ (佐多岬より累計 3752㎞)
※途中、一部自動車に乗せてもらった。
費用 674円 (佐多岬より累計 518715円)

6時40分、民宿の女将さんと連泊の同宿者に見送られて、出発。

旗を振って見送られたのは初めて。むかしのユースホステルの名残かな。女将さんからおにぎりを貰った。女将さんの話では、冬はほぼ半年の間お客は来ない。吹雪と強風で建物が壊れるのではないかと怖くなってしまう。シーズン中も若い人はほとんど来ないし、相部屋は好まれない。そもそも若者が昔のようには旅をしなくなっているのではないか。遠からず、宿を閉めようと思っている、大分県に戻って小さな宿をやってみたい、と。一つの時代が過ぎ去っていく、ということか。寂しいかぎり。
晴れて、風弱し。「海岸緑化造成地」や、クロマツやハンノキの人工林、保安林など、両側が防風林に挟まれた道道34号線を行く。





7時15分、道路上にキタキツネ。

(拡大)

自動車はほとんど通らず。空は抜けるように青く、左手の日高山脈の山々(山頂の建物は自衛隊日高駐屯地)、

右手の海もくっきり見える。




牧場もあり。こちらを見つめる牛たち。

8時、北緯42°地点の碑。

観音堂(左)と、一石一字塔(右)。

一石一字塔は、海難事故犠牲者の供養と航海の安全祈願のため一八〇六年に建立された、と。

右手の百人浜の展望台は、修繕工事のため使用不可。

真下まで行って見たが、案の定上れず。

左、悲恋沼というロマンチックな名前の沼と、日高山脈南部の山々(山座同定はできず)。

悲恋沼は、和人の若者とアイヌの娘の悲恋の伝説による。
振り返れば、稜線に自衛隊駐屯地遠く。

8時55分、こんどは馬の牧場。

国道336号線(襟裳国道)に合流し、庶野漁港を見て行く。襟裳岬の東側にも昆布乾燥場あり。

10時10分、回り込んだところに「これより黄金道路」の碑。


前方に、断崖絶壁ゆえ巨額建設費投下の「黄金道路」。


10時15分、フンコツトンネル、

10時20分、白浜トンネル(622m)、

岩礁。

咲梅トンネル(473m)過ぎて、

「北海道で一番長い道路トンネル」の、えりも黄金トンネルへ。


4941mを62分で通過。1時間以上トンネルの中にいると、体は冷えきってしまうし、

気晴らしに懐メロを歌いながら行くが、ちょっと気分が変になる感じ。
出たところのバス停で、おにぎり休憩。
しばらく日に当たりながら歩くことの有難味を感じつつ行き、
12時5分、猿留川。

川の名の由来――永田地名解によると、サロルン・ウシ(鶴多き処)あるいはシャリオロ(湿沢の処・葦原の処)が語源であろうとされている。

落石・崩壊防止のネット状の補強と「津波注意」警告板。

12時20分、荒磯トンネル。

12時30分、目黒トンネル。トンネルは舗装中で、隣の覆道を行く。

覆道内で、チャリで日本一周中の京都の大学生に出会い、キャンデーをあげた。お互い頑張ろうとエール交換。
さらに行くと、車が停まり、男性が、帯広に行くから広尾まで乗せてくれる、とのこと。甘える。
彼は昆布専門の漁師。他の人は昆布の他にカレイ、エビ、ツブガイなどの漁をする。黄金道路が開通する以前は内地に出稼ぎに行ったが、開通後は地元で食べていかれるようになった、とのこと。
13時、広尾町に入る。

13時30分、フンベの滝で停まってもらい写真を撮る。彼の話では、昔はナイアガラの滝のように一面に流れ落ちていたのだが、徐々に水量が減ってしまった、と。



13時40分、黄金道路終点で降ろしてもらい、お礼を言って別れた。


炎天下の広尾の町中を行き、途中の歯医者で差し歯を直してもらう。運悪く昼休み中で1時間ほど待たされたが、自動車に乗せてもらったので埋め合わせ。暑い中を歩いてきたので、待合室の冷房も気持ちよかった。今日は北海道中で広尾が一番高温だった、と事務員の女性が言っていた。(※歯科治療費は計算外)
15時30分、十勝神社にある、北海道に初めてできた道の記録「東蝦新道記・彫字板」。

その後は、楽古川を目指し、
16時5分、楽古川上流側、

河口側。

川の名の意味――猟虎(らっこ)が流れ寄りつく川

川の先の表示に従って右折。キャンプ場へ。
「日本一のエンレイソウの群落地」で、大木の根元に白い大輪のエンレイソウが盛りだった。


16時30分、キャンプ場はまだ営業しておらず、キャンプ場横の草地に設営。宿泊、無料。
2015年 第48日(佐多岬より110日)
歩数 51163歩 (佐多岬より累計 5641927歩)
距離 48.5㎞ (佐多岬より累計 3752㎞)
※途中、一部自動車に乗せてもらった。
費用 674円 (佐多岬より累計 518715円)