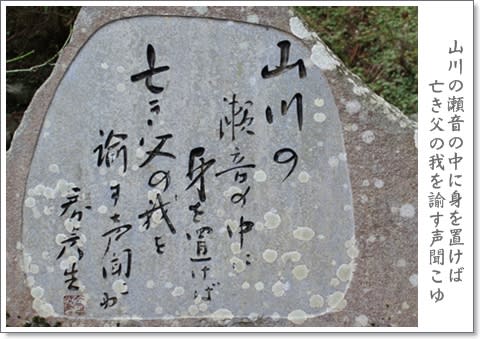今回は私のお気に入りの窯元を紹介します。
豊前吉右衛門窯です。
初代永末吉右衛門(晴美)氏は京都の宇治朝日焼の窯元で修業し、
1949年に福岡県田川郡方城町の生家近くに「 豊前吉右衛門窯 」を開きました。
豊前は旧国名、窯場が吉右衛門谷の入口に位置する事から命名されたそうです。
作風は、初期の頃より絵付けされた陶器作りを目指し、
1950年代半ばより吉右衛門(晴美)氏によって、刻染付(ほりそめつけ)の独特の作風が編み出され、
以後刻染付、染付、青瓷、藁白、などを中心に創作を続けています。
1984年に修策(吉右衛門長男)氏が10年間に渡ってメキシコで陶芸の指導を続けていた生活に
ピリオドを打ち帰国し父を手伝っておりましたが、2005年2月に父 晴美氏が他界しました。
今は修策氏により吉右衛門窯の陶器の美しさを守りながら新しい世界を生み出しています。
私がこの焼き物に心ひかれたのは『刻染付』(ほりそめつけ)の技法でした。
細い陰刻線を輪郭に、淡い呉須や鉄彩を用いるその手法は、周辺の上野焼の伝統とは全く異なった、
繊細にして優雅な独自の雰囲気を醸し出していると思います。
※刻染付とは
陶器の素地が半乾きの時、鉄筆で文様を刻り、乾燥・素焼を経て
刻られた細かい溝状の線に顔料を入れ彩色したものだそうです。(「刻染付」は晴美氏の造語だそうです)
豊前吉右衛門窯です。
初代永末吉右衛門(晴美)氏は京都の宇治朝日焼の窯元で修業し、
1949年に福岡県田川郡方城町の生家近くに「 豊前吉右衛門窯 」を開きました。
豊前は旧国名、窯場が吉右衛門谷の入口に位置する事から命名されたそうです。
作風は、初期の頃より絵付けされた陶器作りを目指し、
1950年代半ばより吉右衛門(晴美)氏によって、刻染付(ほりそめつけ)の独特の作風が編み出され、
以後刻染付、染付、青瓷、藁白、などを中心に創作を続けています。
1984年に修策(吉右衛門長男)氏が10年間に渡ってメキシコで陶芸の指導を続けていた生活に
ピリオドを打ち帰国し父を手伝っておりましたが、2005年2月に父 晴美氏が他界しました。
今は修策氏により吉右衛門窯の陶器の美しさを守りながら新しい世界を生み出しています。
私がこの焼き物に心ひかれたのは『刻染付』(ほりそめつけ)の技法でした。
細い陰刻線を輪郭に、淡い呉須や鉄彩を用いるその手法は、周辺の上野焼の伝統とは全く異なった、
繊細にして優雅な独自の雰囲気を醸し出していると思います。
※刻染付とは
陶器の素地が半乾きの時、鉄筆で文様を刻り、乾燥・素焼を経て
刻られた細かい溝状の線に顔料を入れ彩色したものだそうです。(「刻染付」は晴美氏の造語だそうです)
このような作品です


主人が30年前に買ったマグカップ(父晴美氏の作)

30年前より使っている急須と湯呑み(父晴美氏の作)


私専用の湯呑み

椿の花の輪郭の繊細さがとても好きです
掌の納まり具合が気に入っています
お気に入りの小皿

今回、購入した湯呑みとカップ

柿を表しています



主人が30年前に買ったマグカップ(父晴美氏の作)

30年前より使っている急須と湯呑み(父晴美氏の作)


私専用の湯呑み

椿の花の輪郭の繊細さがとても好きです
掌の納まり具合が気に入っています
お気に入りの小皿

今回、購入した湯呑みとカップ

柿を表しています

作品に興味がある方は
ギャラリー ご覧下さい。