
京大がポスドクを小中高に講師派遣するらしい。
博士号を取得はしたものの、大学や研究機関のポストに就ける人間は多くはない。
といって、企業が博士の採用に及び腰なことも、いつも言っているとおり。
結果、行き場のない博士たちが溢れているという話は、以前から問題となっている。
専門性を何らかの形で生かすことは良いことだと思うし、一部の論者がいうように、
もう一歩進めて公立校の教職員としてのキャリアパスも検討すべきだろう。
それにしても、正直少し驚いた。
京大クラスの大学で“無料派遣”である。
なんだか、量販店に立つメーカー派遣の販売員みたいだ。
ロンダリング生(他大学出身者)だとかなんとかいう人もいそうだが
専門性が評価されないという点では変わらない。
自分の大学院で学んだ博士が、小学校にタダで派遣される現実を見れば、
後輩はどう思うだろうか?
こういうことが起きてしまう理由については、いつも言っているとおり。
・企業が修士以上は取りたがらない(開発職除く)。
・大学-企業-シンクタンクといった研究職ポスト間での人材移動が
日本では非常に少ないので、どの組織にも空きポストなんて出るわけがない。
たまに、「ポスト工業社会はより高度な付加価値が求められるから、もっともっと
高等教育を充実させ、大学の学費も無料化しよう」という論者がいる。
前半はその通りなのだが、後半はどうだろう。
日本企業が欲しいのは、まだまだ一定のポテンシャルを持つ新卒者であり、
専門教育の中身ではない。
なのでいくら予算をつぎ込んで大学進学率を引き上げたり、
修士博士を増やしたところで、大卒以上のフリーターが
増えるだけではないか。
教育の側を変えたからといって、それで社会が変わるわけではないのだ。
まず変えるべきは、労働市場だろう。
「おまえらこれから毎日万刷をATMに補充しろ!学生気分を叩き出してやる!」
というカルチャーから、
「幹部候補は最低でも修士以上の専門性が必要」
と企業がいうようになってから、高等教育は充実させればいい。
博士号を取得はしたものの、大学や研究機関のポストに就ける人間は多くはない。
といって、企業が博士の採用に及び腰なことも、いつも言っているとおり。
結果、行き場のない博士たちが溢れているという話は、以前から問題となっている。
専門性を何らかの形で生かすことは良いことだと思うし、一部の論者がいうように、
もう一歩進めて公立校の教職員としてのキャリアパスも検討すべきだろう。
それにしても、正直少し驚いた。
京大クラスの大学で“無料派遣”である。
なんだか、量販店に立つメーカー派遣の販売員みたいだ。
ロンダリング生(他大学出身者)だとかなんとかいう人もいそうだが
専門性が評価されないという点では変わらない。
自分の大学院で学んだ博士が、小学校にタダで派遣される現実を見れば、
後輩はどう思うだろうか?
こういうことが起きてしまう理由については、いつも言っているとおり。
・企業が修士以上は取りたがらない(開発職除く)。
・大学-企業-シンクタンクといった研究職ポスト間での人材移動が
日本では非常に少ないので、どの組織にも空きポストなんて出るわけがない。
たまに、「ポスト工業社会はより高度な付加価値が求められるから、もっともっと
高等教育を充実させ、大学の学費も無料化しよう」という論者がいる。
前半はその通りなのだが、後半はどうだろう。
日本企業が欲しいのは、まだまだ一定のポテンシャルを持つ新卒者であり、
専門教育の中身ではない。
なのでいくら予算をつぎ込んで大学進学率を引き上げたり、
修士博士を増やしたところで、大卒以上のフリーターが
増えるだけではないか。
教育の側を変えたからといって、それで社会が変わるわけではないのだ。
まず変えるべきは、労働市場だろう。
「おまえらこれから毎日万刷をATMに補充しろ!学生気分を叩き出してやる!」
というカルチャーから、
「幹部候補は最低でも修士以上の専門性が必要」
と企業がいうようになってから、高等教育は充実させればいい。














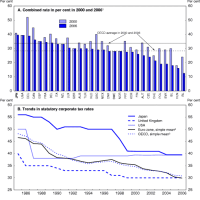





―――――
研究というのは、基本的には『少数の天才』によって行われるべきもの
―――――
という考えは、
20世紀以前の、理論物理学者とか、数学者とか
といったイメージに左右されすぎているように思います。
「輝かしい研究」というのはありますが、
それだけが「研究」の名に値すると考えるのは、
少し早計では?
わたしは将棋・囲碁界のことは知らないので、
―――――
プロの棋士の方法が参考になると思います。
―――――
という意見は、よくわかりません。
このような世界で、
何歳からはじめるのが一般的かはわかりませんが、
仮に、
10歳からはじめて、
25歳で見切りをつけるとしたら、
やめる時点で、すでに、
15年のキャリアがあることになります。
これを研究者に当てはめると、
研究を始めるのが20歳だとして、
キャリア15年で、
35歳であきらめることになります。
おそらく、
プロの棋士を参考にするまでもなく、
ほとんどの人は、15年やって
ものにならなそうならば、
あきらめるのではないかと思います。
(それが良いことかは、わかりませんが)
その場合、
あきらめた年齢が、何歳かによって、
だいぶ立場が違ってしまうのです。
ケビン67さんがおっしゃる
―――――
研究者も才能がないのであれば、早めに見切りを付けられるようにすべきです。
―――――
というのは、もしかしたら、
「2~3年やってだめならあきらめろ」
ということなのかもしれませんが。
つまり、どちらにしろ、
25歳ぐらいであきらめろ、ということなのかもしれません。
あと、渡邊さんがおっしゃることで、
―――――
一般の人らはノーベル賞を取るような革新を起こすものだけが価値があるんだって思いがちなんですけど、
―――――
とありますが、
「一般の人ら」は、「価値がある」とか
そんなことはあまり考えていないと思います。
基本的には、
「日本人が」ノーベル賞をとったときのみ、
話題になると思います。(テレビにたくさん出るから)
「一般の人ら」に、
「今までの日本人受賞者は?」
と聞いても、答えられる人は少ないのでは?
ただ、「一般の人ら」といっても、
幅が広すぎると思います。
さらに、
―――――
学術的なプラスアルファを出し学問を発展させていくことがマネーを生むか、というのと連動していないし関係ないからです。
―――――
「連動してない」は、
そのとおりだと思いますが、
「関係ない」と言ってしまうのは、
かなりまずいと思います。
プロの棋士になろうとすれば、ある一定の年齢までにハードルを越えなければなりません。
要するに研究というのはそこの世界だけで完結しているスポーツやエンターテイメントの世界とは性質の違うものである。人間が知的活動、社会活動を行う上でその一番外側にあるもの。つまり社会に欠かせてはいけない土台なのです。競争かどうかというのも本来そうあるべきものではないと私は思う。ポストを取るにあたってはもちろんそれまでの研究成果の数と質が勝負になってくるのも事実であるが。それは現実の運営に当てはめるためにそうなっているというだけである。
才能があるかどうか早めに見極めろというのも微妙で成果が出るのは長い蓄積が必要な人もいる。その代わり出た時にはものすごい成果となって返ってくるという可能生。
例えば分野によって事情は全然違ってくるが、2年かかる研究と5年かかる研究と10年かかる研究と100年かかる研究があったとして5年以内に完結するものでしか研究することができなくなってきているのが、今日の学問を競争と勘違いする人たちが導入した成果主義の弊害です。
>したがって、「研究のおかげで社会が良くなった」
と認識される状態になっていないとするなら、その原因は、
(1).たいした研究成果も出せない、だめな研究者ばっかり
(2).研究成果があっても、それを活かせないだめな企業ばっかり
要するに、一般の人らはノーベル賞を取るような革新を起こすものだけが価値があるんだって思いがちなんですけど、それはその人の刺激的なものを求めたいっていう欲求からのみ来ていて、実際の学問の場において全然そんなことはないんですね。学術体系を発展させられたって認められたから、博士号の学位が与えられるんですよ。そうした学位が与えられているにもかかわらず、その人たちのポジションがないというのは組織運営上の問題でしょう。なぜなら学術的なプラスアルファを出し学問を発展させていくことがマネーを生むか、というのと連動していないし関係ないからです。
世に必要な研究は不足しているし極論を言えば、研究者の必要な数に限界はないんですね。どんなに優れた人物がノーベル賞の業績を出そうが、それは非常に限られた特定の分野においてのみ革新的なものをプラスアルファしただけであって、ちょっと横にそれればその研究は誰もやってないなんてことはいくらでもあり得るからです。
プロの棋士の方法が参考になると思います。
プロの棋士になろうとすれば、ある一定の年齢までにハードルを越えなければなりません。
それは、才能のない人に見切りをつけれもらうために必要だと思います。
研究者も才能がないのであれば、早めに見切りを付けられるようにすべきです。
もちろん、ハードルを越えた人も、そのあと、競争を続けさせるようにしなければなりません。
わが国の教育にかけているものはこれである。
ゆとり教育は教育をしっている人がすることではない。
臨界期というどうしようもないものを人は持っているからである。
その昔家を建てるとき、左官の親方と話した。彼は伝統技術士と言う資格を持ち、親方と言う感じがした。左官の親分を親方と呼ぶか知らないが。
あるときこのご時勢で高卒でも来る人は少ないと思うが,高卒と中卒とでは左官の腕はいかがですかとたずねると、即座に中卒のほうがいいと答えた。そのわけを聞くと。どうも、左官は体で身に付ける部分があり、其れは高卒では遅い気がする。何かは分からないが、感覚のようなもで、私が見てきた範囲ではそのように思う。と答えた。
これに尽きる。
教育とはあきらめるものを早く見つけることである。引きずられることではない。従って、初等教育と中等教育、高等教育とすすむわけだが、高校のころから22歳頃まで、ごく普通の人は(大半の人、99.97パーセント)それを見つけることである。遅くとも25歳頃までである。
単純なことである。
「研究」という行為の本質は、先人の誰もがたどり着けなかった結論に達するということであるため、相当に優秀な人でなければできない仕事です。だから、研究というのは、基本的には『少数の天才』によって行われるべきものだと思います。
(実験の数をこなせば成果が得られるという研究は別ですが)
だから、そもそも研究者の数を増やすという発想が間違っていたのだと思います。
◆どうすべきか
プロの棋士の方法が参考になると思います。
プロの棋士になろうとすれば、ある一定の年齢までにハードルを越えなければなりません。
それは、才能のない人に見切りをつけれもらうために必要だと思います。
研究者も才能がないのであれば、早めに見切りを付けられるようにすべきです。
もちろん、ハードルを越えた人も、そのあと、競争を続けさせるようにしなければなりません。
「夢を追いかけて」というイメージなのでしょうか?
それはともかく、
使われているロジック自体は、
結構なんにでも当てはまるように思います。
たとえば、
―――――
◆ピアニストを目指している人
(1)ピアニストになる前から、演奏活動で食えるようになる確率は小さいということを理解している。
(2)実際に(自称)ピアニストになってみて、コンサートを開いても客は来ない。CDを出そうとしても、大手レーベルからは相手にされず、自費製作しても誰も買ってくれない。
(3)「やっぱり駄目だった」と認識して、ピアニストの道をあきらめる。
―――――
の、「ピアニスト」の部分を
「起業家」に置き換えても、
けっこう成り立つと思います。
なので、
―――――
そもそも、なぜピアニストで食えないのでしょうか? それは、金を払ってまでピアノの演奏を聴きたいという人が限られているためです。
―――――
ということを基本原理として考えるなら、
(そもそも、ピアニストが本当に「食えない」かはわからないが)
べつに、どのような職業のひとが食えなくとも、
問題はなくなる、と思います。
(医者が食えなくとも、弁護士が食えなくとも、農家が、建築士が、投資家が、平社員が)
なぜなら供給が過剰だから、となります。
わたしの考えでは、
ケビン67さんのロジックは、過度に、
博士を目指す人=芸術家(肌の人)、というようなイメージに依存しすぎているように思えます。
「どうせ好きで目指したんだろ。だからほっとけ(自業自得だ)」というような。
別の点で疑問なのは、
―――――
本当に研究者がいっぱい研究成果を出して、それで本当に社会が良くなるなら、
―――――
というくだりですが、
研究成果が出たからといって、すぐに、社会がよくなるわけではないと思います。
なぜなら、
よい成果も、社会に広がらなければ(流通しなければ)、効果(影響)がないからです。
現時点で、その方法は、「商品化」というのが主流だと思います。
そして、それを担うのは、企業です。
ここで、「分業」を想定するなら、
「研究成果をだす人」=「研究者」
「商品化する人」 =「企業」
となるはずだと思います。
したがって、「研究のおかげで社会が良くなった」
と認識される状態になっていないとするなら、その原因は、
(1).たいした研究成果も出せない、だめな研究者ばっかり
(2).研究成果があっても、それを活かせないだめな企業ばっかり
というものが考えられます。
おそらく、両方の原因があるのでしょう。
それなら、改善していこう、というのが前向きな考えで、
(1)のほうに対しては、大学院改革(?)のはずで、
(2)のほうに対しては、「人事制度」の見直し、ということになると思います。
なぜなら、(2)のような事態が発生するのは、
企業内に、「博士号取得者」のような専門家がほとんどいないため、
研究成果が「商品化」に役立つか評価できない、
とも考えられるからです。
何かを評価するさいに、自分の代理となる「専門家」は必須でしょう。
最後に、
―――――
この問題の本質は、「社会のニーズを上回った人材供給をしたから、ニーズの無い部分が余った」ということだと思います。
人事制度的な問題より、国がニーズを見極めずに、供給を増やしたということに問題があると思います。
―――――
これはむしろ、サラリーマンのホワイトカラー・ノンワーキングリッチのことでは? 社内失業とか。
あるいは、「普通科高校」とかの問題とか。
ビジネスを中心に考えるなら、むしろ、
「商業高校」とかが、地域のトップ校になってもおかしくないはずなのに(理屈の上では)、と思いました。
ああああ、とても長くなってしまいました。すみません。
失礼しました。
20年ほど前の話ですが、小生の父が某旧帝国大学のポストドク(理論物理)を面接して採用しなかった、と言っていました。理由は直接は聴いていないのですが、日頃の父の採用に関する話から類推すると、おそらくは、
1 その会社ではそこまで優秀な人材を活用できない(人事部に”少し頭が悪くてもよいからがんばりのきく人間をとってくれ”と言っていたことがあります)
2 本人に周囲の人間と共同で仕事を遂行できるだけの協調性がかけていると思われていた(旧帝国大学レベルの人材はほとんど入社しない会社でしたから)
では無いかと思います。その後その会社では中央研究所を作ったことからすると、2の理由が大きかったのではないかとは思います。小生の知人に博士号取得者はそれなりにいますが、企業へ就職するからには、その企業にとって利益を生み出すような仕事をすることが必要だ、という意識をもっているとは、必ずしも思えません。
ずっと同じ大学の同じ研究室にいて、大学、国立の研究所に採用されることこそ一流の証、と思っている博士号取得者からみると、企業への就職は、定年まで勤め上げるつもりで入社した財閥系大企業から、中小企業へ不本意ながら転職するくらいの挫折感あるいはあきらめの気持ちがあるのではないでしょうか。企業の技術者など見下してこそ一流大学の教授だ!と考えている教授の元にいると、意識の切り替えが難しいでしょう。ちょっと後ろ向きな気持ちで就職されても、採用される側は良い評価を与えることはできないのではないでしょうか。
小生がこれまで勤めてきた企業では比較的博士号取得者も採用していたので、企業側の問題点が今ひとつ実感できていないかもしれません。また理系の範囲でしか知見がありませんが。
日立さんへの提案ですが「メイドカフェ」ならぬ「博士カフェ」という白衣の博士たちに妄想を抱く主婦層をターゲットにフランチャイズ展開してみたら?赤字の解消になるのではないでしょうか?
目に見えて成果がわかるものかどうかは分野に依るし、第一義的には研究というのは社会役に立つかどうかを目指すものではないのですね。要するに社会の知識基盤を発展させるためのものということです。それが役に立つかって言うとそれぞれ距離があるわけで。まああなたのような人が政府の中枢にいるから物理で言えば基礎研究がおろそかにされるのでしょうけど…。現代の人はこれが何の役に立つか??何かを焦りすぎているように思えます。
>博士がなぜポストを得られないのか? それは、研究成果というものに対する社会ニーズが限られているからです。
違います。大学運営上のコスト(ポスト数)の問題。教員の仕事というのが大学の行政、教育、研究と大きく分けて3つあるんだけど、ポストの需給というのが教育と行政に携わるのに必要な数で決められるから、研究のニーズっていうのは無視されるんですね。
現に今研究者が育たなくて(博士に進む人が少なくて)学問が形骸化すると叫ばれているのはそのためです。例えば京大発のips細胞の研究で、すでに欧米に主導権もって行かれそうなのは研究者の数が向こうと違うからです。
>人事制度的な問題より、国がニーズを見極めずに、供給を増やしたということに問題があると思います。
確かに文科省は無計画だったんだけど、大学院重点化って言うのはやはりこれからの情報編重型の社会においてすごい大事なことだと思いますよ。世界が今大学院教育にシフトしようとしているのは事実で、そこに日本は乗り遅れていることも見逃してはいけない。何も必ず専門を生かせる道を受け皿にするだけでなく、深い知識を身に付けた人が社会にいてくれればそれだけで社会にとってメリットになるわけですよ。それが情報基盤社会の時代に向けた国力を作る上での次世代大学院教育なわけです。
んで企業研究者でいったら、城さんが言ってる年功序列の硬直性があるわけです。大学の雇用もかなり硬直的だが、たとえば海外でも大学は終身雇用だから先進国の大学のポストは非常に少なく日本より難しいとこも多い。でも何で問題が起こってないかというと、民間の労働市場がうけ入れてくれる(専門もしくは専門外でも)からなんですよ。
またがちがちの年功序列の硬直性という要因だけでなく、日本企業は人間関係や社内特殊的な知(派閥)というのが物を言い、大学院で養われるような「普遍的な知」というものは評価されない。外資が博士を普通に取るってところにすべてが表れているように思います。
見てて寒気がしました。現実面での構造を理解せずに上からの教条的説教だけ身につけてしまったというようなパターンでしょう。若者の自己責任の部分にだけ過度に批判がよってってるのは勉強不足だからなのか、職業支援という職業柄からなのか。こういうステレオタイプの社長には何かを頼みたくない気がしますね。
雇用の流動化が行われ外部オプションが増えると博士側の意識が変わり、正の相乗効果が生まれそうな予感がしますが、雇用が硬直化し非ベンチャー指向では負の相乗効果が生まれる。そのような気がします。
確かに一理あると思いますが、欧米では国も国民も基礎研究というものにそれなりの高い評価・価値を見出している:その結果それなりの待遇を与えている、のに対し、日本がそうでもないってことがあるのでは、という気もします。ただ、欧米の研究者は厳しい競争社会であり、いくら教授とはいえポストはいつまでも安泰ではなく実績がなければクビという現実が待っています。そこは日本と違うとこでしょうか?
結局は、ここでも職能と職務の関係に行き着くのではないでしょうか?
大学4年生時に博士号取得のばかばかしさに気がついて、大学院試験には合格しましたが、
ベンチャー企業へ就職しちゃいました。
10年ほど前のことです。
周りの大人たちからは(特に団塊世代の親から)
非難ゴウゴウでしたが、今思えば正解でした。
*城さんの本で富士通を辞めるくだりを読んで、
少しだけ似てるなと思いました。(笑)
ポスドクといえば、藤井哲也先生がこういうポスドク蔑視の記事をかいていました。
http://korosuke.kyo2.jp/e123214.html
こういう偏見こそまさに俗流昭和的価値観であり、至らない者を生きづらくするものではないでしょうか?藤井先生だって、俗流昭和的価値観に照らし合わせれば2つの大きな過ちを犯しています。一つは社会人1,2年目は実家でパラサイトシングルをしていた点です。2つ目は企業をするために勤めていた会社を2年で辞めた点です。何れも保守的な言論人に叩かれても仕方がない行為であり、藤井先生が会社を辞めた行為は、城先生が富士通を辞められたのとどう違うと言いたいのでしょうか?
せっかく勉強してきたのに、それを活かせる場所が無いのはもったいないです。世間でのニーズを大学側は学生に教えるべきだと思います。
企業も大学もポストを提供できないとすれば、「ベンチャーかNPOでも立ち上げて頑張ってくれ、健闘を祈る!!」ってなりますよね。
ただ、これは日本だけの問題なのでしょうか?
工夫して効率を上げるよりも根性でやるのが大事みたいな昭和的価値観じゃ、ぜんぜん生産性が上がらない。
根性で長時間労働するよりも工夫して効率を上げる方がずっといいっていう世界じゃ当たり前の考え方に転換すれば、ホワイトカラーの生産性もルクセンブルグ並みにすることだってできるだろう。
そうすれば少子化が進んでも経済成長できるし、効率を上げて長時間労働を減らすことは少子化対策としても有効だ(子ども手当なんかよりずっと有効だと思う。)
そういうふうに昭和的価値観を転換する社会運動って必要だと思うんだけど、なんかいい方法やアイデアって誰か持っていませんか?
そこは正直に『たらい回し』と言いましょうよ。
人材採用が無計画に行われてるから、そういうことが必要になるんですよ。
>理系は引っ張りだこなんですかね。
そんなことないです。
理学や工学修士くらいまでで学部生と五十歩百歩。
博士に至っては豚に真珠。
外資系企業だけは別みたいですが、それもリーマンショックで新規採用は激減してますので、行き場を失った専門家はかなりいるでしょうね。
ホント、真面目に勉強するのがアホらしくなりますよ。上司のお気に入りに登録されればどんなアホでも出世できますから。逆に上司から嫌われればどんなに優秀でも冷や飯食わされますし。雇用の流動化が進めば冷遇されてる優秀な人材が生かされる世の中が来ると思いますが。
公務員も非正規だらけなんですね。知らなかった。
◆ピアニストを目指している人
(1)ピアニストになる前から、演奏活動で食えるようになる確率は小さいということを理解している。
(2)実際に(自称)ピアニストになってみて、コンサートを開いても客は来ない。CDを出そうとしても、大手レーベルからは相手にされず、自費製作しても誰も買ってくれない。
(3)「やっぱり駄目だった」と認識して、ピアニストの道をあきらめる。
◆博士を目指している人
(1)博士になる前からポストは少ないということを理解している。
(2)博士になってみたら、やっぱりポストはない。
(3)専門知識を活かそうとして、民間企業に就職しようとするも、採用してくれるところはない。
この2つ、何が違って、何が問題なのでしょう?
ピアニストを目指して頑張っても、ピアニストで食えない人はいっぱいいますが、誰も問題にしません。
なぜでしょう?
そもそも、なぜピアニストで食えないのでしょうか? それは、金を払ってまでピアノの演奏を聴きたいという人が限られているためです。
博士がなぜポストを得られないのか? それは、研究成果というものに対する社会ニーズが限られているからです。本当に研究者がいっぱい研究成果を出して、それで本当に社会が良くなるなら、研究者に対するニーズは増えそうですが、そうはなっていません。有り余るほどのポスドクを生み出すほど研究成果を出しているのに、「研究者がいい研究成果を出してくれたから社会が良くなった。もっと、研究者が活躍できる場を作ろう」とは誰も言いません。
私は、この問題の本質は、「社会のニーズを上回った人材供給をしたから、ニーズの無い部分が余った」ということだと思います。
人事制度的な問題より、国がニーズを見極めずに、供給を増やしたということに問題があると思います。
確かに能力の低い研究者がポストにしがみついているということはあるかもしれませんが、それは小さな問題だと思います。
法科大学院生も卒業しても法的素養を評価してもらえず、司法試験に合格しなかった場合、就職が難しい状況です。
さらに、最近では司法試験合格者も就職難です。
おっしゃる通りで、
企業の大学院卒業生への評価、人材の専門性への評価を高める必要がありますね。
社会で実務に使える大学院をというわけで、法科、会計などの大学院ができましたが、それに学生は取られて、地道に研究者を目指す人は払底しました。
一方で、諦めムードで大学院に10年もいると人はいろんな意味で壊れます。特に文系では、壊れてる→業績が出ない→ますます壊れるのスパイラルを回っている人が多く、こういう人たちはなにしろ「批判」することで、自我の拠り所にするので、なるほど確かに使えない。しかも中途半端に頭はいいから、ありとあらゆる批判を思いつきます。
博士号取得者の処遇も問題ですが、博士号をきちんとした水準でのみ出し(理学部なんかでは査読付英文論文3報以上などかなり厳しい。理系だと医学博士だけ楽チンで、あれは開業医の箔をつける機能しかない)基本的には世界に通用する水準にする必要があります。
しかし、そうすると、大学院は基本的に知の世界でのオリンピック強化選手の養成所になりますから脱落者もそれなりに出ます。この脱落者たちは必ずしもさぼっているわけではないので、きちんと復活可能な社会になっておく必要があります。
ただし、大学の先生たち自身が一部以外そんな力量もなく、なかなかうまく回りそうにもありません。
結局、大学院のレベルを下げるだけに終わったなー、というのが実際のところでしょう。
主にどんな学部の人が余ってるんでしょう?
大手なら自社で研修させればいいのかもしれませんが、中小なら専門知識(ツブシのきかないマニアックな分野でも)を持ってる人を欲しがる人も居そうに思いますが。
文系だと、経営・会計・経済関連なんかもあまってるんでしょうか。ウチで採用したいなあ^^;
しかし日本の「学校で勉強した事なんて仕事の役には立たない」という発想は本当に根深いですね。んなモノに血道をあげる受験てなんなんでしょう。それなら全員中卒で働かせれば良いのに。
知識がお金に変わることを知らないんでしょうかね。そりゃ外国企業に勝てねえわ。
小沢選挙を見ていても、感心する反面、日本人てのは本当に愚直が大好きなんだなとあきれてしまいますわ。
すべて抱え込むかですかね。
大前研一さんも述べておられますが日本の企業が
求めている人材の性質と実際に生産される博士の性質
にギャップがあるので解決は難しいかもしれませんね。
日本の企業は一般にできるだけ真っ白な学卒を望みますが博士課程まで学んだかたは当然専門を生かして仕事をしたいと思います。日本の大企業は人事部から経理部へ異動させるなんてことを平気でやりますからそういった柔軟性を求められると博士のかたは難しい。(と少なくとも周りは思う)。米国でも博士過程での研究がキャリアに生かされるのは卒業してから2-3年が限度のようですから日本ではなおさらアカデミックな世界で生きていくことを前提に人生設計するしかないかもしれません。