
佐野眞一の『阿片王』には、「男装の麗人」という時代がかったことばが出てくる。
まずは、梅村淳という、阿片王=里見甫(はじめ)の周囲を彩った女性の一人が登場する。
「一言でいうなら、男装の麗人です。いつも背広にネクタイ、ズボンという服装なんです。髪の毛も七・三の断髪でした。」
との証言が紹介されている。
また、有名な人物としては、「東洋のマタハリ」と称せられた川島芳子(1907 - 48)。
「新京への帰りの列車中に、断髪洋装で、黒い皮の膝までの長靴(ブーツ)をはいている麗人が入ってきて少し離れた座席をとった」
「清朝王族の末裔に生まれた川島は、関東軍の密命で、後に満州国皇帝となる宣統帝溥儀の后の婉容(ワンロン)を天津から脱出させる男まさりの行動で有名な男装の麗人だった。」(佐野眞一『阿片王』)
「男装の麗人」なることばは、おそらく水の江滝子(ターキー。1915 - )を嚆矢とするだろう。
松竹歌劇団(SKD)の男役で、断髪男装姿が人気となったのは、1930年代のことである。
彼女たちの場合には、必要性からという以上に、ファッションという面があったようだが(「男装の麗人」ということば自体が、ファッション性を帯びている)、明治初めの女性の社会進出においては、男装せざるを得なかった(男性の職業とされていた分野に進出するにあたっては特に)。
例えば、荻野吟子(1851 - 1913)の場合。
政府公許の女医第1号である荻野吟子は、その医学生時代に、
「服装は着流しを改め、海老茶の袴を着け素足に日和下駄という男と変わらぬ身装(みなり)にした。」(渡辺淳一『花埋み』)
あるいは、
「ことさらに束髪に素顔で、着物には紺の袴という、ちょっとみると男かと見間違うような服装」(渡辺、前掲書)
であったという。
これは「男装の麗人」というような余裕のあるものではなく、男社会であった医学の世界に入るために、やむを得ず採った服装である。
そして現代、どのような服装であろうが、問題とされないように思えるが、はたしてそうだろうか。
むしろ「空気」としての「同調圧力」は、依然として強いのではないのか。
成人式の振袖姿を初めとして、卒業式の袴姿、入社式での女性の黒っぽいスーツ姿、などなど(男性の場合は、祝儀不祝儀でのドスキンの略礼服)。
そして、それを「圧力」としてすら感じないような感性が生まれているのは、かえって不気味である。










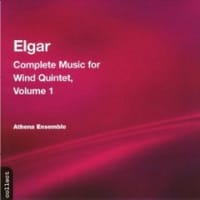
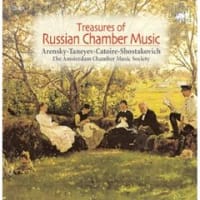
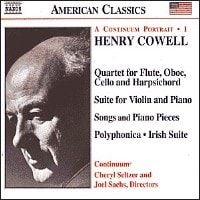

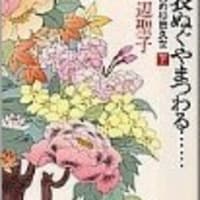
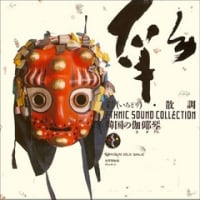
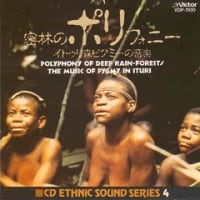
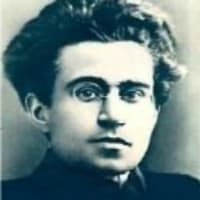
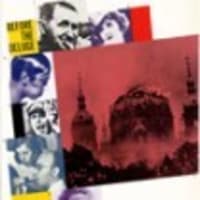
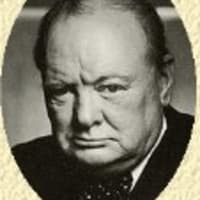
そして私も、近年この圧力が、すごく強まっている気がします。
この真綿で首を絞めるような抑圧が、すごくイヤ。
4月1日に町を歩いたら、黒っぽいスーツ姿の若い女性がわさわさいて(入社式か、会社訪問か、両方か)不気味でした。
なお「同調圧力」ということばは、
おそらく社会学系の専門用語だったはずです。
「空気」は例の「山本七平」が
日本社会の特徴として
述べていたと思います。
それはともかくとして、
同調圧力は、理由をことばでは述べずに
>真綿で首を絞めるような抑圧
として、視線や態度で表されることが多いので、
余計に不気味なんでしょうね。
では、また。