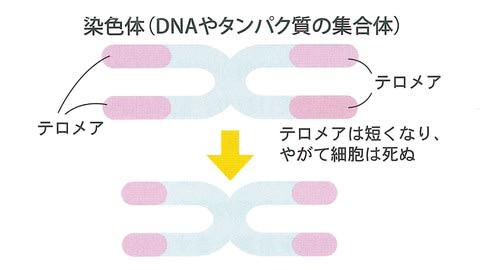今年もあと少しで終わりです。今年はコロナ、コロナの1年でしたね・・・。年末年始も不要不急の外出自粛などにより何かとストレスを感じることが多いと思います。コロナ禍の中では、「常に感染予防に気を遣う」「暗いニュースが多い」「外出しない・人と会わない・話さない」「自粛によるPCやスマホの見過ぎで目が疲れる」などの生活変化によるストレスや不安感を抱えることが増えますよね・・それで今回はストレスの解消方法(心がラクになる方法)を紹介することにします。
ストレスの解消法としては、運動や瞑想、リラクゼーションなどがあります。これらは多幸感をもたらすエンドルフィン等の分泌を増加させたり、免疫力を高めたりする効果があると言われていて、「運動の習慣化」や「マインドフルネス瞑想」は、科学的にもその根拠が証明されています。運動をすると筋肉から様々な種類のマイオカインというホルモンが分泌され、中にはドーパミン神経細胞を守り、うつ病予防の機能を持つものや、ストレスによる神経毒性物質が脳に到着する前に無害化する機能を持つものなどがあります。
マイオカインを分泌させるために激しい運動をする必要はなく、大切なのは「運動の習慣化」ということのようです。例えば、近所で出来るウォーキングやサイクリングなどを続けることでも効果があるそうです。また、週3回の運動を6週間続けると、不安を軽減する脳の領域の神経結合が増えることが明らかになっています。さらに、定期的な運動は脳の構造を変化させ、ランナーズハイなどの運動による高揚感を感じやすくさせます。このように「運動の習慣化」は、体だけでなく心の健康を整える方法としても有効と言えます・・。
「運動の習慣化」よりも、すぐに効果が得られる(心がラクになる)のが「マインドフルネス瞑想」だそうです。ネガティブな感情や痛みに関係する脳の部位の活動が減少し、精神的・肉体的な痛みが感じにくくなると言われるマインドフルネス瞑想は、最近の研究では、初めて実践する場合でも、その効果が得られるということが明らかになっています。マインドフルネス瞑想のポイントは、「今、この瞬間」に意識を集中させることですが、取り組みやすいのは呼吸に意識を向ける方法で、鼻の穴、胸やお腹の動きなどに注目して呼吸を観察します。瞑想中に他のことを考えてしまったら、また意識を呼吸に戻すようにします。1日5~10分ほどでいいそうなので、休憩時間や就寝前などの隙間時間に実践してみてはいかがでしょうか。慣れてくれば電車での移動中などの隙間時間でも出来るようになるらしいですよ・・。
という事で、コロナ禍によるストレスや不安感は来年も続きそうなので、心と身体に異変をきたす前に生活の中で上手く解消していくよう気を付けましょう。それでは、この記事が今年最後の記事になると思いますので、みなさん良いお年を(来年はコロナが終息して日常が戻りますように・・・。)