前回の記事を書いたのが昨年の11月だったので、冬の間はブログ更新が冬眠していたという事になりますね・・・。どういうワケか、ブログ更新が冬眠していた期間にアクセス数が増えましたけどね(記事を書かない方がアクセス数が増えるのかな?)。前回記事でお話しました冬鳥のジョウビタキは、もう春になったので見かけなくなりました。大陸に帰ってしまったのでしょうね。なので、そろそろ私も冬眠から覚めて(ちょっと遅いか)、記事を書こうかなぁ・・と思った次第です。という事で、今回は18回目の「いろいろ独り言シリーズ」です。いろいろと独り言を列記していきます。
まずは、前述しましたブログ更新が冬眠していた期間にアクセス数が増えたというお話です。まぁ、記事を書かないほうがアクセス数が増えるという事はないでしょうから、たまたま・・偶然なのでしょうけど、なぜか昔の古い記事へのアクセスが増えています。このブログも17年目に入っていますから、昔の古い記事はたくさんあります。ブログを始めた頃は毎日のように記事を書いていましたから、ブログ初期の記事の方が圧倒的に多いです。少し前までブログ初期の古い記事へのアクセスは、そんなにはありませんでした。偶然なのか・・何かそのような傾向になる要因があるのか分かりませんが、古い記事へのアクセスが4~5か月ぐらい前から増えています。
それで、アクセス解析に出てくる古い記事のタイトルを見ていると、タイトルだけで記事の内容を覚えているものもあれば、全く記事の内容を覚えていないものもあります。覚えている記事は懐かしい思いから、覚えていない記事は何を書いていたのかという気持ちから、それぞれ読み返してみると、内容の寒い記事もあれば結構調べて濃い内容になっている記事もあったり、ノリノリで書いている記事もあったりします。寒い記事については、このときは時間がなかったのだろうなぁ・・とか、濃い記事については、このときは暇だったのかなぁ・・と思いながら読み返していました。ブログは日記のようなものですから(このブログはそうでない記事も多々ありますが)、昔の古い記事を読み返していると、この記事を書いていた時は、あの工事現場に通っていた頃だなぁ・・とか、こんなプロジェクトもあったなぁ・・、この頃はこんな想いで建築に取り組んでいたんだなぁ・・この頃に比べると最近は建築への情熱が足りていないかも・・と志を新たにしたりできるので、古い記事を読み返してみるのもなかなか良いものです。私は今まで古い記事を読み返すという事をしていませんでしたが、たまには古い記事を読み返してみようと思っています。
話は変わりまして、今日はF1第3戦となる日本グランプリ決勝レースを観ていました。レースは、ポールポジションからスタートしたマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝し、鈴鹿サーキットで4年連続のポール・トゥ・ウィンを達成しました。開幕2戦ではマクラーレンが勝利していたので、フェルスタッペンがここまで完璧なレース展開で勝利を収めるとは正直思っていませんでした。レッドブルとのパートナーシップが最終年となるホンダのホームレースで素晴らしいパフォーマンスをみせてくれた事を称賛したいです。レース全体としては、展開に影響を与えるようなオーバーテイクもなく、単調なレースだったので少し退屈でした・・。実際のところ、予選でトップ6に入ったドライバー全員が決勝でも同じ順位でフィニッシュしていますからね。とは言っても、細かなところでは見どころは色々あったかな・・話すと長くなるのでやめておきますね。それにしても、現行のレギュレーションが最終年となる今シーズンは、マシンデザインの収束だけでなく、オーバーテイクを促進するために導入されたルールを回避する方法もチームによっては見つけ出されています。レースでのオーバーテイクは貴重なものとなるでしょうから、例年になく予選の順位が重要になりそうですね。
日本グランプリの直前にトップチームであるレッドブルに移籍した角田裕毅は、予選の14位から2つ順位を上げて12位でレースを終えました。扱いにくいRB21(レッドブルの2025年型マシン)を操る初めてのグランプリなので、このレース結果は仕方ないと言うか・・健闘した方だと思います。予選では速さを魅せるシーンもありましたし、レースタイムも悪くはなかったです。ただ、14位からのスタートだとポイント圏内(10位以内)に入るのは難しいので、予選が課題になりそうですね。本人も予選の入り方(タイヤの温め方)が難しかったとコメントしていますから、次戦よりこのあたりが改善できれば良い結果が出てくると期待したいです。まぁ、本音を言えば・・角田裕毅がレッドブル移籍後の母国グランプリで世界を驚かすような結果を出してくれる事を期待していたのですけどね(私だけではないと思いますが・・)。

画像はRB21を操る角田裕毅です。日本グランプリでのRB21には、ホンダF1が1965年に初優勝したマシン「RA272」をトリビュートした特別カラーリングが施されており、日本国旗をモチーフとしたスタイルが再現されています。今シーズンは、レッドブルとホンダのパートナーシップ最終年である事に加え、ホンダが初めてF1で勝利した1965年メキシコGPから60周年でもあるので、このカラーリングが実現しました。私は、このカラーリングが気に入っているので、残りのレースもこのカラーリングで走ってほしいと思うのですが、そういうワケにはいかないでしょうね・・。
最後に、建設コスト高騰に関するお話を少しします(ほとんどボヤキですけどね・・)。建築資材の高騰が騒がれて久しくなるように思われますが、さらに・・ここ3年程で急激に価格が上昇しています。私の感覚では3年で3割程度上昇していると思います。それまでにも少しずつ建設コストは上昇していますので、2016年ベースで比べると5~6割は上昇しています。資材の高騰だけでなく、人手不足による人件費の上昇も加わって、建設コスト全体が高騰しているのです。なので、建物を計画(設計)しても予算が合わず、延期や中止になるプロジェクトも少なくありません。
つい先日も、予算がオーバーするプロジェクトがあって、建物規模を縮小した減額プランを再見積りしたのですが、それでも予算が合いませんでした(工事がやりにくい立地条件だった事もあるのですが・・)。どうすればいいのか・・と工務店に相談すると、建物規模を半分にして予算が合うか合わないぐらいだと言うのです。建物を半分にして機能が成り立つのか・・という事です。このプロジェクトも実現する事が困難になってしまうかも知れません。工務店から「3年前でしたら、予算内で建っていました」と言われると、悔しいというか何というか・・やりきれない気持ちになります。まぁ、そんな事もあって、最近では建物を計画しても、どうせ予算が合わないだろうなあ・・と思ってしまいがちです。それでも有難いことに追加の予算を出してくださる施主さんもおられるので、進行しているプロジェクトもあります。なので、ぼやいていてはいけませんね。
という事で、今回のいろいろ独り言はこれぐらいにしておきます・・・。














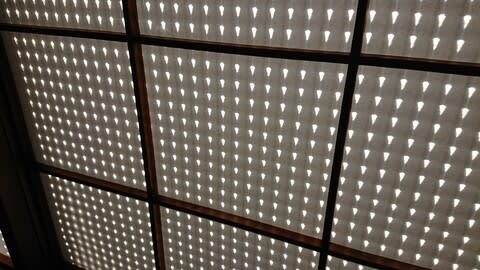







 [Photo 西岡千春]
[Photo 西岡千春]




