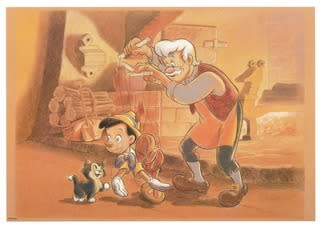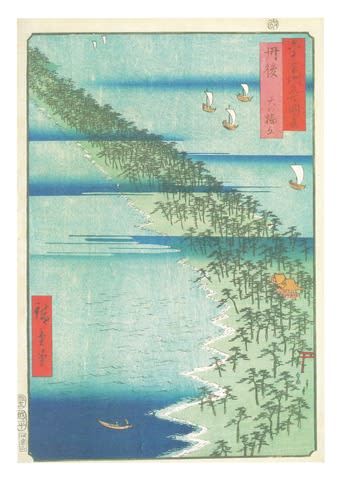今日は本格的な雨降りでしたね・・・。前回の記事でお話しました皇子が丘公園の池で見かけるマガモのつがいですが、1週間ほど前に公園の池を通ったときには、まだ池にいました。居心地がいいのか・・このままだと本当に池で繁殖してマガモの親子を見かける日が来るかも知れません。という事で、今回は久しぶりの「いろいろ独り言シリーズ」です。いろいろと独り言を列記していきます。

まず、画像は先週の金曜日(4月23日)に撮影した日暈(ひがさ)です。とは言っても、日暈とは知らずに太陽の周りに輪ができているので珍しいと思って撮影したものです・・。ネットで調べてみると今週の火曜日(27日)に大阪市の上空で日暈が確認されたそうですが、大津市では23日に日暈が現れていました(撮影したのは午前11時25分)。日暈は薄雲の中の氷の結晶によって太陽の光が屈折されて、虹色や白っぽく見られるもので、視野半径角22度のところに現れるそうです。通常の虹とは違って、上空の薄雲を構成する氷の粒によって太陽光が内側に曲げられて(屈折して)、光の強い部分が環状に見えることから、画像のような現象になるようです。

話は変わりまして・・画像に写っているのは、わが家に咲いているパンジーとビオラです。パンジーとビオラって、「どこが違うの?」っていう事になりますよね・・。ずっと以前の記事でもお話しましたが、ビオラは、スミレ科スミレ属の多年草。ヨーロッパの野生のスミレから改良されたものでガーデンパンジーとも呼ばれています。日本では、小輪系のパンジーをビオラと呼んでいますが、両者(パンジーとビオラ)は容易に交配して採取できるため厳密には区別できないという事になります。
ちなみに、園芸界では、一般的に花の大きさが5cm以上のものをパンジーと呼び、5cm以下の花を咲かせるものをビオラと呼んでいます。しかし、パンジーもビオラも品種改良が進み、多くの種類が流通していて、パンジーでも花が小さいものもあれば、花の大きいビオラもあり、さらにはパンジーとビオラの中間の大きさの花を咲かせる品種を「パノラ」と呼んだりするようで、実際には明確な線引きはないと言ったほうが良いのかも知れません。
という事で・・わが家に咲いているのは、園芸界で言えば画像の両端に咲いている大きな花がパンジーで、中央に咲いている小さい花がビオラという事になりますね・・。

最後に、明日から第3戦ポルトガルGPが開催されるF1のお話です。今シーズン限りでF1から撤退するホンダにとって、タイトルを獲得する最後のチャンスとなるシーズンですが、それは決して夢物語ではありません。ホンダF1は、今シーズンに向けて総力を結集し「新骨格」と称する完全に新しいF1エンジンを導入しており、開幕からの2戦でレッドブル・ホンダF1は、王者メルセデスF1と互角の戦いを演じています。
レッドブル・ホンダの2021年F1マシンであるRB16B(画像)は、開幕からの2戦で最速マシンとしての地位を証明したと言えます。これは、レッドブル・ホンダF1のマシンがフロアの縮小やディフューザーの寸法などを変更した2021年のレギュレーションの影響を最も受けていないと見られており、また、メルセデスF1とは異なり、レッドブルは代々「ハイレーキ」コンセプトを採用していることも規則変更の影響を受けにくかった一因だと考えられています。
なので、現時点では、レッドブル・ホンダ がメルセデス よりも優位に立っていると考えて良いと思います。しかし、レッドブル・ホンダのアドバンテージは小さく、メルセデスはすでにプレシーズンテストからパフォーマンスを大きく取り戻しています。2022年には大幅なレギュレーション変更が待ち受けているので、タイトルを狙うレッドブル・ホンダとメルセデスにとっては、どちらが先に開発レースから手を引くか・・我慢比べの戦いでもあるように思います。
今シーズン、ホンダはF1エンジン(パワーユニット)を大幅に改善させましたが、RB16Bの空力面のアドバンテージを差し引けば、メルセデスのF1エンジン(パワーユニット)の方がまだアドバンテージがあると考えられるので、今後予想される激しいマシン開発に勝ち抜けば、F1ラストイヤーとなる今シーズンのタイトル獲得が現実のものとなると信じたいです。まずは、明日からのポルトガルGPに勝って、ホンダとしてのF1通算80勝目を飾ってもらいましょう・・。
という事で、今回のいろいろ独り言は終わりにします・・・。