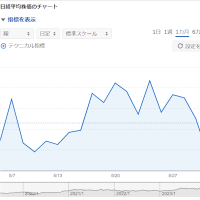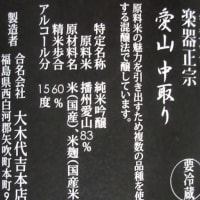■天使たちの探偵 2023.10.9
原尞のただ一冊の短編集『天使たちの探偵』が刊行されたのが、1990年。
天使たちとは、「今を生きにくい少年、少女たち」。沢崎は、彼らに係わり励ましていく。
文庫化にあたり書き下ろされた(1997年)「あとがきに代えて----職業としての探偵/探偵志願の男」のなかで、「沢崎がどうして探偵になったのか」が語られる。
文庫化される前に、『天使たちの探偵』を読まれた方は、その経緯をご存じでないかも知れませんね。
経緯ついては、後ほど記述します。
沢崎が、俊一に「天使たちのその後」の消息を訊ねると、
翼をなくした天使たちのその後は、予想した通り平坦なものではなかったが、それでも健気に生きているようだった。
この言葉には、ほっとするとともになぜかうれしかった。
今も、沢崎の心には、翼をなくした天使たちが生きているからだ。

俊一は何か反論しようとでもするように口を開きかけたが、私はそれを制して続けた。「きみは自分を暴力団から助け出したのは、おれや草薙さんだと思っているようだが。それがそもそも間違っている。きみを助けたのは、私を雇ったきみの母親だ。きみの母親がおれの依頼人になっていなければ、おれはきみに会うことなどなかった。たとえきみの母親がおれの依頼人になったとしても、もし探偵料を払ってくれなければ、おれは何もしなかった。きみを助けたのは、きみの母親が働いて稼いだ大事な母子二人の生活費から、おれが法外に高く捲きあげたあの探偵料なのさ。そんな単純な経済原理も忘れているから、ここで無報酬で働きたいなどと馬鹿なことが言えるんだ。世の中には無報酬で学ばなければならないような仕事もあるだろうが、探偵の仕事がそんなものでないことはおれが保証する」
俊一は私の偽悪的な口調に微笑をもらしていたが、やがてまじめな顔に戻って言った。
「沢崎さんが本気で自分の仕事のことをそんなふうに考えていらっしやるとは信じられませんよ。探偵という仕事は、もっと男の生き方というか、生きざまというか、そういうことに深く根ざした……どう言ったらいいのか、ぼくにはうまく表現できませんが、とにかく、自分の信ずるところにこだわりをもって----」
「どこでそんないい加減なことを憶えてきたんだ? 探偵というのはただの職業さ。胡散臭くて、卑しくて、しがない、ただの職業だ。それ以上でも、それ以下でもない。そんな職業であるという覚悟もできていないようでは、きみは単に訪ねる場所を間違えただけの話だ」
俊一はじっと私の眼を見つめた。そうしていれば私が意見を翻してくれるのではないかというように。だが、やがてその眼を伏せて、力のない声で言った。
「そうですか……どうもすみませんでした。突然お訪ねしたりして……」
彼は両手で持っていたグレーのコートを握りなおして、腰を浮かそうとした。だが、もう一度坐りなおして言った。
「一つだけおうかがいしたいんですが、沢崎さんは探偵の仕事を始められる前は、何をなさっていたんですか」
「それを訊いてどうするんだ?」
「いえ、どうするというわけではありませんが、草薙の小父さんが、たぶん以前は警察の仕事をされていたのではないかと言っていたので」
「いや、おれは警察に勤めたことは一度もない」私は少し考えてから言った。おれに探偵の仕事を教えてくれた男で、渡辺というおれの以前のパートナーは元刑事だった。死んでしまったがね。あるいはその男と混同しているのだろう」
「お母さんは、元気なのか」
「ええ、何とか。夜の勤めなどで無理をしたせいか、四十七才という年齢のわりにはときどき身体の不調を訴えることもあるんですが、大したことはないようです」
「無報酬で働くなどと。そんなことを言っていられる身分じゃないな」
「……そうですね」俊一は大事な約束を思い出したときのように、大きく深呼吸して背筋を仲ばした。
「最後にもう一つだけおうかがいしたいんですが、沢崎さんはどうして探偵になられたんですか」
私は答えを拒否することも、適当な話ですませてしまうこともできた。それがこういう時の私のいつもの反応の仕方だった。だが、何故かそうする気になれなかった。私が探偵になった経緯など別に大したことではなかったが、パートナーだった渡辺と私以外には誰も知らないことだった。渡辺か死んだ今になってみると、それを誰かに聞いてもらいたかったのかも知れない。あるいは、結局のところ何一つ相談にのってやることのできなかった眼の前の若者に対する、それがせめてもの誠意のように思えたのだろうか。
「もう二十年以上も昔のことだ。七〇年代の半ばのことで、おれはもうすぐ三十才になろうとしていた。しがない大学を出て入ったしがない会社が四年でつぶれて、つぎに勤めた会社も二年半ぐらいで倒産してしまった。しばらく職探しをしてから、三つ目の会社に入ったんだが、おかしなことに勤めを替わるたびに会社は大きくて立派になり、給料も上がっていったな。あの時分にはそんなことも珍しくなかったんだ」
私はタバコに火をつけてから話を続けた。
「その三つ目の会社に入ってしばらくすると、今でも名前を憶えているが服部という専務に内密に呼ばれて、本社に付属する研究所勤務を命じられた。そこではこの数年、社運を傾けかねないような重大な企業秘密に属することが、数度にわたって漏洩している疑いがあると言うのだ。すでに半月ほど前から、ある探偵を雇って調査を開始しているのだが、部外の人間が研究所の外から調べているだけでは埓があかず、どうしても研究所内にその探偵と連携して調査をすすめる社員か必要だと言うのだ。三十才になろうという新人りの社員が重役の命令に否やが言えるわけがない。おれは前に勤めていた会社が建築に関する会社でそういう知識も多少あったので、研究所を拡張し新築するための下調べと称して研究所に出向し、所員全員から新しい研究所についての意見や希望を訊くという名目で彼らと接触することになった」
俊一は興味深そうな顔で私の話に聞きいっていた。私はタバコの灰を灰皿に落として、先を続けた。
「服部という専務の目論見通り、研究所の内と外からの調査が功を奏して、一ヵ月もたたないうちに新製品の設計図や重要書類を持ち出そうとしていた犯人を特定することができた。十年以上も勤続していた中堅の研究所員だった。そこまではよかったが、懸案の問題が解決して喜びすぎた専務が、その功労者としておれの名前を漏らしてしまったのがまずかった。もう誰もおれのことをまともに同僚として扱ってくれる者はいなくなった。研究所勤務からは解放されたが、そういう噂はすぐに広がるもので、おれの行くところ、重役の息のかかった監視者に対するように妙に鄭重な態度をとる者や、露骨にスパイ呼ばわりして嫌悪感を表に出す者ばかりだった。当然と言えば当然の反応だかね。
そんなことを気にするおれでもなかったが、お互いに仕事もできないような状態ではしようがない。それに会社を替わるたびに給料が上がるという気楽な時世でもあったし、一週間ばかり我慢をしたあげく、おれは会社を辞めた。そして、研究所の内と外で協力しあった探偵の渡辺という男の事務所----つまり、この事務所を訪ねることにしたんだ」
「探偵になるために、ですね」
私はタバコを消しなから言った。「いや、依頼人になるためだ」
「えッ? どうしてなんですか」俊一は意外そうな顔で訊いた。
「服部専務を調査してもらうためだ。数週間後には、おれたちが挙げた中堅の研究所員は言わばトカゲの尻尾切りで、秘密漏洩の主犯は服部専務だったことを突きとめた。問題が大きくなっていたので、誰かスケープゴートを出しておかなければ、いずれは疑惑が自分に向かう可能性が高いと判断してのことだろうな。尻尾は主犯の口ききで、九州にある同種の会社の研究所に無事転職していたよ。その調査のかなりの部分を、おれはまだその会社に在籍しているように装って、渡辺の仕事を手伝った。そしてすべてか終わったときには、おれは半ばこの事務所に勤めているような恰好になっていたんだ。探偵になる決心など一度もしたことはない」
柏木俊一は納得したような表情で私の話を聞き終わった。
私が俊一のあの当時の不良仲間と見られていた子供たちの消息を訊ねると、彼は自分のことよりも詳しく熱心に教えてくれた。翼をなくした天使たちのその後は、予想した通り平坦なものではなかったが、それでも健気に生きているようだった。......
「それで、三回目の転職でも給料は上がったんですか」
「激減した。しかし、もちろん無報酬ではなかった」
柏木俊一は笑いながら、事務所を出て行った。そのとき八年前の少年の面影がかすかに感じられた。
『 天使たちの探偵/原尞/ハヤカワ文庫JA 』
原尞のただ一冊の短編集『天使たちの探偵』が刊行されたのが、1990年。
天使たちとは、「今を生きにくい少年、少女たち」。沢崎は、彼らに係わり励ましていく。
文庫化にあたり書き下ろされた(1997年)「あとがきに代えて----職業としての探偵/探偵志願の男」のなかで、「沢崎がどうして探偵になったのか」が語られる。
文庫化される前に、『天使たちの探偵』を読まれた方は、その経緯をご存じでないかも知れませんね。
経緯ついては、後ほど記述します。
沢崎が、俊一に「天使たちのその後」の消息を訊ねると、
翼をなくした天使たちのその後は、予想した通り平坦なものではなかったが、それでも健気に生きているようだった。
この言葉には、ほっとするとともになぜかうれしかった。
今も、沢崎の心には、翼をなくした天使たちが生きているからだ。

俊一は何か反論しようとでもするように口を開きかけたが、私はそれを制して続けた。「きみは自分を暴力団から助け出したのは、おれや草薙さんだと思っているようだが。それがそもそも間違っている。きみを助けたのは、私を雇ったきみの母親だ。きみの母親がおれの依頼人になっていなければ、おれはきみに会うことなどなかった。たとえきみの母親がおれの依頼人になったとしても、もし探偵料を払ってくれなければ、おれは何もしなかった。きみを助けたのは、きみの母親が働いて稼いだ大事な母子二人の生活費から、おれが法外に高く捲きあげたあの探偵料なのさ。そんな単純な経済原理も忘れているから、ここで無報酬で働きたいなどと馬鹿なことが言えるんだ。世の中には無報酬で学ばなければならないような仕事もあるだろうが、探偵の仕事がそんなものでないことはおれが保証する」
俊一は私の偽悪的な口調に微笑をもらしていたが、やがてまじめな顔に戻って言った。
「沢崎さんが本気で自分の仕事のことをそんなふうに考えていらっしやるとは信じられませんよ。探偵という仕事は、もっと男の生き方というか、生きざまというか、そういうことに深く根ざした……どう言ったらいいのか、ぼくにはうまく表現できませんが、とにかく、自分の信ずるところにこだわりをもって----」
「どこでそんないい加減なことを憶えてきたんだ? 探偵というのはただの職業さ。胡散臭くて、卑しくて、しがない、ただの職業だ。それ以上でも、それ以下でもない。そんな職業であるという覚悟もできていないようでは、きみは単に訪ねる場所を間違えただけの話だ」
俊一はじっと私の眼を見つめた。そうしていれば私が意見を翻してくれるのではないかというように。だが、やがてその眼を伏せて、力のない声で言った。
「そうですか……どうもすみませんでした。突然お訪ねしたりして……」
彼は両手で持っていたグレーのコートを握りなおして、腰を浮かそうとした。だが、もう一度坐りなおして言った。
「一つだけおうかがいしたいんですが、沢崎さんは探偵の仕事を始められる前は、何をなさっていたんですか」
「それを訊いてどうするんだ?」
「いえ、どうするというわけではありませんが、草薙の小父さんが、たぶん以前は警察の仕事をされていたのではないかと言っていたので」
「いや、おれは警察に勤めたことは一度もない」私は少し考えてから言った。おれに探偵の仕事を教えてくれた男で、渡辺というおれの以前のパートナーは元刑事だった。死んでしまったがね。あるいはその男と混同しているのだろう」
「お母さんは、元気なのか」
「ええ、何とか。夜の勤めなどで無理をしたせいか、四十七才という年齢のわりにはときどき身体の不調を訴えることもあるんですが、大したことはないようです」
「無報酬で働くなどと。そんなことを言っていられる身分じゃないな」
「……そうですね」俊一は大事な約束を思い出したときのように、大きく深呼吸して背筋を仲ばした。
「最後にもう一つだけおうかがいしたいんですが、沢崎さんはどうして探偵になられたんですか」
私は答えを拒否することも、適当な話ですませてしまうこともできた。それがこういう時の私のいつもの反応の仕方だった。だが、何故かそうする気になれなかった。私が探偵になった経緯など別に大したことではなかったが、パートナーだった渡辺と私以外には誰も知らないことだった。渡辺か死んだ今になってみると、それを誰かに聞いてもらいたかったのかも知れない。あるいは、結局のところ何一つ相談にのってやることのできなかった眼の前の若者に対する、それがせめてもの誠意のように思えたのだろうか。
「もう二十年以上も昔のことだ。七〇年代の半ばのことで、おれはもうすぐ三十才になろうとしていた。しがない大学を出て入ったしがない会社が四年でつぶれて、つぎに勤めた会社も二年半ぐらいで倒産してしまった。しばらく職探しをしてから、三つ目の会社に入ったんだが、おかしなことに勤めを替わるたびに会社は大きくて立派になり、給料も上がっていったな。あの時分にはそんなことも珍しくなかったんだ」
私はタバコに火をつけてから話を続けた。
「その三つ目の会社に入ってしばらくすると、今でも名前を憶えているが服部という専務に内密に呼ばれて、本社に付属する研究所勤務を命じられた。そこではこの数年、社運を傾けかねないような重大な企業秘密に属することが、数度にわたって漏洩している疑いがあると言うのだ。すでに半月ほど前から、ある探偵を雇って調査を開始しているのだが、部外の人間が研究所の外から調べているだけでは埓があかず、どうしても研究所内にその探偵と連携して調査をすすめる社員か必要だと言うのだ。三十才になろうという新人りの社員が重役の命令に否やが言えるわけがない。おれは前に勤めていた会社が建築に関する会社でそういう知識も多少あったので、研究所を拡張し新築するための下調べと称して研究所に出向し、所員全員から新しい研究所についての意見や希望を訊くという名目で彼らと接触することになった」
俊一は興味深そうな顔で私の話に聞きいっていた。私はタバコの灰を灰皿に落として、先を続けた。
「服部という専務の目論見通り、研究所の内と外からの調査が功を奏して、一ヵ月もたたないうちに新製品の設計図や重要書類を持ち出そうとしていた犯人を特定することができた。十年以上も勤続していた中堅の研究所員だった。そこまではよかったが、懸案の問題が解決して喜びすぎた専務が、その功労者としておれの名前を漏らしてしまったのがまずかった。もう誰もおれのことをまともに同僚として扱ってくれる者はいなくなった。研究所勤務からは解放されたが、そういう噂はすぐに広がるもので、おれの行くところ、重役の息のかかった監視者に対するように妙に鄭重な態度をとる者や、露骨にスパイ呼ばわりして嫌悪感を表に出す者ばかりだった。当然と言えば当然の反応だかね。
そんなことを気にするおれでもなかったが、お互いに仕事もできないような状態ではしようがない。それに会社を替わるたびに給料が上がるという気楽な時世でもあったし、一週間ばかり我慢をしたあげく、おれは会社を辞めた。そして、研究所の内と外で協力しあった探偵の渡辺という男の事務所----つまり、この事務所を訪ねることにしたんだ」
「探偵になるために、ですね」
私はタバコを消しなから言った。「いや、依頼人になるためだ」
「えッ? どうしてなんですか」俊一は意外そうな顔で訊いた。
「服部専務を調査してもらうためだ。数週間後には、おれたちが挙げた中堅の研究所員は言わばトカゲの尻尾切りで、秘密漏洩の主犯は服部専務だったことを突きとめた。問題が大きくなっていたので、誰かスケープゴートを出しておかなければ、いずれは疑惑が自分に向かう可能性が高いと判断してのことだろうな。尻尾は主犯の口ききで、九州にある同種の会社の研究所に無事転職していたよ。その調査のかなりの部分を、おれはまだその会社に在籍しているように装って、渡辺の仕事を手伝った。そしてすべてか終わったときには、おれは半ばこの事務所に勤めているような恰好になっていたんだ。探偵になる決心など一度もしたことはない」
柏木俊一は納得したような表情で私の話を聞き終わった。
私が俊一のあの当時の不良仲間と見られていた子供たちの消息を訊ねると、彼は自分のことよりも詳しく熱心に教えてくれた。翼をなくした天使たちのその後は、予想した通り平坦なものではなかったが、それでも健気に生きているようだった。......
「それで、三回目の転職でも給料は上がったんですか」
「激減した。しかし、もちろん無報酬ではなかった」
柏木俊一は笑いながら、事務所を出て行った。そのとき八年前の少年の面影がかすかに感じられた。
『 天使たちの探偵/原尞/ハヤカワ文庫JA 』