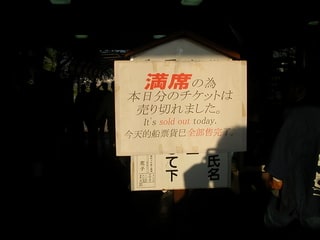保津川の渓谷は日に日に紅葉がすすみ
見頃に近づいています。
船の上から見上げるもみじの葉は、その先の部分から
赤みがかかり、一枚の葉に数色が浮びあがり雅さを
かもし出します。

嵐山も先月の予想では「紅葉が1~2週間遅れる」
とのことでしたが、例年並みに近づいているようです。
‘もみじ’だけでなく、けやきなど雑木も朱色に色つき始め、
緑と相まって見事なコントラストを描き出しています。
今週末あたりからいよいよ嵐山は
見頃の季節を迎えそうですね!
☆《明日の保津川下り予報》
明日の予約数 33隻(午前中に20隻)
待ち時間予想 30分前後’(的中率90%)
天気予報 曇りのち晴れ(川下り日和度90%)
川気温 最高15℃ 最低9℃
午前、午後の船共に防寒対策必要あり
見頃に近づいています。
船の上から見上げるもみじの葉は、その先の部分から
赤みがかかり、一枚の葉に数色が浮びあがり雅さを
かもし出します。

嵐山も先月の予想では「紅葉が1~2週間遅れる」
とのことでしたが、例年並みに近づいているようです。
‘もみじ’だけでなく、けやきなど雑木も朱色に色つき始め、
緑と相まって見事なコントラストを描き出しています。
今週末あたりからいよいよ嵐山は
見頃の季節を迎えそうですね!
☆《明日の保津川下り予報》
明日の予約数 33隻(午前中に20隻)
待ち時間予想 30分前後’(的中率90%)
天気予報 曇りのち晴れ(川下り日和度90%)
川気温 最高15℃ 最低9℃
午前、午後の船共に防寒対策必要あり