いつも通り遅くなってしまいましたが、当ブログの新年のご挨拶も兼ねる 今年の年賀状です。小さな文字が 2,379字、相当に読みづらいと思いまして テキストも併せて載せております。が それでもゴチャゴチャ、読むのはタイヘンです。ご随にどうぞ。

昨年は 4月初旬より病の連鎖に襲われ、食べられないため体重14Kg減 血圧70以下 痛みでほとんど身動きできず寝たきりといった かってない苦しみと遭遇しましたが、体調の微係数が ようやくプラスに転じた 9月末頃、本を読む気力も戻ってきまして、不図、ほとんど毎日 年寄りの甲斐性?で 朝3時には目が覚め 寝床でウロウロしているのなら、いっそのこと いつも別室で興じている抹茶タイムを 4時頃から進め 2時間ほどは本を読んだらどうか と思い付いたのであります。でそれから毎日実践しているのでありますが、最初に読もうと決めたのが 賢治さんの数ある童話でございまして
(1)いちょうの実(2)茨海小学校(3)インドラの網(4)狼森と笊森、盗森(5)おきなぐさ(6)オツベリと象(7)貝の火(8)カイロ団長(9)蛙のゴム長靴(10)かしわばやしの夜(11)風の又三郎(12)風野又三郎(13)ガドルフの百合(14)鳥の北斗七星(15)雁の童子(16)黄色のトマト(17)飢餓陣営(18)気のいい火山弾(19)銀河鉄道の夜(初期型第3次稿)(20)銀河鉄道の夜(21)グスコーブドリの伝記(22)蜘蛛となめくじと狸(23)クンねずみ(24)虔十公園林(25)ざしき童子のはなし(26)さるのこしかけ(27)水仙月の四月(28)鹿踊りのはじまり(29)紫紺染について(30)十月の末(31)シグナルとシグナレス(32)十力の金剛石(33)税務署長の冒険(34)セロ弾きのゴーシュ(35)谷(36)種山ヶ原(37)タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった(38)注文の多い料理店(39)ツエねずみ(40)月夜のけだもの(41)月夜のでんしんばしら(42)土神ときつね(43)毒もみのすきな署長さん(44)とっこべとら子(45)鳥箱先生とフウねずみ(46)鳥をとるやなぎ(47)どんぐりと山猫(48)なめとこ山の熊(49)楢の木大学子の野猫(50)二十六夜(51)猫の事務所(52)林の底(53)ひかりの素足(54)ひのきとひなげし(55)ビジテリアン大祭(56)氷河鼠の毛皮(57)ふたごの星(58)フランドン農学校の豚(59)ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記(60)北守将軍と三人兄弟の医者(61)洞熊学校を卒業した三人(62)ポラーノの広場(63)祭の晩(64)まなづるとダァリヤ(65)マリヴロンと少女(66)山男の四月(67)やまなし(68)雪渡り(69)よたかの星(70)竜と詩人(71)若い木霊 の71編(アイウエオ順にソートしました)を
新訳本の「老人と海」「郵便配達は二度ベルを鳴らす」 坂口安吾さんの「桜の森の満開の下」藤沢周平さんの「雪明かり」 平川さんの「日本の正論」などを 気分転換として混ぜ込み 読み終え
で 次は何といっても漱石さんだろうと、これまでに 「こころ」「吾輩は猫である」「坊ちゃん」「彼岸過迄」「三四郎」と読み進め、今後も継続すべく Amazonで10冊ばかり 中古文庫本を取り寄せ済みであります。
賢治さんの 山 川 草 木 花 雨 風 雲 雪 空 などなどの自然描写は決して作り事や飾り事でなく、賢治さんが折々 実際に感じられた そのまんまが描写されていますから、読む方も真実 その自然の中に在るような気分となり 作品世界に溶け込んでゆけるのでございまして、この感覚が実に 嬉しく心地よいのであります。なお上記71編の童話のなかで愚生が特に惹かれる作品は (3)(20)(29)(48)(55)(57)(69)であります。
一方 明治第一等の頭脳の持ち主であられる漱石さんの著作本からは、氏の想いなり感覚なり考え方に触れる喜びが一番大きいのですが、びっくりしたのは その文章であります。難しい言葉が次々出てくる「吾輩は…」なんぞは 手許にコンパクトな電子辞書がなくば 到底前には進めないぞと直感したものですから、「大辞林」も「広辞苑」も「EXワード」も所持しているものの、急遽別室専用のモノ(SEIKOインスツルメント広辞苑電子辞書)を新規に取り寄せたぐらいですが、文章そのものは、江戸時代から僅か抜け出たばかりの時代にありながら、現代文と寸分違わないのであります。が、これはきっと 漱石さんの日本語が 漱石さん以後の日本人の手本となり 現在に到っているからではないだろうか と思えた次第であります。
このように 未だかってなく読書が捗(はかど)っております。試験勉強もほとんど 勿論受験勉強もやったことのない愚生にとりまして、こんなのは初めての経験ですから ますます嬉しくなりまして、明け方のこの時間を【老読タイム】と名付け、充実した気分の まさに至福とも言えるひとときを過ごしているのでございますが、最後にあたり 今回 漱石さんの著作本から識り得た言葉をやりくりすることで、以下 小生の年頭における所感およびご挨拶を申し上げさせていただくとします。
輸贏(しゅえい) 糅然(じゅうぜん)・冉冉(ぜんぜん) 烈々(れつれつ)なるこの世、冥頑不霊(めいがんぶれい) 翩々(へんべん)たる我にあれど、無何有郷(むかうのきょう)を准(なぞら)わん 吾が蝸牛(かぎゅう)の庵・待月百休庵(まつきひゃっきゅうあん)に在りて、江湖(こうこ)の処士たる風情 則天去私(そくてんきょし)たる心持ちもて、瑣談繊話(さだんせんわ)を語りつつ、残喘(ざんぜん)を保たんと しめやかに願うものなり。扨ても 末尾となりて甚だ恐縮なれど 新たに明けし皇紀2675年の皆々様のご健勝並びにご繁栄を 心より祈念申し上げ、年初におけるご挨拶とさせていただきとうございます。ありがとうございました。
で ↓ これが、如上関連本であります。(如上という単語は「三四郎」で識りました)

恥ずかしいことを告白します。賢治さんの【星めぐりの歌】の歌詞と楽譜、ちっとも捜すことはなかったのです。新潮文庫「新編 銀河鉄道の夜」収録の「双子の星」に詞が、巻末の「注解」ページに楽譜が ちゃんと載っかっているのです。
それとです、何と老生は 漱石さんが亡くなられた ちょうど 29年後の同じ日に生まれているのであります。こんなご縁がありながら、亡くなられて98年経った昨年 やっと気付くなんて・・・本当に恐れ多くて申し訳ない気持でいっぱいであります。こうなれば何が何でも 文庫本なら総て読まなっくちゃと思っています。遅くとも歿後100年を迎える前までには絶対に。
次に「老読タイム」のこと、「明け方の別世界」という題で 一行10文字以下 全14行の詩を作り、昨11月19日 産経新聞「朝の詩」係りさん宛 投稿いたしております。当人は なかなか好い詩だね と思っているのですが、どうでしょう。ボツとなる可能性 大ですが、前回採用された時は 郵送して 約3ヶ月後 突然に でしたから、お披露目は 2月過ぎてからとさせていただきたく思っております。悪しからず ご了承下さい。
以下は漱石さん本の中で 初めて出合ったように感じ、以後 使ってみたいと思う言葉の備忘録です。
・昧爽(まいそう):夜明け 未明
・後架(こうか):便所
・業腹(ごうはら):非常に腹が立つこと
・千金の子は堂陲(どうすい)に坐せず:価値のある者の子は 端っこに座らない
・大声は俚耳(りじ)に入らず 陽春白雪の詩には和するもの少なし:立派な議論は
世間の人々の耳には入らず、最も高尚 な詩に共鳴するものは少ない
・残喘(ざんぜん)を保つ:長くもない余命を保つ
・江湖(こうこ)の処士:名利を求めず平凡な生活に甘んじている人
・瑣談繊話(さだんせんわ):瑣細なつまらない話(繊は 1/1000万 のこと)
・冥頑不霊(めいがんふれい):道理がわからず無知なこと
・琴瑟(きんしつ)相和す:楽器の琴と瑟がよく合うように夫婦の仲が睦まじいこと
・偕老同穴(かいろうどうけつ):共に老い 同じお墓に入る
・嚆矢(こうし):始まり 起源
・宛然(えんぜん):あたかも まるで さながら
・輸嬴(しゅえい):負けと勝ち
・糅然(じゅうぜん):入り乱れているさま
・苟も:いやしくも
・一噱(いっきゃく)を催したくなる:大声で笑いたくなる
・冉冉(ぜんぜん):移り変わるさま
・這裡(しゃり):この間
・岫(しゅう):峰
・枉(ま)げる:曲げる
・烈々:冷たい 寒さが激しい
・截然(せつぜん):区別がはっきりした
・鴻溝(こうこう):大きな溝 堺
・昔の人は己を忘れろと教えたものだが今の人は己を忘れるなと教える
・燕雀焉んぞ大鵬の志を知らんや
・呑気に見える人々も、心の底を叩いてみると、どこか悲しい音がする
・無何有郷(むかうのきょう):「荘子」の中の嘘のない自然のままの楽土 ユートピア
・鉢:頭の横まわり
・尋(ひろ):縄や水深など測る長さの単位 約1.5m or 約1.8m
・肯綮(こうけい)に中(あた)る:急所を突く
・寛仮(かんか):大目に見ること
・好逑(こうきゅう):よい配偶者
・服膺(ふくよう):胸に留めて忘れないこと
・踴(おど)り:踊り
・則天去士(そくてんきょし):小さな私を去って天に則る 大自然に委ねて生きること
・丁年(ていねん):強壮のときに丁(あた)るという意で一人前の齢 満20歳
・用場:便所
・のつそつ:身体を伸ばしたり反らしたり
・命根:命の根本
・翩々(へんべん)たる:風に翻るような お調子者
・纏綿(てんめん):情緒深く細やかで離れがたい
・低徊(ていかい):いろいろ考え巡らすこと
・低徊趣味:世俗的な労苦を避け余裕ある気分で東洋的な詩美の境に遊ぼうとする趣味
・掬(きく)す:両手ですくい取る 事情を汲み取り察する
・晏如(あんじょ):やすらかで落着いている
・談柄(だんぺい):話しのタネ
・没分業(ぼつぶんぎょう):ものわかりの悪いこと
・如上(じょじょう):上述
・田臭(でんしゅう):田舎臭さ

昨年は 4月初旬より病の連鎖に襲われ、食べられないため体重14Kg減 血圧70以下 痛みでほとんど身動きできず寝たきりといった かってない苦しみと遭遇しましたが、体調の微係数が ようやくプラスに転じた 9月末頃、本を読む気力も戻ってきまして、不図、ほとんど毎日 年寄りの甲斐性?で 朝3時には目が覚め 寝床でウロウロしているのなら、いっそのこと いつも別室で興じている抹茶タイムを 4時頃から進め 2時間ほどは本を読んだらどうか と思い付いたのであります。でそれから毎日実践しているのでありますが、最初に読もうと決めたのが 賢治さんの数ある童話でございまして
(1)いちょうの実(2)茨海小学校(3)インドラの網(4)狼森と笊森、盗森(5)おきなぐさ(6)オツベリと象(7)貝の火(8)カイロ団長(9)蛙のゴム長靴(10)かしわばやしの夜(11)風の又三郎(12)風野又三郎(13)ガドルフの百合(14)鳥の北斗七星(15)雁の童子(16)黄色のトマト(17)飢餓陣営(18)気のいい火山弾(19)銀河鉄道の夜(初期型第3次稿)(20)銀河鉄道の夜(21)グスコーブドリの伝記(22)蜘蛛となめくじと狸(23)クンねずみ(24)虔十公園林(25)ざしき童子のはなし(26)さるのこしかけ(27)水仙月の四月(28)鹿踊りのはじまり(29)紫紺染について(30)十月の末(31)シグナルとシグナレス(32)十力の金剛石(33)税務署長の冒険(34)セロ弾きのゴーシュ(35)谷(36)種山ヶ原(37)タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった(38)注文の多い料理店(39)ツエねずみ(40)月夜のけだもの(41)月夜のでんしんばしら(42)土神ときつね(43)毒もみのすきな署長さん(44)とっこべとら子(45)鳥箱先生とフウねずみ(46)鳥をとるやなぎ(47)どんぐりと山猫(48)なめとこ山の熊(49)楢の木大学子の野猫(50)二十六夜(51)猫の事務所(52)林の底(53)ひかりの素足(54)ひのきとひなげし(55)ビジテリアン大祭(56)氷河鼠の毛皮(57)ふたごの星(58)フランドン農学校の豚(59)ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記(60)北守将軍と三人兄弟の医者(61)洞熊学校を卒業した三人(62)ポラーノの広場(63)祭の晩(64)まなづるとダァリヤ(65)マリヴロンと少女(66)山男の四月(67)やまなし(68)雪渡り(69)よたかの星(70)竜と詩人(71)若い木霊 の71編(アイウエオ順にソートしました)を
新訳本の「老人と海」「郵便配達は二度ベルを鳴らす」 坂口安吾さんの「桜の森の満開の下」藤沢周平さんの「雪明かり」 平川さんの「日本の正論」などを 気分転換として混ぜ込み 読み終え
で 次は何といっても漱石さんだろうと、これまでに 「こころ」「吾輩は猫である」「坊ちゃん」「彼岸過迄」「三四郎」と読み進め、今後も継続すべく Amazonで10冊ばかり 中古文庫本を取り寄せ済みであります。
賢治さんの 山 川 草 木 花 雨 風 雲 雪 空 などなどの自然描写は決して作り事や飾り事でなく、賢治さんが折々 実際に感じられた そのまんまが描写されていますから、読む方も真実 その自然の中に在るような気分となり 作品世界に溶け込んでゆけるのでございまして、この感覚が実に 嬉しく心地よいのであります。なお上記71編の童話のなかで愚生が特に惹かれる作品は (3)(20)(29)(48)(55)(57)(69)であります。
一方 明治第一等の頭脳の持ち主であられる漱石さんの著作本からは、氏の想いなり感覚なり考え方に触れる喜びが一番大きいのですが、びっくりしたのは その文章であります。難しい言葉が次々出てくる「吾輩は…」なんぞは 手許にコンパクトな電子辞書がなくば 到底前には進めないぞと直感したものですから、「大辞林」も「広辞苑」も「EXワード」も所持しているものの、急遽別室専用のモノ(SEIKOインスツルメント広辞苑電子辞書)を新規に取り寄せたぐらいですが、文章そのものは、江戸時代から僅か抜け出たばかりの時代にありながら、現代文と寸分違わないのであります。が、これはきっと 漱石さんの日本語が 漱石さん以後の日本人の手本となり 現在に到っているからではないだろうか と思えた次第であります。
このように 未だかってなく読書が捗(はかど)っております。試験勉強もほとんど 勿論受験勉強もやったことのない愚生にとりまして、こんなのは初めての経験ですから ますます嬉しくなりまして、明け方のこの時間を【老読タイム】と名付け、充実した気分の まさに至福とも言えるひとときを過ごしているのでございますが、最後にあたり 今回 漱石さんの著作本から識り得た言葉をやりくりすることで、以下 小生の年頭における所感およびご挨拶を申し上げさせていただくとします。
輸贏(しゅえい) 糅然(じゅうぜん)・冉冉(ぜんぜん) 烈々(れつれつ)なるこの世、冥頑不霊(めいがんぶれい) 翩々(へんべん)たる我にあれど、無何有郷(むかうのきょう)を准(なぞら)わん 吾が蝸牛(かぎゅう)の庵・待月百休庵(まつきひゃっきゅうあん)に在りて、江湖(こうこ)の処士たる風情 則天去私(そくてんきょし)たる心持ちもて、瑣談繊話(さだんせんわ)を語りつつ、残喘(ざんぜん)を保たんと しめやかに願うものなり。扨ても 末尾となりて甚だ恐縮なれど 新たに明けし皇紀2675年の皆々様のご健勝並びにご繁栄を 心より祈念申し上げ、年初におけるご挨拶とさせていただきとうございます。ありがとうございました。
で ↓ これが、如上関連本であります。(如上という単語は「三四郎」で識りました)

恥ずかしいことを告白します。賢治さんの【星めぐりの歌】の歌詞と楽譜、ちっとも捜すことはなかったのです。新潮文庫「新編 銀河鉄道の夜」収録の「双子の星」に詞が、巻末の「注解」ページに楽譜が ちゃんと載っかっているのです。
それとです、何と老生は 漱石さんが亡くなられた ちょうど 29年後の同じ日に生まれているのであります。こんなご縁がありながら、亡くなられて98年経った昨年 やっと気付くなんて・・・本当に恐れ多くて申し訳ない気持でいっぱいであります。こうなれば何が何でも 文庫本なら総て読まなっくちゃと思っています。遅くとも歿後100年を迎える前までには絶対に。
次に「老読タイム」のこと、「明け方の別世界」という題で 一行10文字以下 全14行の詩を作り、昨11月19日 産経新聞「朝の詩」係りさん宛 投稿いたしております。当人は なかなか好い詩だね と思っているのですが、どうでしょう。ボツとなる可能性 大ですが、前回採用された時は 郵送して 約3ヶ月後 突然に でしたから、お披露目は 2月過ぎてからとさせていただきたく思っております。悪しからず ご了承下さい。
以下は漱石さん本の中で 初めて出合ったように感じ、以後 使ってみたいと思う言葉の備忘録です。
・昧爽(まいそう):夜明け 未明
・後架(こうか):便所
・業腹(ごうはら):非常に腹が立つこと
・千金の子は堂陲(どうすい)に坐せず:価値のある者の子は 端っこに座らない
・大声は俚耳(りじ)に入らず 陽春白雪の詩には和するもの少なし:立派な議論は
世間の人々の耳には入らず、最も高尚 な詩に共鳴するものは少ない
・残喘(ざんぜん)を保つ:長くもない余命を保つ
・江湖(こうこ)の処士:名利を求めず平凡な生活に甘んじている人
・瑣談繊話(さだんせんわ):瑣細なつまらない話(繊は 1/1000万 のこと)
・冥頑不霊(めいがんふれい):道理がわからず無知なこと
・琴瑟(きんしつ)相和す:楽器の琴と瑟がよく合うように夫婦の仲が睦まじいこと
・偕老同穴(かいろうどうけつ):共に老い 同じお墓に入る
・嚆矢(こうし):始まり 起源
・宛然(えんぜん):あたかも まるで さながら
・輸嬴(しゅえい):負けと勝ち
・糅然(じゅうぜん):入り乱れているさま
・苟も:いやしくも
・一噱(いっきゃく)を催したくなる:大声で笑いたくなる
・冉冉(ぜんぜん):移り変わるさま
・這裡(しゃり):この間
・岫(しゅう):峰
・枉(ま)げる:曲げる
・烈々:冷たい 寒さが激しい
・截然(せつぜん):区別がはっきりした
・鴻溝(こうこう):大きな溝 堺
・昔の人は己を忘れろと教えたものだが今の人は己を忘れるなと教える
・燕雀焉んぞ大鵬の志を知らんや
・呑気に見える人々も、心の底を叩いてみると、どこか悲しい音がする
・無何有郷(むかうのきょう):「荘子」の中の嘘のない自然のままの楽土 ユートピア
・鉢:頭の横まわり
・尋(ひろ):縄や水深など測る長さの単位 約1.5m or 約1.8m
・肯綮(こうけい)に中(あた)る:急所を突く
・寛仮(かんか):大目に見ること
・好逑(こうきゅう):よい配偶者
・服膺(ふくよう):胸に留めて忘れないこと
・踴(おど)り:踊り
・則天去士(そくてんきょし):小さな私を去って天に則る 大自然に委ねて生きること
・丁年(ていねん):強壮のときに丁(あた)るという意で一人前の齢 満20歳
・用場:便所
・のつそつ:身体を伸ばしたり反らしたり
・命根:命の根本
・翩々(へんべん)たる:風に翻るような お調子者
・纏綿(てんめん):情緒深く細やかで離れがたい
・低徊(ていかい):いろいろ考え巡らすこと
・低徊趣味:世俗的な労苦を避け余裕ある気分で東洋的な詩美の境に遊ぼうとする趣味
・掬(きく)す:両手ですくい取る 事情を汲み取り察する
・晏如(あんじょ):やすらかで落着いている
・談柄(だんぺい):話しのタネ
・没分業(ぼつぶんぎょう):ものわかりの悪いこと
・如上(じょじょう):上述
・田臭(でんしゅう):田舎臭さ














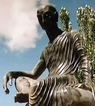
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます